| home |
| �f���_�C�W�F�X�g |
���v����̕��S�̃y�[�W�ɕ����ďЉ�Ă��܂��B�ŐV���́A�f���_�C�W�F�X�g�Ɍf�ڂ��Ă��܂��B�ʐ^�́A���v���B�e�������̂������\��t���܂����B
�@
�@
 ����������� �ɍs���ė��܂����B�����́A�����������́u�������z�e���v�ʼn���ł͂���܂���B���ق̂悤�ȃT�[�r�X�����҂���Ƃ������肵�܂����A�����C�����ꂢ�����A�H�����ʂ͏��Ȃ��ł������������ł��B���������炵���i�F�ƁA���ȍ��R�A���������Ǝv���܂��B���́A�u�܂ނ����v�Ƃ����Ԃ�����̂悤�ł����B��������A�����i�H�����j�Ȃ̂͂����̂��₶����ŁA���̃K�C�h�Ԃ�i�ʐ^�j�͕�����|���̂ł��B�S���Ȃ��܂��Ă���邱�Ɛ��������ł��B���܂�V�C���悭�Ȃ��Ă��������̌i�F���\���ɂ͊��\�ł��܂���ł������A����̒��́u�����@�v�Ƃ����Ƃ���Ńu���b�P�����ۂ����邱�Ƃ��ł��܂����B�܂����A����Ȍo�����ł���Ƃ͎v���Ă��Ȃ������̂Ŋ������܂����B ����������� �ɍs���ė��܂����B�����́A�����������́u�������z�e���v�ʼn���ł͂���܂���B���ق̂悤�ȃT�[�r�X�����҂���Ƃ������肵�܂����A�����C�����ꂢ�����A�H�����ʂ͏��Ȃ��ł������������ł��B���������炵���i�F�ƁA���ȍ��R�A���������Ǝv���܂��B���́A�u�܂ނ����v�Ƃ����Ԃ�����̂悤�ł����B��������A�����i�H�����j�Ȃ̂͂����̂��₶����ŁA���̃K�C�h�Ԃ�i�ʐ^�j�͕�����|���̂ł��B�S���Ȃ��܂��Ă���邱�Ɛ��������ł��B���܂�V�C���悭�Ȃ��Ă��������̌i�F���\���ɂ͊��\�ł��܂���ł������A����̒��́u�����@�v�Ƃ����Ƃ���Ńu���b�P�����ۂ����邱�Ƃ��ł��܂����B�܂����A����Ȍo�����ł���Ƃ͎v���Ă��Ȃ������̂Ŋ������܂����B |
| �@ |
 ����ڂ́A�R�������Ĕ���������́u����������z�e���ĕ�v�Ƃ����Ƃ���ɔ��܂�܂����B�P�O�O�������^�z�e���ŕ��i�͌h������̂ł����A���Ƃ��Ƃ�����ƋC�ɂȂ��Ă����Ƃ���ł����������s���Ă��܂����B�����C�͑傫���ĉ��x�Ǘ����������肵�Ă��Ă����Ǝv���܂����A�z�i�H�ڂ��͂��܂�ڂ����Ȃ��̂Œf���͂ł��܂��A�Ƃ肠�����A������铒�Əo�铒�Ƃ̔䗦����l���āj���ۂ������Ȃ̂��C�ɂȂ�܂����B�H���͂��������Ǝv���܂��B�{�����[��������܂��B ����ڂ́A�R�������Ĕ���������́u����������z�e���ĕ�v�Ƃ����Ƃ���ɔ��܂�܂����B�P�O�O�������^�z�e���ŕ��i�͌h������̂ł����A���Ƃ��Ƃ�����ƋC�ɂȂ��Ă����Ƃ���ł����������s���Ă��܂����B�����C�͑傫���ĉ��x�Ǘ����������肵�Ă��Ă����Ǝv���܂����A�z�i�H�ڂ��͂��܂�ڂ����Ȃ��̂Œf���͂ł��܂��A�Ƃ肠�����A������铒�Əo�铒�Ƃ̔䗦����l���āj���ۂ������Ȃ̂��C�ɂȂ�܂����B�H���͂��������Ǝv���܂��B�{�����[��������܂��B |
 ��È��m�q�����ɍs���Ă����̂ŕ��܂��B�����́A���{�铒������̉�����قł�����u�勬�t�v�ɔ��܂�܂����B���ł��A���m�q����ł͗B��̌���������Ă��闷�ق������ł��B���̗��ق͑g���i�H�j���Ǘ����Ă��邻���ł��B�����������������āA�����͑f���炵���Ǝv���܂����B�����^�̓��D�̕Б����[���Ȃ��Ă��Ēꂩ���ؓ����N���o���Ă��܂��B�����������Q�ŁA���x�����x���������ł����B���ɂ₳������܂��悤�ŁA�u���`��A�Ɋy�Ɋy�I�v��Ԃł����B�܂��ɁA�����ȓ��Ƃ�����ۂ��܂����B�����A�c�O�Ȃ��Ƃɂ��̓��D�͒j����p�Ō��͂Ȃ��A�����̓����͋����āA����قǂ̍D��ۂ͎��ĂȂ��悤�ł��B�܂��A�I�V���C�͒j�������傫���Ȃ̂ł����A����L���ƈ�l��������Ȃ��قǂ̏������ł����B�[�H�́A�����{�����[�����\��������܂���B���������Ǝv���܂��B�f�p�Ȓ��ɂ��ӊO���̂��闿�����Ǝv���܂��B�����܂��B���ƁA�������C�����Ȑl�ŃT�[�r�X���_���_�ł��B ��È��m�q�����ɍs���Ă����̂ŕ��܂��B�����́A���{�铒������̉�����قł�����u�勬�t�v�ɔ��܂�܂����B���ł��A���m�q����ł͗B��̌���������Ă��闷�ق������ł��B���̗��ق͑g���i�H�j���Ǘ����Ă��邻���ł��B�����������������āA�����͑f���炵���Ǝv���܂����B�����^�̓��D�̕Б����[���Ȃ��Ă��Ēꂩ���ؓ����N���o���Ă��܂��B�����������Q�ŁA���x�����x���������ł����B���ɂ₳������܂��悤�ŁA�u���`��A�Ɋy�Ɋy�I�v��Ԃł����B�܂��ɁA�����ȓ��Ƃ�����ۂ��܂����B�����A�c�O�Ȃ��Ƃɂ��̓��D�͒j����p�Ō��͂Ȃ��A�����̓����͋����āA����قǂ̍D��ۂ͎��ĂȂ��悤�ł��B�܂��A�I�V���C�͒j�������傫���Ȃ̂ł����A����L���ƈ�l��������Ȃ��قǂ̏������ł����B�[�H�́A�����{�����[�����\��������܂���B���������Ǝv���܂��B�f�p�Ȓ��ɂ��ӊO���̂��闿�����Ǝv���܂��B�����܂��B���ƁA�������C�����Ȑl�ŃT�[�r�X���_���_�ł��B |
| �@ |
 ����ڂ͓�����È��m�q����́u�ە�ό��z�e���v�ł��B�����Ƃ͑ΏƓI�ȂP�R�O�����炢�����鍋�؋���z�e���ł��B�����̌i�F�����Q�ł����B�l�̔��܂����̂͌k�J���̕����ŁA��ƎR���������܂���B����Ȃ̂ǂ��ɂł�����ƌ���ꂻ���ł����A���̍\�}�����Ƃ������Ȃ��̂ł��B�g�t�̎��ɂ͂��̎R���S�R�g�t���邻���ŁA����͑f���炵���̂ł͂Ƒz���ł��܂��B�����C�́A���K���X����̂R�O���[�g���̍ג����������L���ł����A�̂Ŏv�����قǂ����̗ʂ����銴���ł͂���܂���B��������ꂪ�����Ȃ����ɂȂ��Ă��ĂȂ��Ȃ������Ǝv���܂����B�I�V�͋��嗷�قɂ��Ă͏����߂Ȉ�ۂ��܂����B��������Ȃ�͂܂�Ă��Ă��܂�i�F�͊y���߂܂���B�����C�Ɋւ��Ắu�勬�t�v�Ƃ͑ΏƓI�ɂ����͏����D�ʂł��B�������j�����͂Ȃ��̂ł����A�嗁��ɂ���A�I�V�ɂ���A�O�̓��ɂ��돗���̕������ׂČi�F�������悤�ł��B�����������D�ʂ��ƌ����Ă��܂����B�H���͂��������Ǝv���܂��B���嗷�ق͒c�̂ƈꏏ�ɂȂ�Ȃ�����A�����ė��ّ�����g���Ƃ̋q�ւ̖ڔz���Y��Ȃ�����͈������Ƃ���ł͂Ȃ��Ǝv���܂����B ����ڂ͓�����È��m�q����́u�ە�ό��z�e���v�ł��B�����Ƃ͑ΏƓI�ȂP�R�O�����炢�����鍋�؋���z�e���ł��B�����̌i�F�����Q�ł����B�l�̔��܂����̂͌k�J���̕����ŁA��ƎR���������܂���B����Ȃ̂ǂ��ɂł�����ƌ���ꂻ���ł����A���̍\�}�����Ƃ������Ȃ��̂ł��B�g�t�̎��ɂ͂��̎R���S�R�g�t���邻���ŁA����͑f���炵���̂ł͂Ƒz���ł��܂��B�����C�́A���K���X����̂R�O���[�g���̍ג����������L���ł����A�̂Ŏv�����قǂ����̗ʂ����銴���ł͂���܂���B��������ꂪ�����Ȃ����ɂȂ��Ă��ĂȂ��Ȃ������Ǝv���܂����B�I�V�͋��嗷�قɂ��Ă͏����߂Ȉ�ۂ��܂����B��������Ȃ�͂܂�Ă��Ă��܂�i�F�͊y���߂܂���B�����C�Ɋւ��Ắu�勬�t�v�Ƃ͑ΏƓI�ɂ����͏����D�ʂł��B�������j�����͂Ȃ��̂ł����A�嗁��ɂ���A�I�V�ɂ���A�O�̓��ɂ��돗���̕������ׂČi�F�������悤�ł��B�����������D�ʂ��ƌ����Ă��܂����B�H���͂��������Ǝv���܂��B���嗷�ق͒c�̂ƈꏏ�ɂȂ�Ȃ�����A�����ė��ّ�����g���Ƃ̋q�ւ̖ڔz���Y��Ȃ�����͈������Ƃ���ł͂Ȃ��Ǝv���܂����B |
 ����̏��������������́u�a�̂̏h�킩�܂�v�ł����B��������͂قƂ�ǎ��R�N�o�炵���̂ł����A����������P�O�O���ł������艷�x�Ǘ�����Ă��܂����B�����A�Q�V�����炢�̋K�͂Ȃ̂ŗ����͂��ׂď������̂��c�O�ł��B�����C����A�I�V�̗������Α����A�O�i�H�j�����܂����A���ꂼ�ꉷ�x�������ɂ��炵�Ă���܂��B�_���̂��Ȃ苭��������ł��B�I�V�́A�ڂ̐�ꃁ�[�g���قǂ̂Ƃ���ɍ����͂����߂��点�Ă����āA���߂͂܂���������܂���B�͂��Ȃ肢���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ɒ����O�ɗL�łȃK�X��E�C���Ă���Ƃ̂��ƂŁApH1.3�̎_���x�̊��ɂ͂��܂�Ђ�Ђ肵�Ȃ��������A�̂ɗ����̂ɂ��������܂���܂���ł����B�����͂Ȃ߂Ă݂�ƁA����ȁA������ς����ς��Ƃ����悤�Ȗ������܂��B�H���́A�S�̓I�ɂ��������Ǝv���܂��B�������Ɉ��ς̖{��Ƃ������ƂŁA���ς͒��̂����߂�݂����Ȍ`�̂������ӂ��߂Ĕ��ɂ������������ł��B����ȊO�ɂ����ꂼ��H�v�̂��闿�����o�Ă��܂����B���Ƃ́A�t�����g�̒��q�̂����l���ʔ����ł���B�a�̂̏h�Ƃ������ƂŁA�ڂ���������Ă��܂����B ����̏��������������́u�a�̂̏h�킩�܂�v�ł����B��������͂قƂ�ǎ��R�N�o�炵���̂ł����A����������P�O�O���ł������艷�x�Ǘ�����Ă��܂����B�����A�Q�V�����炢�̋K�͂Ȃ̂ŗ����͂��ׂď������̂��c�O�ł��B�����C����A�I�V�̗������Α����A�O�i�H�j�����܂����A���ꂼ�ꉷ�x�������ɂ��炵�Ă���܂��B�_���̂��Ȃ苭��������ł��B�I�V�́A�ڂ̐�ꃁ�[�g���قǂ̂Ƃ���ɍ����͂����߂��点�Ă����āA���߂͂܂���������܂���B�͂��Ȃ肢���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ɒ����O�ɗL�łȃK�X��E�C���Ă���Ƃ̂��ƂŁApH1.3�̎_���x�̊��ɂ͂��܂�Ђ�Ђ肵�Ȃ��������A�̂ɗ����̂ɂ��������܂���܂���ł����B�����͂Ȃ߂Ă݂�ƁA����ȁA������ς����ς��Ƃ����悤�Ȗ������܂��B�H���́A�S�̓I�ɂ��������Ǝv���܂��B�������Ɉ��ς̖{��Ƃ������ƂŁA���ς͒��̂����߂�݂����Ȍ`�̂������ӂ��߂Ĕ��ɂ������������ł��B����ȊO�ɂ����ꂼ��H�v�̂��闿�����o�Ă��܂����B���Ƃ́A�t�����g�̒��q�̂����l���ʔ����ł���B�a�̂̏h�Ƃ������ƂŁA�ڂ���������Ă��܂����B |
| �@ |
 ����ڂ͏�m�R����́u�t�R�فv�ł����B�����͌���̏h���Ƃ������Ƃł����͖L�x�炵���A�قƂ�ǂ̕����̕��C���O���C�ʼn���ł��B���������x�Ǘ����������肵�Ă��āA�����Ɨ��h�Ȑ����v���Ƃ�����Ă��܂��B�嗁�ꂪ�S�O�x�A�I�V���S�Q�x�ɕۂ���Ă��܂����B������͂�I�V���C�́A�ڂ̐�P���[�g�����͂��Ƃ�����Ԃł����B�l�G���Ƃ������ɔ��܂����̂ł����A�t�R�قƂ����Ύʐ^�ɕK���o�Ă��鉮���뉀�̖ڂ̑O�̕����������̂ɂ͂т����肵�܂����B�����̒��ɂ��ؒ낪����A�����̂����C������Ō������͂Ȃ������ł����A���͑����J����Ɩڂ̑O���Ί_�ŁA�����炵�͂܂������Ȃ��A���̑��͕߂��ςȂ��Ƃ������Ƃł��B�H���͕đ����C���ŁA�X�e�[�L�E�����i�E���ςƕđ��g���Ă��܂����B�����A���̕��i�������Ȃ��đS���Ŏ��i���炢�������Ǝv���܂��B��͂肱���ł����ς��������������ł��ˁB���ꂩ��A�ׂ����������������ł��B���H�͈�ʓI�Ȓ���H�ł����A�Ă����ăp���̒��H���I�ׂ�悤�ɂȂ��Ă��āA������܂�ł݂܂������A������͂�����Ǝv���܂����B���H�̓p���������߂��܂��B ����ڂ͏�m�R����́u�t�R�فv�ł����B�����͌���̏h���Ƃ������Ƃł����͖L�x�炵���A�قƂ�ǂ̕����̕��C���O���C�ʼn���ł��B���������x�Ǘ����������肵�Ă��āA�����Ɨ��h�Ȑ����v���Ƃ�����Ă��܂��B�嗁�ꂪ�S�O�x�A�I�V���S�Q�x�ɕۂ���Ă��܂����B������͂�I�V���C�́A�ڂ̐�P���[�g�����͂��Ƃ�����Ԃł����B�l�G���Ƃ������ɔ��܂����̂ł����A�t�R�قƂ����Ύʐ^�ɕK���o�Ă��鉮���뉀�̖ڂ̑O�̕����������̂ɂ͂т����肵�܂����B�����̒��ɂ��ؒ낪����A�����̂����C������Ō������͂Ȃ������ł����A���͑����J����Ɩڂ̑O���Ί_�ŁA�����炵�͂܂������Ȃ��A���̑��͕߂��ςȂ��Ƃ������Ƃł��B�H���͕đ����C���ŁA�X�e�[�L�E�����i�E���ςƕđ��g���Ă��܂����B�����A���̕��i�������Ȃ��đS���Ŏ��i���炢�������Ǝv���܂��B��͂肱���ł����ς��������������ł��ˁB���ꂩ��A�ׂ����������������ł��B���H�͈�ʓI�Ȓ���H�ł����A�Ă����ăp���̒��H���I�ׂ�悤�ɂȂ��Ă��āA������܂�ł݂܂������A������͂�����Ǝv���܂����B���H�̓p���������߂��܂��B |
�ˑq��R�c�����Ɠ��c������ɍs���Ă��܂����B�ˑq��R�c����́u�����z�e���v�ł��B�����́u�����t�v�Œr�̒�ɖʂ��������ł��B���̒r�͗������̐Β�Ɠ����悤�Ȑ̔z�u���������̂������ŁA�Ȃ��Ȃ������Ȃ̂ł����A�r�����邽�߂Ƀ��[�X�̃J�[�e�����J����ƁA�����̒���������Ƃ��납��ی����ɂȂ��Ă��܂��Ƃ����A���Ȗ������������Ă��܂��B�����͂������Ƃ��Ă��ĐV�����A���ʑ����ʂ���ق��A�S������̕O���C�����Ă��܂��B�܂��A�J�[�h�L�[�����Ă���ȂǁA�C���˂Ȃ������̍D���Ȃ������C�ɓ����Ă����܂��B���Ȗ����������Ε����Ɋւ��Ă͐\�����Ȃ��Ǝv���܂��B���C�͒j�����ŁA�悭�p���t���b�g�ɍڂ��Ă���u�̓��v�i���E��m���[��R���Ɍ�ցj���j���p�ł��B�̓��͂�����Ƃ������͋C������܂��i�ʐ^�P�E�Q�j�B���ɁA�������������ނƁA�_��I�Ȋ����ɂȂ�܂��B���������̋ƂȂ��āA���߂����ʂɔ��˂��A���̓��ʂ���܂��A�ׂ����[�U�[�r�[���̂悤�ɂ������̌�������������A�h�ꓮ���̂ł��B�������A���̂悤�ɂȂ鎞�Ԃ͂���قǒ����͂���܂���B���������\�����炢��������܂���B�ł��A���̂��ƂɋC�Â����肱�̂��Ƃ���ʂȂ悤�ɏ����͖̂l������������܂���A���̐l�͂��܂�C�ɂ��Ȃ��悤�Ȃ��Ƃƌ����Ă��܂�����܂łł��B�܂��A�������������Ԃ͏�ɒj���̓������Ԃ��Ǝv���܂��̂ŁA�����͂�������邱�Ƃ��ł��܂���B����͗�����ŗ����̂ɂ���������܂��B�F�͏����t���Ă���悤�ȋC�����܂���������������܂���B�I�V�͑嗁��ɕ��݂���Ă���^�ŁA�O�l���炢��������Ȃ����̂ƁA��l������ƂƂ������ɂʂ邢���̂̓�̗���������܂����B�����p�̖̘I�V���A����������l���O�l���炢��������܂���B���߂͖ؗ��œ��ɕ��I�ł͂���܂��A��͂藁�����������ł��Ȃ��̂��C�ɂȂ�܂����B���x�͑S�̓I�ɓK���������ƌ����Ă����Ǝv���܂��B�I�V�͂��ʂ�߂ł��B�H���́A���ɋÂ��������Ƃ����̂͂���܂���ł������A�S�̓I�ɂ��������A�t�H�A�O���A�n�}�O���i��A��̎h�g�Ȃǂ����ɂ��������Ǝv���܂����B�e�����Ƃ����ꂼ����̐H�����Œ��E�[�H�������l�ɂȂ��Ă���A���̐H�������������Ƒ����Ă��܂��B���H�͑S�̓I�ɉ��������������Ă��āA���ɂ��������ł��B�f�U�[�g�ɓ��ɂ����������������t���܂����B���H�Ƃ��Ă̊����x�͍����Ǝv���܂��B
 |
 |
 |
 |
���̓��͓��c������u���Â�v�ŁA����́u���ۑ��v�ɔ��܂�܂����B�u���ۑ��v�͂�낸��̌��X�̖{�ق������Ƃ���ŁA���a�S�N�i�H�j�Ɍ��Ă�ꂽ�Â������ł��B�Â������ŕ���������قǍL���͂Ȃ��A���ʑ䂪�L���̕Ћ��ɂ�������A�������e���r�������̋��̑�ɒu���Ă�������A�g�C�������������肵�܂����A���������܂��B�܂��A���ۑ��̊ٓ��S�̂����ɏ��������������̂ł��B���Â�ƌ����Γ��R���C�i�ʐ^�R�j�ł����A����͖l�̓����̃x�X�g�P�ŁA����͓�x�ڂȂ̂ł��̑O�قǂ̊����͂���܂���ł������A�x�X�g�P�Ƃ����͕̂ς��Ȃ��ł����Ǝv���܂��B�L�X�Ƃ��Ă��ď������A�����ł���̂ɂ��܂ł������邨���C�ł��B�܂��A�n���ɉ���������C�Ƃ����̂�����܂�����������Ɍ��������Ȋ��������܂��B�O�͑��V���C�i�ʐ^�R�j�ŁA�����ɂ���Ȃ��瓍�R���C�̌������O���璭�߂�̂��܂��������̂ł��B����́A���̖�V���C�͂�����Ƃʂ�߂ł����B���̖�V���C�͕��C�S�̂��뉀�ɂȂ��Ă���Ƃ������̂ł��ˁB��̂P�P���ɒj�����ł����A������́u���̂̂ߕ��C�v�͍���s���Ă݂���A�I�V���C�����Ă��āi���̑O�͂Ȃ������Ǝv���j���ꂢ�Ȃ����C�ɂȂ��Ă��܂����B�����Ɖ���������C��������ɂ��t���Ă��܂����B�I�V�́A���������L���āA���Ɉ͂܂�Ă͂��܂����A�킸���Ȃ���J���Ă��镔�������茋�\����������Ǝv���܂��B�W���O�W�[���t���Ă��āA���ʂ̗��ق�������\���Ȃ����C�ł��B�����͕����o���ŁA��i��i�^��ł���`�ł��B�⋛�̏Ă������������������̂ł����A���̕t�����킹�ŏo���ꂽ�I���A�������Ɍ����ł��ˁB���o����A�O�A�������A���z���͂�Ȃǖ����ł��܂����B�t�����`�̂悤�ɓr���ŃV���[�x�b�g���o�܂����B���H�������ŁA��͂��ʓI�Ȓ���H�Ƃ͂�����Ƃ������܂����A�������������ł��B�����䂪�o�܂����B
���n���������Ə��J����֍s���Ă��܂����B���n�ŏh�������̂́A�u�z�e���ܗ��فv�ł��B���n�̓y���V�����Ȃǂ������A�����������܂�w�̍����z�e���͂Ȃ��悤�ŁA���̌ܗ��ق̌܊K���Ă͂��Ȃ荂���ق��ł͂Ȃ��ł��傤���B�����̌܊K�ɏh���ł����̂ŁA��������̒��߂͔��ɂ悩�����ł��B�k�A���v�X�Ɣ��n�̃W�����v�䂪�����܂��B���n�̃z�e���̒��ł͒��߂͍ō��̕��ނł͂Ȃ��ł��傤���B�����͍��Ƃ��������ł͂���܂��A�P�O��ƍL���ŏ\���̍L���ł��B��͑ւ�������̂悤�ł����B�����̒��Ŗ������Ă���̂����Ɉ�ۓI�ł��̂ق������̂悤�ȗǂ�����͂��Ȃ蒷�������Ă��܂����B�嗁��(�ʐ^�P�j�́A���ɖ��邢��ۂ��܂��B���������������L�X���Ă��܂��B���n��������̓A���J���x���o�g�P�O�ȏ゠�邻���Ȃ̂ł����A����Ȃɂ͂Ȃ������ł���قǂʂ�ʂ�͂��Ă��܂���B�ł��A�k���X�x�ł��邱�Ƃ͊m���ł��B�����ʂƁA���ڂ��ʂ̍�������̂��A�����Ȃ���C�ɂȂ�܂������A���f�L�͂܂��������܂���B���̂ւ�̏ڂ����Ƃ���͂悭������܂���B�嗁��͓K���A�I�V�͂��ʂ�߂Ƃ������Ƃ���ł��B�I�V(�ʐ^�Q�j�͖k�A���v�X���ł͂���܂��A�����炵�͂悭�A�J����������܂��B���M���̂͌܁E�Z�l���������x�ŁA����قǍL���͂Ȃ��̂ł����A���M�̎���ɂ��Ȃ�X�y�[�X�̗]�T������̂ōL�X���Ă������ł��܂��B�����A���M�S�̂��������������Ă���̂ŁA���C�ɂ���Ȃ��琯�����邱�Ƃ͂ł��܂���B�[�H�́A�����̃J���p�b�`���A���ƃA�{�K�h�̃T���_�A��̏_���ρA�M�B���̂���Ԃ���Ԃ̏t�������ȂǂŁA�S�̓I�ɔ����ŁA�����D���̂ڂ��Ƃ��Ă͋C�ɓ���܂����B���Ă͎В������ʂɎ�����č���Ă�����̂Ƃ��ł��т����ɂ��������ł��B�^��ł���y�[�X���Ȃ��Ȃ��ǂ��������H�ׂ��܂��B���H�͈�ʓI�Ȓ���H�ŁA�[�H�قǂł͂���܂��A���������Ƃ����܂��B���̂��сi���āj�͗[�H�Ƃ͈���ĕ��ʂ̊����ł����B�C���h�l�̃R�b�N������炵���A�J���[�p�����t���̂��ς���Ă��܂��B�����߂������̂����X�g�����Ŕ����Ă���\�t�g�N���[���ł��B����͎|���I�I���ʂ̎�ނ̃\�t�g�̂͂��Ȃ̂ɁA�Ȃ����A�I�����W�ۂ��F�����Ă��܂��B���X�g�����ň��߂锒�n�̐������ɂ��������ł��ˁB�]�ƈ��̊������悩�����ł��B
 |
 |
 |
 |
����ڂ͏��J����́u���ٓȂ̎����v�ł��B���������Ńp���t���b�g������@��������琥��A���ق̎ʐ^�����Ă��������B�u�i�̐X�̒��̈ꌬ�h�̔铒�Ƃ������͋C�ł��B�ł��A����͂�����Ƃ��������邾���ŁA���ۂ͐X�̒��ɂۂ�Ƃ����ł��A�ꌬ�h�Ƃ�����ł�����܂���B�����͂P�O��ƍL���i�T�����A���̂����������̊ԁj�@�ŐV�����̂ł����A���������|���̈ӏ��ŗ������������������܂��B�����ɂ����C�͂���܂���B�嗁��͓K���A�I�V�͂��ʂ�߂������̂ł����A�����͂��ꂪ�t�]���Ă��������ł����B����(�ʐ^�R�j�́A�����`�̕�����^�ŕ����āA��O��������A��̔����������Ƃ��������ŁA���͈�ʂɂ����Ȃ��������������܂����B�S�̂łP�R�������Ȃ��̂ŁA�܂��A�\���ł͂Ȃ��ł��傤���B���̑嗁��̗����̒���ʂ��ĊO�̘I�V(�ʐ^�S�j�֍s���Ƃ����`�ł��B�I�V�́A�Έ݂͂̎l�p�����M�ŁA���x�嗁��̗����Ɠ������炢�̍L���ł��傤���B�����̘I�V�Ƃ̋�������̂ł����A�قƂ�ǎO���ɊJ���Ă���Ƃ����Ă����Ǝv���܂��B������J���Ă��ĊJ�����Ɋւ��Ă͉����������Ƃ͂���܂���B�ڂ̑O�ɖX�����Ȃ�����A���ɖ��邢�������܂��B�I�V���C�͒�ɂ��銴���ŁA�ڂ̑O�̎��R�ɂȂ����Ă��܂��B�L������ڂɐ��݁A�����ɂ����̓��͉J�Ɩ��Ŏ��E�������ꂪ���ł������A�������ꂽ���ɂ͉����̎R�����ʂ��܂����B�����A�c�O�Ȃ���A�����̘I�V�́A�O�����͂܂�Ă��Ă��܂蒭�߂͂Ђ炯�Ȃ��悤�ł��B�����͓����ł���قǂʂ���Ƃ��������͂���܂���B����炵���̂ł����S�R������ς��Ȃ��̂͂ǂ����ĂȂ�ł��傤���B�������A�������ɉ��������āA��͂�ƂĂ��������܂邨���ł��B�[�H�͔��ɂ��������B�R�ؒ��S�ł����A�ǂ̎R�����ׂĂ����������ׂ����܂��B�Ñ�̏Ƃ�Ă��A�R�Ƃ���g�̗g�����A�n�{�̎R���Ă����������i�ł��B���ɁA�Ñ�̏Ƃ�Ă��͂��Ȃ�̂��̂Ǝv���܂����B���X�`�����������ł��B��i���낢�ƌ����Ă����H�����Ǝv���܂����B�Ȃ̎������x���̃��C��������̂ł����A�Q�O�O�O�~�ƌ������ƂȂ��̈����ł��B���͂������������܂���B���H����͂�R�ؒ��S�ł����A����܂������낢�B�ʎq�Ă����g���o�����������ɂ����������̂ł����B�Ă�������������Ƃ����̂��ς���Ă��܂����A����܂����������B���炵���H���ł����B�Ƃ������ƂœȂ̎����́A�ڂ��̍ō��]���̏h�̈�ɂȂ�܂����B�R�X�g�p�t�H�[�}���X��S�̂̊����x���炢������A�ō������m��Ȃ��Ǝv���܂��B�x�z�l�̐������B�A���R�[���ނ̈����B�����̎|���B�I�V���C�̌i�F�́A���]�ƌ����_���炢�����܂łōō��Ƃ����킯�ɂ͂����܂��A�̒��ɗn�����݂����ȓ_�ł́A���܂łł��ō��̕��ނł͂Ȃ������ł��傤���B�T�[�r�X�Ɋւ��Ă��������Ƃ͂���܂���B�������������B�����̏]�ƈ��̂����������̓��͑S�����܂���ł������A���Ȃ��킯�ł͂Ȃ������ł��B��������������܂���B
| �ԓ������Ɣ��z����ɍs���Ă��܂����B�ԓ�����́u����������̏h��g�v�ł��B�ԓ��֍s���Ȃ��͂�܂����̗��قƎv���Ă��܂����B�����͂������̓�����Ȃ��Ă���炵���A�ʂ��ꂽ�͉̂��̍ד����Ƃ����A���Ȃ�Â������̈�K�̈ꎺ�ł����B���́u���̏��R�v�Ƃ��������́A����Ȃɋ������Ȃ��A�܂��V�������ׂ��Ƃ���͐V�������A�Â������͂ɂȂ��Ă���Ƃ���͂�����Ǝc���Ƃ����A�o�����X�̂Ƃꂽ�����ŁA�l�͔��ɋC�ɓ���܂����B����̘a���Ɏl�炢�̍L�������Ă��镔���ł����A�V��������A�O���̓炢���O�~���~���ꂽ�L�����L�X�Ƃ��āA�֎q����͗h��֎q���p�ӂ���Ă���ȂǁA���낰�܂����B�m���ɐ��ʏ��ƃg�C�����ꏏ�ɂȂ��Ă��܂��B�ƌ����Ă��A�������ƃX�y�[�X���Ƃ��Ă��܂��B���̕�������̒��߂͒r�ł����B |
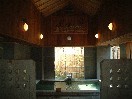 �����C�͍ŋߐV���������悤�ŁA��g�ƌ����A�傫�ȗ�����^�Œj���Ɏd���������Ƃ����C���[�W���������̂ł����A�c�O�Ȃ��炻�̂����C�͂ǂ��ɂ�����܂���ł����B�����͖�̂W���ɒj�������ւ���A��㐧�ł��B�Q�S���ԓ����ł��܂��B���Ԃ̒j���p�̂����C�͐Q�������߁A�������̗���������L�X�Ƃ������̂ł����B������ɂ͓����̊O�ɑ傫�Ȋ������ʂ����Ƃ����I�V���C������܂��B�^�ł����Ă��܂����A�S���łW�l���炢�͂����ł��傤���B�I�V���C�͎�����������茚���ň͂܂�Ă��܂����A��Ԃɂ�Ƃ肪����̂ŁA����Ȃɋ����Ȋ����͎܂���B�������Ƃ����ɂ���܂��B�����̏�ɉ��������Ă��܂����A�K���X�̓V���ɂȂ��Ă���̂ŁA�S�̂ɖ��邢��ۂ��܂��B�����͏���������ς������ł��B�������炨��������o���Ă��܂����A��ɂ�����ꍞ�ނ����Ɨ���o�������̃o�����X���H�ł��B�ł��A���f�L�Ȃǂ͂��܂���B �����C�͍ŋߐV���������悤�ŁA��g�ƌ����A�傫�ȗ�����^�Œj���Ɏd���������Ƃ����C���[�W���������̂ł����A�c�O�Ȃ��炻�̂����C�͂ǂ��ɂ�����܂���ł����B�����͖�̂W���ɒj�������ւ���A��㐧�ł��B�Q�S���ԓ����ł��܂��B���Ԃ̒j���p�̂����C�͐Q�������߁A�������̗���������L�X�Ƃ������̂ł����B������ɂ͓����̊O�ɑ傫�Ȋ������ʂ����Ƃ����I�V���C������܂��B�^�ł����Ă��܂����A�S���łW�l���炢�͂����ł��傤���B�I�V���C�͎�����������茚���ň͂܂�Ă��܂����A��Ԃɂ�Ƃ肪����̂ŁA����Ȃɋ����Ȋ����͎܂���B�������Ƃ����ɂ���܂��B�����̏�ɉ��������Ă��܂����A�K���X�̓V���ɂȂ��Ă���̂ŁA�S�̂ɖ��邢��ۂ��܂��B�����͏���������ς������ł��B�������炨��������o���Ă��܂����A��ɂ�����ꍞ�ނ����Ɨ���o�������̃o�����X���H�ł��B�ł��A���f�L�Ȃǂ͂��܂���B |
 �u���C�v�Ƃ����̂�����܂������A��������Ƃ���ȊO�̂����͌���̂܂܂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤���B������̂����C�ɑ��A���̏����p�̂����C�́A�c�O�Ȃ���I�V������܂���B�����������͐Q���Ƃӂ��̗��������Ȃ��A�j���ł��Ȃ�o�����X�̈����\���ƂȂ��Ă��܂��B�Ⴆ�A�J�b�v�����オ�鎞�Ԃ𑵂��悤�Ƃ���ƁA����͂Ȃ��Ȃ��オ�ꂸ�A��������͂����ɏオ���Ă��Ă��܂��Ƃ��������ɂȂ��Ă��܂��ł��傤�ˁB�l�Ƃ��Ă͘I�V���C��������Ȃ��Ƃ������ƂŁA�啝���_�ł��B�܂��A���̑S�̓I�ɌÂ��C���[�W�̗��قƂ��ẮA�ǂ������̐V���������C�͍���Ȃ����������܂��B�[�H�͕����ŁA�����̔��V���^��Ă��܂��B���V�͑傫���Ă��Ȃ�d�������Ȃ̂ł����A�v�͏ゾ���ŁA���ɂ͉��������Ă��܂���B�R������ނ��������ڂ����Ă��܂��B�R�̕��ɂ͂����ł���B�ڂ��́u�͂��`�A���ꂪ�s�҂ɂ�ɂ����v�Ə��߂Ă܂��܂��ƌ��Ĕ[�����܂����B���C���͂�͂艽�ƌ����Ă��đ̃X�e�[�L�ł��B�h�g�͋��͏o���A���h�������ł��B���}�X�̏����������ɂ������������ł��B�Ō�̂��т́A�Ă����ɂ���ł���������̖����ɂȂ��Ă���悤�ł��B�S�̓I�ɂ��������Ǝv���܂����A���ɉ��i���A���ɂ��ȂǁA�N�Z�̂��閡�t���̂��̂��ł܂��̂ŁA�������������̂����Ȑl�͈�ۂ�������������܂���B���H�͂�͂薼���́u�����v�ł��B�H�����łV�F�S�T���玝�������s���A���̌�Łu�G�ρv�u�������v�u����݂����v�u���낵�����v�u�[�������v�Ȃǂ��ӂ�܂��܂��B�����͉���������Ă������̂ł����A�����ȊO�͂قƂ�ǐH�ׂ���̂�����܂���B�������̂��A�܂����͂���܂��A�i�ʂ��������Ƃ����قǂ̂��̂ł��Ȃ��A�ڂ��̂��̒��H�Ɋւ���]���͒Ⴂ���̂ł��B �u���C�v�Ƃ����̂�����܂������A��������Ƃ���ȊO�̂����͌���̂܂܂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤���B������̂����C�ɑ��A���̏����p�̂����C�́A�c�O�Ȃ���I�V������܂���B�����������͐Q���Ƃӂ��̗��������Ȃ��A�j���ł��Ȃ�o�����X�̈����\���ƂȂ��Ă��܂��B�Ⴆ�A�J�b�v�����オ�鎞�Ԃ𑵂��悤�Ƃ���ƁA����͂Ȃ��Ȃ��オ�ꂸ�A��������͂����ɏオ���Ă��Ă��܂��Ƃ��������ɂȂ��Ă��܂��ł��傤�ˁB�l�Ƃ��Ă͘I�V���C��������Ȃ��Ƃ������ƂŁA�啝���_�ł��B�܂��A���̑S�̓I�ɌÂ��C���[�W�̗��قƂ��ẮA�ǂ������̐V���������C�͍���Ȃ����������܂��B�[�H�͕����ŁA�����̔��V���^��Ă��܂��B���V�͑傫���Ă��Ȃ�d�������Ȃ̂ł����A�v�͏ゾ���ŁA���ɂ͉��������Ă��܂���B�R������ނ��������ڂ����Ă��܂��B�R�̕��ɂ͂����ł���B�ڂ��́u�͂��`�A���ꂪ�s�҂ɂ�ɂ����v�Ə��߂Ă܂��܂��ƌ��Ĕ[�����܂����B���C���͂�͂艽�ƌ����Ă��đ̃X�e�[�L�ł��B�h�g�͋��͏o���A���h�������ł��B���}�X�̏����������ɂ������������ł��B�Ō�̂��т́A�Ă����ɂ���ł���������̖����ɂȂ��Ă���悤�ł��B�S�̓I�ɂ��������Ǝv���܂����A���ɉ��i���A���ɂ��ȂǁA�N�Z�̂��閡�t���̂��̂��ł܂��̂ŁA�������������̂����Ȑl�͈�ۂ�������������܂���B���H�͂�͂薼���́u�����v�ł��B�H�����łV�F�S�T���玝�������s���A���̌�Łu�G�ρv�u�������v�u����݂����v�u���낵�����v�u�[�������v�Ȃǂ��ӂ�܂��܂��B�����͉���������Ă������̂ł����A�����ȊO�͂قƂ�ǐH�ׂ���̂�����܂���B�������̂��A�܂����͂���܂��A�i�ʂ��������Ƃ����قǂ̂��̂ł��Ȃ��A�ڂ��̂��̒��H�Ɋւ���]���͒Ⴂ���̂ł��B |
| �@ |
 ����ڂ́A���z����́u�����v�ł��B�Â��̂Ȃ���̗��ق������̂��A2�N���R�N���O�ɁA�Ύ��ŔR���Ă��܂�����ł��ˁB���̍��̗��ق̂������܂��ȂǁA�l�͒m��Ȃ��̂ł����A����s���Ă݂���A�u�����ȏh�v�ɂȂ��Ă����Ƃ�����ۂł��B�铒���ۂ��Ƃ���́A�����ɂ����c���Ă��Ȃ������ł����B�ʂ��ꂽ�̂́A���H�������オ���Č��ււ����铹�ɂ���A���h�Ȏ}�U��̏��̖�ڂ̑O�ɂ���A�u�j�R�v�Ƃ��������ł����B8��̎厺�ƂS�����̎��̊Ԃ��t���������ł��B�o�X�͗m���̉����̂��̂ł������A�g�C���͉����ł͂�����̂́A�V�����[�g�C���ł͂���܂���ł����B�����C�͒j�����ł͂Ȃ��A���ꂼ���p�̂��̂�����܂��B�����E�ߏ���������ƘI�V�ɍs���Ƃ����`���ł����i�j���j�B�����͑����O�ƕς���Ă��Ȃ����낤�Ǝv�킹��A���ɕ��͋C�̂�����̂ł����B�M������̒������ޏ��Ԃ�ȓ��M�ƁA�����Ƃ��납�琨���ǂ��~�蒍���ł�����������ł��āA���ꂼ��̓��M���炠�ӂꂽ�������A����ɑ傫�ڂ̓��M�ɗ��ꍞ�ނƂ����`���ł��ˁB���̈�A�̗���ɂ͂܂��������ʂ��Ȃ��A����ɂ��̓��M�����̕��ցA�ɂ��݂Ȃ����������o���Ă��܂��B�o�邨���ƁA�������ނ����̃o�����X�ȂǍl����܂ł��Ȃ��A�u����I���ꂱ���w������x�̂������I�v�Ƃ����A����u�ǂ����n�v�̂����ł��ˁB�V��������A��������悤�ɍH�v����Ă��邢�������ł��B�����͑S�̂ɔM�߂ł����A���ԑтɂ���ď������x��������悤�ȋC�����܂����B ����ڂ́A���z����́u�����v�ł��B�Â��̂Ȃ���̗��ق������̂��A2�N���R�N���O�ɁA�Ύ��ŔR���Ă��܂�����ł��ˁB���̍��̗��ق̂������܂��ȂǁA�l�͒m��Ȃ��̂ł����A����s���Ă݂���A�u�����ȏh�v�ɂȂ��Ă����Ƃ�����ۂł��B�铒���ۂ��Ƃ���́A�����ɂ����c���Ă��Ȃ������ł����B�ʂ��ꂽ�̂́A���H�������オ���Č��ււ����铹�ɂ���A���h�Ȏ}�U��̏��̖�ڂ̑O�ɂ���A�u�j�R�v�Ƃ��������ł����B8��̎厺�ƂS�����̎��̊Ԃ��t���������ł��B�o�X�͗m���̉����̂��̂ł������A�g�C���͉����ł͂�����̂́A�V�����[�g�C���ł͂���܂���ł����B�����C�͒j�����ł͂Ȃ��A���ꂼ���p�̂��̂�����܂��B�����E�ߏ���������ƘI�V�ɍs���Ƃ����`���ł����i�j���j�B�����͑����O�ƕς���Ă��Ȃ����낤�Ǝv�킹��A���ɕ��͋C�̂�����̂ł����B�M������̒������ޏ��Ԃ�ȓ��M�ƁA�����Ƃ��납�琨���ǂ��~�蒍���ł�����������ł��āA���ꂼ��̓��M���炠�ӂꂽ�������A����ɑ傫�ڂ̓��M�ɗ��ꍞ�ނƂ����`���ł��ˁB���̈�A�̗���ɂ͂܂��������ʂ��Ȃ��A����ɂ��̓��M�����̕��ցA�ɂ��݂Ȃ����������o���Ă��܂��B�o�邨���ƁA�������ނ����̃o�����X�ȂǍl����܂ł��Ȃ��A�u����I���ꂱ���w������x�̂������I�v�Ƃ����A����u�ǂ����n�v�̂����ł��ˁB�V��������A��������悤�ɍH�v����Ă��邢�������ł��B�����͑S�̂ɔM�߂ł����A���ԑтɂ���ď������x��������悤�ȋC�����܂����B |
 �j���̘I�V�́A�E�ߏ��̂��������ɂ���܂��B�������̂͂P�T�l���x�̋K�͂��ȂƎv���܂����A���Ȃ�L�X���Ă��܂��B���M����ԒႢ�Ƃ���ɂ���A���͂̕��������Ƃ����u�A���n���`�v�̘I�V�ŁA�����܂������ł����A�J���J���Ƃ�̓��ɂ̓L�c�C�I�V�ł��B���̏o���Ȃ��I�V�̌����Ȃڂ��́A���̓��͓����ɂ͂قƂ�Ǔ��炸�A�����X���Ă���������y���݂܂����B�J�����͂R�U�O�x�߂��ƌ����Ă����Ǝv���܂��B���̗т����Ȃ�����邱�Ƃ��o���܂��B�����A����\����Ȃ��̂ł����A�����p�̘I�V�͂���ȂɍL���͂Ȃ��A�J���������܂�Ȃ��悤�ł��B�������I�V���Q�S���Ԃ��ł�����܂��B�p��Ƃ������Ƃł������A�Ȃ����������ۂ������������Ɏc��܂��B�܂��A���M�����Ė������܂�����o���܂���ł����B����̓��������Ă��܂������A�l�̍D���Ȃ��̃R���R���Ƃ��������ł͂���܂���ł����B�Ƒ����C�́A�����^�C�v�̂��̂���A�╗�C�Ƃ������I�V�^�C�v�̂��̂������܂��B���̊╗�C�͕��͋C�������Ă����߂ł��B�H���͌��֘e�̐H�����Ŗ���������������܂��B���̓��̖�́A�đ̃r�[�t�V�`���[�����C���ɁA�R�ؓ�A�֎q�̎ϕ��A�⋛�̏Ă����Ȃǂł����B��͂�A���߂ɂقƂ�ǂ����ׂ��Ă��܂��^�ŁA�⋛�Ȃǂ͗�߂Ă��܂��Ă��܂��B�铒�̏h�Ƃ��Ă͍��i�_�ł͂Ȃ��ł��傤���B�r�[�t�V�`���[�Ȃǂ��������t���ł����B���́A�܂���ʓI�Ȓ���H�ƌ����Ă����ł��傤�B�����A���͒��q�����ɂȂ�܂��B���q���̏o�����A�����Ƃ����Ƃ��������܂������A�S�̓I�ɂ������������ł��B�V���[�x�b�g�̃f�U�[�g���o�܂����B�铒�̏h�ł��̂ŁA�����s������T�[�r�X�͂��܂���҂��Ȃ��Ƃ���A���Ȃ薞���x�͍����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �j���̘I�V�́A�E�ߏ��̂��������ɂ���܂��B�������̂͂P�T�l���x�̋K�͂��ȂƎv���܂����A���Ȃ�L�X���Ă��܂��B���M����ԒႢ�Ƃ���ɂ���A���͂̕��������Ƃ����u�A���n���`�v�̘I�V�ŁA�����܂������ł����A�J���J���Ƃ�̓��ɂ̓L�c�C�I�V�ł��B���̏o���Ȃ��I�V�̌����Ȃڂ��́A���̓��͓����ɂ͂قƂ�Ǔ��炸�A�����X���Ă���������y���݂܂����B�J�����͂R�U�O�x�߂��ƌ����Ă����Ǝv���܂��B���̗т����Ȃ�����邱�Ƃ��o���܂��B�����A����\����Ȃ��̂ł����A�����p�̘I�V�͂���ȂɍL���͂Ȃ��A�J���������܂�Ȃ��悤�ł��B�������I�V���Q�S���Ԃ��ł�����܂��B�p��Ƃ������Ƃł������A�Ȃ����������ۂ������������Ɏc��܂��B�܂��A���M�����Ė������܂�����o���܂���ł����B����̓��������Ă��܂������A�l�̍D���Ȃ��̃R���R���Ƃ��������ł͂���܂���ł����B�Ƒ����C�́A�����^�C�v�̂��̂���A�╗�C�Ƃ������I�V�^�C�v�̂��̂������܂��B���̊╗�C�͕��͋C�������Ă����߂ł��B�H���͌��֘e�̐H�����Ŗ���������������܂��B���̓��̖�́A�đ̃r�[�t�V�`���[�����C���ɁA�R�ؓ�A�֎q�̎ϕ��A�⋛�̏Ă����Ȃǂł����B��͂�A���߂ɂقƂ�ǂ����ׂ��Ă��܂��^�ŁA�⋛�Ȃǂ͗�߂Ă��܂��Ă��܂��B�铒�̏h�Ƃ��Ă͍��i�_�ł͂Ȃ��ł��傤���B�r�[�t�V�`���[�Ȃǂ��������t���ł����B���́A�܂���ʓI�Ȓ���H�ƌ����Ă����ł��傤�B�����A���͒��q�����ɂȂ�܂��B���q���̏o�����A�����Ƃ����Ƃ��������܂������A�S�̓I�ɂ������������ł��B�V���[�x�b�g�̃f�U�[�g���o�܂����B�铒�̏h�ł��̂ŁA�����s������T�[�r�X�͂��܂���҂��Ȃ��Ƃ���A���Ȃ薞���x�͍����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |
| �������ɍs���Ă��܂����B����͑䕗�Ƃ̋����Ƃ��������ŁA�y�������ɂ͍K���ɖl�̕����撅���āA�����ɗ��قɓ��邱�Ƃ��ł��܂����B�u����v�͓y������̒��ł͑傫�ȗ��ق��Ǝv���܂����A�S�̓I�Ȉ�ۂƂ��ẮA���Â��Ȃ������قƂ��������ł����B�����͂W��ŁA�����ȍL�������Ă��܂��B�֎q����r����܂����A���̈֎q�̂Ƃ��낾������i�Ⴍ�Ȃ��������̍��ŁA�S�̓I�ɋ�����ۂ��܂����B�������A�����ɕ��C�����Ă��܂��B��������̒��߂́A���ɍr��̗��ꂪ���߂��A���傤�ǐ삪�Ȃ���Ƃ���ɓ�����̂ŁA�ω��ɕx���߂ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A�т���̕��ւ��肾�����`�ɂȂ��Ă��āA�����Ȃǂ����������߂͗ǂ��ƌ����܂��B |
 ���C�͐[���1���`3�����x�݂ł��̊Ԃɒj������サ�܂��B�嗁��͒j���Ƃ������悤�ȍ��ŁA���ɍג����g�^�̃J�[�u��`���Ă��܂��B�I�V�͓����̒j���p�͊╗�C���㉺�ɓ����A��̕����牺�ւƂ��������ꍞ�ތ`�ɂȂ��Ă��܂��B�������A���̊╗�C�̃��C���͗����̒�����N���o�������ł��B���̓�̊╗�C�̂����ɂ͒��F�ۂ��ׂ��ȓ��̉Ԃ������Ă��܂����B�y������͑S�̓I�ɓ��ʂ͖L�x�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̊╗�C�̊O�ɁA�g��ꂸ�ɗ]�����������ɂ��݂Ȃ��p�C�v���痬��o�Ă��܂����B�Ƃ������ƂŁA���̓�̊╗�C�͊��S�ɗ����肾�Ǝv���܂��B�����A�������Ă��邱�Ƃ��m���ł��B���ق̏]�ƈ��������Ђ˂��ĉ��x���߂����Ă��܂����B ���C�͐[���1���`3�����x�݂ł��̊Ԃɒj������サ�܂��B�嗁��͒j���Ƃ������悤�ȍ��ŁA���ɍג����g�^�̃J�[�u��`���Ă��܂��B�I�V�͓����̒j���p�͊╗�C���㉺�ɓ����A��̕����牺�ւƂ��������ꍞ�ތ`�ɂȂ��Ă��܂��B�������A���̊╗�C�̃��C���͗����̒�����N���o�������ł��B���̓�̊╗�C�̂����ɂ͒��F�ۂ��ׂ��ȓ��̉Ԃ������Ă��܂����B�y������͑S�̓I�ɓ��ʂ͖L�x�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̊╗�C�̊O�ɁA�g��ꂸ�ɗ]�����������ɂ��݂Ȃ��p�C�v���痬��o�Ă��܂����B�Ƃ������ƂŁA���̓�̊╗�C�͊��S�ɗ����肾�Ǝv���܂��B�����A�������Ă��邱�Ƃ��m���ł��B���ق̏]�ƈ��������Ђ˂��ĉ��x���߂����Ă��܂����B |
 �I�V�͌����̈ꕔ��I�V�ɂ����Ƃ����`�ŁA���S�ɏ�ɂ͉��������Ă���A��ʂ����J���Ă��Ȃ��̂ł����A�i�F���������Ƃ�����A�܂��A���ɍL���̂Ŋ��ƊJ�����͂���܂��B�����́A���̃^�C�v�̘I�V�͑S�R�D���ł͂Ȃ��̂ł����A����Ɍ����Ă͉J���S�R�ӂ肱�܂��A��������قǐ����t���Ȃ��̂ŁA���ɍD�s���ł����B�嗁��̂����ɂ͓��̉Ԃ͂܂���������ꂸ�A���̂ւ�̗����͂悭�킩��܂���B�H���́A������x��ɕ��ׂ��A��Œg�������̌n�̂S�i���炢����C�ɉ^���Ƃ����`���ł��B�S�̓I�ɂ��������{�����[��������Ǝv���܂��B���ɁA�Ō�̂킢�͂�`�͂��������Ǝv���܂��B���т͐H�ׂ���Ȃ������炨�ɂ���ɂ��Ă���܂��B�����A�[�H�͗ǂ������̂ł����A�����̃o�C�L���O�́H�ł����B�܂��A�o�C�L���O�̗e�킪�S���v���X�`�b�N���ł��������ƁB�d���Ȃ�Ȃ��悤�ɂƂ����z��������Ǝv���̂ł����A�n��Ȋ����ł���͂�����Ɣ[���ł��܂���ł����B�R�b�v�܂Ńv���X�`�b�N�ł��B����ɁA��ԏd��Ȃ̂͏]�ƈ����q�ƈꏏ�ɂȂ��Ď����̒��H���M�ɐ���t���Ă����ł��B���߂́A���̕s���R�ȋq�̕ς��Ɏ���Ă����Ă���̂��Ǝv���܂������A���̂܂܍T�����̂悤�ȂƂ���ɏ����čs���܂����B�o�C�L���O�̗����̖��͂���قLj����͂���܂���ł������A�ʕ��A�W���[�X�ނ͂���܂���ł����B�����̗␅�͂��邵�A�����ɂ��`�F�b�N�C��������␅�|�b�g������A�܂��A�킴�킴�����ĂR���̃o�X��܂Ō}���ɂ��Ă���A�`�F�b�N�C���O�ł������ɒʂ��Ă����ȂǁA�]�����ׂ��Ƃ��������̂ɁA��̓�_�͔��Ɏc�O�ł����B �I�V�͌����̈ꕔ��I�V�ɂ����Ƃ����`�ŁA���S�ɏ�ɂ͉��������Ă���A��ʂ����J���Ă��Ȃ��̂ł����A�i�F���������Ƃ�����A�܂��A���ɍL���̂Ŋ��ƊJ�����͂���܂��B�����́A���̃^�C�v�̘I�V�͑S�R�D���ł͂Ȃ��̂ł����A����Ɍ����Ă͉J���S�R�ӂ肱�܂��A��������قǐ����t���Ȃ��̂ŁA���ɍD�s���ł����B�嗁��̂����ɂ͓��̉Ԃ͂܂���������ꂸ�A���̂ւ�̗����͂悭�킩��܂���B�H���́A������x��ɕ��ׂ��A��Œg�������̌n�̂S�i���炢����C�ɉ^���Ƃ����`���ł��B�S�̓I�ɂ��������{�����[��������Ǝv���܂��B���ɁA�Ō�̂킢�͂�`�͂��������Ǝv���܂��B���т͐H�ׂ���Ȃ������炨�ɂ���ɂ��Ă���܂��B�����A�[�H�͗ǂ������̂ł����A�����̃o�C�L���O�́H�ł����B�܂��A�o�C�L���O�̗e�킪�S���v���X�`�b�N���ł��������ƁB�d���Ȃ�Ȃ��悤�ɂƂ����z��������Ǝv���̂ł����A�n��Ȋ����ł���͂�����Ɣ[���ł��܂���ł����B�R�b�v�܂Ńv���X�`�b�N�ł��B����ɁA��ԏd��Ȃ̂͏]�ƈ����q�ƈꏏ�ɂȂ��Ď����̒��H���M�ɐ���t���Ă����ł��B���߂́A���̕s���R�ȋq�̕ς��Ɏ���Ă����Ă���̂��Ǝv���܂������A���̂܂܍T�����̂悤�ȂƂ���ɏ����čs���܂����B�o�C�L���O�̗����̖��͂���قLj����͂���܂���ł������A�ʕ��A�W���[�X�ނ͂���܂���ł����B�����̗␅�͂��邵�A�����ɂ��`�F�b�N�C��������␅�|�b�g������A�܂��A�킴�킴�����ĂR���̃o�X��܂Ō}���ɂ��Ă���A�`�F�b�N�C���O�ł������ɒʂ��Ă����ȂǁA�]�����ׂ��Ƃ��������̂ɁA��̓�_�͔��Ɏc�O�ł����B |
| �@ |
 ����ڂ͌�������u�R�[���T���v�ł��B�����͂W��̎厺�ƂS�����̎��̊ԂɍL�������Ă��܂��B���ʑ����ʂ���L�X�Ƃ��Ă��܂����B���߂͐����Ƃ��̌������ɋu�˂��L�����Ă��܂��B�Ƃ͂���ق�Ƃ���܂����A�����̂ł̂������Ƃ������Ƃ͂���܂���B��������A�`�F�b�N�C���O�̎��Ԃɕt�����̂ł����A�w�܂Ō}���ɗ��Ă���A�����ɕ����Ɉē����Ă���܂����B�����ŏ��߂Čo���������Ƃł����A�����W���ē�����O�Ƀt�����g���q�̗��߂̃T�C�Y�f���A�A�����āA���炩���ߕ����ɂ��̃T�C�Y�̗��߂�p�ӂ��Ă����炵���̂ł��B����ɂ͊��S���܂����B���������łɕ����ɗ␅�|�b�g���p�ӂ���Ă��܂����B�����C�͂Q�S����OK�ŁA�j���̌��͂���܂���B�����}����l����ƁA�L���͑S�������̂悤�ł��B�L�߂ł����A�嗁��͂��Ȃ蓒�C���������Ă��܂����B ����ڂ͌�������u�R�[���T���v�ł��B�����͂W��̎厺�ƂS�����̎��̊ԂɍL�������Ă��܂��B���ʑ����ʂ���L�X�Ƃ��Ă��܂����B���߂͐����Ƃ��̌������ɋu�˂��L�����Ă��܂��B�Ƃ͂���ق�Ƃ���܂����A�����̂ł̂������Ƃ������Ƃ͂���܂���B��������A�`�F�b�N�C���O�̎��Ԃɕt�����̂ł����A�w�܂Ō}���ɗ��Ă���A�����ɕ����Ɉē����Ă���܂����B�����ŏ��߂Čo���������Ƃł����A�����W���ē�����O�Ƀt�����g���q�̗��߂̃T�C�Y�f���A�A�����āA���炩���ߕ����ɂ��̃T�C�Y�̗��߂�p�ӂ��Ă����炵���̂ł��B����ɂ͊��S���܂����B���������łɕ����ɗ␅�|�b�g���p�ӂ���Ă��܂����B�����C�͂Q�S����OK�ŁA�j���̌��͂���܂���B�����}����l����ƁA�L���͑S�������̂悤�ł��B�L�߂ł����A�嗁��͂��Ȃ蓒�C���������Ă��܂����B |
 �������A�嗁��̊O�̈�p��I�V�ɂ��Ă���Ƃ����`���ł��B�������̎��͉J���オ���Ă����̂ŁA�L�X�Ƃ������O�̘I�V�̕����ǂ������̂ł����A�c�O�Ȃ��炻���ł͂���܂���ł����B�������A���̘I�V�͂S�l��������ς��ɂȂ��Ă��܂������Ȋ����ŁA���������傫����Ƃ肪�ق����Ǝv���܂����B���̘I�V�͏z�炵���A�܂������O�ɂ���������o���Ƃ��낪����܂���B�����x�͊��Ƃ���̂ł����A�������Ȃǂ͂�����ŊO�ɏo���Ȃ�����A���������ł��B�I�V����ł͂Ȃ��A���������ꍞ�݂�����܂���B�����Č����Αł���������{�����Ă��܂����̂ŁA���ꂪ���ꍞ�݂ƌ����Ό�����̂ł����A�������ɉ��f�L�������悤�ȋC�����܂��B�Ƃɂ����z�ł��邱�Ƃ͊m���ŁA�c�O�ł����B�����A�ł������̂�����������ƂȂ߂Č����̂ł����A�Ö��������Ă������������̂��ӊO�ł����B����菈�ɂ́A�����ƃ������̓������␅���p�ӂ���Ă��܂������A��x���ɂ͕Еt�����Ă��܂����B�����͖l�̍D���Ȉ�i��i�^�ł͂Ȃ��A�قƂ�Ǎŏ��ɕ��ׂ��Ă��܂��܂��B�Ƃ����Ă��A���̒��ɉ����������͂Ȃ��̂ʼn��������̂���߂Ă��܂��Ƃ����S�z�͂Ȃ��̂ł����B���������̂͗B��ォ��o����钃�q�����A���т̎��̂��z�����ƁA�e�[�u���ʼn��g���u���Ă��v�Ɓu��v�����ł����B��i��i�̗ʂ����߂ŁA�m�M������A���Ȃ薞����������܂��B�ӂ��Ђ�̓��������q������A�����A�ɐ��C�V�̃}���l�H�ȂǁA���ׂĂ̗������������������ƌ����Ă����Ǝv���܂��B�������A���i�������Ȃ��A�����̐������܂������Ȃ��̂����������܂���B���H�������o���ŁA���M�����߂ɕ��ׂ���Ƃ����^�ł��B��͂肨�������̂ł����A�قƂ�Ǐݖ����g�����̂ŁA���Ȃ育�т��i��ł��܂��܂��B�����ŏo���ꂽ���͐��L�݂��Ȃ��A���Ȃ肨���������̂ł����B�����W�̓x�e�����炵�������ƎႢ���̎q�̓�l��g�ł����B������̎������̏�����l�ƃt�����g�̒j���ꖼ�������J�ɍŌ�܂ʼn�X�����̂��߂Ɏ��U���Ă���Ă��܂����B���}�������̂悤�ŁA�܂��A�߂��ɂ���o���ق̂����C�ɂ����}�t���œ����ȂǁA�T�[�r�X�ʂł͂��Ȃ�]�����Ă����Ǝv���܂��B �������A�嗁��̊O�̈�p��I�V�ɂ��Ă���Ƃ����`���ł��B�������̎��͉J���オ���Ă����̂ŁA�L�X�Ƃ������O�̘I�V�̕����ǂ������̂ł����A�c�O�Ȃ��炻���ł͂���܂���ł����B�������A���̘I�V�͂S�l��������ς��ɂȂ��Ă��܂������Ȋ����ŁA���������傫����Ƃ肪�ق����Ǝv���܂����B���̘I�V�͏z�炵���A�܂������O�ɂ���������o���Ƃ��낪����܂���B�����x�͊��Ƃ���̂ł����A�������Ȃǂ͂�����ŊO�ɏo���Ȃ�����A���������ł��B�I�V����ł͂Ȃ��A���������ꍞ�݂�����܂���B�����Č����Αł���������{�����Ă��܂����̂ŁA���ꂪ���ꍞ�݂ƌ����Ό�����̂ł����A�������ɉ��f�L�������悤�ȋC�����܂��B�Ƃɂ����z�ł��邱�Ƃ͊m���ŁA�c�O�ł����B�����A�ł������̂�����������ƂȂ߂Č����̂ł����A�Ö��������Ă������������̂��ӊO�ł����B����菈�ɂ́A�����ƃ������̓������␅���p�ӂ���Ă��܂������A��x���ɂ͕Еt�����Ă��܂����B�����͖l�̍D���Ȉ�i��i�^�ł͂Ȃ��A�قƂ�Ǎŏ��ɕ��ׂ��Ă��܂��܂��B�Ƃ����Ă��A���̒��ɉ����������͂Ȃ��̂ʼn��������̂���߂Ă��܂��Ƃ����S�z�͂Ȃ��̂ł����B���������̂͗B��ォ��o����钃�q�����A���т̎��̂��z�����ƁA�e�[�u���ʼn��g���u���Ă��v�Ɓu��v�����ł����B��i��i�̗ʂ����߂ŁA�m�M������A���Ȃ薞����������܂��B�ӂ��Ђ�̓��������q������A�����A�ɐ��C�V�̃}���l�H�ȂǁA���ׂĂ̗������������������ƌ����Ă����Ǝv���܂��B�������A���i�������Ȃ��A�����̐������܂������Ȃ��̂����������܂���B���H�������o���ŁA���M�����߂ɕ��ׂ���Ƃ����^�ł��B��͂肨�������̂ł����A�قƂ�Ǐݖ����g�����̂ŁA���Ȃ育�т��i��ł��܂��܂��B�����ŏo���ꂽ���͐��L�݂��Ȃ��A���Ȃ肨���������̂ł����B�����W�̓x�e�����炵�������ƎႢ���̎q�̓�l��g�ł����B������̎������̏�����l�ƃt�����g�̒j���ꖼ�������J�ɍŌ�܂ʼn�X�����̂��߂Ɏ��U���Ă���Ă��܂����B���}�������̂悤�ŁA�܂��A�߂��ɂ���o���ق̂����C�ɂ����}�t���œ����ȂǁA�T�[�r�X�ʂł͂��Ȃ�]�����Ă����Ǝv���܂��B |
 �z�㒷�쉷���u���k���v�֍s���Ă��܂����B���k���ւ͐V�����̉��O���w��������֑��}�̃o�X���o�Ă���A�T�O�����炢�ŏh�ɓ������܂��B���̎����ɂ킴�킴�V���܂ōs�����̂ł�����A���ƌ����Ă��ړI�͐ጩ�̘I�V���C�ł��B���}�o�X���R�O�����炢�����Ă���ፑ�炵���i�F�ɂȂ�A�h�߂��ɂȂ�ƁA���H�ɉ�������ɂ�������̔��������邱�Ƃ��o���܂����B�h�̎��ӂ͊肢�ǂ��肷�������i�F�ŁA�����ɋC������Ă��̎��͋C�����܂���ł������A��������ƁA���ւ̂��錚���͖ؑ��̎O�K���ĂłȂ��Ȃ����i�����������闧�h�Ȃ��̂ł����B���̓��͓��j�̂������A�������q�Ȃǂ������炵���A�܂��A���}�o�X�����x�ɋq���������������������Ă��A�Ђ����肵���铒�Ƃ��������ł͂���܂���B���������̂͂R�������߂��ŁA�ꉞ�`�F�b�N�C���͂S���Ȃ̂ł����A�����̗p�ӂ��ł��Ă���Q���������邻���ł��B�H���̎��ԂȂǂ̊ȒP�ȑł����킹�̌�A�����ɕ����W��̏����������ֈē����Ă���܂����B���k���ɂ͈�ԐV�����S�́u�k���فv�A���Ɖ��w�O�ɂ������������ڒz�����Ƃ����u�Ε��فv�A�����ď������ꂽ�Ƃ���ɂ���ؑ��́u���ǂ��v�Ƃ����O��ނ̌���������A���̏��ɗ����ɂ����������Ă��܂��B�܂��A�����͑�G�c�Ɍ����Ɓu�t���R�[�X�v�Ɓu�T���߃R�[�X�v�̓��ނ�����A��{�I�ɂ͂��̑g�ݍ��킹�ŗ��������܂�悤�ł��B�ڂ��́A��l���ł���H������V�Ȃ̂Łu���ǂ��v�́u�t���R�[�X�v�Ő\�����݂܂����B�u���ǂ��v�ɂ̓g�C�����t���Ă��āA�ւȂ��傱�̂ڂ��ł����S�ł��B���́A���ǂ��ւƈē����Ă�������̂ł����A�r���A�Ε��ق̑�L�Ԃł͂܂��ɁA�J���I�P���̉������Ȃ�Ƃ��������ŁA�̐����L���ɋ����Ă��܂����B�������̌��ւ̗l�q�Ƃ����A����`�ɐ����Ă�ȂƂ�����ۂł����B�n���Ɉ�����闷�قƂ������Ƃ͑f���炵���̂ł����A�킴�킴��������铒�̏h�����߂Ă������q����͏��X�������肷�邩������܂���B�����A����͂��̓������j�ł����������炵���A�����̌��j�͂����ĕς���ĂЂ�����Ƃ������̂ł����B���̈Ⴂ����ςȂ��̂ł����B �z�㒷�쉷���u���k���v�֍s���Ă��܂����B���k���ւ͐V�����̉��O���w��������֑��}�̃o�X���o�Ă���A�T�O�����炢�ŏh�ɓ������܂��B���̎����ɂ킴�킴�V���܂ōs�����̂ł�����A���ƌ����Ă��ړI�͐ጩ�̘I�V���C�ł��B���}�o�X���R�O�����炢�����Ă���ፑ�炵���i�F�ɂȂ�A�h�߂��ɂȂ�ƁA���H�ɉ�������ɂ�������̔��������邱�Ƃ��o���܂����B�h�̎��ӂ͊肢�ǂ��肷�������i�F�ŁA�����ɋC������Ă��̎��͋C�����܂���ł������A��������ƁA���ւ̂��錚���͖ؑ��̎O�K���ĂłȂ��Ȃ����i�����������闧�h�Ȃ��̂ł����B���̓��͓��j�̂������A�������q�Ȃǂ������炵���A�܂��A���}�o�X�����x�ɋq���������������������Ă��A�Ђ����肵���铒�Ƃ��������ł͂���܂���B���������̂͂R�������߂��ŁA�ꉞ�`�F�b�N�C���͂S���Ȃ̂ł����A�����̗p�ӂ��ł��Ă���Q���������邻���ł��B�H���̎��ԂȂǂ̊ȒP�ȑł����킹�̌�A�����ɕ����W��̏����������ֈē����Ă���܂����B���k���ɂ͈�ԐV�����S�́u�k���فv�A���Ɖ��w�O�ɂ������������ڒz�����Ƃ����u�Ε��فv�A�����ď������ꂽ�Ƃ���ɂ���ؑ��́u���ǂ��v�Ƃ����O��ނ̌���������A���̏��ɗ����ɂ����������Ă��܂��B�܂��A�����͑�G�c�Ɍ����Ɓu�t���R�[�X�v�Ɓu�T���߃R�[�X�v�̓��ނ�����A��{�I�ɂ͂��̑g�ݍ��킹�ŗ��������܂�悤�ł��B�ڂ��́A��l���ł���H������V�Ȃ̂Łu���ǂ��v�́u�t���R�[�X�v�Ő\�����݂܂����B�u���ǂ��v�ɂ̓g�C�����t���Ă��āA�ւȂ��傱�̂ڂ��ł����S�ł��B���́A���ǂ��ւƈē����Ă�������̂ł����A�r���A�Ε��ق̑�L�Ԃł͂܂��ɁA�J���I�P���̉������Ȃ�Ƃ��������ŁA�̐����L���ɋ����Ă��܂����B�������̌��ւ̗l�q�Ƃ����A����`�ɐ����Ă�ȂƂ�����ۂł����B�n���Ɉ�����闷�قƂ������Ƃ͑f���炵���̂ł����A�킴�킴��������铒�̏h�����߂Ă������q����͏��X�������肷�邩������܂���B�����A����͂��̓������j�ł����������炵���A�����̌��j�͂����ĕς���ĂЂ�����Ƃ������̂ł����B���̈Ⴂ����ςȂ��̂ł����B |
 ���ǂ��̕����͎l��������A�ē����ꂽ�͈̂�ԉ��̊p�����ł����B���ǂ��͏��a�R�T�N���z�̖ؑ��ł����A���ŋߓ�����V���������炵�����ꂢ�Ȃ��̂ł��B����قǂ̓��ݍ��݂��オ��ƁA�����Ƀg�C���ł��B���̃g�C���͎l�p����Ԃ̑Ίp����ɕ֊킪���t�����Ă���Ƃ����A�C�f�A�ŁA�Ȃ��Ȃ��L�����������܂��B�����ł����A�c�O�Ȃ���V�����[�g�C���ł͂���܂���B�����͂W��ŁA��������ʼn��s��������قǂ̏��̊ԂɃe���r�A���ɂȂǂ��u����A����ɂR�炢�̂�����肵���L���������Ă��܂��B�L���ɐ��ʂ����Ă���^�C�v�ł��B�ؑ��Ƃ������ƂŁA�������뜜���Ă����̂ł����A���łɕ����ɂ͒g�[��������A������G�A�R���ƃK�X�q�[�^�[�̓���������Ă��܂��̂ŁA�����������邱�Ƃ͂܂���������܂���ł����B�܂��A�����ɒ����܂ł��A�L���̂Ƃ���ǂ���ɃX�g�[�u���u����A���܂ōs�������ł����܂Ŕz������Ă��闷�ق͏��Ȃ������Ǝv���܂��B�p�����ł�����A���͓�ʂ���A�{���Ȃ琙�̗т����߂���炵���̂ł����A���͊O�ɏd�@�⌚�z���ނ��u����Ă��܂��B�Ƃ����̂́A���ǂ��̕����̖ڂ̑O�ɐV����������߁X�������邻���ŁA�܂��ɂ��̍H�����Ȃ̂ł��B���̓��ɍH�����̗���������Ă��炢�܂������A��̘I�V�������A���͒j���ʁA��݂͑���̉Ƒ����C�ɂȂ�悤�ł��B�n��L��������Ă����`�ŁA�Ȃ��Ȃ��悳�����ȕ��͋C�̂��̂��o�������ŁA�������Ă��痈��Ηǂ��������ȂƂ�����ƌ�����܂����B ���ǂ��̕����͎l��������A�ē����ꂽ�͈̂�ԉ��̊p�����ł����B���ǂ��͏��a�R�T�N���z�̖ؑ��ł����A���ŋߓ�����V���������炵�����ꂢ�Ȃ��̂ł��B����قǂ̓��ݍ��݂��オ��ƁA�����Ƀg�C���ł��B���̃g�C���͎l�p����Ԃ̑Ίp����ɕ֊킪���t�����Ă���Ƃ����A�C�f�A�ŁA�Ȃ��Ȃ��L�����������܂��B�����ł����A�c�O�Ȃ���V�����[�g�C���ł͂���܂���B�����͂W��ŁA��������ʼn��s��������قǂ̏��̊ԂɃe���r�A���ɂȂǂ��u����A����ɂR�炢�̂�����肵���L���������Ă��܂��B�L���ɐ��ʂ����Ă���^�C�v�ł��B�ؑ��Ƃ������ƂŁA�������뜜���Ă����̂ł����A���łɕ����ɂ͒g�[��������A������G�A�R���ƃK�X�q�[�^�[�̓���������Ă��܂��̂ŁA�����������邱�Ƃ͂܂���������܂���ł����B�܂��A�����ɒ����܂ł��A�L���̂Ƃ���ǂ���ɃX�g�[�u���u����A���܂ōs�������ł����܂Ŕz������Ă��闷�ق͏��Ȃ������Ǝv���܂��B�p�����ł�����A���͓�ʂ���A�{���Ȃ琙�̗т����߂���炵���̂ł����A���͊O�ɏd�@�⌚�z���ނ��u����Ă��܂��B�Ƃ����̂́A���ǂ��̕����̖ڂ̑O�ɐV����������߁X�������邻���ŁA�܂��ɂ��̍H�����Ȃ̂ł��B���̓��ɍH�����̗���������Ă��炢�܂������A��̘I�V�������A���͒j���ʁA��݂͑���̉Ƒ����C�ɂȂ�悤�ł��B�n��L��������Ă����`�ŁA�Ȃ��Ȃ��悳�����ȕ��͋C�̂��̂��o�������ŁA�������Ă��痈��Ηǂ��������ȂƂ�����ƌ�����܂����B |
 �����C�͌k���ق̈�K�ɂ���A�j���ʂŌ��͂���܂���B���Ԃ͂Q�S���ԓ���OK�ł����A�|���̎��Ԃ��X�����`�P�P���A�R���`�S���ƈ�����܂��B�����C�̓�����ɗ␅�@���u����Ă��܂����A�␅�@�ɂ����ۂ�Ƃ��Ԃ���悤�Ȍ`�ŁA�|�H�̖��|���̃J�o�[���|�����Ă��܂��B�J�o�[�Ȃǂ͎���ŁA���ɋ�S�̐Ղ������܂��B�܂��A���q���u����Ă��܂������A��邱�ƂȂ���[����Ă��ėǂ������Ǝv���܂��B�嗁��͏�����܂肵�������ł���������������܂��B�j���̕��͓�ʂ����ɂȂ��Ă��薾�邳�����������܂��B���M������قǑ傫���͂���܂��A�P�V���̕������ɂ͂��傤�ǎ育��ȑ傫�����Ǝv���܂��B���f�L�͂܂��������܂���B���ɂ�����ς������ŁA���܂œ��������ł��A���Ȃ肵����ς������Ɗ����܂����B�����̂ւ藁�����炨�������ӂ��ӂ�͒��F�����������т���Ă��܂��B�����͂�≷�߂̓K���Ƃ����Ƃ���ł��B�������班���������͂��ӂ�Ă��܂����A�z�����Ă���悤�ł��B�I�V�͑嗁�ꂩ��ʂ��Ă���^�C�v�ŁA�����߂̊╗�C�ł��B��l������L������R�l�����x���Ǝv���܂��B�ڂ̑O�͐Ⴊ�ς����Ă��āA�����͂Ȃꂽ�Ƃ���ɁA���̖��܂�ɂ���Ζʂ������܂��B���̎Ζʂ̎�O�ɂ͐삪����Ă���̂ł����A�c�O�Ȃ��������邱�Ƃ͂ł��܂���B�������A��Ɛ��̎ΖʂƐ�A���ꂾ���Őጩ�̘I�V�̌i�F�Ƃ��Ă͏\���ł͂Ȃ��ł��傤���B���܂��Ȃ�����A�������Ǝ��Ԃ������ē���܂����B �����C�͌k���ق̈�K�ɂ���A�j���ʂŌ��͂���܂���B���Ԃ͂Q�S���ԓ���OK�ł����A�|���̎��Ԃ��X�����`�P�P���A�R���`�S���ƈ�����܂��B�����C�̓�����ɗ␅�@���u����Ă��܂����A�␅�@�ɂ����ۂ�Ƃ��Ԃ���悤�Ȍ`�ŁA�|�H�̖��|���̃J�o�[���|�����Ă��܂��B�J�o�[�Ȃǂ͎���ŁA���ɋ�S�̐Ղ������܂��B�܂��A���q���u����Ă��܂������A��邱�ƂȂ���[����Ă��ėǂ������Ǝv���܂��B�嗁��͏�����܂肵�������ł���������������܂��B�j���̕��͓�ʂ����ɂȂ��Ă��薾�邳�����������܂��B���M������قǑ傫���͂���܂��A�P�V���̕������ɂ͂��傤�ǎ育��ȑ傫�����Ǝv���܂��B���f�L�͂܂��������܂���B���ɂ�����ς������ŁA���܂œ��������ł��A���Ȃ肵����ς������Ɗ����܂����B�����̂ւ藁�����炨�������ӂ��ӂ�͒��F�����������т���Ă��܂��B�����͂�≷�߂̓K���Ƃ����Ƃ���ł��B�������班���������͂��ӂ�Ă��܂����A�z�����Ă���悤�ł��B�I�V�͑嗁�ꂩ��ʂ��Ă���^�C�v�ŁA�����߂̊╗�C�ł��B��l������L������R�l�����x���Ǝv���܂��B�ڂ̑O�͐Ⴊ�ς����Ă��āA�����͂Ȃꂽ�Ƃ���ɁA���̖��܂�ɂ���Ζʂ������܂��B���̎Ζʂ̎�O�ɂ͐삪����Ă���̂ł����A�c�O�Ȃ��������邱�Ƃ͂ł��܂���B�������A��Ɛ��̎ΖʂƐ�A���ꂾ���Őጩ�̘I�V�̌i�F�Ƃ��Ă͏\���ł͂Ȃ��ł��傤���B���܂��Ȃ�����A�������Ǝ��Ԃ������ē���܂����B |
| ���āA���悢��[�H�ł��B���ٌn�ł͓��ɐH���̕]�����ǂ������̂ŁA�y���݂ɂ��Ă��܂����B�����\���a�S�̑傫���̈�������̎��ŁA�����ɏڂ���������������Ă��܂��B����H�ׂĂ���̂��A�܂���ɂȂ��Ă�����H�ׂ��̂����ǂ�������A��͂茣���\������̂͂����ł��ˁB����������Ȃɑ傫���̂͏��߂Ăł��B�H���́A���߂ɁA�O�A�R�ؗށA��A�ϕ��A�J�j�����ׂ��A��ő��̕i����i���^���Ƃ����`�ł��B�܂��H�O�����쑐���Ƃ������ƂŃ}�^�^�r���A�����葐���Ȃǂ��u�����h�����h���ł����A�����͈�������܂���B�~���Ȃǂ̊Ì��̂������{���̐H�O���Ƃ��Ă̖������ʂ����Ă���Ǝv���܂��B�O�̒��ɂ��R�ؗނ�������������Ă���A�R�������̗����̑傫�ȓ����ł��傤�B�ǂ�����̎R�̎��������悭�����o���Ă��܂��B������͌�̐ŁA����̐l�������悤�ł����A���̌�͂܂������L�݂�����܂���B�����������悭�A���̌�Ȃ���Ȑl�����v���낤�Ɗ����܂����B�܂��A���̌�ɂ���|���X�ɂ�����������A�h�q���ƂĂ����������ŗ����Ă��܂��B��̓G�T�ɂ���āA���ꂪ��H�Ǝv�킹��悤�ȔZ���Ȗ��������������̂�����܂����A�����̌�̖��͐����h�́A�������N�Z�̂Ȃ����̂ł����B�|���X�ƂƂ��ɔ��ɕ]���ł��܂��B����ڂ̂��������Ǝv�����̂ł����A���h�g�̎O�퐷��ɕς���Ă��܂����B�������A���̂��h�g�������������̂ł����B���ɉ^��Ă����R�����̉��Ă��́A���������܂������C�ɂ����Ɋۂ�����ł��A�������g�����炩���Ƃ����▭�̏Ă������Ő\��������܂���B�Ă����͓̂���ڂ͈��̓c�y�Ă��ŁA�ʂ͏��Ȃ߂ł�����̂́A����܂��R�����ɕ�������炸�Ƃ������Ƃ���ł����B�n�{�̓���������ӂ�A����ڂ͂��̓�ɕς���āA���`���o����܂������A���̊��`�͐�i�ŁA���ɂ��܂݂̂��鉷�܂���̂ł����B���̗��k���͎R����łȂ��A�畨�A�`���Ɏ��M����ƌ��܂����B�g�����́A�����͊C�V�Ȃǂ�f�ނɂ������̂ŁA������������������̂ł����A����ڂ̌����͓��ɋC�ɓ���܂����B��X�����Ȃ���������Ɩ��Ɏ咣�������������ł����B�Ō�̋����̐ΏĂ��͏Ă������̏�ɋ������ڂ��ďĂ����̂ł����A�������ɂ������Ă��܂��A���X���ɂ����A���������l���Ă������̂ł͂Ȃ����Ɗ����܂����B����ڂ͂��̓��ɑ����Ĕ����̃O���^�����o�܂������A�O���^���D���̂ڂ��Ƃ��Ă�����̂Ȃ����������O���^���ł����B�����A����ڂɋ��ʂ������̂Ƃ��Ă͐�Y���C�K�j���o����܂����B���������Ƃ͎v���܂����A���̗����̒��ł͂���͓��ɋ�����ۂ͎c��܂���ł����B�����ڂ��́A���܂łǂ��̃J�j�Ɋւ��Ă��A����́I�Ǝv�������Ƃ��Ȃ��̂ŁA����͂����܂ł��A�l�I�ȗ��R�ɂ����̂ł��傤�B�Ō�̂��т͏��������ƃC�N���̂��сA����ڂ͎��R���Ƃ�낲�тł���������������A��������������ł��邻���ŁA�Ƃ�낲�т���D���Ȗl�͎����Ă��Ă��ꂽ���ɁA�����ɂ���������肢���Ă��܂��܂����B����Ȃڂ��̑ԓx�ɂ��A��������͂܂���������Ȋ�������A�����ɂ�������^��ł���܂����B�܂��A���̐l�����������Đ�������Ă���Ƃ����킯�ł͂���܂��A�S�̂ɂ���������낪���Ă����l�Ȃ������A������������悤�Ɋ������܂����B�Ƃ������ƂŁA�H���Ɋւ��Ă͂قƂ�nj������Ƃ�����܂���B���ɖ����ł��܂����B���̂��ǂ��̕����͌����S�̂̒[�ɂ���̂ɁA�������A�O�͊����̂ɁA���������̂͂��ׂĉ������܂ܐH�ׂ邱�Ƃ��ł��܂����B�����ɋC�������č�藧�Ă������Ɏ����Ă������Ƃ������Ƃł��B�܂��A�������^�ԃ^�C�~���O���悭�A�����҂�����A�t�ɂ���ĂĐH�ׂ���Ƃ������Ƃ͂���܂���ł����B�S�̂ɓy�n�̑f�ނ����������Ƃ����p��������A��A�`����R�Ƃ������ӗ����������Ă��āA�������������H�ׂ����܂��B���Ȃ�̍����_���Ǝv���܂��B�����A�a�H�̃R�[�X�Ƃ��Ă̌��܂育�ƂȂ̂����m��܂��A�f�U�[�g�̉ʕ��͂�����H�v�����Ă��������ȂƂ����C�����܂����B�ʕ��ɂ�����炸�ɁA�a�H�̃f�U�[�g�Ƃ������_�ŁA�����Â������̂��l���Ă������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂��A�S�̂Ƀ{�����[���̂���H���ŁA���ꂪ�H������V�̂ڂ��Ƃ��Ă͑傢�ɋC�ɓ������̂ł����A�����ɔ�ׂē���ڂ̓{�����[���������������悤�ȋC�����܂����B����ڂɂ��т������肵���̂́A�������Ƃ�낲�т���D��������ł����A�����炩�͂��̂�������������������܂���B�܂��A�H��͂���قLj����͂Ȃ��Ƃ͎v���܂������A�����̈����i�̊�ł���u���܂���v�́A�ŋ߂͖{���̕X���ł߂����̂��قƂ�ǂł��̂ŁA����ɔ�ׂ���ƃL�c�C�Ɗ����܂����B�ނ��땁�ʂ̊�ŋ����������ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���H������������͂�{�����[��������܂����B�����̒��H�̓����͂��т̂ق��ɁA����Ő����������䂪�o�����Ƃ������Ƃł��B�������A�������̂܂ܐ����̂ł͂Ȃ��A�����炩���͒����Ă���Ƃ͎v���܂����A�ƂĂ������������̂ł��B���̋��͏����͍����o�܂������A��������Ă��āA��͂苛�����������H�ׂ�����ȂƊ����܂����B����ڂ͉����o��낤�Ɗy���݂ɂ��Ă����̂ł����A���炱�ł����̂ŁA�Ă��������҂��Ă����ڂ��Ƃ��Ă͎c�O�ł����B���̑��A�������A�C�ہA�T���_�A�ϕ��A�������A�ȂǁA��̈�ʓI�Ȓ���H���ƌ����Ă����Ǝv���܂��B�����͂��̑��ɃC�J�h�����o�Ă���������܂����B���Ȃ߂ł����A�R�����̃W���[�X��[�O���g���o�܂��̂ŁA��͂薞���x�͍����Ǝv���܂��B |
 ���āA���k���̐H���Ƃ��ĐG��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂́u���ʂ��`�v�ł��傤�B�����Ń_���������Ƃ������Ƃ��Ă����̂ŁA�ڂ��͍ŏ�����Q�e���m���낤�Ǝv���A�H�ׂ�C�͂Ȃ������̂ł��B�Ƃ��낪�A�����̗[�H�̎��A�b�̂��łɒ�������ɂǂ�Ȗ��������Ă݂�ƁA�N�Z���Ȃ��ĂƂĂ����������Ƃ����ӊO�ȕԎ��ł����B�����ŋ}篁A�����̒��ɐH�ׂ悤�Ǝv���������̂ł��B���ʂ��`�𒍕�����Ƒ�̏������^��ł��邻���ł��B�ڂ��̎����ŏ��͏������A�Ƃ����b�������̂ł����A�}�ɏo�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����Ƃ������ƂŁA�����������Ă��܂����B�����A��������͑������ʂ��`�Ɏv�����ꂪ����炵���A�[�H�̎��ɂ킴�킴��������ɑ����Ċ��`���^�т��Ă�A���ʂ��`�̐����ɗ��Ă���܂����B�Ȃ�ł��A���ʂ��̓��͂悭�ύ����̂ƁA�ύ���ł��Ȃ����̂̓��ނ��g���Ă��邻���ł��B�悭�ύ��߂ΓƓ��̓����͏�����炵���̂ł����A�����Ă��ʂ��Ƃ������̂������Ă��炤���߂Ɏύ���ł��Ȃ����̂�����邻���Ȃ̂ł��B���̘b���āA�����܂ł̂������ɁA���S���܂����B���́A�u����̓E�}�C�I�v�ƂЂ���ł܂ł͍s���܂��A�▭�̃o�����X���Ƃ��Ă��閡���Ɗ����܂����B�����͗���Ă��Ă��v�[���Ɠ����Ă���Ƃ�������Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�X�[�v�S�̂��炩�����ɁA�������m���ɕY���Ă���Ƃ�����ۂł��B���͏_�炩�������Ă܂����͂���܂���B���̑��l�M�₵�������Ȃǂ����܂݂��o���Ă��āA�~�͑̂��c����g�܂肻���ł��B�ق�̏����������C�ɂȂ������x�ŁA�ڂ��͂���قǒ�R�Ȃ��Ō�̈�H�܂ň��݊����Ă��܂��܂����B����ɂ��Ă��A��������̂����܂ł̂������́A�畨�A�`���ɑ���m�ł��鎩�M���痈��悤�Ɋ������܂����B ���āA���k���̐H���Ƃ��ĐG��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂́u���ʂ��`�v�ł��傤�B�����Ń_���������Ƃ������Ƃ��Ă����̂ŁA�ڂ��͍ŏ�����Q�e���m���낤�Ǝv���A�H�ׂ�C�͂Ȃ������̂ł��B�Ƃ��낪�A�����̗[�H�̎��A�b�̂��łɒ�������ɂǂ�Ȗ��������Ă݂�ƁA�N�Z���Ȃ��ĂƂĂ����������Ƃ����ӊO�ȕԎ��ł����B�����ŋ}篁A�����̒��ɐH�ׂ悤�Ǝv���������̂ł��B���ʂ��`�𒍕�����Ƒ�̏������^��ł��邻���ł��B�ڂ��̎����ŏ��͏������A�Ƃ����b�������̂ł����A�}�ɏo�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����Ƃ������ƂŁA�����������Ă��܂����B�����A��������͑������ʂ��`�Ɏv�����ꂪ����炵���A�[�H�̎��ɂ킴�킴��������ɑ����Ċ��`���^�т��Ă�A���ʂ��`�̐����ɗ��Ă���܂����B�Ȃ�ł��A���ʂ��̓��͂悭�ύ����̂ƁA�ύ���ł��Ȃ����̂̓��ނ��g���Ă��邻���ł��B�悭�ύ��߂ΓƓ��̓����͏�����炵���̂ł����A�����Ă��ʂ��Ƃ������̂������Ă��炤���߂Ɏύ���ł��Ȃ����̂�����邻���Ȃ̂ł��B���̘b���āA�����܂ł̂������ɁA���S���܂����B���́A�u����̓E�}�C�I�v�ƂЂ���ł܂ł͍s���܂��A�▭�̃o�����X���Ƃ��Ă��閡���Ɗ����܂����B�����͗���Ă��Ă��v�[���Ɠ����Ă���Ƃ�������Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�X�[�v�S�̂��炩�����ɁA�������m���ɕY���Ă���Ƃ�����ۂł��B���͏_�炩�������Ă܂����͂���܂���B���̑��l�M�₵�������Ȃǂ����܂݂��o���Ă��āA�~�͑̂��c����g�܂肻���ł��B�ق�̏����������C�ɂȂ������x�ŁA�ڂ��͂���قǒ�R�Ȃ��Ō�̈�H�܂ň��݊����Ă��܂��܂����B����ɂ��Ă��A��������̂����܂ł̂������́A�畨�A�`���ɑ���m�ł��鎩�M���痈��悤�Ɋ������܂����B
���k���́A�`�F�b�N�C�����S���i���ɂ���Ă͂Q���ł��j�A�R���`�S���܂ł����C�̐��|���ԁA�x�O���͂Q�l�h�����ł��Ȃ��ꍇ������A�ȂǁA���̗��قɂ͂��܂茩���Ȃ��A���\�d�����A�h���q����h�����ꂻ���ȗv�f�������Ă��܂��B�ڂ��́A���̂R�_�͖����ɉz�������Ƃ͂Ȃ��Ƃ͎v���܂����A�P�V���Ƃ������K�͗��قł���Ȃ���A�k���فA�Ε��فA���ǂ��Ƃ������ꂼ��ɈقȂ��������̂��錚���Ōo�c���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ���J�䂦�̂��Ƃ��Ƒz���ł��܂��B����̓W�����}��������܂���ˁB�������A���Ƃ������̓������o���Ăق����Ǝv���܂��B���ٌo�c�ɂ͗l�X�ȋ�J������Ƃ͎v���܂����A�u�������f���A���������߂āA�n���ȓw�͂��R�c�R�c�Ɛςݏd�˂Ă����B���k���͂��������Ăق����Ɗ肢�܂��B�ӂƖ������ꂽ���A�܂��܂��悪�����Ǝv���Ă�������ɁA���������炪�����Ă������ƂɋC�Â��B����ȓ�����������h���ƐM���܂��傤�B |
| �V���������́u��ȉ����فv�ɍs���Ă��܂����B���z���߂��āA�V����s���̃��[�v�E�G�[���ꂩ�炳��ɏ�ɓo���čs���̂ł����A���̍�̃L�c�C���ƁA���͊��S�ɏ��Ⴕ�Ă���܂������A���Ȃ�̋}��ł���ŐႪ�~������A���������肵����ǂ�����낤�Ǝv���܂����B�ł��A�ʔN�c�Ƃ��Ă���̂ŁA�܂����v�Ȃ̂ł��傤���E�E�o�X��܂ŁA�h����̑��}������悤�ł��B�m���ɁA�ƂĂ������C�ɂ͂Ȃ�܂���B�S�����ɏh�ɒ����āA�������������Ɉē����Ă��炢�܂����B�ו��͎����Ă���܂������A�ē��̓h�A�̂Ƃ���܂łł��B�����͂Q�P�P�����ŁA���ݍ��݂͂Ȃ��A�����ɂU��̘a���ɂȂ�܂��B�����ɂ͍L�������̊Ԃ����ʂ��①�ɂ�����܂���B�������A�g�C�����Ȃ��A�m���\�N�߂��O�Ƀg�C���̂Ȃ��y���V�����ɔ��܂������Ƃ������āA����ȗ��g�C���̂Ȃ��͓̂��ڂł��B�e�B�b�V���{�b�N�X�͂���܂������A���ɂ͓��������Ă��܂���ł����B���̑��A���ɂƃe���r�͂���܂��B�z�b�g�J�[�y�b�g���~����Ă��āA�K�X�X�g�[�u�����芦���͊��������܂���B�z�c�������ɐς�ł���A�����ŕ~���̂������ł��B�o�X�^�I���͂���܂���B�Ȃ��Ȃ��Â����ł����A�������������͗^���܂���B�S�̓I�ɏ�����܂�Ƃ��āA�������͂���܂��B��������̒��߂͉����ɐ�����Ԃ����A�R�A����͐�̏����c�����R�A��O�ɂ͓����̉����������܂��B�������A�`�����݂͂���܂���B |
 ���āA���������I�V�ɍs���܂����B�h�̌��ւ��o�ď������������Ƃ���ɁA�����ȓ��M����ƒE�ߏ��A����Ɍܒi���炢���������Ƃ���ɁA�������̍L���I�V�ƒE�ߏ�������܂����A������̏㉺�̘I�V���s��������̂́A���ւ���K�v�͂���܂���B�����̘I�V�͂��ׂď�����p�̖�V���`�W���ȊO�͍����ł��B���������ƁA�H�����ԂƊ��S�Ƀo�b�e�B���O����Ǝv����ł��傤���A�H���͂T���P�T�����납��n�܂��āA�ʂ����Ȃ��̂ŁA�܂��������v�ł��B�܂��ڂ��́A�L���I�V�ł��났�܂����B������Ԃ��������̎R���͂��ތ`�ŋ߂��̎R������܂��B������Ɠd�����ڗ��̂����͋C���Ă��܂����A�Ȃ��Ȃ��̌i�F���Ǝv���܂����B�܂��A����������܂��̂ŁA�J�̎��ł��C�ɂ����ɓ����Ă����܂��B�����͂V�E�W�l���炢�̑傫���ł��傤���B�^�ɑ傫�Ȋ₪����܂��̂ŁA�����ł��l�������Ȃ���Α���̎��p�ɓ��邱�Ƃ��ł��܂��B�ꏊ�ɂ���ĈႤ�Ƃ͎v���܂����A��ԑO�̂Ƃ���͂�≷�߂ł����B�����������̉Ԃ������āA���ꂪ��ɐς���̂��A���Ȃ�ꂪ�ʂ�ʂ邵�܂��B���ׂ�Ȃ��悤�ɂ����������܂����B��̓�̓��M�́A��͖̂���ʂ����C�i���������C�j�A������͏����߂̏炢�̑傫���������߂̗����ŁA�Q���ɋ߂��`�ő̂�L���܂��B������͉���������܂���̂ŁA���V�̐���߂�̂ɂ͐�D�ł��B�ڂ��͖�A�I�V�ɓ���Ȃ������̂Ő���͒��߂��܂���ł����B�����͔��ɕ��͋C�̂�����̂��ƁA�ڂ��͊����܂����B�l�p���̗����ŁA������S�O�Z���`���炢�����グ�Ă���܂��B�����͓�������ł�����������������Ǝv���܂��B�����A����قǍL���Ȃ��̂ŁA���������S�l���炢�ł��傤���B�܂������͂��M�߂ł��B�����̗��ꍞ�ޘe�ɐ���������A�������班����������Ă��܂����B�ǂɂ̓R�b�v�������t�����Ă���A���ł��܂��B���ɂ���Ƃ�������ۂ͎c���Ă��܂��A���݂₷�����̂ł����B�����A���̓����ɂ͐�Ƃ������̂��S���Ȃ��A�̂�����l�ɂ͂��Ȃ�s�����c��ł��傤�B�ꉞ�V�����v�[�ƃ{�f�B�\�[�v�͂���̂ł����g���ɂ����Ǝv���܂��B ���āA���������I�V�ɍs���܂����B�h�̌��ւ��o�ď������������Ƃ���ɁA�����ȓ��M����ƒE�ߏ��A����Ɍܒi���炢���������Ƃ���ɁA�������̍L���I�V�ƒE�ߏ�������܂����A������̏㉺�̘I�V���s��������̂́A���ւ���K�v�͂���܂���B�����̘I�V�͂��ׂď�����p�̖�V���`�W���ȊO�͍����ł��B���������ƁA�H�����ԂƊ��S�Ƀo�b�e�B���O����Ǝv����ł��傤���A�H���͂T���P�T�����납��n�܂��āA�ʂ����Ȃ��̂ŁA�܂��������v�ł��B�܂��ڂ��́A�L���I�V�ł��났�܂����B������Ԃ��������̎R���͂��ތ`�ŋ߂��̎R������܂��B������Ɠd�����ڗ��̂����͋C���Ă��܂����A�Ȃ��Ȃ��̌i�F���Ǝv���܂����B�܂��A����������܂��̂ŁA�J�̎��ł��C�ɂ����ɓ����Ă����܂��B�����͂V�E�W�l���炢�̑傫���ł��傤���B�^�ɑ傫�Ȋ₪����܂��̂ŁA�����ł��l�������Ȃ���Α���̎��p�ɓ��邱�Ƃ��ł��܂��B�ꏊ�ɂ���ĈႤ�Ƃ͎v���܂����A��ԑO�̂Ƃ���͂�≷�߂ł����B�����������̉Ԃ������āA���ꂪ��ɐς���̂��A���Ȃ�ꂪ�ʂ�ʂ邵�܂��B���ׂ�Ȃ��悤�ɂ����������܂����B��̓�̓��M�́A��͖̂���ʂ����C�i���������C�j�A������͏����߂̏炢�̑傫���������߂̗����ŁA�Q���ɋ߂��`�ő̂�L���܂��B������͉���������܂���̂ŁA���V�̐���߂�̂ɂ͐�D�ł��B�ڂ��͖�A�I�V�ɓ���Ȃ������̂Ő���͒��߂��܂���ł����B�����͔��ɕ��͋C�̂�����̂��ƁA�ڂ��͊����܂����B�l�p���̗����ŁA������S�O�Z���`���炢�����グ�Ă���܂��B�����͓�������ł�����������������Ǝv���܂��B�����A����قǍL���Ȃ��̂ŁA���������S�l���炢�ł��傤���B�܂������͂��M�߂ł��B�����̗��ꍞ�ޘe�ɐ���������A�������班����������Ă��܂����B�ǂɂ̓R�b�v�������t�����Ă���A���ł��܂��B���ɂ���Ƃ�������ۂ͎c���Ă��܂��A���݂₷�����̂ł����B�����A���̓����ɂ͐�Ƃ������̂��S���Ȃ��A�̂�����l�ɂ͂��Ȃ�s�����c��ł��傤�B�ꉞ�V�����v�[�ƃ{�f�B�\�[�v�͂���̂ł����g���ɂ����Ǝv���܂��B |
 �����͖{���Ȃ炻�̕����ł��Ǝv���܂����A��X�̂��߂ɁA���ʂɈႤ������p�ӂ��Ă���܂����B�����͏��߂ɁA���X�`���т��ӂ��߂đS�������Ă��Ă��܂��܂��B�Ƃ����Ă��A�M�����̂Ƃ����̂͂���قǂȂ��̂ŁA���܂�e���͂Ȃ���������܂���B�����A���X�`�Ƃ��т͊��S�ɗ�߂܂��B���i�����͂Ȃ��A�����͂����������ł��i�ڂ��͂�����ƒx��čs���܂����j�B�ĕ��͎R���ł܂��������������̂ł����B�����A�ۂ��Ɠ����炩�Ԃ�����̂ł����A���͐H�ׂ��܂���ł����B��͂Ȃ߂����A���̏_�炩�ρA�ӂ��A������ɂႭ�̎ϕ��A�R���Z���A�R�ؘa�����A���X�`�A���̕��A�ȂǂŁA�S�̓I�ɕi�������Ȃ��Ɗ����܂����B���Ɠ�i���炢�~�����C�����܂����B���͂���قLj����͂���܂��A���M���ׂ����̂͂���܂���B�����͂���A�[����C�ہA���Ƃ�����Ԃɋ��͊⋛�̊ØI�ρA������Ƃ����V���v���Ȍ`�ł����B������A����قǓ��M����ׂ����̂͂���܂���B�����̎��l���Ǝv���̂ł����A���[���A�������čD�܂�����ۂł��B�܂��A�]�ƈ��������ƈ��A���ł��āA�S�̓I�ɔ��ɍD�������Ă܂��B�����A�u�R�̏h�ł��̂ŁE�E�v�Ƃ����f�肪�����A�����������ɂ��Ă���Ƃ��낪�Ȃ��͂Ȃ����H�@�Ǝv���܂����B�铒�A�ȑf�A�����n�̏h�Ƃ����J�e�S���[�ł��傤���B�H���Ɋւ��Ă͕s�����c�邵�A�����̂������ς肵����������l����ƁA���ƍŋ߉��������悤�ȋC�����܂����A���̎��Ƀg�C�����̕����������Ă��ǂ������̂ł͂Ȃ����Ɗ����܂����B�����Ɨ����ɗ͂����A��ʂ̐l���C�y�ɗ�����悤�ɂ���A���\�l�C���o�����ȋC�����Ȃ��ł�����܂���B���l�Ƙb���������ł��A������ƌ��f���x���^�C�v�̐l���ȂƂ����C�����܂����B �����͖{���Ȃ炻�̕����ł��Ǝv���܂����A��X�̂��߂ɁA���ʂɈႤ������p�ӂ��Ă���܂����B�����͏��߂ɁA���X�`���т��ӂ��߂đS�������Ă��Ă��܂��܂��B�Ƃ����Ă��A�M�����̂Ƃ����̂͂���قǂȂ��̂ŁA���܂�e���͂Ȃ���������܂���B�����A���X�`�Ƃ��т͊��S�ɗ�߂܂��B���i�����͂Ȃ��A�����͂����������ł��i�ڂ��͂�����ƒx��čs���܂����j�B�ĕ��͎R���ł܂��������������̂ł����B�����A�ۂ��Ɠ����炩�Ԃ�����̂ł����A���͐H�ׂ��܂���ł����B��͂Ȃ߂����A���̏_�炩�ρA�ӂ��A������ɂႭ�̎ϕ��A�R���Z���A�R�ؘa�����A���X�`�A���̕��A�ȂǂŁA�S�̓I�ɕi�������Ȃ��Ɗ����܂����B���Ɠ�i���炢�~�����C�����܂����B���͂���قLj����͂���܂��A���M���ׂ����̂͂���܂���B�����͂���A�[����C�ہA���Ƃ�����Ԃɋ��͊⋛�̊ØI�ρA������Ƃ����V���v���Ȍ`�ł����B������A����قǓ��M����ׂ����̂͂���܂���B�����̎��l���Ǝv���̂ł����A���[���A�������čD�܂�����ۂł��B�܂��A�]�ƈ��������ƈ��A���ł��āA�S�̓I�ɔ��ɍD�������Ă܂��B�����A�u�R�̏h�ł��̂ŁE�E�v�Ƃ����f�肪�����A�����������ɂ��Ă���Ƃ��낪�Ȃ��͂Ȃ����H�@�Ǝv���܂����B�铒�A�ȑf�A�����n�̏h�Ƃ����J�e�S���[�ł��傤���B�H���Ɋւ��Ă͕s�����c�邵�A�����̂������ς肵����������l����ƁA���ƍŋ߉��������悤�ȋC�����܂����A���̎��Ƀg�C�����̕����������Ă��ǂ������̂ł͂Ȃ����Ɗ����܂����B�����Ɨ����ɗ͂����A��ʂ̐l���C�y�ɗ�����悤�ɂ���A���\�l�C���o�����ȋC�����Ȃ��ł�����܂���B���l�Ƙb���������ł��A������ƌ��f���x���^�C�v�̐l���ȂƂ����C�����܂����B |
| �@ |
 �����͏���쉷��́u���������فv�ł��B��l�����̊����ȗ����ɂ�������炸�A�u���������فv�͍��܂Ŗl���h�������h�̒��ł͍Œᗿ���ŁA�قƂ�NJ��҂����ɍs���܂����B�������́u�v�̋߂��ɂ���A�Ԍ���Ԃقǂ̏����ȏh�ŁA����Ƃ����G���g�����X������킯�ł͂Ȃ��A����X�ɖʂ��āA���ʂ̉Ƃ̂悤�ɂ��̂܂܌��ւ�����܂��B���ւ��J����ƁA�L��������A�֎q������ׂ��Ă��܂��B������ƃ��r�[�Ƃ͌Ăׂ܂���B�܂��A����Ƃ������̂��Ȃ��A�������̂悤�ȓ���������邾���ł��B�����A����������Ɗ����̂����������o�Ă��āA�R:�O�O�̃C���ɂ͂R�O�����炢�������̂ł����A�����Ɉē����Ă���܂����B�o�b�N�͎����Ă��ꂽ�悤�ȋC�����܂����A���܂�o���Ă��܂���B��������͈ꉞ�����ɂ͓������Ǝv���܂����A�����o���͂���܂���B�܂����̗����ł́A��������R���ȂƎv���܂����B�����A���߂̃T�C�Y�̋C�Â����͂���܂����B�����͂��������Ƃ�����K�̊p�����ŁA�L���ɃX���b�p���ʂ��A�ӂ��܂��J����ƁA�����Ȃ�a���ɂȂ�܂��B���͂ӂ��܂Ɏ��t����^�C�v�ł����B�������̂͌Â����������A��͐V������l�����ł��P�O��̍L��������܂��B�܂��A�p�����ő�����ʂ��邹�������邢��ۂł��B���߂͋߂��̏h�₱�̏h�̑嗁��̔w�ʂȂǂł���قǗǂ�����܂���B�ǂ����炩�`�����C�����܂��B�L���͒���������A�����L�߂ł��B���̍L���ɐ��ʂ�����^�C�v�ł����A��������Ƀg�C���͂���܂���ł����B���ɂ��Ȃ��A�①�ɂ͐\�����ł��B�c�O�Ȃ��ƂɃe�B�b�V��������܂���B�o�X�^�I�����t���Ă��܂���B�����A���M���ׂ��͈�ԁi����j������Ƃ̏��̊Ԃɗ��h�ȉԂ������Ă���_�ł��B���̗����ʼnԂƂ͂������ȂƎv���܂����B�����͘L���Ȃǂɂ�������Ƃ����Ԃ������Ă��āA�Ԃ̍D���ȏ�������ȂȂƊ����܂����B �����͏���쉷��́u���������فv�ł��B��l�����̊����ȗ����ɂ�������炸�A�u���������فv�͍��܂Ŗl���h�������h�̒��ł͍Œᗿ���ŁA�قƂ�NJ��҂����ɍs���܂����B�������́u�v�̋߂��ɂ���A�Ԍ���Ԃقǂ̏����ȏh�ŁA����Ƃ����G���g�����X������킯�ł͂Ȃ��A����X�ɖʂ��āA���ʂ̉Ƃ̂悤�ɂ��̂܂܌��ւ�����܂��B���ւ��J����ƁA�L��������A�֎q������ׂ��Ă��܂��B������ƃ��r�[�Ƃ͌Ăׂ܂���B�܂��A����Ƃ������̂��Ȃ��A�������̂悤�ȓ���������邾���ł��B�����A����������Ɗ����̂����������o�Ă��āA�R:�O�O�̃C���ɂ͂R�O�����炢�������̂ł����A�����Ɉē����Ă���܂����B�o�b�N�͎����Ă��ꂽ�悤�ȋC�����܂����A���܂�o���Ă��܂���B��������͈ꉞ�����ɂ͓������Ǝv���܂����A�����o���͂���܂���B�܂����̗����ł́A��������R���ȂƎv���܂����B�����A���߂̃T�C�Y�̋C�Â����͂���܂����B�����͂��������Ƃ�����K�̊p�����ŁA�L���ɃX���b�p���ʂ��A�ӂ��܂��J����ƁA�����Ȃ�a���ɂȂ�܂��B���͂ӂ��܂Ɏ��t����^�C�v�ł����B�������̂͌Â����������A��͐V������l�����ł��P�O��̍L��������܂��B�܂��A�p�����ő�����ʂ��邹�������邢��ۂł��B���߂͋߂��̏h�₱�̏h�̑嗁��̔w�ʂȂǂł���قǗǂ�����܂���B�ǂ����炩�`�����C�����܂��B�L���͒���������A�����L�߂ł��B���̍L���ɐ��ʂ�����^�C�v�ł����A��������Ƀg�C���͂���܂���ł����B���ɂ��Ȃ��A�①�ɂ͐\�����ł��B�c�O�Ȃ��ƂɃe�B�b�V��������܂���B�o�X�^�I�����t���Ă��܂���B�����A���M���ׂ��͈�ԁi����j������Ƃ̏��̊Ԃɗ��h�ȉԂ������Ă���_�ł��B���̗����ʼnԂƂ͂������ȂƎv���܂����B�����͘L���Ȃǂɂ�������Ƃ����Ԃ������Ă��āA�Ԃ̍D���ȏ�������ȂȂƊ����܂����B |
 ���āA�嗁��ł����Q�S����OK�Œj�����͂���܂���B�j���͊╗�C�ɂȂ��Ă��ă��C���h�Ȋ����ł��B��͌܂��炢��������܂��A�܂����ق̋K�͂��猾�����炱��Ȃ���ł��傤�B�����͌܁A�Z�l���������x�ł�͂肱��Ȃ��ȂƂ��������ł��B�V�ق��������ĐV�����A�������ɂȂ��Ă��ĉ��K�ł��B�����A�����͔M�߂ŁA�m���A���ʂւ̂����̗��ꍞ�݂��Ȃ������̂Ŗ����m���߂邱�Ƃ��ł��܂���ł����B�������A�����肾�Ƃ͎v���܂��B�����v��������ł��āA������S�S�x�ɂȂ��Ă��܂����B�I�V�͑嗁�ꂩ��o��^�C�v�ŁA�Q,�R�l���x��������Ȃ��ق�̏����Ȃ��̂ł��B�ق�̂����邵�I�V�ƌ����Ă��Ǝv���܂����A�ڂ̑O�ɖ��R�{���炢�A�����Ă��܂��̂ŁA�ɒ[�ɋ����Ƃ��������͂��܂���B�����A���͂��͂��Ă��邱�Ƃ͊m���ł��B ���āA�嗁��ł����Q�S����OK�Œj�����͂���܂���B�j���͊╗�C�ɂȂ��Ă��ă��C���h�Ȋ����ł��B��͌܂��炢��������܂��A�܂����ق̋K�͂��猾�����炱��Ȃ���ł��傤�B�����͌܁A�Z�l���������x�ł�͂肱��Ȃ��ȂƂ��������ł��B�V�ق��������ĐV�����A�������ɂȂ��Ă��ĉ��K�ł��B�����A�����͔M�߂ŁA�m���A���ʂւ̂����̗��ꍞ�݂��Ȃ������̂Ŗ����m���߂邱�Ƃ��ł��܂���ł����B�������A�����肾�Ƃ͎v���܂��B�����v��������ł��āA������S�S�x�ɂȂ��Ă��܂����B�I�V�͑嗁�ꂩ��o��^�C�v�ŁA�Q,�R�l���x��������Ȃ��ق�̏����Ȃ��̂ł��B�ق�̂����邵�I�V�ƌ����Ă��Ǝv���܂����A�ڂ̑O�ɖ��R�{���炢�A�����Ă��܂��̂ŁA�ɒ[�ɋ����Ƃ��������͂��܂���B�����A���͂��͂��Ă��邱�Ƃ͊m���ł��B |
| �[�H�͕����o���ł��B�����Ȃ��V�����������ׂ�`�ŁA���C���͋��̓��Ă��ł��B�����đ��Ǝv���܂��B���̒l�i�ŁH�Ǝv���܂����A�܂��đɂ����낢�날��̂ł��傤�B���̑��ɕđ��̌�̊Îς��t���܂��B�đ���ӎ����������I�ȗ��ٗ�����������܂���B���̌�̊Îς͂��N�Z����������̂ŁA������Ȑl�͂���͑������߂��Ǝv���܂��B���i�����͂Ȃ�����������܂���B���X�`�A���шȊO�͂��ׂčŏ��ɂ����ė��Ă��܂��A���Ă��ɂ������悤�Ƃ����̂ŁA����ĂĂƂ߂܂����B�ŏ��͂킩��܂��A���R�A�H�ׂ�Ƃ��ɂ͗�߂Ă��܂��Ă�����̂������Ȃ��Ă��܂��B�����A�{�����[�������Ȃ肠��A���ƌ�ȊO�ɂ́A�^�R�̏����A���q�����A�h�g�A�R���u�ߕ��A�̂��Z���A���g���̃z�C���Ă��A�֎q�̋l�ߕ����o����܂����B�z�C���Ă��Ɖ֎q�͂��V�ɍڂ炸�A��̏�ɒu����܂����B�܂��A���ꂼ�ꂪ�{�����[��������̂ł��Ȃ薞���ɂȂ�܂��B�����A�������܂��f�U�[�g�͂���܂���ł����B���̕����ƒ��H�����������s���邩�ȂƊ��҂����̂ł����A�ǂ������A���ł����߂����̂悤�ɁA���̕i���͂��Ȃ菭�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�������܂ōs�����h�̒��ł̍ŏ��V�L�^���Ǝv���܂��B���i���W�E�����H�j�[���A���A��܂��ǂ̂��Z���A���̕��A���X�`�A���сA���N���g�B�ȏセ�ꂾ���ł��B�������ŁA���Ђ̂��т�S���H�ׂĂ��܂��܂����B���͈����͂Ȃ��̂ł����A���Ȃǂ��ǂ��Ƃ����قǂ̂��̂ł͂���܂���B
�ڂ��͕ɗ����ɂ��Ă͂قƂ�Ǐ����Ȃ��̂ł����A�����͏h�̖��_�̂��߂ɏ����Ă����܂��傤�B�~���Ȃ̂Œg�[�����T�O�O�~������̂ł����A��������Ă������͂W�T�O�O�~�ł��B��������l�łł��B����ŁA���̓��e�ł�����A�R�X�g�p�t�H�[�}���X�Ƃ��Ă͂��Ȃ�̂��̂��Ǝv���܂��B�����C�������͂Ȃ��Ǝv�����A����������ɂ͂�����������܂���B�܂��A�V�ق̗���������قǍ����͂Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA�V�ق��Ƃǂ�ȓ��e�ɂȂ�̂��C�ɂȂ�܂����B�����͂��̓��������������q�������Ă����悤�ł����A�����ăp�t�H�[�}���X�̂����h�Ƃ��Đl�C�ɂȂ邩������܂���B��������ق̈�̂�������ȂƎv���܂����B�Ō�̌�����ɂ���l���L���ɍ����Č����낤�Ƃ��Ă��܂����B�ʐ^���B�邽�߂ɊO�ɏo�ė��Ă�����Ă��܂����̂ł����A�����Č������Ă���������Ƃ͂��܂�L���ɂ���܂���B����������������悩�������A���̓_�ł͕]���ł���Ǝv���܂��B���삳��炵���l�����āA�����̔��l�������ł��B |
|
���R�c�����u���R���v�֍s���Ă��܂����B�����͔铒�̏h�̒��ł��A���ɕ]���̂����h�ŁA����s�������Ǝv���Ă����Ƃ���ł����B�i�F�������悤�Ȃ̂ŁA��������������A���ł�����肷�邱�Ƃɂ��܂����B�܂��A�`�F�b�N�C�����Ԃɂ��傤�ǂ����o�X�̕ւ�����A���̎��Ԃɍ��킹�ė��ق̌}�������Ă����̂ŁA�ڂ��̂Ƃ��납��ł����Ƌ�ɂȂ�Ȃ������ł����B �}���̎Ԃŏh�ɒ������̂��R���߂��B�V��������Ǘ������������̃��r�[�ł��Β������������܂��B���N���̕��������������Ƃ������ƂŁA����������Ƃ��̃��r�[�����̎��V�����������̂�������܂���B���̖��R���ɂ͂������̓���������܂����A�܂����_�̓X���b�p���͂��Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�B���~���̗��قȂ牽���͂��Ȃ��͓̂�����O�Ȃ̂ł����A�����͏��~���ł͂Ȃ��A���ׂăt���[�����O�ł��B�|���ɂ���ۂǂ̎��M���Ȃ��ƁA����Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤�B�c�O�Ȃ��甒���C���ł͂Ȃ������̂ŁA�|����̓`�F�b�N�ł��܂���ł������A���������|���͗ǂ��s���͂��Ă����Ǝv���܂��B�����̑��_�͂����͑S���łP�O�������Ȃ��A�Ƒ��l�l�����ł���Ă���Ƃ������Ƃł��B�ɖZ���ɂ͑|���͗���ł���炵���̂ł����A����ȊO�͎l�l�ł���Ă���Ƃ������Ƃł����B�`�F�b�N�C���̎��ɂ������o���Ă��ꂽ�̂����������ŁA�[�т̎��ɘb�����ɂ���Ă����̂��َ�ł��邨���������B�ł��A����ȊO�́A���ׂĎ�v�w�����ڂɂ��܂���ł����B����͂Ƃ�ł��Ȃ���ςȂ��Ƃ��Ɗ����܂����B���̂����ŁA�܂��d���Ȃ����Ƒ�ڂɌ��镔���������Ă��܂����C�����܂��B���܂��܂R�g�̋q���}���̎Ԃňꏏ�ɂȂ�A�����������t���A�Ƃ������ƂŁA�ē��͂R�g�܂Ƃ߂ĂƂ������ƂɂȂ�܂����B���l���ē����Ă���܂������A�ו��͂������S���̂����Ă��͂Ȃ��A�N���̉ו����\���Ď��Ƃ��������ł��B���̕����ł��ƌ����A�Q�O�Q�����́u���v�Ƃ��������ɒʂ���܂����B�����ˌ^�̃h�A���J����ƁA������̂����ɉE�ɐ��ʑ䂪����A�����g�C���ɂȂ��Ă��܂��B����ɂӂ��܂��J����ƁA�P�O��̕����ɂ��łɕz�c���~����Ă��āA�����ɂł����ɂȂ邱�Ƃ��ł��܂��B���̐�ɂS����̍L��������A���[���ق̒��֎q���u����Ă��܂����B�P�O��̍��������̊ԂɂȂ��Ă��āA�e���r��u���Ă��镔���Ə��̊ԂƂ���������d���Ă��܂����B������͋߂��̎R�X�Ɖ����ɂ͓��{�A���v�X�̕ǂ̂悤�ȎR�X�A�P�������Ȃǂ����߂��܂��B���ɂ����i�F�Ȃ̂ł����A�c�O�Ȃ��瑋�̔������炢�͉��̕����̉��������E�����������Ă��܂��B���ʂ͊O�̌i�F�������ꍇ�A�����̍����������������Ȃ̂ł����A�����͋t�ʼn��̕����̕����i�F�͂悭�A�����ݒ�������悤�ł��B���炭���āA���̕������ē����Ă������l���߂��Ă��āA�ȒP�Ȑ��������Ă���܂����B�����͗��߂ł͂Ȃ��얱�߂Ȃ̂ł����A�T�C�Y�̋C�Â���������܂����B�����A�����������璠��̂Ƃ���ɂ邵�Ă������炵�Ă���ƌ������Ƃł����B���Ă݂�ƁA�����ɂ͓����d�b���A���ɂ��A�①�ɂ��A�e�B�b�V��������܂���B�铒�̏h�Ƃ��Ă͗����ݒ�͂�⍂�߂ł��̂ŁA������e�B�b�V�����炢�͂����Ă������̂ł͂Ȃ����Ɗ����܂����B |
 �����������C�Ɍ������܂��B���C�͈ꖜ�ڕ��C�Ɩ��t�����Ă��āA�I�V����Y��ȓ��{�A���v�X�̎p�����߂��܂��B�������A���܂�������ԂŎR�X�̑S�̂�ʂ��Č��n�����Ƃ������Ԃ͂Ȃ��A���Ԃ�ς��ĕ����I�Ɍ���ꂽ�Ƃ��������ł����B�j�����͂���̂ł����A��㎞�Ԃ͗[�H�����̂P�O���܂ł����ŁA������߂���Ƃ܂����ɖ߂��Ă��܂��܂��B�����̘I�V�͏����̕������߂��ǂ��炵���A�܂�A���̘I�V�ɒj���������͖̂�Ɍ����Ă���Ƃ������ƂŁA����͔��Ɏc�O�ł����B�i�F�����߂��Ȃ��Ⴕ�傤���Ȃ��Ǝv���A���ǂ�����̕��C�ɂ͑S�R����܂���ł����B�j���p�̘I�V�͓����̌����ɉ����ĉV�̐Q�����ɍג������̂ŁA�R�E�S�l���炢��������Ȃ������ł��B�����A����͓���Ƃ��j���̏h���q�����Ȃ��A�ǂ̎��Ԃł����Ƃ������Ɠ��邱�Ƃ��ł��܂����B���������ǂ��Ȃ��Ƃ͂����A����Ȃ�ɓ��{�A���v�X�����߂��邵�A����������邢���I�V���Ǝv���܂��B����������قǍL���͂Ȃ��A�S�E�T�l��������ς��ɂȂ肻���ł��B��≷�ڂ̕����ƔM�������Ƃ�������Ă��܂����A�S�̓I�ɘI�V���܂߂ēK�����Ɗ����܂����B����͂X�U�x�ŁA�������啪���̌�������Ă��邻���ł��B�����̑���͘I�V�̏�ɏ��������������悤�Ȋ����ł��B���M�͊╗�C�Ŏ���ɖ̔����菄�炳��A�V��͔����v���X�`�b�N�̔g�ł��B�������Ŕ��ɖ��邭�A�ڂ��͂��̓����͍D�܂������̂Ɋ����܂����B��͂S�E�T��������A�����ƃV�����[�����Ă��܂����B�����A��̂Ƃ���ɂԉ��̋�̗e�킪�������u����A���̈�ɂ͐��H�����܂��Ă��܂����B���̕ӂ͋C��z���ė~���������ł��B�͗�����ł����A���Ɋ܂ނƎ_���ς��₵����ς��Ȃǂ̎h���I�Ȗ��͂܂����������A���Â��������L����܂��B �����������C�Ɍ������܂��B���C�͈ꖜ�ڕ��C�Ɩ��t�����Ă��āA�I�V����Y��ȓ��{�A���v�X�̎p�����߂��܂��B�������A���܂�������ԂŎR�X�̑S�̂�ʂ��Č��n�����Ƃ������Ԃ͂Ȃ��A���Ԃ�ς��ĕ����I�Ɍ���ꂽ�Ƃ��������ł����B�j�����͂���̂ł����A��㎞�Ԃ͗[�H�����̂P�O���܂ł����ŁA������߂���Ƃ܂����ɖ߂��Ă��܂��܂��B�����̘I�V�͏����̕������߂��ǂ��炵���A�܂�A���̘I�V�ɒj���������͖̂�Ɍ����Ă���Ƃ������ƂŁA����͔��Ɏc�O�ł����B�i�F�����߂��Ȃ��Ⴕ�傤���Ȃ��Ǝv���A���ǂ�����̕��C�ɂ͑S�R����܂���ł����B�j���p�̘I�V�͓����̌����ɉ����ĉV�̐Q�����ɍג������̂ŁA�R�E�S�l���炢��������Ȃ������ł��B�����A����͓���Ƃ��j���̏h���q�����Ȃ��A�ǂ̎��Ԃł����Ƃ������Ɠ��邱�Ƃ��ł��܂����B���������ǂ��Ȃ��Ƃ͂����A����Ȃ�ɓ��{�A���v�X�����߂��邵�A����������邢���I�V���Ǝv���܂��B����������قǍL���͂Ȃ��A�S�E�T�l��������ς��ɂȂ肻���ł��B��≷�ڂ̕����ƔM�������Ƃ�������Ă��܂����A�S�̓I�ɘI�V���܂߂ēK�����Ɗ����܂����B����͂X�U�x�ŁA�������啪���̌�������Ă��邻���ł��B�����̑���͘I�V�̏�ɏ��������������悤�Ȋ����ł��B���M�͊╗�C�Ŏ���ɖ̔����菄�炳��A�V��͔����v���X�`�b�N�̔g�ł��B�������Ŕ��ɖ��邭�A�ڂ��͂��̓����͍D�܂������̂Ɋ����܂����B��͂S�E�T��������A�����ƃV�����[�����Ă��܂����B�����A��̂Ƃ���ɂԉ��̋�̗e�킪�������u����A���̈�ɂ͐��H�����܂��Ă��܂����B���̕ӂ͋C��z���ė~���������ł��B�͗�����ł����A���Ɋ܂ނƎ_���ς��₵����ς��Ȃǂ̎h���I�Ȗ��͂܂����������A���Â��������L����܂��B |
 �[�H�͂U������ƌ��߂��Ă���A�u�eood���y�v�Ƃ����H�����ň�Ăɂ͂��܂�܂��B�����A�s���ɂ���Ă͂��炵�Ă��\��Ȃ��悤�ŁA�ׂ̐Ȃ̐l�͂U�����ɂ���Ă��܂����B�ł��A���̏ꍇ�́A�O�Ȃǂ�H�ׂ�]�T�̂Ȃ������Ɏ��̕i�����������Ă��܂��悤�ł��B�H�����͏W���^�ł����A�Z���X�悭�d���Ă��肠�܂�C�ɂȂ�܂���B�����\�������Ƃ��Ă���A����Ɏ��l�����̏�̉��g���̋q�ɕ�������悤�ɁA�傫�Ȑ��Ő��������܂��̂ŁA����H�ׂĂ���̂����ǂ�������܂��B�悭���ւ��̌����Ƃ������̂�����܂����A���Ƃ����̌����͓��ւ��ł��B�Ƃ����Ă��A�R�U�T�������������ς��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�������̃T�C�N���ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�A������Ƃ��̋q�����Q���ڂ͈Ⴄ�����Ƃ������ƂɂȂ�̂����ʂł����A���ւ��̂������ŁA���̓��̏h���q�̌����͑S�������ł��B��������A�A���q�p�ɕʂɗ�����p�ӂ��Ȃ��Ă��ςނ��A�����������ł����̂ŁA�Ȃ�قǂ悭�l���Ă���ȂƎv���܂����B����ڂ̐H�O���͔����C�����x�[�X�ɂ������́A����ڂ͐ԃ��C�����x�[�X�ɂ������̂ɂ��ꂼ��l�X�Ȃ��̂�Ђ����葢��̐H�O���ł��B�ŏ��ɑO�⏬���ȂǂT�i���炢�����ׂ��A���̌�A��i�����Ԃ����v����Ď����Ă��Ă���܂��B���̃y�[�X�͑������������A�x�����������ŁA�������ƐH�ׂ邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��A����ڂ͓V�Ղ炪�g���邽�тɁA��i���A����~�����唫�̒��ɓ���Ă����Ă����Ƃ������@�ŁA�܂��ɁA�u�����͓V�n�����H�v�Ƃ����A���߂ׂ̍����H�ׂ������ł����B���Ƃ��Ƒf�ނ������̂ł����A�������ł��ׂĂ����̂܂܁A���������H�ׂ邱�Ƃ��ł��܂����B�V�n���͈ӊO�ȑf�ނ����������������邱�Ƃ��܂܂���̂ł����A���̓��͐M�B��̓V�n���������ł����B�Ö�������A�߂ƈ�̂ɂȂ��ĐV�������������������o���Ă���悤�Ɋ����܂����B�܂��A����ڂ͒��S�ƂȂ�f�ނƂ���⡂����グ���Ă���A⡂̎h�g�A�Ă�⡂ȂǁA���������H�ׂ邱�Ƃ��ł��܂����B�����A⡂͒n���̂��̂ɂ͂܂������A��B����̂��̂Ƃ������Ƃł�������A�n���̂��̂��g����V�[�Y���ɂȂ�Ƃ���ɂ����������̂��H�ׂ��邱�ƂƎv���܂��B�����Ɏg���Ă���f�ނ͂悭�ᖡ����Ă�����̂ł��B���Ɉ���ڂ̎R�T���_�̂��Ⴋ���Ⴋ�Ƃ�������������쐫���͉��Ƃ������܂���ł����B�܂��A�����������̂ŁA����ڂ̊��̂������A����ڂ��u��Ӗ��������ł����ĐH�ׂ銛��͐�i�ł����B���͈���ڂ��R���A����ڂ��⋛�ŎR���͔��Ɏp���������A�⋛�͍����ƐH�ׂ�ꂢ����������������̂ł��B�����͐M�B�̎R�̒��ł��̂ŁA�h�g�͈���ڂ����̂������A�����t�A����ڂ����̂������A�s���i�A���G�j�A⡁A�Ƃ����\���ŁA�����Ȃ��Ă��\�������ł��܂��B���̑��A����ڂ̓`�[�Y�̒��q�������a�m�̌����ȍ����A����ڂ͒��������߂�̑u������]���������Ǝv���܂��B�H���͈���ڂ͔~�����Ђ��A����ڂ͖��ؒ��Ђ��B�f�U�[�g�͈���ڂ���V���b�v�ρA����ڂ������ς肵�Ă��Ă����������A�C�X�ŁA���ꂼ��䕂�����܂��B����������̂��g���A��M�A�唫�ȂNJ�Â��������ɑ�_�ł��B�܂��ɁA�ǂ����Ƃ��Ă��A���ꂪ�M�B�̔铒�̐H�����Ǝv�킹����ɃZ���X�̂������̂ŁA���̌������J��Ԃ����̂łȂ���A�܂������ł��H�ׂɗ������Ǝv�킹���܂����B���̗��������̂��A�����݂���i�����̖������l�̉�����j�ŁA�{�i�I�ȗ����̏C�Ƃ͂܂������������Ƃ��Ȃ������ł��B�����A�����̕��������i��������H�̂ǂ��炩�j���o�Ă���炵���A�����A�������炭��Z���X�̗ǂ��������ɂ��\����������Ă���̂��Ɗ����܂����B���͓����H�����ŁA�o�C�L���O�ɂȂ�܂��B�P�O�������Ȃ��̂Ƀo�C�L���O�Ƃ͋����܂������A�������̕�����Ԃ��������ɂ��ނ̂��낤�Ǝv���܂��B�������ɋ��嗷�ق̗������ɂ͋y�т܂��A��ނ�������������A��W���[�X�A�����A�R�[�q�[�Ȃǂ�����܂��B����͈���ڂƓ���ڂƂł͂܂������ς�炸�A�m�����X�`�������������Ǝv���܂��B���X�`���炢�͕ς��Ă������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�������ɁA�[�H�قǂ̃p���[�͊����܂��A���͂��ׂč��i�_�ƌ����Ă����Ǝv���܂��B�����A�o����Ă���ʂ����Ȃ߂ŁA�����Ղ���͉̂������Ă��܂����������܂��B�o�C�L���O�̎��͂����ڂ��͎�肷���Č�����A�H�ׂ�̂Ɉꎞ�Ԃ��炢�������Ă��܂��̂ł����A�������͂R�O���ŏI����Ă��܂��܂����B�����A�݂�Ȃ��������邹�����A�Ō�͌��\�c���Ă���̂ł����E�E�B �[�H�͂U������ƌ��߂��Ă���A�u�eood���y�v�Ƃ����H�����ň�Ăɂ͂��܂�܂��B�����A�s���ɂ���Ă͂��炵�Ă��\��Ȃ��悤�ŁA�ׂ̐Ȃ̐l�͂U�����ɂ���Ă��܂����B�ł��A���̏ꍇ�́A�O�Ȃǂ�H�ׂ�]�T�̂Ȃ������Ɏ��̕i�����������Ă��܂��悤�ł��B�H�����͏W���^�ł����A�Z���X�悭�d���Ă��肠�܂�C�ɂȂ�܂���B�����\�������Ƃ��Ă���A����Ɏ��l�����̏�̉��g���̋q�ɕ�������悤�ɁA�傫�Ȑ��Ő��������܂��̂ŁA����H�ׂĂ���̂����ǂ�������܂��B�悭���ւ��̌����Ƃ������̂�����܂����A���Ƃ����̌����͓��ւ��ł��B�Ƃ����Ă��A�R�U�T�������������ς��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�������̃T�C�N���ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�A������Ƃ��̋q�����Q���ڂ͈Ⴄ�����Ƃ������ƂɂȂ�̂����ʂł����A���ւ��̂������ŁA���̓��̏h���q�̌����͑S�������ł��B��������A�A���q�p�ɕʂɗ�����p�ӂ��Ȃ��Ă��ςނ��A�����������ł����̂ŁA�Ȃ�قǂ悭�l���Ă���ȂƎv���܂����B����ڂ̐H�O���͔����C�����x�[�X�ɂ������́A����ڂ͐ԃ��C�����x�[�X�ɂ������̂ɂ��ꂼ��l�X�Ȃ��̂�Ђ����葢��̐H�O���ł��B�ŏ��ɑO�⏬���ȂǂT�i���炢�����ׂ��A���̌�A��i�����Ԃ����v����Ď����Ă��Ă���܂��B���̃y�[�X�͑������������A�x�����������ŁA�������ƐH�ׂ邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��A����ڂ͓V�Ղ炪�g���邽�тɁA��i���A����~�����唫�̒��ɓ���Ă����Ă����Ƃ������@�ŁA�܂��ɁA�u�����͓V�n�����H�v�Ƃ����A���߂ׂ̍����H�ׂ������ł����B���Ƃ��Ƒf�ނ������̂ł����A�������ł��ׂĂ����̂܂܁A���������H�ׂ邱�Ƃ��ł��܂����B�V�n���͈ӊO�ȑf�ނ����������������邱�Ƃ��܂܂���̂ł����A���̓��͐M�B��̓V�n���������ł����B�Ö�������A�߂ƈ�̂ɂȂ��ĐV�������������������o���Ă���悤�Ɋ����܂����B�܂��A����ڂ͒��S�ƂȂ�f�ނƂ���⡂����グ���Ă���A⡂̎h�g�A�Ă�⡂ȂǁA���������H�ׂ邱�Ƃ��ł��܂����B�����A⡂͒n���̂��̂ɂ͂܂������A��B����̂��̂Ƃ������Ƃł�������A�n���̂��̂��g����V�[�Y���ɂȂ�Ƃ���ɂ����������̂��H�ׂ��邱�ƂƎv���܂��B�����Ɏg���Ă���f�ނ͂悭�ᖡ����Ă�����̂ł��B���Ɉ���ڂ̎R�T���_�̂��Ⴋ���Ⴋ�Ƃ�������������쐫���͉��Ƃ������܂���ł����B�܂��A�����������̂ŁA����ڂ̊��̂������A����ڂ��u��Ӗ��������ł����ĐH�ׂ銛��͐�i�ł����B���͈���ڂ��R���A����ڂ��⋛�ŎR���͔��Ɏp���������A�⋛�͍����ƐH�ׂ�ꂢ����������������̂ł��B�����͐M�B�̎R�̒��ł��̂ŁA�h�g�͈���ڂ����̂������A�����t�A����ڂ����̂������A�s���i�A���G�j�A⡁A�Ƃ����\���ŁA�����Ȃ��Ă��\�������ł��܂��B���̑��A����ڂ̓`�[�Y�̒��q�������a�m�̌����ȍ����A����ڂ͒��������߂�̑u������]���������Ǝv���܂��B�H���͈���ڂ͔~�����Ђ��A����ڂ͖��ؒ��Ђ��B�f�U�[�g�͈���ڂ���V���b�v�ρA����ڂ������ς肵�Ă��Ă����������A�C�X�ŁA���ꂼ��䕂�����܂��B����������̂��g���A��M�A�唫�ȂNJ�Â��������ɑ�_�ł��B�܂��ɁA�ǂ����Ƃ��Ă��A���ꂪ�M�B�̔铒�̐H�����Ǝv�킹����ɃZ���X�̂������̂ŁA���̌������J��Ԃ����̂łȂ���A�܂������ł��H�ׂɗ������Ǝv�킹���܂����B���̗��������̂��A�����݂���i�����̖������l�̉�����j�ŁA�{�i�I�ȗ����̏C�Ƃ͂܂������������Ƃ��Ȃ������ł��B�����A�����̕��������i��������H�̂ǂ��炩�j���o�Ă���炵���A�����A�������炭��Z���X�̗ǂ��������ɂ��\����������Ă���̂��Ɗ����܂����B���͓����H�����ŁA�o�C�L���O�ɂȂ�܂��B�P�O�������Ȃ��̂Ƀo�C�L���O�Ƃ͋����܂������A�������̕�����Ԃ��������ɂ��ނ̂��낤�Ǝv���܂��B�������ɋ��嗷�ق̗������ɂ͋y�т܂��A��ނ�������������A��W���[�X�A�����A�R�[�q�[�Ȃǂ�����܂��B����͈���ڂƓ���ڂƂł͂܂������ς�炸�A�m�����X�`�������������Ǝv���܂��B���X�`���炢�͕ς��Ă������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�������ɁA�[�H�قǂ̃p���[�͊����܂��A���͂��ׂč��i�_�ƌ����Ă����Ǝv���܂��B�����A�o����Ă���ʂ����Ȃ߂ŁA�����Ղ���͉̂������Ă��܂����������܂��B�o�C�L���O�̎��͂����ڂ��͎�肷���Č�����A�H�ׂ�̂Ɉꎞ�Ԃ��炢�������Ă��܂��̂ł����A�������͂R�O���ŏI����Ă��܂��܂����B�����A�݂�Ȃ��������邹�����A�Ō�͌��\�c���Ă���̂ł����E�E�B
���āA������Y��Ă͂Ȃ�Ȃ������́A�����َ̊�x�]���l�Y����ł��傤�B���̗��ق���ďグ���l�ł����A�ꌾ�ł����Ɛl�Ȃ����ʔ�����������ł��B���ʂ̗��ق͗[�H�̎��ɏ��������A�ɗ����肵�܂����A�����͕��l�Y���A�ӂ��Ƃ���Ă��ċq�ɘb�������A��g���b���Ă����܂��B�l�Ȃ����S�R���C�̂Ȃ��l�ł����A�Ƃ�����Ƃ��̘b�������b�ł���A���ǂ��ǂ��Ă���Ɗ�����q������ł��傤�B�܂��A�����Ȑ��i���炩�A�Ⴂ�����̃O���[�v�قǘb�������Ȃ�X��������悤�Ɍ����܂����B�b���ʔ����̂͂����̂ł����A���̊ԁA�H�������f���ꂽ��A�W���͂������ꂽ�肵�܂��B����ڂ͖^����n�̎Ꮧ���T�l�̃O���[�v���h�����Ă����炵���̂ł����A���������������Ԃ������܂��Ęb���Ă����悤�ł��B�������A���l�Y����Ƃ̘b���y���݂ɂ���Ă���q����������Ǝv���܂��̂ŁA����͔ᔻ�ł����ł��Ȃ��A���������ʔ�������������Ƃ������Ƃł��B�����ɂ́u�R�̏h�ł��̂Łv�u�Ƒ��S�l�ł���Ă���h�ł��̂Łv�Ƃ����f�菑���A������͈����܂���B���̓_�͗��h���Ƃ͎v���̂ł����A�����A�������Ƃ��ĕ\��Ă��Ă��܂��Ƃ��낪����܂��B�܂��A���ɁA�①�ɂ͂����Ƃ��Ă��Œ�C���^�[�t�H���͂���ׂ��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������J���邱�Ƃ̂ł��Ȃ��ً}�̎��Ԃ��N���邩������܂���B�܂��A�A�����Ă��V�����얱�߂̒������A�A���j�e�B�̒lj��A�����̑|���A�V�[�c�Ȃǂ̑ւ�������܂���B�|����V�[�c�͂��̂܂܂ō\���܂��A�������Ǝ��u���V�Ȃǂ̃A���j�e�B�͂��������������Ǝv���܂��B�X���b�p���Ȃ����A�A���j�e�B�ɂ͑��܂��������t���Ă��܂����A�_�o���Ȑl�͑ւ����ق����ł��傤�B��x�����Ɉē�������A���Ƃ͈�ؕ����ɂ͗�������Ȃ��Ƃ������j�ł���̂͂����Ǝv���܂����A���H�̌�ɒ��ւ���n���ȂǁA���̓_�����͍čl��v����Ǝv���܂��B���̏h�͉Ƒ��o�c�̏h�Ƃ����R���̒��ł͂����炭�ō���̈�ł͂Ȃ��ł��傤���B���ɗ����͑f���炵���B�܂��A�铒�ł��������K�ȏh�Ƃ����R���̒��ł���ʂɓ���ł��傤�B���ƁA�ق�̂킸���Ȃ��Ƃ��N���A����������A���{�̈�̏h�Ƃ��Ă̑����I�ȕ]�������܂�Ǝv���܂��B���ł��A���s�[�^�[�̑����h�ł��B�\��̎��Ȃ��h�ƂȂ�̂������������Ƃł͂Ȃ���������܂���B |
| �V���ւ̎l���̗��ɍs���Ă��܂����B�O���͏����A����J���܂������A�㔼�͂ǂ���Ƃ����܂��Ŕ����������ł����B�Ƃ͌����A���V�R�̔��l�сA�܂��A���Ë������߂Ƃ���V���̐V�Ƃ��̒��ɓ_�݂���A����˂̉Ԃ̏�i�ȓ��F�Ɍ����ꂽ�ܓ��Ԃ̗��ł����B |
| �@ |
| �����͉z�㓒��́u�z�e���o�t�v�ł��B�����͂V�V���̑�^���قŁA���ƍŋ߁A�R�̓��Ƃ����V������������������ł��B���Ƃ��Ƃ����̂����C�͉z�㓒��̒��ł������炵���������炵���̂ŁA��x�s���Ă݂����Ǝv���Ă����̂ł����B�h�ɓ��������̂͂P���R�O�����ŁA�����͂Q�����C���̎��ԂȂ̂ł����A�ڂ��������������_�ŏh�̑O�ɂ͘a���𒅂������Ƃ�����l�̏]�ƈ����o�}���ɗ����Ă��܂����B����͂�����ʋq�̂��߂ɗ����Ă����̂��A����Ƃ��c�̂̓������Ԃ��܂��Ȃ��Ȃ̂ŗ����Ă����̂��͂킩��܂���ł������A��ʋq�̂��߂ɂR�O�����O����Ȃ炽���������̂��Ǝv���܂��B���ԑO�ł������A�҂�����邱�Ƃ��Ȃ��A�����Ɉē����Ă��炦�܂����B���r�[��L���ɂ͉Ԃ������Ɋ������Ă��܂��B���̕ӂ͑�^���قȂ�ł͂̍����Ƃ������������܂����B�����͓��̓��ݍ��݂ɂP�O��̎厺�A�L�߂̍L���Ƃ�����ʓI�ȍL���ł��B�܂��V���ڂƂ��������ł��傤���B������̏��̊Ԃɂ͉Ԃ������Ă���܂����A�L���̍��Ȋ����ɔ�ׂāA�Ƃ肠���������Ă܂��Ƃ����f���C�����ł����B���̓��͓V�C���ǂ��A�z�㓒��̉w�}��������̂ł����A����Ȃɉ����Ȃ������يX�������Ă݂悤�Ƃ������Ƃŕ����ė����̂ŁA�����̒����Ə��������܂��B�����ňē��W�̏����ɗ�[�ɂ��Ăق����Ɨ��Ƃ���A�������ɂ傲�ɂ匾���āA�G�A�R�������Ă����܂����B�ē��W�̏�������������A����Ă��ꂽ����������A�����݂̂����肩�炨�����|�g�|�g�E�E�B����ƒ�������Z���ɂȂ��Ă��܂����B�G�A�R�����S���������A�����o�����Ɏ�ĂĂ݂�ƂȂ�Ɖ����������o�Ă��܂����B�ǂ��������͑S�و�Ă̗�g�[�ŁA��͗₦�邽�߂܂��g�[�̂܂܂������悤�ł��B���̈ē��W�͎g���܂���B�g�C���̓V�����[�g�C���A�����C������܂�����������ł͂Ȃ��ł��傤�B�܂��A������������тɂ݂��݂������ނ̂��C�ɂȂ�܂����B������̒��߂́A�����̂܂��������ɐ�̎c��R�X�A�߂��̗̎R�X�Ƃ��������ł����A���̊K�̉������������Ȃ莋�E���߂Ă��܂��B |
 ���������A�����C�������܂��B�ŋ߂ł����炵���R�̓��Ƃ����͍̂L���A��������̗���������̂ł����A�ꂩ�������Ȃ��̂Œj�����ɂȂ�܂��B�j���͒������̂W���܂łŁA����ȊO�̎��Ԃ͂��ׂď����ł��B���̏h�͏����D�ʂ̏h�ł��邱�Ƃ�搂��Ă���炵���A�A���j�e�B�̑��܂����������A�f�U�[�g�̂��������������̃T�[�r�X�ŁA�������ɂ��̓��������̒c�̋q�����������悤�ł��B���Ƃ��ƒj���ʂɂ������嗁��Ƃ���ɑ����I�V����㐧�ŁA��̂����������Ƃ�������̂���I�V�̕�����܂ŏ����p�A�j���͒������ł����B�R�̓��́A�L�߂̓����Ə����߂̘I�V������������ԂƂ�������ɂȂ��Ă��܂����A����ɓ���Ȃ肩�����ȉ��f�L�����܂��B���ꂾ����������̗�����������̂ł�����A�z�͓��R��������܂���B�������Ȃ߂Ă݂Ă��A�قƂ�Ǔ����̂Ȃ������Ƃ��������ł����B�m����������Ƃ������Ƃł����A�����͂��܂���B���ʂ�ڂ̓K���ł��傤���B�����͓����̎d�肪�قƂ�ǃK���X�˂ɂȂ��Ă��āA���Ԃ͂��̃K���X�˂����ׂĊJ������āA���I�V�̊����ɂȂ��Ă��܂��B���邭�J����������A�����ŏ\�������ł��܂����B���Ƃ��Ə��������D�͍D���ł͂Ȃ��̂ŁA���̑��̓��M�͈ꉞ�����������ł����B���������D�̈�ɁA����ɐ^��̕�����ꂽ�Ƃ����u�^�앗�C�v�Ȃ���̂������āA�������Ă��܂��B�����͏����ɂ͐l�C�̗����̂悤�ł��B���̎R�̓��̓��オ��ǂ���ɂ͂����Ɨ␅���u���Ă���A���~�Ə����Ȃ��イ��̂����̂��H�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B���̂��イ��͂����������̂ł����B���Ƃ��Ƃ������嗁��ƘI�V���Ȃ��Ȃ��������ǂ��A��R�X�̌����炵�������Ă��ꂾ���ł��\�������ł�����̂ł��B ���������A�����C�������܂��B�ŋ߂ł����炵���R�̓��Ƃ����͍̂L���A��������̗���������̂ł����A�ꂩ�������Ȃ��̂Œj�����ɂȂ�܂��B�j���͒������̂W���܂łŁA����ȊO�̎��Ԃ͂��ׂď����ł��B���̏h�͏����D�ʂ̏h�ł��邱�Ƃ�搂��Ă���炵���A�A���j�e�B�̑��܂����������A�f�U�[�g�̂��������������̃T�[�r�X�ŁA�������ɂ��̓��������̒c�̋q�����������悤�ł��B���Ƃ��ƒj���ʂɂ������嗁��Ƃ���ɑ����I�V����㐧�ŁA��̂����������Ƃ�������̂���I�V�̕�����܂ŏ����p�A�j���͒������ł����B�R�̓��́A�L�߂̓����Ə����߂̘I�V������������ԂƂ�������ɂȂ��Ă��܂����A����ɓ���Ȃ肩�����ȉ��f�L�����܂��B���ꂾ����������̗�����������̂ł�����A�z�͓��R��������܂���B�������Ȃ߂Ă݂Ă��A�قƂ�Ǔ����̂Ȃ������Ƃ��������ł����B�m����������Ƃ������Ƃł����A�����͂��܂���B���ʂ�ڂ̓K���ł��傤���B�����͓����̎d�肪�قƂ�ǃK���X�˂ɂȂ��Ă��āA���Ԃ͂��̃K���X�˂����ׂĊJ������āA���I�V�̊����ɂȂ��Ă��܂��B���邭�J����������A�����ŏ\�������ł��܂����B���Ƃ��Ə��������D�͍D���ł͂Ȃ��̂ŁA���̑��̓��M�͈ꉞ�����������ł����B���������D�̈�ɁA����ɐ^��̕�����ꂽ�Ƃ����u�^�앗�C�v�Ȃ���̂������āA�������Ă��܂��B�����͏����ɂ͐l�C�̗����̂悤�ł��B���̎R�̓��̓��オ��ǂ���ɂ͂����Ɨ␅���u���Ă���A���~�Ə����Ȃ��イ��̂����̂��H�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B���̂��イ��͂����������̂ł����B���Ƃ��Ƃ������嗁��ƘI�V���Ȃ��Ȃ��������ǂ��A��R�X�̌����炵�������Ă��ꂾ���ł��\�������ł�����̂ł��B |
 �H���͖�͕����ŁA���̓o���P�b�g���[���ł̃o�C�L���O�ɂȂ�܂��B��͂��i�������t���܂��������͂���܂���B�H�O���͂�������Ƃ����A�����ɂ�����̉Ԃ���ꂽ���̂ł����������̂ł����B�O�i�̒�����I�ׂ���̂ƁA��i�̒�����I�ׂ���̂Ɠ��ގ����őI�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B�ڂ��̓X�e�[�L�ƁA�����̃N���[���ςɂ��Ă݂܂����B���߂ɑO�A�h�g�ȂǘZ�i�����ׂ��B�����ƒn�{��ɉ����悤�Ƃ����̂ŁA�n�{�炾���͂�����ł��邩��ƁA�Ƃ肠�������̂܂܂ɂ��Ă��炢�܂����B�H�ׂĂ��邤���ɒlj��̗������^��Ă��邾�낤�Ǝv���Ă����̂ł����A�Ȃ��Ȃ�����Ă��܂���B���̓��ɐH�ׂ���̂��Ȃ��Ȃ肻���ɂȂ��Ă����̂ŁA����ĂĒn�{��ɉ����܂����B�Ȃ�قǁA��ɉ����悤�Ƃ����̂͂�����������炩�Ɣ[���������܂����B�����͐���ɐ��������A���̒��ɂɂ���Ɠ����̓��������q���Ŏg���悤�ȊW�t���̗e�킪���܂��Ă��āA�ڂ̑O�ō��Ƃ�������ł��B��ɏo���ꂽ�Z�i�̒��ł́A���̒n�{��A�����͂��������������̂́A���̑��ɂ͈�ۂɎc�������̂͂���܂���ł����B�O�̒��ɂ�͂�\���}�����ꗱ�����Ă��āA�V���Ƀ\���}���̖@������ꂻ���ł��B�ꎞ�Ԃقǂ��āA�O�i��x�ɉ^��Ă��܂������A�Ȃ�ƃX�e�[�L�͗�ߐ��Ă��܂��B���̊Ԃɉ����͂��܂ꂽ�����Â������̂Ȃ̂ŁA����������Ɨ�d���ĂȂ̂��ȂƂ��v���܂������A��͂肱��͉�����������ɂ����������낤�Ƃ������ł����B�����̃N���[���ς͉��������̂����Ă��܂������A��͂��߂Ă��č��ʐ^�Ō��Ă��A�\�ʂɔ��������͂��Ă��̖��ɂ��킪����Ă��܂��B�܂��A���ɐ[�݂�����܂���B������i�����͂����ł������A�c�O�Ȃ��疡�͍���ł��B�Ō�̖��X�`�����̌���͔��ɉ��܂邨���������̂ł����B�f�U�[�g�͈ǐm�����̈ǐm�ɐ��N���[����Y�������̂ł��������ł����B�Ƃ������ƂŁA���̂悤�ɂ�����x�O�]���̂����h�ŁA�₽�����̂�H�ׂ�������Ƃ������肵�܂��B���̗������^��ł��ꂽ��������͂������̈ē��W�Ƃ͈���Ĕ��Ɋ����̂����l�����������ɁA�����͒�������̂����ł͂Ȃ��Ƃ͂����A�c�O�ł����B���̃o�C�L���O���������ʂŁA�܂���̎R�|���ȊO�͖ڗ��������̂͂Ȃ��A�X���܂ł̎��ԑтłW���ɂ������̂ɂ�������炸�A���͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���̌�lj����ꂽ�݂����ł����A�����ڂ����������Ȃ������ł����B�S�ʓI�ɁA���͂�����ʓI�������Ǝv���܂��B�����A�����̊O�ɂ��Ȃ����肻��ȂɌ����炵�͗ǂ��Ȃ��̂ł����A�������Ɍ܌��̂���₩�ȕ��͐H�~���������ĂĂ���܂����B����̑o�t�قǑ�^���ق̌��_���o�Ă��܂����Ƃ���͂Ȃ��悤�Ɋ����܂��B�����A�[�H�̎��ԑт͒c�̂Ɏ���Ƃ��Čl�q�͕����Ă����ꂽ�̂ł��傤�B�����́A���Ԃ̎��Ԃɂ̓Z�~�i�[�Ȃǂ��J����Ă����炵�����ɂɂ�����Ă����ۂł��B�c�̌����̗��ق��A�����݂��������Ȃ钆�A�܂��ɒc�̌����ł܂��Ȃ��������Ă��闷�قƂ������Ƃ��ł���ł��傤�B �H���͖�͕����ŁA���̓o���P�b�g���[���ł̃o�C�L���O�ɂȂ�܂��B��͂��i�������t���܂��������͂���܂���B�H�O���͂�������Ƃ����A�����ɂ�����̉Ԃ���ꂽ���̂ł����������̂ł����B�O�i�̒�����I�ׂ���̂ƁA��i�̒�����I�ׂ���̂Ɠ��ގ����őI�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B�ڂ��̓X�e�[�L�ƁA�����̃N���[���ςɂ��Ă݂܂����B���߂ɑO�A�h�g�ȂǘZ�i�����ׂ��B�����ƒn�{��ɉ����悤�Ƃ����̂ŁA�n�{�炾���͂�����ł��邩��ƁA�Ƃ肠�������̂܂܂ɂ��Ă��炢�܂����B�H�ׂĂ��邤���ɒlj��̗������^��Ă��邾�낤�Ǝv���Ă����̂ł����A�Ȃ��Ȃ�����Ă��܂���B���̓��ɐH�ׂ���̂��Ȃ��Ȃ肻���ɂȂ��Ă����̂ŁA����ĂĒn�{��ɉ����܂����B�Ȃ�قǁA��ɉ����悤�Ƃ����̂͂�����������炩�Ɣ[���������܂����B�����͐���ɐ��������A���̒��ɂɂ���Ɠ����̓��������q���Ŏg���悤�ȊW�t���̗e�킪���܂��Ă��āA�ڂ̑O�ō��Ƃ�������ł��B��ɏo���ꂽ�Z�i�̒��ł́A���̒n�{��A�����͂��������������̂́A���̑��ɂ͈�ۂɎc�������̂͂���܂���ł����B�O�̒��ɂ�͂�\���}�����ꗱ�����Ă��āA�V���Ƀ\���}���̖@������ꂻ���ł��B�ꎞ�Ԃقǂ��āA�O�i��x�ɉ^��Ă��܂������A�Ȃ�ƃX�e�[�L�͗�ߐ��Ă��܂��B���̊Ԃɉ����͂��܂ꂽ�����Â������̂Ȃ̂ŁA����������Ɨ�d���ĂȂ̂��ȂƂ��v���܂������A��͂肱��͉�����������ɂ����������낤�Ƃ������ł����B�����̃N���[���ς͉��������̂����Ă��܂������A��͂��߂Ă��č��ʐ^�Ō��Ă��A�\�ʂɔ��������͂��Ă��̖��ɂ��킪����Ă��܂��B�܂��A���ɐ[�݂�����܂���B������i�����͂����ł������A�c�O�Ȃ��疡�͍���ł��B�Ō�̖��X�`�����̌���͔��ɉ��܂邨���������̂ł����B�f�U�[�g�͈ǐm�����̈ǐm�ɐ��N���[����Y�������̂ł��������ł����B�Ƃ������ƂŁA���̂悤�ɂ�����x�O�]���̂����h�ŁA�₽�����̂�H�ׂ�������Ƃ������肵�܂��B���̗������^��ł��ꂽ��������͂������̈ē��W�Ƃ͈���Ĕ��Ɋ����̂����l�����������ɁA�����͒�������̂����ł͂Ȃ��Ƃ͂����A�c�O�ł����B���̃o�C�L���O���������ʂŁA�܂���̎R�|���ȊO�͖ڗ��������̂͂Ȃ��A�X���܂ł̎��ԑтłW���ɂ������̂ɂ�������炸�A���͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���̌�lj����ꂽ�݂����ł����A�����ڂ����������Ȃ������ł����B�S�ʓI�ɁA���͂�����ʓI�������Ǝv���܂��B�����A�����̊O�ɂ��Ȃ����肻��ȂɌ����炵�͗ǂ��Ȃ��̂ł����A�������Ɍ܌��̂���₩�ȕ��͐H�~���������ĂĂ���܂����B����̑o�t�قǑ�^���ق̌��_���o�Ă��܂����Ƃ���͂Ȃ��悤�Ɋ����܂��B�����A�[�H�̎��ԑт͒c�̂Ɏ���Ƃ��Čl�q�͕����Ă����ꂽ�̂ł��傤�B�����́A���Ԃ̎��Ԃɂ̓Z�~�i�[�Ȃǂ��J����Ă����炵�����ɂɂ�����Ă����ۂł��B�c�̌����̗��ق��A�����݂��������Ȃ钆�A�܂��ɒc�̌����ł܂��Ȃ��������Ă��闷�قƂ������Ƃ��ł���ł��傤�B |
| �@ |
| ����ڂ͏��V�R�ł��B�r���A���l�тɗ������܌��̏��V�R�̔������Ԃȗт����\������A�����̏h�u翂̏h��v�ւƌ������܂����B�u翂̏h��v�͏��V�R�̉���X�̂��[�Ɉʒu���Ă���A������܂�Ƃ������قł��B���r�[���L���͂���܂��A���ւ���������ʂɒ���̂悤�Ȃق�̏����Ȓ낪����A�r�ɂ͋��F�̌��������j���ł��āA�Â߂̎����ɉ₩�ȃA�N�Z���g�������Ă��܂��B�`�F�b�N�C�������̂͂R��������ƑO�ŁA�����ɂ͂������邱�Ƃ��ł��܂����B�m�������W��̒��������̂܂܈ē����Ă���܂����B���̒�������͐^�ʖڂ����Ȏ��������Ȑl�ł����B�������َq�͌��݂Ƃ����R�V�q�J���̕����g�����A���̏h�̃I���W�i���������ŁA���ɂ����������̂ł����B�����̓h�A�������Ă����E��ɐ��ʏ�������A���̉����g�C���ɂȂ��Ă��āA���̃g�C���̓V�����[�g�C���ł��B���ʂ̂ӂ��܂�������Ə\��̎厺�B���̐�ɍL�߂̍L���Ƃ�������ł��B�L���̉E�����̊ԂɂȂ��Ă��Ă����Ɍ@�育�������炦���Ă��܂��B�������A�������̎����ɂ͂����z�c�͊O����Ă��܂����B���̍����ɂ̓}�b�T�[�W�`�F�A���u����Ă��܂����B�ł��c�O�Ȃ���A�S�~����Ȃ��Ɠ����܂���B���������Ȃ��ō���ƁA�����������������ō��育�����������A�}�b�T�[�W�`�F�A���g��Ȃ��l�ɂƂ��ẮA���������̍L�߂̍L����苒����ז����ɂ����܂���B�����͑S�̂ɐV�������������ł��B���̊O�ɂ͉���X�̑O�̏��X�₻�̏���ɂ͖X�����߂��A�`�����݂͂���܂���B���������������������Ǝv���܂��B�␅�����߂���Z�b�g���Ă���܂��B |
 ������������̘I�V�ւƏo�����܂����B���̂����͌��̓��Ɩ��Â����A�����ォ����ꂽ���̂��Ǝv���܂��B���Ƃ��Ƃ̂����C�͈�K�ɒj���ʂɂ��ꂼ��I�V�����Ă���̂ł����A������͉����ŏz�̂悤�ł��B�������A���f�L�͂��܂���B���āA���̌��̓��ł����A�l�E�ܐl�قǓ���闁���̒[���猹������Ă��܂��B���������ł��B���Ƃŗ��ق̐l�����x�v�������Čv��ɂ����̂ł����A���������ԉ����Ίp���̂Ƃ���łS�S�x�A�߂��̒[�̂Ƃ���łS�V�x�B�����̂Ƃ���łV�V�x�i�H�j�������悤�ł��B�\�ʂ��M�����瓒���݂��ē���悤�ɂƂ������������蓒���ݔ��u���Ă���܂����̂ŁA���߂ē����݂��Ă݂܂������A����͂Ȃ��Ȃ����܂������Ȃ��ł��ˁB���Â̔M�̓��̓����݃V���[�݂����ɂ͂����Ȃ����Ȃ��Ǝv���܂����B�����ɂ͞w�̞e���u���Ă������ł���悤�ɂȂ��Ă��܂������A���̂��������炭�u���Ă����Ȃ��ƔM���Ĉ��߂܂���B��܂��Ĉ��Ƃ���A������ρ[���I�I�Ƃ��������ŁA���܂܂ň����ł̂�����ς��ō���Ƃ����C�����܂��B�܂��A���̏��V�R�͓��{�O��ł���炵���A�m���ɉ����̖�������悤�Ȗ������܂��B����ɞw�̞e�̂ɂ�����������ĉ��Ƃ����G�Ȗ��Ƃɂ����ɂȂ��Ă��܂����B���̐l�̓A�u���L���ƌ����Ă��܂������A�ڂ��͞w�̓������Ǝv���Ă��܂����B�Ƃɂ����A������ς����āA�e��t�����ɑ̂Ɉ����ȂƎv���Ă�����A�Ă̒�A����̍ۂ͎O�{�ɔ��߂Ĉ��ނ悤�ɂƂ����A������������܂����B�������������ɂ��ꂾ���̉����ł�����A�������܂邱�Ƃ͍ō��ł��ˁB�����A�c�O�Ȃ��Ƃɂ����͎R�ɋ߂��Ƃ������ƂŁA�u���������A�₽��Ɋ��ݕt���Ă��܂��B�A�u�قǂ͋���ł͂Ȃ����̂́A���܂肢�������͂��܂���B�܂��A�ĂɂȂ�ƘI�V�̒��ɂ�������̃��}�}���邪����t���Ă���Ƃ̏�A����̏�������܂����B�Ƃɂ����A�ڂ��͂��̔M�����ɏo����������肵�Ȃ���A���\�������ԓ����Ă��܂����B�����炵�͂܂��������̂́A�����ł��̂ő厩�R�̒��ƌ��������ł͂���܂���B�嗁����z���Ă���Ƃ͂����A���\�M���Ȃ��Ă��܂��B���f�L�͂��܂���̂ŁA���Ȃ藬����ɋ߂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B������܂肵�������ł����A���ق̋K�͂ɂ͍����Ă���Ƃ������܂��B�܂��A���݂��ꂽ�I�V����O�l�����x�Ƃ����������ŁA�����炵���܂���������܂��A�������ɋ��̉j�����ł̂悤�Ȃ��̂�����A�ʔ����Ǝv���܂����B�����A�����ɗ␅������Ƃ͂����A���オ��ǂ���ɂ��␅���ق����C�����܂����B ������������̘I�V�ւƏo�����܂����B���̂����͌��̓��Ɩ��Â����A�����ォ����ꂽ���̂��Ǝv���܂��B���Ƃ��Ƃ̂����C�͈�K�ɒj���ʂɂ��ꂼ��I�V�����Ă���̂ł����A������͉����ŏz�̂悤�ł��B�������A���f�L�͂��܂���B���āA���̌��̓��ł����A�l�E�ܐl�قǓ���闁���̒[���猹������Ă��܂��B���������ł��B���Ƃŗ��ق̐l�����x�v�������Čv��ɂ����̂ł����A���������ԉ����Ίp���̂Ƃ���łS�S�x�A�߂��̒[�̂Ƃ���łS�V�x�B�����̂Ƃ���łV�V�x�i�H�j�������悤�ł��B�\�ʂ��M�����瓒���݂��ē���悤�ɂƂ������������蓒���ݔ��u���Ă���܂����̂ŁA���߂ē����݂��Ă݂܂������A����͂Ȃ��Ȃ����܂������Ȃ��ł��ˁB���Â̔M�̓��̓����݃V���[�݂����ɂ͂����Ȃ����Ȃ��Ǝv���܂����B�����ɂ͞w�̞e���u���Ă������ł���悤�ɂȂ��Ă��܂������A���̂��������炭�u���Ă����Ȃ��ƔM���Ĉ��߂܂���B��܂��Ĉ��Ƃ���A������ρ[���I�I�Ƃ��������ŁA���܂܂ň����ł̂�����ς��ō���Ƃ����C�����܂��B�܂��A���̏��V�R�͓��{�O��ł���炵���A�m���ɉ����̖�������悤�Ȗ������܂��B����ɞw�̞e�̂ɂ�����������ĉ��Ƃ����G�Ȗ��Ƃɂ����ɂȂ��Ă��܂����B���̐l�̓A�u���L���ƌ����Ă��܂������A�ڂ��͞w�̓������Ǝv���Ă��܂����B�Ƃɂ����A������ς����āA�e��t�����ɑ̂Ɉ����ȂƎv���Ă�����A�Ă̒�A����̍ۂ͎O�{�ɔ��߂Ĉ��ނ悤�ɂƂ����A������������܂����B�������������ɂ��ꂾ���̉����ł�����A�������܂邱�Ƃ͍ō��ł��ˁB�����A�c�O�Ȃ��Ƃɂ����͎R�ɋ߂��Ƃ������ƂŁA�u���������A�₽��Ɋ��ݕt���Ă��܂��B�A�u�قǂ͋���ł͂Ȃ����̂́A���܂肢�������͂��܂���B�܂��A�ĂɂȂ�ƘI�V�̒��ɂ�������̃��}�}���邪����t���Ă���Ƃ̏�A����̏�������܂����B�Ƃɂ����A�ڂ��͂��̔M�����ɏo����������肵�Ȃ���A���\�������ԓ����Ă��܂����B�����炵�͂܂��������̂́A�����ł��̂ő厩�R�̒��ƌ��������ł͂���܂���B�嗁����z���Ă���Ƃ͂����A���\�M���Ȃ��Ă��܂��B���f�L�͂��܂���̂ŁA���Ȃ藬����ɋ߂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B������܂肵�������ł����A���ق̋K�͂ɂ͍����Ă���Ƃ������܂��B�܂��A���݂��ꂽ�I�V����O�l�����x�Ƃ����������ŁA�����炵���܂���������܂��A�������ɋ��̉j�����ł̂悤�Ȃ��̂�����A�ʔ����Ǝv���܂����B�����A�����ɗ␅������Ƃ͂����A���オ��ǂ���ɂ��␅���ق����C�����܂����B |
 �[�H�͕����ł��������܂��B���i�����͂���܂���ł������A��������������܂����B���߂ɂ���܂��A���тȂǂ̎R�̑O�A�ڂ���C�V�̓������h�g�A�A�P�r�̉��������̗��ŐH�ׂ�������́A�X�e�[�L�A�ȂǘZ�i�B�ォ�炯��O���^���A�g�����̂����A����A��̎ϕ��Ȃǎl�i���^��Ă��܂����B�X�e�[�L�͉����ł����ƕ����Ă������Ƃ����Ԏ��͂Ȃ������̂ł����A�ڂ��͂��Ȃ肨�������Ǝv���܂����B�ڂ��̐H�ׂ��X�e�[�L�͕đ̃`�����s�I�������g�����i�H�j��m�R�́u�×q�v�̂��̂��ō���Ȃ̂ł����A���g�̑�ϑ��́u���㋍�v�₱�̐�̋��ȂǐV���̋������̎����炢�̃��x���ł͂Ȃ����Ƃ��������܂����B�h�g�����������������A�������Ƃ����|�C���g�����������H�����Ǝv���܂��B��o���̂��̂͂��ׂĂ����ł����������������܂����B�f�U�[�g�̓[���[�ōH�v�̋Â炳�ꂽ���̂ł����B�S�̓I�Ƀo�����X�̂Ƃꂽ���������H�����Ǝv���܂����B�����A�����C���𗊂̂ł����A���C�����₷���C���N�[���[���Ȃ������̂��c�O�ł��A���C��������ނ��p�ӂ��Ă���h�ŁA���C���N�[���[���Ȃ��Ƃ͉����܂���B���H�������ł����B�����������������܂����B�R�،n�����S�ŏĂ����̑���ɂ��炷���t���܂������A�~����������ɉ����ďĂ������ق��������ł��B�܂����n�̗������Ȃ������̂��c�O�ł����B�Ƃ͂����A�����������т��H�ׂ��܂����B�������悤�ɁA���_���c�O�ȕ���������܂������A�S�̓I�ɐS�z�肪�s���͂��������h���Ǝv���܂��B����������قǍ����͂���܂���B �[�H�͕����ł��������܂��B���i�����͂���܂���ł������A��������������܂����B���߂ɂ���܂��A���тȂǂ̎R�̑O�A�ڂ���C�V�̓������h�g�A�A�P�r�̉��������̗��ŐH�ׂ�������́A�X�e�[�L�A�ȂǘZ�i�B�ォ�炯��O���^���A�g�����̂����A����A��̎ϕ��Ȃǎl�i���^��Ă��܂����B�X�e�[�L�͉����ł����ƕ����Ă������Ƃ����Ԏ��͂Ȃ������̂ł����A�ڂ��͂��Ȃ肨�������Ǝv���܂����B�ڂ��̐H�ׂ��X�e�[�L�͕đ̃`�����s�I�������g�����i�H�j��m�R�́u�×q�v�̂��̂��ō���Ȃ̂ł����A���g�̑�ϑ��́u���㋍�v�₱�̐�̋��ȂǐV���̋������̎����炢�̃��x���ł͂Ȃ����Ƃ��������܂����B�h�g�����������������A�������Ƃ����|�C���g�����������H�����Ǝv���܂��B��o���̂��̂͂��ׂĂ����ł����������������܂����B�f�U�[�g�̓[���[�ōH�v�̋Â炳�ꂽ���̂ł����B�S�̓I�Ƀo�����X�̂Ƃꂽ���������H�����Ǝv���܂����B�����A�����C���𗊂̂ł����A���C�����₷���C���N�[���[���Ȃ������̂��c�O�ł��A���C��������ނ��p�ӂ��Ă���h�ŁA���C���N�[���[���Ȃ��Ƃ͉����܂���B���H�������ł����B�����������������܂����B�R�،n�����S�ŏĂ����̑���ɂ��炷���t���܂������A�~����������ɉ����ďĂ������ق��������ł��B�܂����n�̗������Ȃ������̂��c�O�ł����B�Ƃ͂����A�����������т��H�ׂ��܂����B�������悤�ɁA���_���c�O�ȕ���������܂������A�S�̓I�ɐS�z�肪�s���͂��������h���Ǝv���܂��B����������قǍ����͂���܂���B |
| �@ |
| �O���ڂ͂܂��z�㓒��ɂ��ǂ�A���x�̓o�X�Ő��Ë��������܂��B����̂ق��ق����������ł����A����ɂ��܂�{�����Ȃ��̂ŁA���ʓI�ɑ��߂ɏh�ɂ��Ă��܂��܂��B���̓������K�̃C���̎��Ԃ͂R���Ȃ̂ł����A�o�X�̎��Ԃ̊W�łQ���O�ɂ͒����Ă��܂��܂����B�����������X�Ƃ����\���̗��h�Ȍ����ł��B�ł��A���̗��ق̗��j�ɂ͐���łԂ���Ă��܂����Ƃ����߂����ߋ�������悤�ł��B�������A���グ�Ă�����Ȃɍ����R�����ɂ����ł��Ȃ��A��̂ǂ�����ǂ�ȕ��ɐ��������Ă����̂��낤�Ƃ����C�����܂��B |
 ���āA�ꎞ�Ԉȏ�O�ł����A�������������Ɉē����Ă���܂����B�R�K���Ă̂R�K�́u�ȁv�Ƃ��������ł����B�h�A�����Ɠ��ݍ��݂̉E��ɐ��ʏ�������ׂ��g�C���ɂȂ��Ă��܂��B���̃g�C���͗m���ł��������ł͂Ȃ��A����ƂЂ���Ƃ��܂��B�g�C���̈ʒu�͈Ⴄ���̂̍���̐�Ǝ�������ł��B���ʂ̂ӂ��܂��J���A�\��̎厺�ɂ͂���܂��B����S�ʂ����̊ԁA���ʂɍL�߂̍L��������܂��B������͑O�̌���������ɁA�E��ɂ͐��Ð�̗��ꂪ���߂��܂��B�܂��Ζʂ͗ɂ������Ă��܂��B���̊Ԃɂ͗��h�ȉԂ��������Ă��܂����B�ē��W�̐l�����Ă������o���Ă���A�䂩���̃T�C�Y�̋C�Â���������ȂǁA�铒�̏h�̊��ɂ͂����ҋ��ł����B���̊Ԃ����h�Ȃ��̂ŁA���E�Ɏd���A�e���r��C���^�[�t�H�����u���Ă���Ƃ���ƃ��C���̏��̊ԂƂ���ʂ���Ă��܂����B�V�����������A���Ȃ肵�����肵����肾�Ɗ����܂����B�h�A�̓I�[�g���b�N�Ŕ铒�̏h�ɂ͒������Ǝv���܂��B�����A�I�[�g���b�N�̓z�e���̂悤�ɃJ�[�h�L�[������������Ƃ��͂����Ǝv���̂ł����A�s�ւȂ��Ƃ������̂ł��܂�D���ł͂���܂���B ���āA�ꎞ�Ԉȏ�O�ł����A�������������Ɉē����Ă���܂����B�R�K���Ă̂R�K�́u�ȁv�Ƃ��������ł����B�h�A�����Ɠ��ݍ��݂̉E��ɐ��ʏ�������ׂ��g�C���ɂȂ��Ă��܂��B���̃g�C���͗m���ł��������ł͂Ȃ��A����ƂЂ���Ƃ��܂��B�g�C���̈ʒu�͈Ⴄ���̂̍���̐�Ǝ�������ł��B���ʂ̂ӂ��܂��J���A�\��̎厺�ɂ͂���܂��B����S�ʂ����̊ԁA���ʂɍL�߂̍L��������܂��B������͑O�̌���������ɁA�E��ɂ͐��Ð�̗��ꂪ���߂��܂��B�܂��Ζʂ͗ɂ������Ă��܂��B���̊Ԃɂ͗��h�ȉԂ��������Ă��܂����B�ē��W�̐l�����Ă������o���Ă���A�䂩���̃T�C�Y�̋C�Â���������ȂǁA�铒�̏h�̊��ɂ͂����ҋ��ł����B���̊Ԃ����h�Ȃ��̂ŁA���E�Ɏd���A�e���r��C���^�[�t�H�����u���Ă���Ƃ���ƃ��C���̏��̊ԂƂ���ʂ���Ă��܂����B�V�����������A���Ȃ肵�����肵����肾�Ɗ����܂����B�h�A�̓I�[�g���b�N�Ŕ铒�̏h�ɂ͒������Ǝv���܂��B�����A�I�[�g���b�N�̓z�e���̂悤�ɃJ�[�h�L�[������������Ƃ��͂����Ǝv���̂ł����A�s�ւȂ��Ƃ������̂ł��܂�D���ł͂���܂���B |
 �����͘I�V���C���Ȃ��A�ǂ����h�͈ȑO�͌��ݒ��ԏ�ɂȂ��Ă���Ƃ���ɂ���A�h�̑O�̒r���I�V���C�������悤�ł��B�������A���݂͍����������Ȃ̂łȂ��Ȃ��v���悤�ɂ����Ȃ��Ƃ������Ƃł����B���������āA���̂Ƃ���͘I�V���C��v��͂Ȃ��悤�ł��B�Ƃ������ƂŁA�c�O�Ȃ�������ɓ���т���̐����ɂȂ�܂����B�����͔��ɖ��邭��ʂɑ傫�������Ƃ��A�O�̗����Ȃ�����邱�Ƃ��ł��܂��B�������A�O������Ă���l������ی����ɂȂ��Ă��܂��̂����_�ł��B�O���猩���Ă��܂������Ƃ����̂��������Ǝv���܂��B���������̂����C�͂���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B���M�͂���قǍL���͂Ȃ��A�l�ܐl�ň�t�ɂȂ��Ă��܂��ł��傤�B�܂��A�V�����[�̕t���Ă���J���������������܂���B�����A���̓��͎O�g�����q�����Ȃ������̂ŁA�����ԓ����Ă��Ă����f�������邱�Ƃ͂���܂���ł����B�����͓K���ł�ŗ����ނ������̂������ȗ��L�����܂��B���ɏ�i�ȗ��L�ł��B�����̘e�ɂ͉����������т�����ƌł܂��Ă��܂��B���V�R�̋���Ȃ����Ƃ͈Ⴂ�A�����͂����ł����������Ɗ����܂����B���������ŁA�|���̎��Ԃ������ĂQ�S���ԓ����\�ł��B�܂��A���オ��ǂ���Ƃ����ׂ����̂͂���܂��A�������o���Ƃ���ɗN�����̗␅�W���[���u����Ă��܂��B�[�H�͕����ł��B����������U���Ƃ����w��ŁA�������q���R�g�������Ȃ��̂ɁA�U�����߂��Ȃ��Ă悤�₭�Ꮧ�����^��ł��܂����B���i�����͂Ȃ��A��������������܂����B�[�H�̃��C���ƂȂ���̂͊���ŁA���̂���ŏo���̂Ɠ����A�����т̉�������痑�ŐH�ׂ���̂������ł��o�܂����B����͉������A��������H�ׂĂ���悤�ȐH���ŁA�D��ۂł��B���̓�����߁A�⋛�̏ĕ��A�R�̌Ӗ��悲���ȂǍŏ��Ɏ��i�B�ォ���̃}���l���h�g�A�R�̓V�n���A���q�����̎O�i���o����܂����B�����A���ꂾ���҂����āA�܂��⋛�̏ĕ������������߂Ă��܂��Ă���B����͗�߂Ă��������������̂ŁA�Ă����Ă�������ǂ�Ȃɂ��Ǝv�킹���܂����B����ɁA��o���̓V�n��������߂Ă���̂͂ǂ�������ł��傤���B���q�������A���̐��i�ォ���낤���ĉ����������Ƃ������x�ł����B��̃}���l���h�g�͏L�݂��Ȃ����������������A�Ō�Ɏ����Ă������X�`����̌���͂������ɉ������A���ɂ��������������A�S�̓I�ɖ��t���͂��Ȃ肢���Ǝv���܂����B�����A���������̂��̖��t�������Ȃ���Ԃ͉��Ƃ��l���Ȃ�������Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ō�̃f�U�[�g�͏����ȃX�|���W�P�[�L��䕂ł���͂������������̗]�n����Ɗ����܂����B���H�͈�K�̐H���ŁA�T���_�A�Ă����A���A�C�ہA�ϕ��A���Z���Ƃ������ɃI�[�\�h�b�N�X�Ȃ��̂ł��B�܂��A�ŏ��ɉ���Ő����������䂪���܂��B�����A���т����������������݂Ȃ��������������āA�Ȃ��Ȃ������x�̍������H�ł����B�����͕������͑S���łP�P���B�����Ɣ�������悤�ł��B�������ē��W�̏�����A���̑����l���̏]�ƈ����������܂����B����ł͌o�c�������������낤�ȂƎv���܂����B�₽�����̂̕����o���ƁA�啔���ł����������̂����������H�ׂ���̂ƁA���q�͂ǂ����]�ނł��傤���B���Ƃ��Ƃ��������H���Ȃ̂ł�����A����������ƐH�ׂ���悤�ɂ��邱�ƁA�ł���ΘI�V�邱�ƁA���Ƃ��ƃ��P�[�V�����Ɍb�܂�Ă���h�Ȃ̂ł�����A���ꂾ���ł����Ԃ�]�����オ��Ǝv���܂��B �����͘I�V���C���Ȃ��A�ǂ����h�͈ȑO�͌��ݒ��ԏ�ɂȂ��Ă���Ƃ���ɂ���A�h�̑O�̒r���I�V���C�������悤�ł��B�������A���݂͍����������Ȃ̂łȂ��Ȃ��v���悤�ɂ����Ȃ��Ƃ������Ƃł����B���������āA���̂Ƃ���͘I�V���C��v��͂Ȃ��悤�ł��B�Ƃ������ƂŁA�c�O�Ȃ�������ɓ���т���̐����ɂȂ�܂����B�����͔��ɖ��邭��ʂɑ傫�������Ƃ��A�O�̗����Ȃ�����邱�Ƃ��ł��܂��B�������A�O������Ă���l������ی����ɂȂ��Ă��܂��̂����_�ł��B�O���猩���Ă��܂������Ƃ����̂��������Ǝv���܂��B���������̂����C�͂���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B���M�͂���قǍL���͂Ȃ��A�l�ܐl�ň�t�ɂȂ��Ă��܂��ł��傤�B�܂��A�V�����[�̕t���Ă���J���������������܂���B�����A���̓��͎O�g�����q�����Ȃ������̂ŁA�����ԓ����Ă��Ă����f�������邱�Ƃ͂���܂���ł����B�����͓K���ł�ŗ����ނ������̂������ȗ��L�����܂��B���ɏ�i�ȗ��L�ł��B�����̘e�ɂ͉����������т�����ƌł܂��Ă��܂��B���V�R�̋���Ȃ����Ƃ͈Ⴂ�A�����͂����ł����������Ɗ����܂����B���������ŁA�|���̎��Ԃ������ĂQ�S���ԓ����\�ł��B�܂��A���オ��ǂ���Ƃ����ׂ����̂͂���܂��A�������o���Ƃ���ɗN�����̗␅�W���[���u����Ă��܂��B�[�H�͕����ł��B����������U���Ƃ����w��ŁA�������q���R�g�������Ȃ��̂ɁA�U�����߂��Ȃ��Ă悤�₭�Ꮧ�����^��ł��܂����B���i�����͂Ȃ��A��������������܂����B�[�H�̃��C���ƂȂ���̂͊���ŁA���̂���ŏo���̂Ɠ����A�����т̉�������痑�ŐH�ׂ���̂������ł��o�܂����B����͉������A��������H�ׂĂ���悤�ȐH���ŁA�D��ۂł��B���̓�����߁A�⋛�̏ĕ��A�R�̌Ӗ��悲���ȂǍŏ��Ɏ��i�B�ォ���̃}���l���h�g�A�R�̓V�n���A���q�����̎O�i���o����܂����B�����A���ꂾ���҂����āA�܂��⋛�̏ĕ������������߂Ă��܂��Ă���B����͗�߂Ă��������������̂ŁA�Ă����Ă�������ǂ�Ȃɂ��Ǝv�킹���܂����B����ɁA��o���̓V�n��������߂Ă���̂͂ǂ�������ł��傤���B���q�������A���̐��i�ォ���낤���ĉ����������Ƃ������x�ł����B��̃}���l���h�g�͏L�݂��Ȃ����������������A�Ō�Ɏ����Ă������X�`����̌���͂������ɉ������A���ɂ��������������A�S�̓I�ɖ��t���͂��Ȃ肢���Ǝv���܂����B�����A���������̂��̖��t�������Ȃ���Ԃ͉��Ƃ��l���Ȃ�������Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ō�̃f�U�[�g�͏����ȃX�|���W�P�[�L��䕂ł���͂������������̗]�n����Ɗ����܂����B���H�͈�K�̐H���ŁA�T���_�A�Ă����A���A�C�ہA�ϕ��A���Z���Ƃ������ɃI�[�\�h�b�N�X�Ȃ��̂ł��B�܂��A�ŏ��ɉ���Ő����������䂪���܂��B�����A���т����������������݂Ȃ��������������āA�Ȃ��Ȃ������x�̍������H�ł����B�����͕������͑S���łP�P���B�����Ɣ�������悤�ł��B�������ē��W�̏�����A���̑����l���̏]�ƈ����������܂����B����ł͌o�c�������������낤�ȂƎv���܂����B�₽�����̂̕����o���ƁA�啔���ł����������̂����������H�ׂ���̂ƁA���q�͂ǂ����]�ނł��傤���B���Ƃ��Ƃ��������H���Ȃ̂ł�����A����������ƐH�ׂ���悤�ɂ��邱�ƁA�ł���ΘI�V�邱�ƁA���Ƃ��ƃ��P�[�V�����Ɍb�܂�Ă���h�Ȃ̂ł�����A���ꂾ���ł����Ԃ�]�����オ��Ǝv���܂��B |
| �@ |
| ���悢��Ō�͎l���ڂ̑��R������قł��B�܂��܂��z�㓒��ɂ��ǂ��ď�z���ő��w�������܂��B���}�͓���ɂ��Ăق����ƌ����Ă����̂ł����A�d�Ԃ͂P�����ɒ����Ă��܂��A�܂��A�܂ő҂̂����傤���Ȃ���Ǝv�����قɓd�b�����̂ł����A����Ȃ��₻���Ȋ����ł��Ȃ��A���H�����Ă���̂ŏ����҂��Ă��������ƁA��������OK���Ă���A����ȂɎ��Ԃ��o�����Ɍ}���ɗ��Ă���܂����B�����A���̐l�����킳�̎�l���Ȃƈ�ڂŕ����銴���ŁA�ڂ��͏����x�����Ă����̂ł����A�������Ȋ����ŁA�Ԃ̒�����i�F�̐����Ȃǂ��Ă���܂����B �h�ɒ����Ƃ����ɂ͂Ȃ�Ƃ����h�Ȗ傪�����Ă��܂����B���������������悤�Ȗ�ł����A�ł��A���̗��ق͂���Ȃɗ��j�̂��闷�قł͂Ȃ��A���̎�l�̑ォ��n�߂��悤�ł��B���������ƏĂ����̂������肪�Y���Ă��܂��B��̗��ɂ��̎��オ��������Ƃ͑ΏƓI�ȃs�J�s�J�̏Ă����@�����������Ă��܂��B���ł��R���߂��ɂ͏Ă��邩��A�D���Ɏ���Ă����Ă��܂�Ȃ��Ƃ������Ƃł����B���ւ̈����˂��J����ƁA�オ�肩�܂��̍����ɐ��������炦���A���������ăg�}�g�₫�イ��A�ÉĂȂǂ���₳��Ă��܂��B������D���Ȃ����H�ׂĂ����Ƃ������Ƃł��B���̗��ɂ͈͘F���̂��鏬����������A�Y��������A���̂��ɂȂ܂��^�̂��݂��������ĕ��ׂ��Ă��܂����B������A�Y�ŏĂ��ĐH�ׂĂ��������ł��B�܂��A���͏o����Ă��܂��A��̎��Ԃɂ́A�����ɂ����Ă����ɂ�����o����邻���ł��B�H�ו��������ς�����Ƃ́A�m���Ă����̂ł����A�Ƃɂ����A���ۂɖڂ̓�����ɂ��āA���̃T�[�r�X���_�ɂ͈��|����܂����B����ȗ��ق͏��߂Ăł��B �܂����K�̃`�F�b�N�C�����Ԃɂ͑啪�Ԃ��������̂ł����A�ē����Ă����Ƃ������ƂŁA�����Ɍ������܂����B�����̓g�C��������A���킬�����������Ȃ�����Ƃ����ʊقɂ��܂����B�ʊق͎O�K���ĂŁA��K�ƎO�K�ɎO����������܂����A���̓�K�̐^�́u�ȁv�Ƃ��������ł����B�ʊق֍s���r���A�I�V���C�ւ̓������ʂ�̂ł����A�����ɂ��ǂ����ݒ���A����ɂႭ�̖��X�c�y�Ȃǂ��u����Ă��܂����B�����ł͈ē��W�̏���������������Ă���܂����B���߂̋C�Â���������A�Ԃ������Ă��ĕ���̂��悤������܂���B�A���j�e�B�͔����|�[�`�̒��Ƀt�F�C�X�^�I���A���u���V�Ƃ�����Ԃ̑��ɁA�Ȗ_��ւ��܁A�y�܂ł�����܂����B������T�[�r�X���_�̕\��ł��傤���B�����͊i�q�˂ŁA�����˂��J�������ʂɐ��ʏ��ƃg�C���B���̃g�C���͉����ł͂�����̂̃V�����[�͂Ȃ��c�O�ł����B�E��̕����ɓ���Ǝl�����̎��̊ԁA���̎��̊Ԃ�ʂ��ď\��̖{�Ԃ֓���܂��B�����̕ǂ����ׂď��̊ԂɂȂ��Ă��肳��ɁA�L���̕��ɂ�����I�������Ă��܂��B�V��������A���Ԃ�����A�܂����~�ƍL���Ƃ̋��ɏ�q�����Ă��Ă���A���Ȃ�ǂ����肵����ۂ�^����{�i�I�ȓ��{�Ԃł��B������͌����낷�����̗̌i�F�ƁA�E��ɂ͒j���I�V���C�A����ɂ͒j�������ƁA���Ɍ������Ȃ����̂������Ă��܂��܂����A�J�����̂���Ȃ��Ȃ��̕��i�ł��B���̕����͂�������C�ɓ����Ă��܂��܂����B |
 ���āA���������I�V���C�Ɍ������܂����B�������猩�������A�I�V���C���Ȃ��Ȃ��ǂ������ł��B�܂��A�Q����������ƑO�Ő��|���̎D�������Ă��܂������A�t�����g�ł���OK�Ƃ������Ƃ��m�F���Ă����̂ŁA�C�ɂ����������Ɠ���܂����B�I�V�͈�̗���ɂȂ��Ă��āA������܂����ɖ{�i�I�Ȃ��̂ł��B�V�䂪�������������n����A�����̑O�ʂƍ����ʂ̓�������J������Ă��܂��B�����̏�ɂ�����S�̂̉������n����Ă��܂�����A���m�Ɍ����Ɣ��I�V�Ƃ������Ƃł��傤���A��͂蒭�߂��낷�i�F�̍L����͊J�����������Ղ薡�키���Ƃ��ł��܂��B�R���[�g���l���̌ܘZ�l���x�̗����ł����A�������������̓��ł��A����Ȃɍ��ݍ����Ƃ������Ƃ͂���܂���ł����B�����́A��͂艖���������Ǝv���܂����A������ς��͑S�R�����܂���ł����B�܂��A�����������ďz�����Ă���悤�ł����A���f�L�͂܂��������܂���B�Ȃ߂Ă݂�ƁA�Â��������邨�����������ł��B���̘I�V�̌��_�́A�܂��I��肪��̂P�O���Ƒ������ƁB���������Ă��邱�Ƃł����A���߂ĂP�Q���܂łɂ��Ăق����Ƃ���ł��B���ꂩ��A�I�V�܂ł͓n��L��������ė��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����A���̓n��L������j���I�V�����������Ă��܂����ƁB����͘L��������Ă��鏗�������₾�Ǝv���܂��B�܂��A�����C�ɓ����Ă��鑤���ǂ������������܂���B�Ƃ͂����A���ɓ�����Ȃ���������̓n��L�����Ȃ��Ȃ�����̂�����̂ł��B�����͂��̓n��L�����͂���ŁA�I�V�Ƃ͑Ώ̂̈ʒu�ɂ�͂�A��������яo�����`�Ō��Ă��Ă��܂��B�╗�C�ŁA���M�͘I�V������⏬���߂��炢�̊����ł����A�O�ʂƉE���ʂ̓�ʂɑ傫�ȃK���X�����Ƃ��āA��͂�Ђ�т�Ƃ����i�F�߂���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�����p�͂��ׂ̗ł��̂őO�ʂƍ����ʂƂ������ƂɂȂ�܂��B�����̓����̍����ɂ͖쐶�̑傫�ȓ��̖������āA���܂܂��ɖ��J�ƌ��������ł�������̉Ԃ����Ă��܂����B������������A���̉Ԃ����łȂ�������ʼn߂����̂��������낤�ȂƎv���܂����B���̓����͌��͂Ȃ��Q�S���܂łł����B ���āA���������I�V���C�Ɍ������܂����B�������猩�������A�I�V���C���Ȃ��Ȃ��ǂ������ł��B�܂��A�Q����������ƑO�Ő��|���̎D�������Ă��܂������A�t�����g�ł���OK�Ƃ������Ƃ��m�F���Ă����̂ŁA�C�ɂ����������Ɠ���܂����B�I�V�͈�̗���ɂȂ��Ă��āA������܂����ɖ{�i�I�Ȃ��̂ł��B�V�䂪�������������n����A�����̑O�ʂƍ����ʂ̓�������J������Ă��܂��B�����̏�ɂ�����S�̂̉������n����Ă��܂�����A���m�Ɍ����Ɣ��I�V�Ƃ������Ƃł��傤���A��͂蒭�߂��낷�i�F�̍L����͊J�����������Ղ薡�키���Ƃ��ł��܂��B�R���[�g���l���̌ܘZ�l���x�̗����ł����A�������������̓��ł��A����Ȃɍ��ݍ����Ƃ������Ƃ͂���܂���ł����B�����́A��͂艖���������Ǝv���܂����A������ς��͑S�R�����܂���ł����B�܂��A�����������ďz�����Ă���悤�ł����A���f�L�͂܂��������܂���B�Ȃ߂Ă݂�ƁA�Â��������邨�����������ł��B���̘I�V�̌��_�́A�܂��I��肪��̂P�O���Ƒ������ƁB���������Ă��邱�Ƃł����A���߂ĂP�Q���܂łɂ��Ăق����Ƃ���ł��B���ꂩ��A�I�V�܂ł͓n��L��������ė��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����A���̓n��L������j���I�V�����������Ă��܂����ƁB����͘L��������Ă��鏗�������₾�Ǝv���܂��B�܂��A�����C�ɓ����Ă��鑤���ǂ������������܂���B�Ƃ͂����A���ɓ�����Ȃ���������̓n��L�����Ȃ��Ȃ�����̂�����̂ł��B�����͂��̓n��L�����͂���ŁA�I�V�Ƃ͑Ώ̂̈ʒu�ɂ�͂�A��������яo�����`�Ō��Ă��Ă��܂��B�╗�C�ŁA���M�͘I�V������⏬���߂��炢�̊����ł����A�O�ʂƉE���ʂ̓�ʂɑ傫�ȃK���X�����Ƃ��āA��͂�Ђ�т�Ƃ����i�F�߂���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�����p�͂��ׂ̗ł��̂őO�ʂƍ����ʂƂ������ƂɂȂ�܂��B�����̓����̍����ɂ͖쐶�̑傫�ȓ��̖������āA���܂܂��ɖ��J�ƌ��������ł�������̉Ԃ����Ă��܂����B������������A���̉Ԃ����łȂ�������ʼn߂����̂��������낤�ȂƎv���܂����B���̓����͌��͂Ȃ��Q�S���܂łł����B |
 �ʊق̋q�̗[�H�͕����o���ŁA�{�ق̋q�͘I�V�ւƑ����n��L���ɖʂ����H�����ɂȂ�悤�ł��B�ŏ��ɐH�O�����͂��ߏ\��i���ǂ���Ɖ^��Ă��܂��܂��B���i�������Ȃ��A�������قƂ�ǂ���܂���B�H�O���͔����C���ŁA�����Ȃǂ͕����܂���ł������A��������̂��������������̂ł����B�^�ꂽ���̂́A�����Ȃǂ̑O�A���̏ĕ��A�V�n���A�h�g�A�|�̕��A�R���g�����������̗����A�⋛�ƕ����̓��o�^�[�Ă��ȂǂŁA�o�^�[�Ă��ɂ͂܂��������Ă��Ȃ��̂͗ǂ��Ǝv���܂����A�e�[�u���ɂ͉��C�Ȃ��`���b�J�}�����u����ǂ����A�����B�ŏ���ɍ��������v����Ă���悤�ł��B����͑S�R�\�킸�A�ނ��낻�̕��������̂ł����A�ꌾ�u���D���Ȏ��ɁE�E�v�ȂǂƂ������t���ق����Ǝv���܂����B�����ł��A�������ɂ��ꂸ�A�Ă����A�V�n���Ȃǂ͗₦���Ă��܂����B���̗₦�Ă��邱�Ƃ͕ʂɂ��Ă������S�̂Ƀp���[�s���ŁA�����������̂�H�ׂ����Ă�낤�Ƃ����ӋC���݂��`����Ă��܂���B�h�g������̎l���̒��ōł��͂��������Ǝv���܂��B�Ƃɂ����A����͂Ǝv�킹����̂��قƂ�ǂȂ��A���낤���Ėڂ̑O�ŏĂ����⋛�ƕ����̓��o�^�[�Ă����������������ƌ����邾���ł����B�����A���ɂ���͂܂����Ƃ������̂��Ȃ������̂ł����E�E�B��o�������������A�Ȃ߂����g���������������ŁA����͂�����H�ׂ��܂������A���͍��ꂾ�����L���ł��B�Ō�ɂ����܂��Ƃ��тł����A���т͉���R�V�q�J�����g���Ă��邻���ŁA���߂ɂ܂ŃR�V�q�J���̖����������ĕU���̂��̂��g���Ă��邭�炢������肪����悤�ł��B�m���ɁA���͂�͂��������Ǝv���܂����B�f�U�[�g�͖����o�o���A�̏��q�����i�H�j�ŁA������G��ł܂ł����܂���B���H�͕����ł͂���܂��A�V�ق̋q�����������Ƃ����Ƃ���ł̐H���ɂȂ�܂��B�C�ہA���A�T���_�A�Ă����A�Ђ����A�ϕ��Ƃ�����Ԃ̂��̂ŁA����ɋ������I�����W�W���[�X�A�L�E�C�ƃI�����W�̃f�U�[�g���t���܂��B���H�̋��͉����������C�����܂����A�悭�o���Ă��܂���B���͓��ɂ���Ƃ������̂͂�͂肠��܂���ł������A���͂������������������A�S�̓I�ɂ����������������܂����B���͂�͂ނ����Ȃ���̂��Ђŏo����A���ɂ������������Ǝv���܂��B���ЂS���H�ׂ�ꂻ���ł������A�l�������������̂��Ƃ��l���A�O�t�ł�߂Ă����܂����B���āA���̂���������̎�l�̂��Ƃł����A�K���s�K�����̓��A��l�͑����A���Ă��܂��������ŁA�ӂ���͂ǂ�ȏ�ԂȂ̂�������܂���ł����B��������́u��낵��������E�E�v�ƌ����Ă܂����̂ŁA�����̂ӂ�܂��͂������Ǝv���܂��B�����A�ڂ��͏ꏊ�����֘e�̂����̂���Ƃ��낾�Ǝv���āA�l�q�����ɂ������̂ł����A�����͖����肪�����Ă��ĉ��̋C�z������܂���ł����B�����A�H�����I���ĕ����ɖ߂낤�Ƃ����Ƃ���I�V�̓�����߂��Ɂu�����v�Ƃ�������������̂����܂����B�͂͂��A�����������ȂƎv���܂������A���̂�������オ���Ă�����̑O��ʂ������ɋC�Â����͂��ł��B�����A��l�����Ȃ��̂ł�������Ȃ��������A���߂ɂ��J���ɂȂ��Ă��܂����̂ł��傤�B���̎�l�ɂ��Ă͒���������u����������Ȃ���E�E�v�ƌ����Ă������A����������u��d�l�i�ł��v�ƌ����Ă��܂����̂ŁA���ꂵ���F�߂�Ƃ���Ȃ̂ł��傤�B�ڂ��͎��ۂɐ������l�q��ڂɂ��Ă��Ȃ��̂ŋC�y�Ɍ�����̂�������܂��A�h�̗l�q����l����ɁA�{���I�ɂ͂��ĂȂ��̐S�ɂ��ӂꂽ�l�Ȃ̂��Ǝv���܂��B�h�́A���낢��Ȃ��̂��D���ɐH�ׂ��邱�Ƃɂ��āA��������Ɂu���ĂȂ��̐S�ɂ��ӂ�Ă��܂��ˁv�ƌ�������u��l���������狃���Ċ�ԁE�E�v�ƌ����Ă��܂����̂ŁA���������Ȃ̂��Ǝv���܂��B���ꂾ���ɁA�����͎c�O�Ȃ��Ƃł��ˁB���Ƃ́A��͂�A���݂̐H�������Ƃ����邱�Ƃ��K�v�ł��傤�B�ڂ��́A��l�̕]������A�����Ă���l�̐S��h���̂��r��Ă���̂ł͂Ȃ����ƐS�z���Ă����̂ł����A����Ȃ��Ƃ͑S���Ȃ��A�݂�Ȗ��邭�A�h�������ň��S���܂����B�{���I�ɂ͂��Ȃ�]���ł���h�ł��̂ŁA��l�̐S�����ʼn��Ƃ��O�̕]�����Ƃ���ǂ��Ăق����Ɗ����܂����B �ʊق̋q�̗[�H�͕����o���ŁA�{�ق̋q�͘I�V�ւƑ����n��L���ɖʂ����H�����ɂȂ�悤�ł��B�ŏ��ɐH�O�����͂��ߏ\��i���ǂ���Ɖ^��Ă��܂��܂��B���i�������Ȃ��A�������قƂ�ǂ���܂���B�H�O���͔����C���ŁA�����Ȃǂ͕����܂���ł������A��������̂��������������̂ł����B�^�ꂽ���̂́A�����Ȃǂ̑O�A���̏ĕ��A�V�n���A�h�g�A�|�̕��A�R���g�����������̗����A�⋛�ƕ����̓��o�^�[�Ă��ȂǂŁA�o�^�[�Ă��ɂ͂܂��������Ă��Ȃ��̂͗ǂ��Ǝv���܂����A�e�[�u���ɂ͉��C�Ȃ��`���b�J�}�����u����ǂ����A�����B�ŏ���ɍ��������v����Ă���悤�ł��B����͑S�R�\�킸�A�ނ��낻�̕��������̂ł����A�ꌾ�u���D���Ȏ��ɁE�E�v�ȂǂƂ������t���ق����Ǝv���܂����B�����ł��A�������ɂ��ꂸ�A�Ă����A�V�n���Ȃǂ͗₦���Ă��܂����B���̗₦�Ă��邱�Ƃ͕ʂɂ��Ă������S�̂Ƀp���[�s���ŁA�����������̂�H�ׂ����Ă�낤�Ƃ����ӋC���݂��`����Ă��܂���B�h�g������̎l���̒��ōł��͂��������Ǝv���܂��B�Ƃɂ����A����͂Ǝv�킹����̂��قƂ�ǂȂ��A���낤���Ėڂ̑O�ŏĂ����⋛�ƕ����̓��o�^�[�Ă����������������ƌ����邾���ł����B�����A���ɂ���͂܂����Ƃ������̂��Ȃ������̂ł����E�E�B��o�������������A�Ȃ߂����g���������������ŁA����͂�����H�ׂ��܂������A���͍��ꂾ�����L���ł��B�Ō�ɂ����܂��Ƃ��тł����A���т͉���R�V�q�J�����g���Ă��邻���ŁA���߂ɂ܂ŃR�V�q�J���̖����������ĕU���̂��̂��g���Ă��邭�炢������肪����悤�ł��B�m���ɁA���͂�͂��������Ǝv���܂����B�f�U�[�g�͖����o�o���A�̏��q�����i�H�j�ŁA������G��ł܂ł����܂���B���H�͕����ł͂���܂��A�V�ق̋q�����������Ƃ����Ƃ���ł̐H���ɂȂ�܂��B�C�ہA���A�T���_�A�Ă����A�Ђ����A�ϕ��Ƃ�����Ԃ̂��̂ŁA����ɋ������I�����W�W���[�X�A�L�E�C�ƃI�����W�̃f�U�[�g���t���܂��B���H�̋��͉����������C�����܂����A�悭�o���Ă��܂���B���͓��ɂ���Ƃ������̂͂�͂肠��܂���ł������A���͂������������������A�S�̓I�ɂ����������������܂����B���͂�͂ނ����Ȃ���̂��Ђŏo����A���ɂ������������Ǝv���܂��B���ЂS���H�ׂ�ꂻ���ł������A�l�������������̂��Ƃ��l���A�O�t�ł�߂Ă����܂����B���āA���̂���������̎�l�̂��Ƃł����A�K���s�K�����̓��A��l�͑����A���Ă��܂��������ŁA�ӂ���͂ǂ�ȏ�ԂȂ̂�������܂���ł����B��������́u��낵��������E�E�v�ƌ����Ă܂����̂ŁA�����̂ӂ�܂��͂������Ǝv���܂��B�����A�ڂ��͏ꏊ�����֘e�̂����̂���Ƃ��낾�Ǝv���āA�l�q�����ɂ������̂ł����A�����͖����肪�����Ă��ĉ��̋C�z������܂���ł����B�����A�H�����I���ĕ����ɖ߂낤�Ƃ����Ƃ���I�V�̓�����߂��Ɂu�����v�Ƃ�������������̂����܂����B�͂͂��A�����������ȂƎv���܂������A���̂�������オ���Ă�����̑O��ʂ������ɋC�Â����͂��ł��B�����A��l�����Ȃ��̂ł�������Ȃ��������A���߂ɂ��J���ɂȂ��Ă��܂����̂ł��傤�B���̎�l�ɂ��Ă͒���������u����������Ȃ���E�E�v�ƌ����Ă������A����������u��d�l�i�ł��v�ƌ����Ă��܂����̂ŁA���ꂵ���F�߂�Ƃ���Ȃ̂ł��傤�B�ڂ��͎��ۂɐ������l�q��ڂɂ��Ă��Ȃ��̂ŋC�y�Ɍ�����̂�������܂��A�h�̗l�q����l����ɁA�{���I�ɂ͂��ĂȂ��̐S�ɂ��ӂꂽ�l�Ȃ̂��Ǝv���܂��B�h�́A���낢��Ȃ��̂��D���ɐH�ׂ��邱�Ƃɂ��āA��������Ɂu���ĂȂ��̐S�ɂ��ӂ�Ă��܂��ˁv�ƌ�������u��l���������狃���Ċ�ԁE�E�v�ƌ����Ă��܂����̂ŁA���������Ȃ̂��Ǝv���܂��B���ꂾ���ɁA�����͎c�O�Ȃ��Ƃł��ˁB���Ƃ́A��͂�A���݂̐H�������Ƃ����邱�Ƃ��K�v�ł��傤�B�ڂ��́A��l�̕]������A�����Ă���l�̐S��h���̂��r��Ă���̂ł͂Ȃ����ƐS�z���Ă����̂ł����A����Ȃ��Ƃ͑S���Ȃ��A�݂�Ȗ��邭�A�h�������ň��S���܂����B�{���I�ɂ͂��Ȃ�]���ł���h�ł��̂ŁA��l�̐S�����ʼn��Ƃ��O�̕]�����Ƃ���ǂ��Ăق����Ɗ����܂����B |
| �k�C���֍s���Ă��܂����B�U���͔~�J�̎����B�ł��A�k�C���ɂ͔~�J�͂Ȃ��ƕ����A�ł͍��N�͖k�C���ɂ��Ă݂悤�Ƃ������ƂɂȂ����̂ł��B�����āA�v���ʂ萰�V�̖k�C�����y����ł��邱�Ƃ��ł��܂����B�����A�d�Ԃ�o�X�ňړ����邽�߁A���܂艓���܂ł͍s�����A�n�}�Ƃɂ�߂��������Ȃ���A�o�ʁ��ۋ������Ƃ������Ɍ��߂��̂ł����B�{���́A��Ԃ����h���Ō�Ɏ����Ă���̂��A�ڂ��̗��ق̌��ߕ��Ȃ̂ł����A�Ō�ɏ��M�̊ό�������̂ŁA�ŏ��������h�ɂȂ��Ă��܂��܂����B |
| �@ |
| �����͓o�ʉ���́u�o�ʉ���ό��z�e����̉Ɓv�ł��B�����͑S���łU�O���Ƃ������K�̗͂��قł��B�o�ʂ̉w����o�X�œo�ʉ���ցA������������ĂS�����炢�炵���̂ł����A�ǂ̕����ɕ����čs���Ă����̂��킩��Ȃ��̂ŁA�h�ɓd�b���Č}���ɗ��Ă��炢�܂����B�قƂ�Ǒ҂��ƂȂ��A�����ɗ��Ă���܂����B�o�ʂ̉���X�͂���ȂɍL���Ȃ��A���Ȃ肩���܂��ė��ق������Ă����ۂł��B�������̂��R���߂��ŁA�C�����Q���ł��̂łڂ��Ƃ��Ă͂��Ȃ�x�������ł��B�����Ɉē����Ă���A�ʂ��ꂽ�̂��߂Ƃ����A�O�K���Ă̌����̓�K�̊p�����ł����B�h�A�����Ƃ��̂܂܂W����̗m�ԂւƂȂ���A����ɂ��̉��ɂP�Q��̘a���������Ă��܂��B�m�ԂƂ����Ă��x�b�h�͂Ȃ��A���ڃZ�b�g���u����Ă��܂��B���������āA�a���ɂ͍L���͂��Ă��܂���B�a���ɂ͍����ɋ߂��悤�Șa�Ƌ�ƕ������u����Ă��āA�������������͋C��������킹�Ă��܂��B���̊Ԃɂ͂������Ԃ��������Ă��܂��B�p�����ł��̂ŁA���ɑ��������A�m���Ɉ�ʁA�a���ɎO�ʂ̑�������܂����B�m���̈�ʂ����ۂ́A���ڃZ�b�g�̒u����Ă��邠���肪�A�傫�ȏo���̂悤�ɔ�яo�����`�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�R�̎��^�ɑ��Ɉ͂܂�Ă���̂ł��B�m������a���Ɍ����������ʂ̑��͒�ɖʂ��A���̎O�ʂ̎��E�͊ԋ߂̎Ζʂ��s�����X�Ő�߂��Ă��܂��B���ʂ̑��߂��ɍs���Α��̕����������܂����`�����݂͂Ȃ��ƌ����Ă����ł��傤�B�����̂Ƃ���ǂ���ɒY�������Ղ���Ăɓ���Ēu����Ă���̂���ۓI�ł����B�\�����̂Ȃ������ł����A���ʂƃo�X�����j�b�g�ɂȂ��Ă��āA���̕����͏�Ɍ����܂��B�������g�C���͕ʂŁA�V�����[�g�C���ł����B���߂̃T�C�Y�̋C�Â���������܂����B |
 �嗁��͑|���̎��Ԃ������ĂQ�S���ԁA�I�V���ӂ��߂ē����\�ł��B�j���̓���ւ��͂���܂���B�����A�I�V�̍\����̗��R���Ǝv���܂��B�j���̘I�V���ꕔ�̕������猩���Ă��܂��̂ł��B�嗁��́A�����`�ŁA�����Ɏl�p�����D���A�O���ԂɂȂ��ł��܂��B��Ԏ�O���A���F�����̐H����ʼn��߁A�^��������ŔM�߁A��ԉ������W�E����Œ��ԂƂȂ��Ă��܂��B���ꂼ��̓��D�͊��Ƒ傫���U�E�V�l�͓����ł��傤���B���D�̔��Α��ɐꂪ���сA�_��̋{�藷�قƓ����悤�ɒY�V�����v�[�ƃI�����W�V�����v�[�����݂ɒu����Ă��܂����B�V�F�[���B���O�t�H�[�����u����Ă���̂́A�l�Ƃ��Ă͍��]���ł��B���D�͘I�V���܂߂ĎO�̐����ׂČ�����ŁA���������������Ղ�y���ނ��Ƃ��ł��܂��B���̘I�V�́A�嗁��̒[�̃h�A���班���������Ƃ���ɂ���A���Ȃ�L�X�Ƃ��Ă��܂��B�Q�O�l���炢�͓��ꂻ���Ȋ����ł��B���̘I�V���C�ɂ̓��W���[��������Ă���悤�ł��B������A���W���[����Ƃ��������Ă��܂����A�ǂ��炩�Ƃ����Ɨ�����͗Όn�A���W���[����͐n�������ƋL�����Ă��܂��B�I�V�̂����e�ɍׂ����H�������A�����x�̍����₽����������Ă��āA�I�V������L���ΊȒP�ɐG�邱�Ƃ��ł��܂��B���̓����x��₽������l����ƁA�����N�����������悤�ɂ��Ă���̂��Ǝv���܂��B������X�Ɉ͂܂�A���Ƃ̔����͌����Ɉ͂܂�Ă��܂����A�L���̂ł���قǂ̈������͂���܂���B���̘I�V�͂�≷�߂ŁA�������艷�܂邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A���オ�菈�ɂ͗␅�@���u����āA���オ��ɗ₽���������ނ��Ƃ��ł��܂����B �嗁��͑|���̎��Ԃ������ĂQ�S���ԁA�I�V���ӂ��߂ē����\�ł��B�j���̓���ւ��͂���܂���B�����A�I�V�̍\����̗��R���Ǝv���܂��B�j���̘I�V���ꕔ�̕������猩���Ă��܂��̂ł��B�嗁��́A�����`�ŁA�����Ɏl�p�����D���A�O���ԂɂȂ��ł��܂��B��Ԏ�O���A���F�����̐H����ʼn��߁A�^��������ŔM�߁A��ԉ������W�E����Œ��ԂƂȂ��Ă��܂��B���ꂼ��̓��D�͊��Ƒ傫���U�E�V�l�͓����ł��傤���B���D�̔��Α��ɐꂪ���сA�_��̋{�藷�قƓ����悤�ɒY�V�����v�[�ƃI�����W�V�����v�[�����݂ɒu����Ă��܂����B�V�F�[���B���O�t�H�[�����u����Ă���̂́A�l�Ƃ��Ă͍��]���ł��B���D�͘I�V���܂߂ĎO�̐����ׂČ�����ŁA���������������Ղ�y���ނ��Ƃ��ł��܂��B���̘I�V�́A�嗁��̒[�̃h�A���班���������Ƃ���ɂ���A���Ȃ�L�X�Ƃ��Ă��܂��B�Q�O�l���炢�͓��ꂻ���Ȋ����ł��B���̘I�V���C�ɂ̓��W���[��������Ă���悤�ł��B������A���W���[����Ƃ��������Ă��܂����A�ǂ��炩�Ƃ����Ɨ�����͗Όn�A���W���[����͐n�������ƋL�����Ă��܂��B�I�V�̂����e�ɍׂ����H�������A�����x�̍����₽����������Ă��āA�I�V������L���ΊȒP�ɐG�邱�Ƃ��ł��܂��B���̓����x��₽������l����ƁA�����N�����������悤�ɂ��Ă���̂��Ǝv���܂��B������X�Ɉ͂܂�A���Ƃ̔����͌����Ɉ͂܂�Ă��܂����A�L���̂ł���قǂ̈������͂���܂���B���̘I�V�͂�≷�߂ŁA�������艷�܂邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A���オ�菈�ɂ͗␅�@���u����āA���オ��ɗ₽���������ނ��Ƃ��ł��܂����B |
 �H���͗[�H�A���H�Ƃ������ł��B���C����オ���ĕ����ɓ���ƁA���łɔ����e�[�u���N���X���~����ĐH���̗p�ӂ��o���Ă��܂����B���i�������u����A���сA�f�U�[�g�������ď\�i�̕i�ڂ�������Ă��܂��B�����A�H�O�����Ȃ��͖̂l�Ƃ��Ă͂Ȃ�Ƃ��c�O�ł����B������x�̗������Ƃ�Ȃ���A�H�O�������Ȃ����ق͂�����������A��������A�������̍l���������Ă̂��Ƃł��傤���A�������̗��قȂ�ł͂̐H�O�����ق����ȂƁA�ڂ��͎v���Ă��܂��܂��B�ӂƌ���ƁA�O�̒��Ƀ\���}������ԓ����Ă��܂����B���߂Ắu�e�[�u���N���X�̖@���v�u�r�u�\���}���̖@���v�ł��B��́u�e�[�u���N���X�̖@���v�̗��ق͈�i���Ȃ̂ł����A���̑�̉Ƃ͍ŏ��ɂ�����x���ׂĂ��܂��^�ł����B��t�A�O�A���A�ϕ��A���ւ��A�|�̕������ׂ��Ă��āA���Ƃ����ɋz�����Ƃ����肪�^��Ă��܂����B���̌�ŊW���ƖъI�A���x�߂��o���ꓩ�ɉ������āA���̌オ���тƖ��X�`�ɂȂ�܂��B����ɋ����[���[�̃f�U�[�g�A�H��������ɂ������ɗm�i�V�̃A�C�X�N���[���Ɩ�H�p�̈���i���^��܂��B�A�C�X�N���[���͂����ς肵�������A��̓�����ɐH�ׂ�����i�͂ƂĂ������������̂ł����B�u�e�[�u���N���X�̖@���v�̗��ق͂��̃e�[�u���N���X�̂��߂��A�e�[�u���ʼn��g��Ȃ��Ƃ��낪�قƂ�ǂł������A�����̓n�[�u�̓��Ă�������܂����B���̋������Ƃ����A�\���}���Ƃ����A���g���Ƃ���Ƃ����A�����́u�e�[�u���N���X�̖@���v�̗��قƂ��Ăْ͈[�ł��ˁB�����͖ъI�ƃn�[�u�̓��Ă������C���ł��ꂼ��ɂ����������̂ł����B�����A�ъI�����C���Ȃ̂ɂ��i�����ɂ͏�����Ă��Ȃ��̂��傫�ȓ�ł��B�ǂ̗��������ꂼ�ꂪ�����������̂ł������A������ɏo����Ă��܂��Ă���̂ŁA���܂��i��i���키�Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ����A��ۂ��������Ȃ��Ă��܂�����������܂���B�݂�ȕ��ϓ_�ȏゾ�Ǝv���܂����A���ƈ��i�A����Ƃ����p���`�̌��������̂�����ΐ\�����Ȃ������Ƃ���ł��B�u�e�[�u���N���X�̖@���v�u�r�u�\���}���̖@���v�́u�e�[�u���N���X�̖@���v�̕����������Ă��܂����A�����A��͂芮���ɑł��̂߂����Ƃ����Ƃ���܂ł͍s���Ȃ������悤�Ɏv���܂��B���H�͍��A�������A���A����҂�S�{�E�A�T���_�A���Z���A���炱�Ƃ���������ʓI�Ȓ���H�ł����A���ׂă��x���͍������ꂼ��ɂ����������̂Ŕ��ɖ����ł��܂����B�S�̓I�ɂǂ����Ƃ��Ă����ϓ_�ȏ�̏h���Ƃ͎v���܂��B�t�����g�̏]�ƈ��̈��A�͂������A�����Ɍ}���̎Ԃ�������A����̎Ԃ��o���Ă��ꂽ��ƋC�z����s���͂��Ă��܂��B�����A�����W��̌�����͏h���K�̃G���x�[�^�[�܂ł��������A�A�E�g�̎��ɏ����͌����������y�Y�R�[�i�[�̋�����Ɉꐶ�����ł����B�Ƃ����悤�ɁA�c�O�Ȃ��犮���Ƃ܂ōs���Ȃ��悤�ł��B �H���͗[�H�A���H�Ƃ������ł��B���C����オ���ĕ����ɓ���ƁA���łɔ����e�[�u���N���X���~����ĐH���̗p�ӂ��o���Ă��܂����B���i�������u����A���сA�f�U�[�g�������ď\�i�̕i�ڂ�������Ă��܂��B�����A�H�O�����Ȃ��͖̂l�Ƃ��Ă͂Ȃ�Ƃ��c�O�ł����B������x�̗������Ƃ�Ȃ���A�H�O�������Ȃ����ق͂�����������A��������A�������̍l���������Ă̂��Ƃł��傤���A�������̗��قȂ�ł͂̐H�O�����ق����ȂƁA�ڂ��͎v���Ă��܂��܂��B�ӂƌ���ƁA�O�̒��Ƀ\���}������ԓ����Ă��܂����B���߂Ắu�e�[�u���N���X�̖@���v�u�r�u�\���}���̖@���v�ł��B��́u�e�[�u���N���X�̖@���v�̗��ق͈�i���Ȃ̂ł����A���̑�̉Ƃ͍ŏ��ɂ�����x���ׂĂ��܂��^�ł����B��t�A�O�A���A�ϕ��A���ւ��A�|�̕������ׂ��Ă��āA���Ƃ����ɋz�����Ƃ����肪�^��Ă��܂����B���̌�ŊW���ƖъI�A���x�߂��o���ꓩ�ɉ������āA���̌オ���тƖ��X�`�ɂȂ�܂��B����ɋ����[���[�̃f�U�[�g�A�H��������ɂ������ɗm�i�V�̃A�C�X�N���[���Ɩ�H�p�̈���i���^��܂��B�A�C�X�N���[���͂����ς肵�������A��̓�����ɐH�ׂ�����i�͂ƂĂ������������̂ł����B�u�e�[�u���N���X�̖@���v�̗��ق͂��̃e�[�u���N���X�̂��߂��A�e�[�u���ʼn��g��Ȃ��Ƃ��낪�قƂ�ǂł������A�����̓n�[�u�̓��Ă�������܂����B���̋������Ƃ����A�\���}���Ƃ����A���g���Ƃ���Ƃ����A�����́u�e�[�u���N���X�̖@���v�̗��قƂ��Ăْ͈[�ł��ˁB�����͖ъI�ƃn�[�u�̓��Ă������C���ł��ꂼ��ɂ����������̂ł����B�����A�ъI�����C���Ȃ̂ɂ��i�����ɂ͏�����Ă��Ȃ��̂��傫�ȓ�ł��B�ǂ̗��������ꂼ�ꂪ�����������̂ł������A������ɏo����Ă��܂��Ă���̂ŁA���܂��i��i���키�Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ����A��ۂ��������Ȃ��Ă��܂�����������܂���B�݂�ȕ��ϓ_�ȏゾ�Ǝv���܂����A���ƈ��i�A����Ƃ����p���`�̌��������̂�����ΐ\�����Ȃ������Ƃ���ł��B�u�e�[�u���N���X�̖@���v�u�r�u�\���}���̖@���v�́u�e�[�u���N���X�̖@���v�̕����������Ă��܂����A�����A��͂芮���ɑł��̂߂����Ƃ����Ƃ���܂ł͍s���Ȃ������悤�Ɏv���܂��B���H�͍��A�������A���A����҂�S�{�E�A�T���_�A���Z���A���炱�Ƃ���������ʓI�Ȓ���H�ł����A���ׂă��x���͍������ꂼ��ɂ����������̂Ŕ��ɖ����ł��܂����B�S�̓I�ɂǂ����Ƃ��Ă����ϓ_�ȏ�̏h���Ƃ͎v���܂��B�t�����g�̏]�ƈ��̈��A�͂������A�����Ɍ}���̎Ԃ�������A����̎Ԃ��o���Ă��ꂽ��ƋC�z����s���͂��Ă��܂��B�����A�����W��̌�����͏h���K�̃G���x�[�^�[�܂ł��������A�A�E�g�̎��ɏ����͌����������y�Y�R�[�i�[�̋�����Ɉꐶ�����ł����B�Ƃ����悤�ɁA�c�O�Ȃ��犮���Ƃ܂ōs���Ȃ��悤�ł��B |
| �@ |
| ����ڂ͐�܂ł��ǂ�A��������o�X�Ŏx┌܂Ō������܂��B�o�X�ւ����������قǂ����Ȃ��A�{���͑�̉Ƃł����Ƃ������ł����̂ł����A�P�P�����̃o�X�ɊԂɍ��킹�邽�߂ɁA�`�F�b�N�A�E�g���Ԃ�葁�߂ɏo�Ă��܂����B�Ƃ��낪�A�P�P�����̃o�X���ƁA�����̏h�A�x┌̊ۋ�قւ͂P���O�ɒ����Ă��܂��܂��B�����`�F�b�N�C�����Ԃ͂R���ł��̂ŁA�܂�����܂ł͏h�̎��ӂł��U�����������ƍl���āA�Ƃ肠�����h�ɁA�o�X��ɒ������Ԃ�A�����A�}�������肢���܂����B�}���ɂ͍s���邪�A�܂������ɂ͓���Ȃ��Ƃ������Ƃł������A����͓��R�ł��̂ō\��Ȃ��|�A�Ԏ������܂����B�o�X��ɒ����ƁA�}���̃o�X�ɂ͂������łɉ��l����肱��ł��āA��͂葁�߂ɏh�Ɍ������l�������悤�ł��B�x┌̃o�X�₩��ۋ�قւ͌��l���̈�����炢���Ȃ���Ȃ�܂���B���Ԃɂ��ĂP�T�����炢�ł��傤���B�x┌͍L���Ė��邢�ŁA�J���I�ȋC���ɂȂ�܂��B�h�ɒ����Ƃ����͔铒�Ƃ������͋C�͂܂������Ȃ��A���������]�[�g���ۂ��O�ςł��B�O�K���Ă̌������ɖʂ��ĉ��ɍג��������Ă��܂��B���ɓ����Ă݂�ƍL�X�Ƃ��Ă���ꂽ�����ɂȂ��Ă��܂��B���������Ԃ͂��傤�Ǘ������̃s�[�N�Ȃ̂��A�吨�̐l�Ŕ��ɂɂ�����Ă��āA�����Ȃ̂ɔɐ����Ă�ȁ`�ƁA�т����肵�܂����B�ǂ��ɂ��铒�̏h�Ƃ������͋C�͂���܂���B���炭����U�����āA�P�����Ɉꉞ�t�����g�ɖ߂��Ă݂�Ƃ��������Ƃ������ƂŁA�����ɕ����ւƈē����Ă���܂����B���̎��A���ݏ��̍H�����ōH���̉������邳�������Ƃ����f�菑����n����܂����B�ł��A�������H���͂R���ł�߂�Ƃ̂��ƂŁA���ۂɍH���͑S���C�ɂȂ�܂���ł����B��������A�킴�킴�f�菑��������Ĉ�l��l�ɓn���Ƃ����h�̑ԓx�Ɋ��S���܂����B�����͓��Ƀt�����g�̐l�͐l�����肪���ɂ��炩���Ƃ�����ۂ��܂����B�\���͓̂��ȏ�O�ŁA���̎��̏h�̂g�o�ɂ́A�܂�����̊�悪�o�Ă��Ȃ������̂ł����A�ꉞ���ʂ̃v�����ŗ\�Ă����āA���݂Ɠ����悤�Ȋ�悪�����čs����悤��������A������ɏ�芷����������A�����Ă����悤�ɗ���A�����ƘA�����Ă���܂����B���R�ƌ����Γ��R�ł����A�Y�ꂿ�Ⴄ���낤�ȂƂ����C�����Ă����̂ŁA�����ƘA�����Ă��ꂽ���ƂɊ��S���܂����B�Ƃ������Ƃ�����A�����̃t�����g�͍��]���ł��B�ē����Ă��ꂽ�����͂Q�K�̃��X�g�����̂ȂȂߏ゠����A�R�K�̂R�O�V�����Ō����̐^�ӂ̕������낤�Ǝv���܂��B���̏h�͘L�����͂���ŌΑ��ƎR���́A���Ε���������������������A�Α��̕��������炩�����������Ȃ��Ă��܂����A��͂菭�������Ă��Α����Ɏ��ׂ��ł��B�L��Ȏx┌ƕ��s���x�̎p�͉��Ƃ������܂���B�ē��̓h�A�̑O�܂łŁA�����o���͂���܂���ł������A����̓`�F�b�N�C�����ԑO�ɓ��������炩������܂���B���߂̃T�C�Y�̋C�Â����͂���܂����B�����͏オ���Ă����Ƀg�C���Ɛ��ʂ�����A���̃g�C�����V�����[�g�C���ł���̂ɂт����肵�܂����B���ʂ͑f���C���������̂��̂ł����A�����a���͂P�O��A����ɑ��ۂɂQ����̍L���������Ă��Ĉ֎q����r����܂��B�V�䂪�����A�Ђ�т낵�������ł��B���ɂ��A�①�ɂ��A�o�X�^�I�����t���Ă��āA�m���ɑS�̓I�ɂ͎E���i�ʼnԂ�����܂��A�ł����̗����̔铒�̏h�Ƃ��Ă͏\���ł͂Ȃ��ł��傤���B���v���̕�����肸���Ƃ����C�����܂����B�����A���̓��͏��������đ��i�����Ƃ������肵���Ԍ˂����Ă��܂��j���J���������ɂ��܂������A�����ɂ͗�[���Ȃ��A��@���u���Ă���܂����B�W���̓����͏���������������܂���B |
 �����C�͎x┌̌ΖʂƐ��ʂ��������Ƃ�������I�V���C�A�����ē����Ƃ��̊O�ɂ���W�]�I�V���C�̎O��ނŁA���ꂼ��j�����͂���܂���B����I�V���C�݂̂Q�S���ԓ����\�ŁA�����ƓW�]�I�V���C�͂Q�R���܂ł������ł��B�������A���͂S����������Ƃ������Ƃł����B�����C�ɍs�����̂͂��傤�ǂQ�����炢�ŁA��͂藧�����̃s�[�N�������Ă���炵���A���ɏ����̕��͂��Ȃ荬�ݍ����Ă���悤�ł����B�����ƓW�]�I�V�͂���ȂɍL������܂���̂ŁA���ݍ����Ă���Ƃ��܂��ۂ͗ǂ��Ȃ���������܂���B�ڂ��́A�ŏ��Ɍ���I�V���C�ɍs�����̂ł����A�����͂���Ȃɂ͍���ł��܂���ł����B���̌���I�V�͎x┌̐��ʂɂ���Đ��ʂ��㉺���A���傤�Ǎ��͏��Ȃ�����ŁA�[���͂T�P�����Ƃ������Ƃł����B�䕗�V�[�Y���ɂ͐��ʂ��㏸���A�P���[�g�����z���悤�ł����A���̓��͊��ƒ����˂��ׂ�Ȃ��ƁA���܂œ���܂���ł����B�ʂ�ڂ̂����ŁA���̏�ɂ͖̎}��t���傫���A�����A�����͂��̑O�̒����ق̂������̓��Ɠ����悤�ɗΉA�n�̘I�V�ł��B�����A�������Ɉ͂܂�ΐ��͑S�������܂���B���[���ꃁ�[�g�����z���ė��������ۂ��Ȃ��Ă��A�ǂ����ΐ��͌�������������܂���B�\���N�Ԃ肩�ŗ����Ƃ����l���C���[�W��������Ƃ����Ă��܂����̂ŁA�̂Ƃ͕ς���Ă��܂����̂�������܂���ˁB�����A�����炵�͂���܂��A�Ɉ͂܂�A����Ȃ�ɖ������I�V���Ƃ͎v���܂��B�ڂ��͂����Ɉꎞ�ԋ߂����āA�W�]�I�V�ւƈړ����܂����B���̓W�]�I�V�͎x┌ƁA���s���x�̗Y��Ȍi�F��S�s���܂Ō��n����܂��ɓW�]�n�̘I�V�ł��B�����Ɉړ������̂͂R�����ŁA���D�̏�ɂ͉����������Ȃ��̂ł����A���łɈ����ł��Ă��āA�ڂ��̑匙���Ȓ��˓����������邱�Ƃ��ł��܂��B����̓|�C���g�����������ł��ˁB�m���ꎞ�Ԃ����Ȃ������ɓ��D�S�̂����̒��ɓ������Ǝv���܂��B�����͔M�߂ʼn��y�F�ɐ��܂��Ă��܂����B������ł��܂��B���̓W�]�I�V�͔��ɋC�ɓ���܂����B���̓��͕����̂������A�ŗV�ԃ��W���[�q�͂܂��������炸�A�S�s���܂ő厩�R�ɒ��ߓ��邱�Ƃ��ł��܂����B�����Ă��鎞�ɁA�����̂����炳�����𑪂�ɗ��āA�S�R�x���ƌ����Ă��܂����B���̂�����肳��Ɏ���������̂ł����A���Ȋ�������ɂɂ��₩�ɖ����ɓ����Ă���A���̐l���D��ۂł����B���ł��Q�R���ɕ߂�ƁA�������Ă��̐l����l�ł��ׂĂ̗����̑|�������ċA��Ƃ������Ƃł��B�����炳���A�������痈���l�A��肩�痈���l�ȂǂƘb�Ȃǂ����Ȃ���A���̓W�]�I�V�ɂ͂Q���ԋ߂���������������܂���B���݂���Ă������������ȂɈ�����ۂł͂���܂��A������ƌÂ��Ȃ������ȂƂ��������ł��B���̓��ɒ�����������Ȃ��Ƃ�����肳�����Ă��܂����B���ׂĂ̂�����������ŁA�W�]�I�V�͂ق�̏��������������Ă���Ƃ�����肳�����Ă��܂����B�����܂���ł������A�����������ق�̏����������Ă���Ǝv���܂��B���Ȃ݂Ɍ���̉��x�͂T�P���ł��B�܂��A���y�F�ɕω����Ă���͓̂W�]�I�V�����ŁA����I�V�����������F�����ł����B �����C�͎x┌̌ΖʂƐ��ʂ��������Ƃ�������I�V���C�A�����ē����Ƃ��̊O�ɂ���W�]�I�V���C�̎O��ނŁA���ꂼ��j�����͂���܂���B����I�V���C�݂̂Q�S���ԓ����\�ŁA�����ƓW�]�I�V���C�͂Q�R���܂ł������ł��B�������A���͂S����������Ƃ������Ƃł����B�����C�ɍs�����̂͂��傤�ǂQ�����炢�ŁA��͂藧�����̃s�[�N�������Ă���炵���A���ɏ����̕��͂��Ȃ荬�ݍ����Ă���悤�ł����B�����ƓW�]�I�V�͂���ȂɍL������܂���̂ŁA���ݍ����Ă���Ƃ��܂��ۂ͗ǂ��Ȃ���������܂���B�ڂ��́A�ŏ��Ɍ���I�V���C�ɍs�����̂ł����A�����͂���Ȃɂ͍���ł��܂���ł����B���̌���I�V�͎x┌̐��ʂɂ���Đ��ʂ��㉺���A���傤�Ǎ��͏��Ȃ�����ŁA�[���͂T�P�����Ƃ������Ƃł����B�䕗�V�[�Y���ɂ͐��ʂ��㏸���A�P���[�g�����z���悤�ł����A���̓��͊��ƒ����˂��ׂ�Ȃ��ƁA���܂œ���܂���ł����B�ʂ�ڂ̂����ŁA���̏�ɂ͖̎}��t���傫���A�����A�����͂��̑O�̒����ق̂������̓��Ɠ����悤�ɗΉA�n�̘I�V�ł��B�����A�������Ɉ͂܂�ΐ��͑S�������܂���B���[���ꃁ�[�g�����z���ė��������ۂ��Ȃ��Ă��A�ǂ����ΐ��͌�������������܂���B�\���N�Ԃ肩�ŗ����Ƃ����l���C���[�W��������Ƃ����Ă��܂����̂ŁA�̂Ƃ͕ς���Ă��܂����̂�������܂���ˁB�����A�����炵�͂���܂��A�Ɉ͂܂�A����Ȃ�ɖ������I�V���Ƃ͎v���܂��B�ڂ��͂����Ɉꎞ�ԋ߂����āA�W�]�I�V�ւƈړ����܂����B���̓W�]�I�V�͎x┌ƁA���s���x�̗Y��Ȍi�F��S�s���܂Ō��n����܂��ɓW�]�n�̘I�V�ł��B�����Ɉړ������̂͂R�����ŁA���D�̏�ɂ͉����������Ȃ��̂ł����A���łɈ����ł��Ă��āA�ڂ��̑匙���Ȓ��˓����������邱�Ƃ��ł��܂��B����̓|�C���g�����������ł��ˁB�m���ꎞ�Ԃ����Ȃ������ɓ��D�S�̂����̒��ɓ������Ǝv���܂��B�����͔M�߂ʼn��y�F�ɐ��܂��Ă��܂����B������ł��܂��B���̓W�]�I�V�͔��ɋC�ɓ���܂����B���̓��͕����̂������A�ŗV�ԃ��W���[�q�͂܂��������炸�A�S�s���܂ő厩�R�ɒ��ߓ��邱�Ƃ��ł��܂����B�����Ă��鎞�ɁA�����̂����炳�����𑪂�ɗ��āA�S�R�x���ƌ����Ă��܂����B���̂�����肳��Ɏ���������̂ł����A���Ȋ�������ɂɂ��₩�ɖ����ɓ����Ă���A���̐l���D��ۂł����B���ł��Q�R���ɕ߂�ƁA�������Ă��̐l����l�ł��ׂĂ̗����̑|�������ċA��Ƃ������Ƃł��B�����炳���A�������痈���l�A��肩�痈���l�ȂǂƘb�Ȃǂ����Ȃ���A���̓W�]�I�V�ɂ͂Q���ԋ߂���������������܂���B���݂���Ă������������ȂɈ�����ۂł͂���܂��A������ƌÂ��Ȃ������ȂƂ��������ł��B���̓��ɒ�����������Ȃ��Ƃ�����肳�����Ă��܂����B���ׂĂ̂�����������ŁA�W�]�I�V�͂ق�̏��������������Ă���Ƃ�����肳�����Ă��܂����B�����܂���ł������A�����������ق�̏����������Ă���Ǝv���܂��B���Ȃ݂Ɍ���̉��x�͂T�P���ł��B�܂��A���y�F�ɕω����Ă���͓̂W�]�I�V�����ŁA����I�V�����������F�����ł����B |
 �[�H�͕����ɂȂ�܂��B��l��l�̌�V�ɕ��ׂ���Ƃ����^�̐H���ŁA���шȊO�͂��ׂčŏ��ɕ��ׂ��Ă��܂��܂��B���̕ӂ͔铒�̏h���ȂƂ��������ł��B���̊ۋ�قɂ́A�H���̓��e�ɍ��킹�ėl�X�ȃ^�C�v�̊�悪����̂ł����A�ڂ��̑I�̂͂��Ȃ�����ق��ɓ���Ǝv���܂��B�ł�����A�H���Ɋւ��Ă͈�T�ɂ����Ȃ��̂ł����A�ꉞ�ȒP�Ȃ��i�������t���A�Ō�̂��т�f�U�[�g�Ȃǂ������ĂW�i��������܂��A�S�̂ɏ��Ȃ�����Ƃ�����ۂ͂���܂���ł����B���̕ӂ̖������Ƃ����n�X�J�b�v���C�������݂Ȃ���ł������A�����������Ȃ��ă��C�����]���Ă��܂����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���ł����B���C���͊��̓��Ă��Ō��\�����܂��B�m�M�ŋ��L�̃N���[���V�`���[���o�āA���͎�藧�Ăđf���炵���Ƃ����܂ł̂��Ƃ͂���܂��A������z���C�g�\�[�X�D���̂ڂ��Ƃ��Ă͗ǂ������Ǝv���܂��B�S�̂ɁA����͂܂����Ƃ������̂͂���܂���B���ł����q���͂��������Ǝv���܂����B������̓T�[�����A�����A�ÊC�V�Ƃ�������f���̂��Ȃ����̂ł����A�����Ɨ₽���܂ܐH�ׂ���悤�ɔz������Ă������A�N���[���V�`���[��A���q���ȂǁA�����������������Ɖ������A�₦���Ă����Ƃ���������ۂ̂��̂͂���܂���ł����B�f�U�[�g�̓������ŐH��ɗ␅���o�āA�������l����Ώ\���R�X�g�p�t�H�[�}���X�̂���H���������ƌ����܂��B���H�̓t�����g�߂��̃��X�g�����ł̃o�C�L���O�ɂȂ�܂��B�i���������������ϓI�ŁA�܂��܂��ƌ������Ƃ���ł��B�S��ނ�H�ׂ��킯�ł͂���܂��A���ɂ���́A�Ƃ������̂��Ȃ�����ɁA���ɂ܂����Ƃ������̂��Ȃ������Ǝv���܂��B�x�[�R���͂����������̂ł����B�~���N�͂���A�W���[�X�̓I�����W�W���[�X�����ł����B�������A�R�[�q�[������܂��B�����W��̃��C�h����i�����̓��C�h����Ƃ����悤�ł��B�j�͂Ԃ�����ڂ��Ȋ����̐l�ł������A�����Č��Ȉ�ۂł͂���܂���B�]�ƈ��͑�̍D��ۂł��B �[�H�͕����ɂȂ�܂��B��l��l�̌�V�ɕ��ׂ���Ƃ����^�̐H���ŁA���шȊO�͂��ׂčŏ��ɕ��ׂ��Ă��܂��܂��B���̕ӂ͔铒�̏h���ȂƂ��������ł��B���̊ۋ�قɂ́A�H���̓��e�ɍ��킹�ėl�X�ȃ^�C�v�̊�悪����̂ł����A�ڂ��̑I�̂͂��Ȃ�����ق��ɓ���Ǝv���܂��B�ł�����A�H���Ɋւ��Ă͈�T�ɂ����Ȃ��̂ł����A�ꉞ�ȒP�Ȃ��i�������t���A�Ō�̂��т�f�U�[�g�Ȃǂ������ĂW�i��������܂��A�S�̂ɏ��Ȃ�����Ƃ�����ۂ͂���܂���ł����B���̕ӂ̖������Ƃ����n�X�J�b�v���C�������݂Ȃ���ł������A�����������Ȃ��ă��C�����]���Ă��܂����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���ł����B���C���͊��̓��Ă��Ō��\�����܂��B�m�M�ŋ��L�̃N���[���V�`���[���o�āA���͎�藧�Ăđf���炵���Ƃ����܂ł̂��Ƃ͂���܂��A������z���C�g�\�[�X�D���̂ڂ��Ƃ��Ă͗ǂ������Ǝv���܂��B�S�̂ɁA����͂܂����Ƃ������̂͂���܂���B���ł����q���͂��������Ǝv���܂����B������̓T�[�����A�����A�ÊC�V�Ƃ�������f���̂��Ȃ����̂ł����A�����Ɨ₽���܂ܐH�ׂ���悤�ɔz������Ă������A�N���[���V�`���[��A���q���ȂǁA�����������������Ɖ������A�₦���Ă����Ƃ���������ۂ̂��̂͂���܂���ł����B�f�U�[�g�̓������ŐH��ɗ␅���o�āA�������l����Ώ\���R�X�g�p�t�H�[�}���X�̂���H���������ƌ����܂��B���H�̓t�����g�߂��̃��X�g�����ł̃o�C�L���O�ɂȂ�܂��B�i���������������ϓI�ŁA�܂��܂��ƌ������Ƃ���ł��B�S��ނ�H�ׂ��킯�ł͂���܂��A���ɂ���́A�Ƃ������̂��Ȃ�����ɁA���ɂ܂����Ƃ������̂��Ȃ������Ǝv���܂��B�x�[�R���͂����������̂ł����B�~���N�͂���A�W���[�X�̓I�����W�W���[�X�����ł����B�������A�R�[�q�[������܂��B�����W��̃��C�h����i�����̓��C�h����Ƃ����悤�ł��B�j�͂Ԃ�����ڂ��Ȋ����̐l�ł������A�����Č��Ȉ�ۂł͂���܂���B�]�ƈ��͑�̍D��ۂł��B�����͐��̂��������́u�������j�R�j�R�A�������j�R�j�R�v�Ƃ������t���ɂ��Ă���悤�ł����A���̐��_�͂�������Ǝp����Ă���悤�Ɏv���܂����B�A��͂܂��x┌̃o�X��܂ő����Ă��炢�܂������A���낵���Ẵo���ŁA���߂Ă��q������悹��Ƃ������Ƃł����B���̃o���̌�����ɎВ��v�Ȃ��܂��Ƀj�R�j�R�Ǝ��U���đ����Ă���܂����B�����A���̍H�������Ă���Ƃ��납��l����ƁA�����͂��������L����v�悪����̂�������܂���B���̑�O�I�Ȕɐ��U����l����ƁA���ӁA�铒�̏h����O����Ă��܂��悤�ȋC�����܂��B |
| �@ |
| �x┌���o�X�ŎD�y�ցB����ɏ��M�܂ő���L���A���M�ŏ����ό��������ƁA�^�N�V�[�ŎO���ڂ̒����쉷��u�G�y���v�������܂����B�����Ƌ߂����ȂƎv���Ă����̂ł����A�P�T�����炢���������ł��傤���B���H�ɖʂ��đ傫�ȊŔ��������������Ă����܂��B�����͍L��ȕ~�n�������Ă��āA���̍����͍��̖����Ƃ��ď��M�ł͗L���Ȃ悤�ł��B���傤�nj܌��̘A�x�����肪���̌�����ɓ�����炵���A���̎��͑�ςȂɂ��킢�ɂȂ�ƒ�������������Ă��܂����B������̓��H�ɖʂ��āA�u������v�Ƃ����ē��̒��c�X���X���\���Ă��āA���邩��ɑ�O�I�ȗ��قƂ��������ł��B�������̂͂R��������ƑO���炢�ŁA���傤�ǃ`�F�b�N�C�����Ԃ���ł����B�����ɕ����ւƈē����Ă��炦�܂����B�ٓ��̊K�i�̂Ƃ���ł͓�K���牺�������ꗎ���A���̉��Ɍ�j���ł�����A�h�A�̉��̂Ƃ���ɁA�Ђ������傫������o���Ă���ȂǁA�Â�������ɂȂ��Ă��܂����A�ǂ��ɂ��������ꂽ�����͎܂���B�ʂ��ꂽ�̂́u��������v�Ƃ����A�{�ق̊K�i���オ���Ă����̓�K�̕����ł����B�����͖{�ق̈�K�̊e�������I�V���C�t���ɂȂ��Ă��Ă��Ȃ�l�C������悤�ł��B�����͌��\��������̂ł����A�����Ȃǂ͂��܂�ς�肪�Ȃ��Ƃ������Ƃł����B�~�ɂ͘I�V���C�t���̕����ł��i���̃v����������悤�ł����A���̓V�[�Y�����Ƃ������ƂŘI�V���C�t���͂������������A�������ς��Ȃ��̂Ȃ�ƁA�������ʂ̕�����\�܂����B�����͓��������ւ̂Ƃ��낪�ʍ����ӂ��̕~�ɂȂ��Ă��āA�������̃h�A�̉������ʁA����ɂ��̉����g�C���ɂȂ��Ă��܂��B���̃g�C�����V�����[�g�C���ł����B�����J���Ē��֓���ƁA�܂��l��̎��̊ԁA���̉��ɏ\��̖{�ԂƓ�炢�̍L���̍L���Ƒ����Ă��܂��B�Ƃɂ����A�ٓ��Ɠ����悤�ɋÂ��Ă��邱�Ƃ͋Â��Ă��āA���̊Ԃɏオ��Ƃ���͉����݂����ȑ���ɂȂ��Ă��邵�A���̊Ԃ̋��͌͂�R������|���������悤�Ȋ����ɂȂ��Ă��邵�A���̊Ԃ̔��Α��̕ǂɂ͑傫�ȊG�H���͂ߍ��܂�Ă���܂����B����������Ɩl�̕Ό��ŁA�������������ق�������A�������E�E�Ǝv���̂�������܂��i�v�����ȁH�j�A�Ȃ��܂�f���Ɋ��Q�ł��Ȃ���ł���ˁB�����ɂ��A�����A�Â��Ă݂܂����Ƃ����悤�Ȉ�ۂł����B�����͍��N�̏��ߍ��͊؍��⒆���̂��q�����ɑ��������Ƃ������Ƃł������A�O���̂��q����Ȃ�f���Ɋ����ł��邩�ȁA�Ƃ��������ł��B��������͒�̗������܂����A�L��Ȓ�����n����ƌ��������ł͑S�R����܂���B�ڂ̑O�ɂ����������Ă���̂ŁA���E�͂����ŃX�g�b�v�ł��B�܂��A���̕����ɘI�V���C�����邹���ŁA���̕����̂Ђ������傫������o���Ă��܂��B�O����̔`�����݂͑S������܂���B���̊ԂɉԂ͂���܂���ł������A�␅�͏��߂���p�ӂ���Ă��܂����B |
 �����C�͖{�قƕʊقɂ��ꂼ������ƘI�V������܂��B�I�V�͂Q�Q���܂łœ����͂Q�S���܂łł��B���C�͂��ׂĒj����ւ��A�����͂U����������邱�Ƃ��ł��܂��B��㎞�Ԃ͉�����₱���������̂ŁA�悭�o���Ă��܂��A�����ς�������ւ��Ă��܂����̂ŁA����Ȋ����Ȃ̂��낤�Ǝv���܂��B�����̉��x�͑�̂ǂ̗������K���ł����A�����26.8���ł��̂ŁA���ׂĉ��M�ł��B�܂��A�S���z���낤�Ǝv���܂��B���ׂĂ̗����ʼn��f�L�������܂������A�������炷���������ł���������o���Ă��܂����B����Ȑ����ŗ��ꍞ��ŁA����������������o���Ă��Ȃ��̂�����A����ʂłȂ��Ă��A����ɂł��z���ƕ�����d�g�݂ł��BpH�l��9.6�ł��Ȃ荂�����̂ŁA�������ʂ���Ƃ��������͂��܂����A����قǂ̃k���k�����͂���܂���ł����B�{�ق̓����͏����Â߂ŁA����������قǑ傫���͂���܂���B�{�ق̘I�V�́A�����j���̕��͊��ƍL���A�Ɉ͂܂�Ă܂��܂��̊����ł����A�����̕��̓R���j�A�����̑���ŁA�ڂ��Ƃ��Ă͑S�����������Ȃ��I�V�ł����B�ʊق̕��͖{�ق����L���Ė��邭�A�������I�V���Ȃ��Ȃ����������ł��B���ɁA�����͏����j���̕������A�����̕��������L�����邢�������܂����B������͒�̗����߂��ĕ]���������������Ǝv���܂��B�I�V�͂��ꂼ��A�r�߂Ȃ��������̂ŁA���̒r�����������L���A�����̏�ɓV��͂���܂����A�J������������I�V�ł��B�r�̌������ɂ͐��ԏ���������A�r�̒��̓��ɂȂ��Ă���悤�ȂƂ��납��͐������ӂꂾ���Ă��܂��B�܂��A�Ƃ���ǂ���ɉԂ��炫�A�ʂ�������Ă��܂��B�����A�������S�e�S�e�Ƃ����Ȃ��̂�����Ƃ�����ۂ��ʂ����܂���B���������������肳����Ƃ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�܂��A�r�Ƃ���������d�����Ȃ��̂�������܂��A������ǂ�ł��銴���ł��܂�u�₩�Ȋ����͎܂���ł����B�����A�����Ȃ璷���͂ł��邩�ȂƂ͎v���܂����B���オ��̐��͂ǂ��ɂ��Ȃ��A�����ɏ��߂���␅���p�ӂ���Ă���̂͂��̂������Ƃ��v���܂����A��͂�A���オ��ɂ������␅���ق����Ƃ���ł��B �����C�͖{�قƕʊقɂ��ꂼ������ƘI�V������܂��B�I�V�͂Q�Q���܂łœ����͂Q�S���܂łł��B���C�͂��ׂĒj����ւ��A�����͂U����������邱�Ƃ��ł��܂��B��㎞�Ԃ͉�����₱���������̂ŁA�悭�o���Ă��܂��A�����ς�������ւ��Ă��܂����̂ŁA����Ȋ����Ȃ̂��낤�Ǝv���܂��B�����̉��x�͑�̂ǂ̗������K���ł����A�����26.8���ł��̂ŁA���ׂĉ��M�ł��B�܂��A�S���z���낤�Ǝv���܂��B���ׂĂ̗����ʼn��f�L�������܂������A�������炷���������ł���������o���Ă��܂����B����Ȑ����ŗ��ꍞ��ŁA����������������o���Ă��Ȃ��̂�����A����ʂłȂ��Ă��A����ɂł��z���ƕ�����d�g�݂ł��BpH�l��9.6�ł��Ȃ荂�����̂ŁA�������ʂ���Ƃ��������͂��܂����A����قǂ̃k���k�����͂���܂���ł����B�{�ق̓����͏����Â߂ŁA����������قǑ傫���͂���܂���B�{�ق̘I�V�́A�����j���̕��͊��ƍL���A�Ɉ͂܂�Ă܂��܂��̊����ł����A�����̕��̓R���j�A�����̑���ŁA�ڂ��Ƃ��Ă͑S�����������Ȃ��I�V�ł����B�ʊق̕��͖{�ق����L���Ė��邭�A�������I�V���Ȃ��Ȃ����������ł��B���ɁA�����͏����j���̕������A�����̕��������L�����邢�������܂����B������͒�̗����߂��ĕ]���������������Ǝv���܂��B�I�V�͂��ꂼ��A�r�߂Ȃ��������̂ŁA���̒r�����������L���A�����̏�ɓV��͂���܂����A�J������������I�V�ł��B�r�̌������ɂ͐��ԏ���������A�r�̒��̓��ɂȂ��Ă���悤�ȂƂ��납��͐������ӂꂾ���Ă��܂��B�܂��A�Ƃ���ǂ���ɉԂ��炫�A�ʂ�������Ă��܂��B�����A�������S�e�S�e�Ƃ����Ȃ��̂�����Ƃ�����ۂ��ʂ����܂���B���������������肳����Ƃ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�܂��A�r�Ƃ���������d�����Ȃ��̂�������܂��A������ǂ�ł��銴���ł��܂�u�₩�Ȋ����͎܂���ł����B�����A�����Ȃ璷���͂ł��邩�ȂƂ͎v���܂����B���オ��̐��͂ǂ��ɂ��Ȃ��A�����ɏ��߂���␅���p�ӂ���Ă���̂͂��̂������Ƃ��v���܂����A��͂�A���オ��ɂ������␅���ق����Ƃ���ł��B |
 �[�H�͕����ŁA�ŏ��ɑO�A�����̂���Ԃ���ԁA�^���o�K�j�̑��A������A�����������ׂ��Ă��܂������A���i���������������ɂ���܂���B�H�O�����t���A����͂Ȃ��Ȃ������������̂ł����B�����Ă݂��炿�����Ƃ������Ƃł������A����ȏ�̂��Ƃ͏ڂ��������܂���ł����B�O�͊����ځA������͂������Ƃ��Ă��܂����B����Ԃ���Ԃ̓��͂Ȃ��Ȃ��������̂ł����B�������A�S�̂ɂ���Ƃ����p���`�̂�����̂͂���܂���B���̂��ƂŊC�V�̋S�k�Ă��A�W���̓�i�����āA���̌オ���тɂȂ�܂��B�������ď����Ă݂�ƕi�������Ȃ������ł��ˁB�^���o�̑�������Ȃɗʂ͂Ȃ������̂ł����A�ł������̂悤�ɁA���т������肵�Ė���������Ƃ������Ƃ͂���܂���ł����B�f�U�[�g�̓�������䕂ŁA䕂͍���ł������A�������͂����������̂ł����B �[�H�͕����ŁA�ŏ��ɑO�A�����̂���Ԃ���ԁA�^���o�K�j�̑��A������A�����������ׂ��Ă��܂������A���i���������������ɂ���܂���B�H�O�����t���A����͂Ȃ��Ȃ������������̂ł����B�����Ă݂��炿�����Ƃ������Ƃł������A����ȏ�̂��Ƃ͏ڂ��������܂���ł����B�O�͊����ځA������͂������Ƃ��Ă��܂����B����Ԃ���Ԃ̓��͂Ȃ��Ȃ��������̂ł����B�������A�S�̂ɂ���Ƃ����p���`�̂�����̂͂���܂���B���̂��ƂŊC�V�̋S�k�Ă��A�W���̓�i�����āA���̌オ���тɂȂ�܂��B�������ď����Ă݂�ƕi�������Ȃ������ł��ˁB�^���o�̑�������Ȃɗʂ͂Ȃ������̂ł����A�ł������̂悤�ɁA���т������肵�Ė���������Ƃ������Ƃ͂���܂���ł����B�f�U�[�g�̓�������䕂ŁA䕂͍���ł������A�������͂����������̂ł����B�@���H�͑�L�ԂŁA������Ɗe�����̐H�������ׂ�Ă��܂��B�v�X�Ƀ{�����[�����̂��钩�H�ŁA���̐�g���傫���A��Ԃ̃T���_�A�������A�C�ہA���Ă��A���Z���A���炱�A�V���X���낵�A�ώς̑��ɁA�C�J�h���ƃT�[�����̎h���g�������ł����t���Ă��Ă���͂����������̂ł����B���͂�����ς��ł߂ł������A�H���͑S�̓I�ɂ��������H�ׂ��܂����B�����́A���̓��͖����������悤�ł��B���H�������Ă��A������ƐH�������ׂ��A���̗��ق�������A���܂������낤�ȂƊ����܂����B�ł��A���ł���Ȃɐl�C������̂��Ƃ������Ƃ͍���킩��܂���B����������ȂɈ����킯�ł͂���܂���B���C���z�ł��邱�Ƃ��l����ƍ���ł����A�������f���炵���Ƃ͂����܂���B�������A�l�C������悤�ł��ˁB�]�ƈ��̑ԓx�������ƌ������Ƃ͂܂���������܂��A���ĂȂ��̐S���������͍̂Ō�̌�����ɏo�Ă��ꂽ���������ł����B�ł��A�l�C������A�݂�Ȃ��������������Ă���l�q�ł��B��O�����̍������ۂ����قƂ������Ƃł��傤���B |
| �Ó��́u�ፑ�v�֍s���Ă��܂����B�Ó�ւ͉z�㓒��o�X�łT�O���B���͈ӊO�ɋ߂��̂ł����B�������A���̃o�X�ւ͈���Ɏl�{�قǂ�������܂���̂ŁA���x�ꂽ���ςł��B�o�X��ɍ~��ĘA������ƌ}���ɗ��Ă���A���̎Ԃ��T�E�U���Œ����Ă��܂��܂��B�`�F�b�N�C���͂R���ŁA�Q��������ɒ������̂ł��������Ɉē����Ă���܂����B���z���ĂR�N�Ƃ������Ƃł܂��ǂ����V�����A�����ꂢ�Ȋ����ŁA�S�̓I�ɂ��炵�F�������Ɨ������������悤�ȐF����̂悤�ł��B�L�������ꂢ�ȃJ�[�y�b�g���~����Đ\��������܂���B�����͂Q�K�̂Q�P�T�����u�璹���v�Ƃ��������ł����B�����ɂ͂��ׂĉԂ̖��O�������A�ٓ���e�����ɂ͉����Ԃ������Ă��܂��B�\��������Ƃ��Ƀp���t���b�g�𑗂��Ă�������̂ł����B�菑���̂������������Ă��Ă���ɂ������ȉ����Ԃ����Ă��܂����B���̕ӂ������ɐl�C�̂䂦��ł��傤�B�����͓���ƒ��߂̃X�y�[�X������A���ɋȂ���ƈ����̓��ݍ��݂�����܂��B���ݍ��݂̐��ʂɂ͏��^�̗①�ɂ��u����Ă��܂����A���̗①�ɂ͋�Ȃ̂Ŏ����̎��R�Ɏg�����Ƃ��ł��܂��B�~�������̂̓t�����g�ɗ��ނ��A���̋@�Ŕ����Ă��̒��ɓ���܂��B���ݍ��݂̍���ɐ��ʏ��ƃg�C��������A���ʏ��ɂ͐�p�̃^�I�������炵���ق̂����ɓ����Ă��܂����B�g�C���͉����ł͂�����̂̃V�����[�g�C���ł͂���܂���ł����B���������̐V���������������̂ɂ��̓_�͔��Ɏc�O�ł����B���ݍ��݂̉E�ɂP�O��̘a�����z�u����Ă��܂��B�����A�L���͂���܂���B�N���Ȃǂ͍��|���������y�Ƃ����l�������̂ŁA�ڂ��͍L���ƈ֎q�͂��������������Ǝv���̂ł����B���܂�C�ɂ��Ȃ��Ⴂ�l�������̂ł��傤�B������̏��̊Ԃ�����A���Α��ɂ̓e���r����ɂ��u����Ă��܂��B���̊Ԃɂ͉��炵���Ԃ��u����Ă��܂������A����͑��Ԃł����B�����͐��Ԃ��ق����Ƃ���ł��ˁB������͐M�Z�삪�����܂����A��K�Ȃ̂ŁA���Ȃ艡���猩�銴���ɂȂ�܂��B���̎�O��������݂ɂ͉Ƃ������A�`�����݂͊��Ƃ���ق��ł��B�����ɂ͂��ׂẴT�C�Y�̗��߂��������Ă��Ď����ɍ��������߂�I�Ԃ��Ƃ��ł��܂��B�����A�g���̖ڈ��Ȃǂ̏����ꂽ���̂��Ȃ��̂ŁA���̂ւ�͏����s�e��������܂���B�o�X�^�I���ƃt�F�C�X�^�I�����u����Ă��܂������A�ނ������Ń|�[�`��r�j�[���܂Ȃǂ�����܂���B�S�̓I�ɂ��̐ፑ�͔��ɍs���͂��Ă���h�������̂ł����A����ł͔G�ꂽ�^�I���̏��������ɂ����A���̓_�͐ፑ�炵���Ȃ������Ǝv���܂��B���̃t�F�C�X�^�I���͎����A��s���Ǝv�����̂ł����A�`�F�b�N�A�E�g�̎��Ɋm�F����ƁAOK�Ƃ������Ƃł����B��̂ނ������Œu����Ă���Ƃ���͎����A��s�ł��̂ŁA���̂ւ��������ɂ����Ǝv���܂����B���̖ʂ���l����ƁA�����͉��炵���|�[�`�Ȃǂ��ɗp�ӂ��Ă��銴���̏h�Ȃ̂ł����A���̓_�Ɋւ��Ă��D�ɗ����܂���B�^�I�����̂́u�ፑ�v�Ǝh�J�Ŗ��O��������Ă���^�C�v�́A�������̂ł��B�S�̓I�ɕ������̂͐V�������������Ė��邭�����Ő\��������܂���B�}���َq�͏����̊��}�̌��t�������ꂽ�܂�߂̊��A��͂�܂莆�̗e��ɓ������ȂǁA���Ɏ肪����ł��܂��B�o���Ă������ݕ��͂������Ϗo���č���������W���[�X�ŁA�V�����V�����ƖA�͗����Ă��܂��A�Y�_�������Ă���悤�Ȃ�����Ƃ������ł����������̂ł����B���́u�ፑ�v�ɂ͂U�l�̏���������Ƃ������Ƃł��B���̓��̓o�X��܂Ō}���ɗ��Ă��ꂽ�̂��U�ԏ����A��ɐڋq���Ă��ꂽ�̂͂T�ԏ����ł����B��l�͎o���Ŕ��ɖ��邭���C�ŁA���ĂȂ��̐S�����������Ă���܂����B |
 �ŏ�K�̂S�K�������C�����̃t���A�ɂȂ��Ă��܂��B�����ɒj����ւ���^�C�v�ŁA���オ�菈�ɂ͗␅�@���u����A���������������ł����߂�悤�ɂȂ��Ă��܂��B�I�V�͂P�O���܂ŁA�嗁��͂P�P���܂łŁA���͂U������ł��B�E�ߏ����嗁�������ꂽ�����̂��̂ł����B�嗁��̓��D�͂U�E�V�l�Ƃ��������ł����A���ق̋K�͂��猾�����炿�傤�ǂ������炢�ł��傤�B��̐����\���ɂ���܂����B���D�ɂ́A�����ł����C���F�̂������������ӂ�Ă��܂����B���D�̉�����������͗���o���Ă��܂��B�������A�����̒�����������悭�������o�Ă��܂��̂ŁA���z���Ǝv���܂��B���܂��ȓ��̉Ԃ�����A�K���łȂ��Ȃ������������Ǝv���܂��B�����A�����̒�����o�Ă��邨���̐����������̂ŁA�߂��ɂ���Ƃ킸��킵���C�����܂����B����Ȉ�ۂ�^���邨���ł͂Ȃ��̂ł����A�ӂƎ߂��瓒�ʂ�����ƁA�p�x�ɂ���Ă͖����̂悤�ȃM�����������܂��B���L�͂܂������Ȃ��̂ł����A��͂苰��ׂ��V���̓��Ƃ����Ƃ���ł��傤���B �ŏ�K�̂S�K�������C�����̃t���A�ɂȂ��Ă��܂��B�����ɒj����ւ���^�C�v�ŁA���オ�菈�ɂ͗␅�@���u����A���������������ł����߂�悤�ɂȂ��Ă��܂��B�I�V�͂P�O���܂ŁA�嗁��͂P�P���܂łŁA���͂U������ł��B�E�ߏ����嗁�������ꂽ�����̂��̂ł����B�嗁��̓��D�͂U�E�V�l�Ƃ��������ł����A���ق̋K�͂��猾�����炿�傤�ǂ������炢�ł��傤�B��̐����\���ɂ���܂����B���D�ɂ́A�����ł����C���F�̂������������ӂ�Ă��܂����B���D�̉�����������͗���o���Ă��܂��B�������A�����̒�����������悭�������o�Ă��܂��̂ŁA���z���Ǝv���܂��B���܂��ȓ��̉Ԃ�����A�K���łȂ��Ȃ������������Ǝv���܂��B�����A�����̒�����o�Ă��邨���̐����������̂ŁA�߂��ɂ���Ƃ킸��킵���C�����܂����B����Ȉ�ۂ�^���邨���ł͂Ȃ��̂ł����A�ӂƎ߂��瓒�ʂ�����ƁA�p�x�ɂ���Ă͖����̂悤�ȃM�����������܂��B���L�͂܂������Ȃ��̂ł����A��͂苰��ׂ��V���̓��Ƃ����Ƃ���ł��傤���B |
 �I�V�͑嗁�ꂩ��o��^�C�v�ŁA���̓��ɓ��������̓x�����_�^�ł����B��������������A�����ȃv���X�e�B�b�N�Ɉ͂܂�Ă��܂��B��E�O�l�Ƃ����������ł��傤���B�l�K�ł��̂œ�K�̕������͐M�Z��̗��ꂪ�]�߂܂��B�������A��݂Ɍ��ƂȂǂ���`�����݂͌��\���肻���ł��B�����͗����͏����p�ɂȂ�̂ŁA���v�Ȃ̂�������ƐS�z���Ă��܂��܂����B������ւ������̘I�V�́A��͂蓯�������������Ă���̂ł����A�Ƃ����Ȃ��`�����݂͂قƂ�ǂ���܂���B�S�ʂɉ����͂���܂����A������̕����J����������I�V�ł����B���āA�ŏ��ɂ������܂������A���̘I�V�ʼn��Ƃ��c�O�Ȃ̂��A�����͉���ł͂Ȃ����Ƃł��B�����Ɣ�אF�����Ă��܂���̂ł����ɕ�����܂��B�������A���������D����͏������ł������������ӂ�Ă���̂ŁA���z�ɋ߂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�嗁����A�I�V������������f�L�͂��܂���ł����B �I�V�͑嗁�ꂩ��o��^�C�v�ŁA���̓��ɓ��������̓x�����_�^�ł����B��������������A�����ȃv���X�e�B�b�N�Ɉ͂܂�Ă��܂��B��E�O�l�Ƃ����������ł��傤���B�l�K�ł��̂œ�K�̕������͐M�Z��̗��ꂪ�]�߂܂��B�������A��݂Ɍ��ƂȂǂ���`�����݂͌��\���肻���ł��B�����͗����͏����p�ɂȂ�̂ŁA���v�Ȃ̂�������ƐS�z���Ă��܂��܂����B������ւ������̘I�V�́A��͂蓯�������������Ă���̂ł����A�Ƃ����Ȃ��`�����݂͂قƂ�ǂ���܂���B�S�ʂɉ����͂���܂����A������̕����J����������I�V�ł����B���āA�ŏ��ɂ������܂������A���̘I�V�ʼn��Ƃ��c�O�Ȃ̂��A�����͉���ł͂Ȃ����Ƃł��B�����Ɣ�אF�����Ă��܂���̂ł����ɕ�����܂��B�������A���������D����͏������ł������������ӂ�Ă���̂ŁA���z�ɋ߂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�嗁����A�I�V������������f�L�͂��܂���ł����B |
| �H���͈�K�̐H�����ł��B�w���̍����������֎q�ɍ��|���Ă̐H���ł��B�Ȃɒ����Ƃ��łɐȂɂ͐H�O�����܂߂ĂV�i���u����Ă��܂����B���ʁA���̗������Ɗ�͑S�R��ۂɎc��Ȃ����̂��قƂ�ǂȂ̂ł����A�т����肵���̂́A����Ȃ�ɋC���������킪���ׂ��Ă������Ƃł��B�H�����e�ɂ��ĊȒP�Ȑ����͂���܂������A�c�O�Ȃ��炨�i�����͂���܂���B�H�O���͂��������B�葢��̂悤�ł��B���̂���A�I���̐|�̕��A�c�y���낢��A��̖��X�āA�Ȃǂ����ׂ��Ă��āA�����������̂���ɉ������܂��B���^���ύ��݂ɂ͕ۉ��p�̂낤�ɉ����Ă���Ƃ������Ƃ������̂ŁA���������ɂ��Ă�����A�͂��Ă��炸�A�₽�����̂�H�ׂ�͂߂ɂȂ��Ă��܂��܂����B���炭���āA�܂��A�T���_���h�g�A����A���̏ĕ��A�������肩�������ƃY�b�L�[�j�̓V�n�����A���̏��ň�i���^��Ă��܂��B�T���_���h�g�Ɋւ��Ă͂ڂ��͕��ʂ̂�����̕����������ȂƎv���Ă��܂��܂����A����͓��Ɂu�����̌���v�Ɩ��t�����Ă���悤�ɂ����̎����̕i�炵���A�m���ɐ�i�ł����B�L�݂͂܂������Ȃ��A���X���Ƃ悭���a���āA���܂ŐH�ׂ���_�炩���ł��B�����Ă̈��̉��Ă��������������̂ŁA�Ō�̏������肩�������ƃY�b�L�[�j�̓V�n�����������悭�����Ŗ����ł��܂����B���߂ɕ��ׂ��Ă��邫�̂�������������Ղ�ŁA���̂��̍D���Ȑl�ɂ͂��������Ȃ����Ƃł��傤�B�^��ł���y�[�X������قǑ��������肹���A�����^�C�~���O�������Ǝv���܂��B�Ō�̃f�U�[�g�̓������ł����B���H�������Ȃł��B���̏ĕ��≷�͂���܂����A���̑��͈�ʓI�Ȓ���H�Ƃ͈ꖡ�������������ł��B����ł����ÊC�V�̎h�g���o����Ă��ċ����܂����B���Ƃ��A���̎h�g�ł��낤�ƁA���̗����ł͕��ʂ͕t���܂���B�S�̂ɎR���g�����c�ɗ����Ƃ����������ŁA�e�[�u���̏�ɉ��i�����ׂ��A����ɁA�����̋��̃e�[�u���ɂ����i���A�o�C�L���O�`���Ŏ���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�H�������Ă���ƏĂ����ẴN�����b�T���������Ă��Ă���܂����B����͎����A���Ă����̂��ƕ����ƁA�����ƂԂ�Ȃ��悤�ɔz�����đ܂ɓ���Ă���܂����B���̒��H���\�������ł�����̂ł����B�����͔��u�����܂莆�łł��Ă���ȂǁA���Ɏ�Ԃ������āA���������Օi�𑽗p���Ă��ĂȂ��Ă���܂��B�A���P�[�g�ɓ�����ƁA����������܂��悤�ɂƁA�T�~�ʂ������������̉��炵��������������܂��B�ׂ₩�ȐS�����ŁA�����ɂƂ��Ă͔��Ɋ����̑����h���Ǝv���܂��B������Ɋւ��Ă��A�Ԃ��o��܂ł������茩�����Ă���܂����B�����Ă�������p���t���b�g�ɂ́A�o�X�̎����\�Ȃǂ�����̐g�ɂȂ����A�K�v�Ȃ��̂������Ă��܂����B�����A����ƈꏏ�Ɏ��ԊO�͈ꎞ�ԂP�O�O�O�~�Ƃ������e�̎菑���̃����������Ă��܂����B�e�ؐS���炾�Ǝv���̂ł����A����͌��킸�����Ȃ��ȂƂ����C�����܂����B���܂ł͂ǂ̏h���A���Ȃ葁�������Ă������̗p�ӂ��ł��Ă���Ε����ɓ���Ă���܂������A�p�ӂ��ł��Ă��Ȃ���Α҂�����܂����B����ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���_���C�ɂȂ�_�������Ă��܂������A�S�̓I�ɂ͂قƂ�nj������ƂȂ��ł��BJTB�̋��藷�قł͂Ȃ������Ȃ̂����Ȃ̂��AJTB�̖����x�X�O�_�ȏ�̏h�ɓ����Ă��܂��A���������x�X�O�_�ȏ�̏h�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B����Ɍ����āA���ɃR�X�g�p�t�H�[�}���X�̍����h�ŁA�����A�T���l�グ���Ă��܂������s���͊����Ȃ��ł��傤�B�܂��S���I�ɒm���Ă��Ȃ��������A���̓����͂������������������ł����A���Ӄ��s�[�^�[�Ő�߂��邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�����Ȃ��Ă��ǂ����l�グ���Ȃ��Ŋ撣���ė~�����Ɗ�킸�ɂ͂����܂���B |
| �`�F�b�N�C�����Ԃ̂R�����傤�ǂɏh���ꏊ�A���̑�u�̂悳�̗��v�ɒ����܂����B�ڂ������̒���ɂ�͂������g�������āA���̓��̏h���͂��̓�g�����ł����B�t�����g�ɂ͎Ⴂ�j������l���āA��œ���������g���c���āA�������ē����Ă���܂����B���́u�̂悳�̗��v�̓t�����g�̂���u�{�Ɓv���牮���̕t�����n��L����ʂ��āA�h�����ł���u���Ɓv�֍s���Ƃ����`�ɂȂ��Ă��܂��B�{�Ƃɂ́A�����A�H����������A�H���͒��E�[�Ƃ������ł��������܂��B�����͂P�O���܂łŁA�I�����Ԃ������̂ł����A����͕��Ƃ���{�Ƃ֒ʂ���ʗp�����P�O���ɕ߂Ă��܂��Ƃ������R�̂悤�ł��B���̂����A��͂�n��L����ʂ��Ă����I�V���C�͂Q�S���ԓ����\�Ƃ����A���̏h�Ƃ͂܂������t�̎��Ԑݒ�ɂȂ��Ă��܂��B���Ƃ͎��̏h��������Ȃ�A���ꂼ�ꂪ�Ɨ���������̌`���ɂȂ��Ă��܂����A�����͓��ɏ�̂�����̂ł͂Ȃ��A��������ӂꂽ�����̊ȑf�Ȍ����ł����B�n��L���͖̔ň͂��A�������肵���V�������������Ă��܂����B�ȑO�͍����������������ł����A���͂����Ƃ����L���ɂȂ��Ă��܂��B�r���ŘI�V���C�����Əh���������ɕ�����A�h�����͊ȒP�Ɍ����ƈ�{�̊������獶�E�Ɍ݂��Ⴂ�ɕ����ꂽ������̐�Ɉꌬ������Ƃ����`���̂悤�ł����B���̊����͂��Ȃ蒷�������ɉ��тĂ��āA��͂P�O�O���[�g�����炢����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�ڂ������܂����͓̂�Ԗڂ́u���ܘY�v�Ƃ��������ł������A��Ԑ�̕����͂����C�ɍs���ɂ��Ă��A�H���ɍs���ɂ��Ă����Ȃ莞�Ԃ������肻���Ȋ����ł����B�����ˎ��̌˂��J����ƁA�L���̊ԂɂȂ��Ă��āA�����Ɉ͘F�������Ă���܂��B���ʂ̉Ƃ̑䏊�ɂ���悤�ȃX�e�����X�̗����䂪�����̋��ɂ��Ă��܂��B�����A���̗�����ɂ̓K�X�ȂǁA���g������̂�����܂���̂ŁA�����Œ������邱�Ƃ͂ł��܂���B�①�ɂ����ʂ̉ƒ�p�̏��^�̂��̂��u����Ă��āA���ɂ̓r�[���Ȃǂ������Ă��܂������A�܂������̂��̂�������]�T�������Ղ肠��܂��B����͎��Ȑ\�����ł��B�����̔��Α��Ƀg�C��������A�g�C���̃h�A���J����ƁA���ɑ傫�Ȓg�����������Ă��ď�������܂ł��B�g�C���͘a���ł����B�����̃g�C�����ɂ͗��������̐��ʑ���u����Ă��܂��B�������C�͂���܂��A���ɂ��A�e�B�b�V�����o�X�^�I��������܂����B���̔̊Ԃ͍L���A���m�ȂƂ���͕�����܂��A�P�S���傭�炢�͂������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̔̊Ԃ̉��ɂW��̘a���ƁA�S�����̘a��������ł��܂��B���̓�̘a���͉��̏���C���Ȃ������ŁA���̊ԂȂǂ��Ȃ��E���i�ł��B�W��̕��ɕz�c���l������܂�Ă��āA�Q�鎞�͎����ŕ~�����ƂɂȂ��Ă��܂��B�����Â��Ȃ��������Ƃ��������ł����A�Ԍ˂Ȃǂ͂������肵�Ă��܂����B���̊O�ɂ͎���̖X�������܂��B�`�����݂͂���܂��A���ʂ̉ƂƓ����悤�Ȋ����ł�����A�˒���͂������肵�Ă����K�v�͂���܂��B�����̌��ւɂ̓X���b�p�ł͂Ȃ��A��炶�ɋ߂������̑������u����Ă��܂����B |
 �I�V�͒��b�R�̛����̂悤�ȎR������O�ɒ��߂���A�R�W�]�n�̊╗�C�ł��B�j�����͂Ȃ��A�j���p�̘I�V�́A���D����o�Ď�������낤�낵�Ă��鎞�ɂ́A�n��L�����猩���Ă��܂���������܂���B���̓������������b�R�͌��邱�Ƃ��o���܂������A�[���͋t���̂��߂ɃV���G�b�g�ɂȂ��Ă��܂��܂��B���̑���A���͎R���Ɍ����������āA���ɂ��������ł��B���b�R�͂ǂ̂��炢�̍����Ȃ̂�������܂��A���Ȃ�傫��������߂܂��B���̘I�V�͂��������L���̂ł����A������߂ŁA�̂����Ȃ蒾�߂Ȃ��ƌ��܂ł��邱�Ƃ��ł��܂���B�����͂��M���Ƃ��������ŁA�������炨����������ɗ��ꍞ��ł��܂����A���������ǂ��ɂ�����o���Ă��炸�A�z���Ǝv���܂��B�{�C���[�̍쓮����炵�������������Ă��܂��̂ŁA�ߔM�����Ă���̂�������܂���B���͂��̗��ꍞ�݂����Ȃ����������߂ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA�Q�S����OK�Ƃ͂������̂́A��͉��M��}���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���D�ɂ����Ă���Ƃ��͉��f�L�͊����܂���ł������A������@�ɋ߂Â������ɁA��H�Ƃ������������܂����B�Ƃ͂����A���̘I�V�̒��߂͑f���炵���A�R�߂Ȃ��炨���C�ɓ���̂��D���Ȑl�ɂ͐�D�̘I�V�ł��B�{�Ƃɂ�������͏����߂œ�E�O�l�Ƃ��������ł��傤���B����������Ȃɏ������Ƃ��������ł͂Ȃ��A�E���i�ł��B������̌i�F���Ȃ��A�����ɂ����ƌ��������^�C�v�̂����C�ł��B��������ŁA����������M�߂̂������Â��ɗ��ꍞ��ł��܂��B���D�ɐg�߂�ƁA���ӂꂽ��������͂苷�ڂ̗���̔r�����ɗ��ꍞ�މ������܂��B�Â������̂����C�ł����A��͎O����A��������V�����[���t���Ă��Ă��̂ւ�͋C��z���Ă��܂��B�܂��A�D�Y�Ό�������܂����B �I�V�͒��b�R�̛����̂悤�ȎR������O�ɒ��߂���A�R�W�]�n�̊╗�C�ł��B�j�����͂Ȃ��A�j���p�̘I�V�́A���D����o�Ď�������낤�낵�Ă��鎞�ɂ́A�n��L�����猩���Ă��܂���������܂���B���̓������������b�R�͌��邱�Ƃ��o���܂������A�[���͋t���̂��߂ɃV���G�b�g�ɂȂ��Ă��܂��܂��B���̑���A���͎R���Ɍ����������āA���ɂ��������ł��B���b�R�͂ǂ̂��炢�̍����Ȃ̂�������܂��A���Ȃ�傫��������߂܂��B���̘I�V�͂��������L���̂ł����A������߂ŁA�̂����Ȃ蒾�߂Ȃ��ƌ��܂ł��邱�Ƃ��ł��܂���B�����͂��M���Ƃ��������ŁA�������炨����������ɗ��ꍞ��ł��܂����A���������ǂ��ɂ�����o���Ă��炸�A�z���Ǝv���܂��B�{�C���[�̍쓮����炵�������������Ă��܂��̂ŁA�ߔM�����Ă���̂�������܂���B���͂��̗��ꍞ�݂����Ȃ����������߂ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA�Q�S����OK�Ƃ͂������̂́A��͉��M��}���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���D�ɂ����Ă���Ƃ��͉��f�L�͊����܂���ł������A������@�ɋ߂Â������ɁA��H�Ƃ������������܂����B�Ƃ͂����A���̘I�V�̒��߂͑f���炵���A�R�߂Ȃ��炨���C�ɓ���̂��D���Ȑl�ɂ͐�D�̘I�V�ł��B�{�Ƃɂ�������͏����߂œ�E�O�l�Ƃ��������ł��傤���B����������Ȃɏ������Ƃ��������ł͂Ȃ��A�E���i�ł��B������̌i�F���Ȃ��A�����ɂ����ƌ��������^�C�v�̂����C�ł��B��������ŁA����������M�߂̂������Â��ɗ��ꍞ��ł��܂��B���D�ɐg�߂�ƁA���ӂꂽ��������͂苷�ڂ̗���̔r�����ɗ��ꍞ�މ������܂��B�Â������̂����C�ł����A��͎O����A��������V�����[���t���Ă��Ă��̂ւ�͋C��z���Ă��܂��B�܂��A�D�Y�Ό�������܂����B |
| �H���͖�͂U������A���͂V��������Ǝw�肳��܂����B�{�Ƃ̐H�����́A�^�Ɉ͘F�������Ă���A�����傫������Ă��āA���b�R�߂Ȃ���H������邱�Ƃ��ł��܂��B�H�����ɕt���ƁA���łɓV�n�������ߗ��������ׂ��Ă��āA���̗����̉��ɕ~����Ă��鎆�����i�����ɂȂ��Ă��܂����B�����͂���܂���B���т̂��т��т����ׂĒu����Ă��܂������A�⋛�̉��Ă������͏����o���Ă���Ă����Ă������Ă��Ă���܂����B�܂��A���z���������͂�̎��Ɏ����Ă��Ă���܂��B�R�쑐�̓V�n���͏��߂ɏo����Ă���̂ł����A�f�ނ���������������̂��A�g�����������̂��A��߂Ă��Ă�����قǖ��͗����Ă��Ȃ��C�����܂����B�H�R�����̓c�y�Ƃ����̂�����A����͔��ɂ��������Ǝv���܂����B�܂��A�R�ؒ��ЁA�Ȃ߂��Ƃ������������Ǝv���܂��B�R�،n�������A�S�̓I�ɖ��͂���قLj����͂Ȃ��Ɗ����܂����B�������A�R�̒��ł��肨���肪�Ȃ��ȂǁA�i���͑啪���Ȃ߂ŁA����Ɉ�i��i�̗ʂ������Ȃ��̂ŁA���̕ӂɊւ��Ă͂��Ȃ�s�����c��l�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ڂ��̓r�[�����i��ŕ����ӂ��ꂽ���Ƃ�����A����قǂɂ͊����Ȃ������̂ł����A�q�ϓI�Ɍ��Ă݂�ƁA���Ȃ�s�����炽�炾�����낤�Ǝv���܂��B���͂�͂��т��тŁA���͂�̒��ɉ��F�������|�`�|�`�ƌ����܂����A�S�̖̂��ɂ���قlje���͋y�ڂ��Ă͂��܂���B�f�U�[�g�͂���܂���ł����B���H�����ɗ҂����n�̐H���ł��B�������A���X�`��M���ɁA���̔Z�����̂������A���т��Œ��t�H�ׂȂ��ƁA���̗҂����n�ł��炷�ׂĐH�ׂ��܂���ł����B���H���ɂ͂ǂ��������l�͂��Ȃ������ŁA�o���ꂽ���̂͋��̊ØI�ς����߁A���ׂĕۑ��̂������̂Ƃ������������܂����B�ۑ��𗘂����邽�߂ɁA�����ĔZ���ڂ̖��ɍ���Ă���̂�������܂���B�[�т̂Ƃ��͂����������̂��������̂ɁA�c�O�ł����B���e�͋��̊ØI�ς̉��ɗ��Ă��̏�������M�A�R�������傱���傱���Ɠ������������l�i�A����ƊC�ۂƂ����������ł��B���͂�͂�͂肫�т��тł��B�h�������́A�傫�ȗ���Ɉ�l�Ŕ��܂����Ƃ������Ƃ��l��������͂Ȃ��̂�������Ȃ�����ǁA�����̂��Ƃ��l����ƁA�����Ƃ��������ł��ˁB�����͉h���U�����ЂƂ����Ƃ��낪����Ă��鏀�����̏h�炵���̂ł����A���̕ӂ������̏h�̌��E���ȂƂ������܂����B����̕��Ƃ�������������ł�悤�Ɏ�����A�����������Ƃ����Ə[��������A�I�V�̌i�F�͔��Q�Ȃ̂ł�����A���\�l�C���o��̂ł͂Ȃ����Ƃ����悤�ȋC�����܂��B���c��������A�K���ɖ͍�����Ƃ���ł��傤���A�o�c�ɐ������������Ă��邩�A���Ȃ����͔��ɏd�v���Ȃƍ��X�Ȃ��犴���܂����B�ł��A���̂܂܂ɂ��Ă��A�{�Ƃ͂���������������āA�t�����g�̒j���������͈�������܂���ł����B�����Ɋ��҂������Ȃ��̂ł���A���Ƃ͂���قLj����͂Ȃ��̂ŁA�����߂��Ă������h���Ǝv���܂��ˁB |
| �M�B�A�����܂⍂���̂����܂⍂���z�e���ɍs���Ă��܂����B�k�������ł͂Ȃ��A���Ƃ��ƍ����ȂǎR�̌i�F���D�������A������́A����������ƍg�t�����ꂢ���ȂƂ����C����������܂����B�����܂⍂���z�e���ւ́A��c����z�e���̑��}�ԂłT�O���߂�������܂��B���S�ȍg�t�܂Ō�ꑧ�Ƃ����i�F�̒��A���}�o�X�͂����܂⍂���ւƌ������܂��B�����͊m���P�T�O�O���[�g�����ƌ����Ă��܂������猋�\�ȍ����ł��B�z�e���͊O�ς̓I�V�����Ȋ����ł����A����������Ƃ݂₰������ꂪ��������A������ƎG�R�Ƃ��Ă��܂��B���}�o�X�ʼn��g���̋q����x�ɓ��������̂ŁA�ē��܂ł��炭�҂�����܂������A���Ƒ��߂Ɉē����Ă��炦�܂����B�ē��͒j���ʼnו��͎����Ă���܂��B�����͂R�K�ł��̃z�e���̓��]�[�g�^�ł��̂ŁA�R�K���ŏ�K�ł��B�L�[�̓z�e���炵���h�A�̓����̕ǂ̃|�P�b�g�ɓ���ĕ����̓����_������`�ł��B�ł��A�I�[�g���b�N�ł͂���܂���B�����ɂ́A�قƂ�Nj�̗①�ɂ��u���Ă�����A�����̍D���Ɏg�����Ƃ��ł��܂��B�␅�����߂���u���Ă���A���߂̋C�Â����������Ƃ���܂����B�������A�z�e���`���ł��̂ŁA�����o���͂���܂���B�}���َq���u���ĂȂ������̂ŁA����Ȃ��̂��Ǝv���A�킴�킴�t�����g�ɖ₢���킹���肵�Ȃ������̂ł����A�啪�����ė①�ɂ̒��ɂ��َq����₵�Ă���̂ɋC�Â��܂����B���̂��َq�͂قƂ�NJ����`�Ƃ����Ă������̂ŁA���ꂪ�l�p���J�b�g��������Ă��܂����B�Ȃ��Ȃ������������َq�ł����B���̈ē��̒j���͑S�̂ɑΉ��������͂Ȃ������̂ł����A���̌}���َq�ɂ��Ă̈ē����Ȃ������̂��傫�Ȍ��_�����ł����B�����͈�ʓI�ȃz�e���̕����̍�肾�Ǝv���̂ł����A�h�A������Ă܂����ɐ��ʏ��i�����̐��ʑ�͓�ʂ���܂����j�B���ʑ�Ɍ����������āA��⋷�ڂ̃o�X�A���ׂ̗��g�C���ŁA�V�����[�g�C���ł����B�L��������Ő��ʏ��̔��Α��ɃN���[�[�b�g�����Ă��܂��B����ɐi�ނƂP�O����̃x�b�h���[��������A���̐�ɘZ��̘a�����t���Ă��܂��B���̎��܂őS�R�m��Ȃ������̂ł����A�\���v�����͂ǂ����a�m���������悤�ł��B�L������x�b�h���[���ɓ���Ƃ���ɁA�h�A�����Ă��܂����B���܂ł̌o���ł͂����̃h�A���Ă��Ă��Ȃ����������C������̂ł����A�C�Â��Ȃ����������ł��傤���B�a���ɂ͔������ŁA�Ԃ��Ȃ��Ƃ͂������̊Ԃ�����A�S�̓I�ɂ����ꂢ�Ȋ����ł��B�����A�c�O�Ȃ��Ƃɂǂ��������������A���������̌i�F��傫���y���ނ��Ƃ��ł��܂���B���̊O�ɂ͉����ɕ������������ԎR�A�߂��ɂ͐F�Â����сA���̒��Ԃ̎Ζʂɂ͉��t�����X�̏d�Ȃ�ƁA�Ȃ��Ȃ��̌i�F�Ȃ̂ł����E�E�E�B�`�����݂܂���������܂���B���̃z�e���͍����z�e���ł͂Ȃ����A�����Ȃǂ͑債�����Ƃ͂Ȃ����낤�Ǝv���Ă����̂ł����A�L�����A�����̒�������Ȃ���Y��ɐ������Ă��āA�j�]�͌����Ă��܂���B�L���ɏ����Ă����g�t�̑��Ԃ͂��������܂��A�S�̓I�Ɉ����͂Ȃ��Ǝv���܂����B |
 �����C�̓G���x�[�^�[�Œn���܂ō~��܂��B�������n�����ł͂Ȃ��A�ΖʂȂ̂ł��̂悤�ȊK�\���ɂȂ�悤�ł��B�j�����͂Ȃ��Q�S���ԓ���܂��B������߂��ɗ␅�@���ݒu����Ă��܂����B�嗁�ꂩ��I�V�ɏo��^�C�v�ŁA�嗁��͂P�O�l���炢�̍L���ł��傤���B��͂V�������炢�������Ǝv���܂��B�������̂���嗁��ł����A����قǓ���������킯�ł͂���܂���B�I�V�͂��������L�߂̊╗�C�ł��B�㉺��i�ɕ�����Ă��āA��̂ق��͉���������A���̂ق��͉�������Ă���`�ł��B�ォ�������������������̂����������ŗ���o���Ă��āA���̐������Ƃǂ��l���Ă��z���ȂƎv�킹�܂��B���ɁA���̘I�V�ʼn��C�Ȃ��A�����~�낵����u�M�����I�I�v���K�����j��ꖂ�ꂽ���Ǝv���܂����B���̂������z�����݂ł��B�����A���f�L�͑S�����܂���B��̘I�V����͉��̘I�V�ւƂ��������ꍞ��ł��܂��B��ɂ͋z���������Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA�ゾ���͗����肩�Ǝv���܂������A�ǂ��������̏o�����l���Ă����̂������܂���ɗg���Ă���C�����܂��B�����A�������ʂ�ʂ邵�������͏\���ɂ���܂��B�����̌���͂Q�U�x�Ƃ������Ƃł��̂ʼn��M�����Ă���킯�ł��B���M�����Ă��邨���C�̏ꍇ�A�钆�̂P�Q���܂łȂǂƂ����悤�ɁA���Ԑ���������Ƃ��낪�����̂ł����A�����͂��̍L���I�V�̓��D�ɂQ�S���ԓ����킯�ł��B�Ȃ��Ȃ����ȂƊ����܂����B�I�V�̌i�F�͕����ƑS�������ŁA��ԎR�A���t�̎ΖʁA�߂��̗тƁu���A���A�߁v�̌i�F��������������Ȃ��̂ł��B�w���Ƀz�e���̌���������܂��̂ŁA���E�͂P�W�O���ł����A�\���J����������܂��B���̓��͓܂��Ă��Ă��߂ł������A���ꂽ��́A���̘I�V�Ő�������i�ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �����C�̓G���x�[�^�[�Œn���܂ō~��܂��B�������n�����ł͂Ȃ��A�ΖʂȂ̂ł��̂悤�ȊK�\���ɂȂ�悤�ł��B�j�����͂Ȃ��Q�S���ԓ���܂��B������߂��ɗ␅�@���ݒu����Ă��܂����B�嗁�ꂩ��I�V�ɏo��^�C�v�ŁA�嗁��͂P�O�l���炢�̍L���ł��傤���B��͂V�������炢�������Ǝv���܂��B�������̂���嗁��ł����A����قǓ���������킯�ł͂���܂���B�I�V�͂��������L�߂̊╗�C�ł��B�㉺��i�ɕ�����Ă��āA��̂ق��͉���������A���̂ق��͉�������Ă���`�ł��B�ォ�������������������̂����������ŗ���o���Ă��āA���̐������Ƃǂ��l���Ă��z���ȂƎv�킹�܂��B���ɁA���̘I�V�ʼn��C�Ȃ��A�����~�낵����u�M�����I�I�v���K�����j��ꖂ�ꂽ���Ǝv���܂����B���̂������z�����݂ł��B�����A���f�L�͑S�����܂���B��̘I�V����͉��̘I�V�ւƂ��������ꍞ��ł��܂��B��ɂ͋z���������Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA�ゾ���͗����肩�Ǝv���܂������A�ǂ��������̏o�����l���Ă����̂������܂���ɗg���Ă���C�����܂��B�����A�������ʂ�ʂ邵�������͏\���ɂ���܂��B�����̌���͂Q�U�x�Ƃ������Ƃł��̂ʼn��M�����Ă���킯�ł��B���M�����Ă��邨���C�̏ꍇ�A�钆�̂P�Q���܂łȂǂƂ����悤�ɁA���Ԑ���������Ƃ��낪�����̂ł����A�����͂��̍L���I�V�̓��D�ɂQ�S���ԓ����킯�ł��B�Ȃ��Ȃ����ȂƊ����܂����B�I�V�̌i�F�͕����ƑS�������ŁA��ԎR�A���t�̎ΖʁA�߂��̗тƁu���A���A�߁v�̌i�F��������������Ȃ��̂ł��B�w���Ƀz�e���̌���������܂��̂ŁA���E�͂P�W�O���ł����A�\���J����������܂��B���̓��͓܂��Ă��Ă��߂ł������A���ꂽ��́A���̘I�V�Ő�������i�ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |
 �H���̓��X�g�����łU������Ǝw�肳��܂��B���ԏ����O�ɍs���Č���ƁA��������̂��q�����݂Ȃ��ɂ��낤�낵�Ă��܂��B�ǂ����U���҂�����ɊJ�������炵���A������Ƀ��[�v�������Ă��āA�W���̎p���܂���������܂���B���q�����܂��āA�������C�w���s�̒c�̂̂悤�ȋC���ɂȂ�܂����B���ԂɂȂ�A�ē����ꂽ�e�[�u���͈�i�����������ۂ̂����Ȃł������A��Ȃ̂ŊO�̌i�F���܂�����������܂���ł����B���Ƀ��C�g�A�b�v����Ă����ł�����܂���B�e�[�u���ɂ͂��łɗ������u����Ă��āA��͂�g���������łɂ���܂����B�������茩���ɗ₦���Ă��܂��B�����A�Ƃ�뒃�ЁA���q�i��ȂǗ₦�Ă��Ă������������������A�g�����Ă������炩�Ȃ肢�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B���i�����͂���܂������A���ɐ����͂���܂���B���C���͋e�ؓ�Ƃ����C�N��̂悤�Ȃ��̂ŁA�傫�ȐH�p�e�������Ă��܂��B������āA�H�p�H���Ă����قǂ̑傫���ł������A��͂�H�ׂĂ݂�Ɩ�L���A�H�ׂȂ���悩�����ƌ�����܂����B�ł��A�H�ׂ��ɂ͂����Ȃ����i�ł��ˁB�H�O���͔~���ŁA�h�g���܂��܂��ł��B�m�M�ɐ��n�������T���_������A���̐��n���͔��ɂ����������̂ł����B���т₨�o�A�f�U�[�g�ȊO�ł́A�R���̉��Ă������͌ォ��o���ꂽ�̂ł����A�����ł͂Ȃ��A�����Ȃ��Ă��܂����B�R���͍ŏ�������̓�����߂��Ɏh����Ēu����Ă��āA���̎����łɉ͏����Ă����悤�ȋC�����܂��B�ł��A�����̋ꖡ�ȂǁA���������R���ł����B���̑��ɂ͑O��ϕ��ȂǁA�S�̓I�ɖ��͗ǂ������Ǝv���܂��B�f�U�[�g�͂Ԃǂ����[�X�ł���������������̂ł����B���H�͓������Ńo�C�L���O�ɂȂ�܂��B��ނ͈�ʓI���A��⏭�Ȃ߂Ƃ����Ƃ���ł��傤���B�W���[�X�̓I�����W�����Ȃ��A�M�B�̂���Ȃ��̂��s���ł����B�S�̓I�Ƀo�C�L���O�̑f�ނ□�͂��������܂���B���炷���낵�͌ł��A���Z�������Ⴋ���Ⴋ���Ă�Ƃ��������A�����ł������Ƃ�����ۂł��B�����ɑS�̓I�ɍ���ł����B��ƒ��Ƃł͂ǂ����Ĉ���Ă��܂��̂ł��傤���B�R�[�q�[�܂ō���ł����B���̃z�e���̓��s�[�^�[�����ɑ����悤�ł��B������A�N�z�̐l�������̂������̂悤�Ɏv���܂����B�ŏ��̑��}�o�X�̒��◷�قɒ������Ƃ��Ȃǂ́A���ׂĂڂ����N��̐l����ł����B�Ȃ��A�N�z�̐l�������̂�������܂��A���͂̌i�F���������ƁA����������قǍ����͂Ȃ����ƁA����Ȃ�ɂ����ꂢ�Ȃ��ƁA�I�V�̌i�F���������ƂȂǂ����R�ł͂Ȃ��ł��傤���B�[�H���������o�Ă�����Ȃ薞���ł���悤�Ɏv���܂��B�����A���H�̃o�C�L���O�̖��͂ǂ��ɂ����Ăق��������ł��B �H���̓��X�g�����łU������Ǝw�肳��܂��B���ԏ����O�ɍs���Č���ƁA��������̂��q�����݂Ȃ��ɂ��낤�낵�Ă��܂��B�ǂ����U���҂�����ɊJ�������炵���A������Ƀ��[�v�������Ă��āA�W���̎p���܂���������܂���B���q�����܂��āA�������C�w���s�̒c�̂̂悤�ȋC���ɂȂ�܂����B���ԂɂȂ�A�ē����ꂽ�e�[�u���͈�i�����������ۂ̂����Ȃł������A��Ȃ̂ŊO�̌i�F���܂�����������܂���ł����B���Ƀ��C�g�A�b�v����Ă����ł�����܂���B�e�[�u���ɂ͂��łɗ������u����Ă��āA��͂�g���������łɂ���܂����B�������茩���ɗ₦���Ă��܂��B�����A�Ƃ�뒃�ЁA���q�i��ȂǗ₦�Ă��Ă������������������A�g�����Ă������炩�Ȃ肢�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B���i�����͂���܂������A���ɐ����͂���܂���B���C���͋e�ؓ�Ƃ����C�N��̂悤�Ȃ��̂ŁA�傫�ȐH�p�e�������Ă��܂��B������āA�H�p�H���Ă����قǂ̑傫���ł������A��͂�H�ׂĂ݂�Ɩ�L���A�H�ׂȂ���悩�����ƌ�����܂����B�ł��A�H�ׂ��ɂ͂����Ȃ����i�ł��ˁB�H�O���͔~���ŁA�h�g���܂��܂��ł��B�m�M�ɐ��n�������T���_������A���̐��n���͔��ɂ����������̂ł����B���т₨�o�A�f�U�[�g�ȊO�ł́A�R���̉��Ă������͌ォ��o���ꂽ�̂ł����A�����ł͂Ȃ��A�����Ȃ��Ă��܂����B�R���͍ŏ�������̓�����߂��Ɏh����Ēu����Ă��āA���̎����łɉ͏����Ă����悤�ȋC�����܂��B�ł��A�����̋ꖡ�ȂǁA���������R���ł����B���̑��ɂ͑O��ϕ��ȂǁA�S�̓I�ɖ��͗ǂ������Ǝv���܂��B�f�U�[�g�͂Ԃǂ����[�X�ł���������������̂ł����B���H�͓������Ńo�C�L���O�ɂȂ�܂��B��ނ͈�ʓI���A��⏭�Ȃ߂Ƃ����Ƃ���ł��傤���B�W���[�X�̓I�����W�����Ȃ��A�M�B�̂���Ȃ��̂��s���ł����B�S�̓I�Ƀo�C�L���O�̑f�ނ□�͂��������܂���B���炷���낵�͌ł��A���Z�������Ⴋ���Ⴋ���Ă�Ƃ��������A�����ł������Ƃ�����ۂł��B�����ɑS�̓I�ɍ���ł����B��ƒ��Ƃł͂ǂ����Ĉ���Ă��܂��̂ł��傤���B�R�[�q�[�܂ō���ł����B���̃z�e���̓��s�[�^�[�����ɑ����悤�ł��B������A�N�z�̐l�������̂������̂悤�Ɏv���܂����B�ŏ��̑��}�o�X�̒��◷�قɒ������Ƃ��Ȃǂ́A���ׂĂڂ����N��̐l����ł����B�Ȃ��A�N�z�̐l�������̂�������܂��A���͂̌i�F���������ƁA����������قǍ����͂Ȃ����ƁA����Ȃ�ɂ����ꂢ�Ȃ��ƁA�I�V�̌i�F���������ƂȂǂ����R�ł͂Ȃ��ł��傤���B�[�H���������o�Ă�����Ȃ薞���ł���悤�Ɏv���܂��B�����A���H�̃o�C�L���O�̖��͂ǂ��ɂ����Ăق��������ł��B |
| �@ |
| ����ڂ͏�c�ɂ��ǂ�A���x�̓o�X�Ŏ���������܂Ō������܂��B�ꎞ�Ԉȏォ�����Ď��������Ƃ����o�X��ō~��܂����B�������̏h�́u�O���فv�Ƃ����h�ł��B�o�X�₩��̍s�������ǂ�������Ȃ��̂Ōg�тœd�b������A�Ă��˂��ɋ����Ă���܂������A�}���ɍs���Ƃ������t�͂���܂���ł����B�����͂W�����̏h�ŁA���}����ɂ͐l��ɗ]�T���Ȃ��̂��Ǝv���܂��B�������̗��يX����͏������ꂽ��Ԓ[�Ɉʒu����Ƃ���ɂ���܂��B��ŕ������Ƃ���ɂ��ƁA���Ƃ��Ƃ͗��يX�̂Ƃ���ɂ������̂��A�����ɓy�n���w�����A��N�O�ɂ����ł���l����肽���h���n�߂��Ƃ������Ƃł����B����ɉƂ̂Ȃ���������Ă����ƁA�E��̏������Ƃ���ɓ�K���Ă̌����������Ă��܂��B�N���[���F�̊O�ς͂ӂ��̉Ƃ̂悤�ŁA���܂藷�قƂ������������܂���B�O���ʂ�A���ւ��J����ƁA�y�Ԃ̂悤�ȂƂ��낪����A�����Ƀt�����g������܂��B����Ɍ˂��J���Ď����ɓ���Ƃ����`�ł��B��������ו���a���Ă܂��������̗��يX�����������A���ǂ����̂��R��������ƑO�ł����B�C���̎��Ԃ��Q���ł��̂ŁA�����ɕ����ֈē����Ă��炦�܂��B�ٓ��͑S�̓I�ɏł�������Ƃ����a�߂̗�����������ۂŁA���͔���ł��B���g�[���قǂ�����A�X���b�p�͂���܂���B���̑��蕔���ɂ͑��܌C�����p�ӂ���Ă��܂��B���ւ��オ�����K�i�̂Ƃ��낪���������ɂȂ��Ă��āA��K�͂��̎l�p�����������̋�Ԃ��͂�ŕ������z�u����Ă��܂��B���������̏ォ��͌�����������ł����L��������܂��B�ʂ��ꂽ�̂́A���������������Ɖ������K�̈�Ԓ[�A�u�ה��v�Ƃ��������ł����B���߂̋C�Â���������A�����Ă������o����A�}���َq�������Ă��Ă���܂����B�v���[���W�������g�����葢��̃p�C�Ƃ������ƂŁA�����������̂ł��B�����́A�ٓ��Ɠ����悤�ɏł�������Ƃ��Ă��āA���������Ă��܂��B�V���|���̑���Ƃ����������ŁA�����ɂ������ɍD�܂ꂻ���ȕ��͋C�ł��B�h�A���J���A�̊Ԃ̓��ݍ��݂��オ��ƁA����ɊȒP�Ȑ����A���ׂ̗����ʏ��ƂȂ��Ă��āA�˂������肪�g�C���ł����B�����ɂ͂��łɗ␅���p�ӂ���Ă��܂��B�g�C���ɂ͑�������A�������V�����[�g�C���ł��B�①�ɂ͐\�����ŁA���Ƌ�Ԃ͑��������Ǝv���܂��B�E��̂ӂ��܂��J����ƁA�W��̘a���ŁA�L����֎q�͂���܂���B�����ɂ͉��炵���ȉ~�`�������e�[�u�����u����A�悭����ǂ�����Ƃ����e�[�u���͂���܂���B�H���͐H�����ł��̂ŁA�l���Ă݂�Α傫�ȃe�[�u���͕K�v�Ȃ��̂ł��ˁB�E��ɂ͈�����̏��̊ԂɉԂ��������A���Α��̉�����Ƀe���r��������Ă��܂��B�ז��Ȑl�͂ӂ��܂�߂�e���r�����E����������Ƃ��ł��܂��B�e���r���̃R�s�[���u���ĂȂ��āA���̏h�ł͂��������e���r�͑j�Q����Ă���悤�ł��B�������A�e���r���̂͑傫���ė��h�Ȃ��̂ł��B���̏�q���J����ƁA�T�b�V�ł͂Ȃ��Ԍ˂������Ă��܂��B�V��ɂ͂悵���̂悤�Ȃ��̂������Ă��āA�����ɂ͑���������肪����悤�Ɍ����܂����B�����Ŋm�F�����킯�ł͂Ȃ��̂ł����A���̂��q����̉�b��R�ꕷ���Ƃ���ɂ��ƁA�������ƂɈӏ����������Ƃ������Ƃł����B���̕����͂��傤�nj��ւ̏�̕��Ɉʒu���Ă��đ�����͂��̏h�Ɍ������q�̎p��A������ߕӂɐA�����Ă��傤�nj�������}�����g�t�̖X�������낹�܂��B�ڂ̑O�͏������u�ł����̖X�����ʂɌ����܂��B���ɋ߂Â��ƊO�̐l�Ɩڂ������Ă��܂��܂����A�����Δ`�����݂͂���܂���B |
 �����C�͐�p�̗�������Ă��Ă��āA�{�ق���O�ɏo�ĕ����čs���܂��B�ƌ����Ă��A�߂��āA�ق�̂P�T���[�g�����炢�ł��傤���B�O�C�ɂ͐G��܂����A�����͂���܂��B�j���͖�̂W���Ɍ�ւ��A�`�F�b�N�A�E�g�܂ł��̂܂܂ŁA�Q�S���ԓ����\�ł��B���߂̒j���p�͉��̕��̗���ŁA�����ؘ͖g�̗����A��������o�čs���`�̘I�V�͐Α���̉~�`�̂��̂ł��B�����͓�������̖{�i�I�Ȃ��̂ŁA���C�Ȃǂ������邱�ƂȂ����K�ł����A�����A�I�V�Ƃ���⏬���߂ł��B�����̓��D�͂R�A�S�l�A�I�V���R�l���x�ł͂Ȃ��ł��傤���B��͂S��������܂���B�S���łW�����ł��̂ŁA���Ԃ���������Ȃ������ŏ\���Ȃ̂ł��傤���A�����͏����D�݂̏h�Ȃ̂ŏ����̃O���[�v�������A�l���̑����O���[�v�̏ꍇ���ƁA���̃O���[�v�����ł��I�V�ɂ͓��肫��Ȃ��ɂȂ��Ă��܂��܂��B����ɁA���̃O���[�v�Ǝ��Ԃ������������肵�Ă��܂��ƁA���Ȃ�s�����o��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ӊO�Ǝ��Ԃ������������Ƃ͑����悤�ŁA�����ׂœԋ߂������Ă���Ԃ��A�ƂĂ��ɂ��₩�Ȏ��Ƃ܂������Â��Ȏ��Ƃ��ɒ[�ɕ�����Ă��܂����B�ŏ��j���p�̘I�V�͎����O��̈͂��Ɉ͂܂�Ă��܂����A���͂ɂ��]�T������A�����ɐA����ꂽ�g�t�������ɐF�Â��Ă��Ă̂�т�ł��܂����B�I�V�ɉ������Ȃ��A�J�̎��ɂ͓���ɂ������ł����A���̕��J�����͂���܂��B��サ�����̂����C�͓������Α���A�I�V���ؘg�ƁA�t�̍\���ɂȂ��Ă��܂��B���������̑傫���͂���قǕς��Ȃ��Ǝv���܂����A�I�V�͓��D�̏�ɑ������ʂ���Ă��邱�Ƃ�����A�����炭����������l��������Ȃ��Ǝv���܂��B����ɁA�ׂ̍g�t�ƈ���āA������͑����ڗ����A�������쓒�ɓ����Ă���C���ɂȂ�܂��i�����Ӗ��ł͂Ȃ��āj�B�����͓����͓�������A�Α���̘I�V�͓��D�̒����瑽��������Ă��܂����A���̂����͖������L�Ƃ��������ł��B���f�L�͂܂��������Ȃ��̂ŁA���ꂾ�����Ǝ������̂����͂���Ȋ����Ȃ̂��Ǝv���čς�ł��܂������ł��B�����A���������̗��ق̗ǐS�Ȃ̂ł��傤���A�I�V�Ɉ�{��������낿���ƒ|���Œ�����Ă��邨��������̂ł��B���̂����͏��ʂŁA�������ʂ邢�̂ł����A�������Ȃ��܂��L�����āA�͂́`���ꂪ�{���̎������̂����ȂƋ����Ă���܂��B�܂�A���̓����̂����͉��M�E�z�Ƃ������Ƃł��ˁB�ؘg�̘I�V�ɓ����Ă���ƃ{�C���[�̉����������Ă��܂����B�������̂����͂����Ƃ������Ƃł�����A���̂����Ɋւ��Ă͉��Ƃ��c�O�ȋC�����܂����B�����͑g�����Ǘ����Ă���Ƃ������Ƃł����A�V���������������ċ����ʂ����Ȃ��̂ł��傤���B �����C�͐�p�̗�������Ă��Ă��āA�{�ق���O�ɏo�ĕ����čs���܂��B�ƌ����Ă��A�߂��āA�ق�̂P�T���[�g�����炢�ł��傤���B�O�C�ɂ͐G��܂����A�����͂���܂��B�j���͖�̂W���Ɍ�ւ��A�`�F�b�N�A�E�g�܂ł��̂܂܂ŁA�Q�S���ԓ����\�ł��B���߂̒j���p�͉��̕��̗���ŁA�����ؘ͖g�̗����A��������o�čs���`�̘I�V�͐Α���̉~�`�̂��̂ł��B�����͓�������̖{�i�I�Ȃ��̂ŁA���C�Ȃǂ������邱�ƂȂ����K�ł����A�����A�I�V�Ƃ���⏬���߂ł��B�����̓��D�͂R�A�S�l�A�I�V���R�l���x�ł͂Ȃ��ł��傤���B��͂S��������܂���B�S���łW�����ł��̂ŁA���Ԃ���������Ȃ������ŏ\���Ȃ̂ł��傤���A�����͏����D�݂̏h�Ȃ̂ŏ����̃O���[�v�������A�l���̑����O���[�v�̏ꍇ���ƁA���̃O���[�v�����ł��I�V�ɂ͓��肫��Ȃ��ɂȂ��Ă��܂��܂��B����ɁA���̃O���[�v�Ǝ��Ԃ������������肵�Ă��܂��ƁA���Ȃ�s�����o��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ӊO�Ǝ��Ԃ������������Ƃ͑����悤�ŁA�����ׂœԋ߂������Ă���Ԃ��A�ƂĂ��ɂ��₩�Ȏ��Ƃ܂������Â��Ȏ��Ƃ��ɒ[�ɕ�����Ă��܂����B�ŏ��j���p�̘I�V�͎����O��̈͂��Ɉ͂܂�Ă��܂����A���͂ɂ��]�T������A�����ɐA����ꂽ�g�t�������ɐF�Â��Ă��Ă̂�т�ł��܂����B�I�V�ɉ������Ȃ��A�J�̎��ɂ͓���ɂ������ł����A���̕��J�����͂���܂��B��サ�����̂����C�͓������Α���A�I�V���ؘg�ƁA�t�̍\���ɂȂ��Ă��܂��B���������̑傫���͂���قǕς��Ȃ��Ǝv���܂����A�I�V�͓��D�̏�ɑ������ʂ���Ă��邱�Ƃ�����A�����炭����������l��������Ȃ��Ǝv���܂��B����ɁA�ׂ̍g�t�ƈ���āA������͑����ڗ����A�������쓒�ɓ����Ă���C���ɂȂ�܂��i�����Ӗ��ł͂Ȃ��āj�B�����͓����͓�������A�Α���̘I�V�͓��D�̒����瑽��������Ă��܂����A���̂����͖������L�Ƃ��������ł��B���f�L�͂܂��������Ȃ��̂ŁA���ꂾ�����Ǝ������̂����͂���Ȋ����Ȃ̂��Ǝv���čς�ł��܂������ł��B�����A���������̗��ق̗ǐS�Ȃ̂ł��傤���A�I�V�Ɉ�{��������낿���ƒ|���Œ�����Ă��邨��������̂ł��B���̂����͏��ʂŁA�������ʂ邢�̂ł����A�������Ȃ��܂��L�����āA�͂́`���ꂪ�{���̎������̂����ȂƋ����Ă���܂��B�܂�A���̓����̂����͉��M�E�z�Ƃ������Ƃł��ˁB�ؘg�̘I�V�ɓ����Ă���ƃ{�C���[�̉����������Ă��܂����B�������̂����͂����Ƃ������Ƃł�����A���̂����Ɋւ��Ă͉��Ƃ��c�O�ȋC�����܂����B�����͑g�����Ǘ����Ă���Ƃ������Ƃł����A�V���������������ċ����ʂ����Ȃ��̂ł��傤���B |
 �H���͂U���ȍ~�ŗp�ӂ��o������A�����Ă����Ƃ������Ƃł����B�H���͐H�����ŁA������Ƌ��ꂽ�Ƃ��������܂����A��̈�̕����Ƃ��������������Ǝv���܂��B�e�[�u���ɂ͐�t�̗����Ƃ��̂��̎ϕ��A�O�؎���A���C���̂��̂���̑��Ƌ�u����Ă��܂��B���i�����͂Ȃ��A���߂ɒu����Ă�����̂Ɋւ��Ă͐���������܂���B�O�͍ג�����M�Ɏ��퐷���Ă��Ă�������M�Ɏ�蕪����`�ŁA���܈��A���Ă��A�{���A���Ȃǂ��ꂼ�ꂨ�������A�y�����H�ׂ��܂����B�����̗����͂���l�≜��������߁A�]�ƈ��ō���Ă���Ƃ������Ƃł����B�܂��Ɏ葢��̖��̑O�ł����B�h�g�͋��h���Ŕ��ɂ����������̂ł��B�𒆐S�Ƃ����|�̕��ƌI������A�T���_�Ȃǂ��o����Ă��邤���ɁA���C���̂��̂���ɉ��ʂ��Ă��܂��B���̂��̂���̃{�����[���͂��Ȃ肠��܂��B���͌{���ƌ{���̃~���`����ɂ��̂���������܂��B���̂��ɂ͎c�O�Ȃ��珼���͂���܂���ł������A���Ȃ�̎�ށA����������Ə\��ނ��炢�͓����Ă�����������܂���B�Ƃɂ����������ӂ�銴���łƂĂ������������̂ł��B�Ō�͂��̏`��������ɂ��ĐH�ׂ�̂ł����A����͂��܂���ꂽ���Ƃ������āA���ɂ�������������ł����B������̎��Ɏ����Ă��Ă��ꂽ���̕���������ɂ悭���������̂ł����B�ق��̗����ɂ����̂��������g���Ă������Ƃ�����A���̂��̍D���Ȑl�ɂ͂��܂�Ȃ��H���ł��傤�B�����A�t�Ɍ����ƁA�����Ȑl�ɂƂ��Ă͍ň��̐H���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���H�ׂĂ���Ԃɂ��⋛�̉��Ă��������Ă��Ă���܂����B�{���ɏĂ����ĂŁA�M�X�̂����������̂ł������A���������������C�����܂����B�f�U�[�g�͏ꏊ��ւ��A������n���郍�r�[�̈֎q�łԂǂ��[���[�����������܂����B���̂Ԃǂ��[���[���\�������ł�����̂ł����B���H�͂W������A�����ꏊ�A�����Ȃł��B�S�̓I�ɔ��ɃV���v���ŁA��������Ƃ��킵�i�H�j�̊ۊ����A���A�Ђ����A���Z���A���炷���낵�A���̕��A����ɂ��тƖ��X�`�����ł��B�f�U�[�g�Ɋ`�Ƃ����ꂸ�t���܂������A������Ȃ��C�����܂����B������Ƃ������̂ō\��Ȃ��̂ŁA���Ɠ�i���炢�~���������ł��B�������A�ǂ�������������̂ŁA�o���ꂽ���̖̂��Ɋւ��Ă͕���̂��悤������܂���B�H��͂܂����r�[�ŁA�Z���t�T�[�r�X�ł����A�R�[�q�[�����ނ��Ƃ��ł��܂��B�`�F�b�N�A�E�g�̎��ɂ���l�Ə����b�����܂����B���₩�����Ȋ����̐l�ōD��ۂ������܂����B�h�Ƃ������̂ɑ���ӎ��͍����Ɗ����܂����B����������̂���l����������x���Ă���Ƃ��������ł��B�����Ɋւ��Ă͏������悤�ɂ܂��܂����_������A����͉��P���e�Ղł͂Ȃ��Ǝv���̂ł����A���Ƃ��ǂ��Ȃ�Ƃ����ȂƎv���܂��B�H���Ɋւ��ẮA����͂��̂���̈�ۂ��������āA���̗���������ł��܂��������ł��B�G�߂��ς��Ƃǂ��Ȃ�̂��A����������܂��B�܂��A���̂悤�Ɉ�̗����̔�d�������Ȃ�̂ł��傤���B������������A����������d�������āA������i����Ƃ������̂���������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�Ƃɂ������̏h�����s�[�^�[�������A���ɂT���Ƀe���r�ɏo�Ă���͖����̓��������Ă���悤�ł��B����������قǍ����͂Ȃ��A�����ȂǁA�����ɍD�܂��v�f���\���Ɏ������h�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B �H���͂U���ȍ~�ŗp�ӂ��o������A�����Ă����Ƃ������Ƃł����B�H���͐H�����ŁA������Ƌ��ꂽ�Ƃ��������܂����A��̈�̕����Ƃ��������������Ǝv���܂��B�e�[�u���ɂ͐�t�̗����Ƃ��̂��̎ϕ��A�O�؎���A���C���̂��̂���̑��Ƌ�u����Ă��܂��B���i�����͂Ȃ��A���߂ɒu����Ă�����̂Ɋւ��Ă͐���������܂���B�O�͍ג�����M�Ɏ��퐷���Ă��Ă�������M�Ɏ�蕪����`�ŁA���܈��A���Ă��A�{���A���Ȃǂ��ꂼ�ꂨ�������A�y�����H�ׂ��܂����B�����̗����͂���l�≜��������߁A�]�ƈ��ō���Ă���Ƃ������Ƃł����B�܂��Ɏ葢��̖��̑O�ł����B�h�g�͋��h���Ŕ��ɂ����������̂ł��B�𒆐S�Ƃ����|�̕��ƌI������A�T���_�Ȃǂ��o����Ă��邤���ɁA���C���̂��̂���ɉ��ʂ��Ă��܂��B���̂��̂���̃{�����[���͂��Ȃ肠��܂��B���͌{���ƌ{���̃~���`����ɂ��̂���������܂��B���̂��ɂ͎c�O�Ȃ��珼���͂���܂���ł������A���Ȃ�̎�ށA����������Ə\��ނ��炢�͓����Ă�����������܂���B�Ƃɂ����������ӂ�銴���łƂĂ������������̂ł��B�Ō�͂��̏`��������ɂ��ĐH�ׂ�̂ł����A����͂��܂���ꂽ���Ƃ������āA���ɂ�������������ł����B������̎��Ɏ����Ă��Ă��ꂽ���̕���������ɂ悭���������̂ł����B�ق��̗����ɂ����̂��������g���Ă������Ƃ�����A���̂��̍D���Ȑl�ɂ͂��܂�Ȃ��H���ł��傤�B�����A�t�Ɍ����ƁA�����Ȑl�ɂƂ��Ă͍ň��̐H���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���H�ׂĂ���Ԃɂ��⋛�̉��Ă��������Ă��Ă���܂����B�{���ɏĂ����ĂŁA�M�X�̂����������̂ł������A���������������C�����܂����B�f�U�[�g�͏ꏊ��ւ��A������n���郍�r�[�̈֎q�łԂǂ��[���[�����������܂����B���̂Ԃǂ��[���[���\�������ł�����̂ł����B���H�͂W������A�����ꏊ�A�����Ȃł��B�S�̓I�ɔ��ɃV���v���ŁA��������Ƃ��킵�i�H�j�̊ۊ����A���A�Ђ����A���Z���A���炷���낵�A���̕��A����ɂ��тƖ��X�`�����ł��B�f�U�[�g�Ɋ`�Ƃ����ꂸ�t���܂������A������Ȃ��C�����܂����B������Ƃ������̂ō\��Ȃ��̂ŁA���Ɠ�i���炢�~���������ł��B�������A�ǂ�������������̂ŁA�o���ꂽ���̖̂��Ɋւ��Ă͕���̂��悤������܂���B�H��͂܂����r�[�ŁA�Z���t�T�[�r�X�ł����A�R�[�q�[�����ނ��Ƃ��ł��܂��B�`�F�b�N�A�E�g�̎��ɂ���l�Ə����b�����܂����B���₩�����Ȋ����̐l�ōD��ۂ������܂����B�h�Ƃ������̂ɑ���ӎ��͍����Ɗ����܂����B����������̂���l����������x���Ă���Ƃ��������ł��B�����Ɋւ��Ă͏������悤�ɂ܂��܂����_������A����͉��P���e�Ղł͂Ȃ��Ǝv���̂ł����A���Ƃ��ǂ��Ȃ�Ƃ����ȂƎv���܂��B�H���Ɋւ��ẮA����͂��̂���̈�ۂ��������āA���̗���������ł��܂��������ł��B�G�߂��ς��Ƃǂ��Ȃ�̂��A����������܂��B�܂��A���̂悤�Ɉ�̗����̔�d�������Ȃ�̂ł��傤���B������������A����������d�������āA������i����Ƃ������̂���������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�Ƃɂ������̏h�����s�[�^�[�������A���ɂT���Ƀe���r�ɏo�Ă���͖����̓��������Ă���悤�ł��B����������قǍ����͂Ȃ��A�����ȂǁA�����ɍD�܂��v�f���\���Ɏ������h�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B |
| �@ |
| �O���ڂ͕ʏ�����ł��B����������o�X�ŏ�c�ɖ߂��c����܂��ʏ����ŕʏ�����ւƂ����s�������Ǝ��Ԃ̃��X�Ȃ̂ŁA�^�N�V�[�Ō������܂����B�Ԃ��ƂR�O�����x�ł��Ă��܂��܂��B�ʏ��̏h���ꏊ�u�����̓��v�ɕt�����̂͂P�P��������ł����B�u�����̓��v�́A�k���ω��̊K�i���~��Ă��āA����X��˂���A�ق�̏����������A�ʏ�����̒��S���Ƃ����ׂ��Ƃ���Ɉʒu���Ă��܂��B����ɐi�߂A����̔��p�O�d���ŗL���Ȉ��y���ւƒʂ��܂��B���̂悤�Ɋό��ɕ֗��ȂƂ���Ȃ̂ŁA�����̓��ɉו���a���āA�܂��ό��Ƃ����킯�ł��B����X�Ɉʒu���Ă��܂��̂ŁA�ꉞ���ւ֓��邽�߂̒ʘH�̂悤�Ȃ��̂͂���܂����A�O��Ȃǂ͂܂���������܂���B���̂�����͓����ʏ��ł��ȑO�h�������ԉ��ȂǂƂ͑傫���Ⴄ�Ƃ���ł��B���ւ��J����ƁA�O���قƂ͑ΏƓI�Ȗ��邭�₩�Ȋ����̏��~���̃t���A���L�����Ă��܂����B�a���𒅂��������߂Â��Ă����̂ŁA�����h����������̂����A�ו���a�����ė~�����|��������ƁA�܂��A�R�[�q�[�ł��ǂ����ƁA���֘e�̃e�[�u���Ɉē����A�����Ղ�Ɨʂ̂��邨�������R�[�q�[��Ă���܂����B���̎����A���������Ă������ȂƎv�����̂ł����A��ł�͂肱�̐l���������ƕ�����܂����B�܂��O�\��Ƃ��������̎Ⴂ�l�ł������A�Ꮧ���ł͂Ȃ��A������Ƃ��������������ł��B�R�[�q�[�����ނ����ɁA���x�͎Ⴂ�����̏]�ƈ����A���ӂ̊ό��n�}�������Ă��āA�ʏ��̌����A���������H���ǂ���̉������������Ă���܂����B�������͂����ו���a���邾���̂���ŁA�n�}�����炤�̂��Y���Ƃ��낾�����̂ŁA���肵�ċC�������Ă����Ή��ɏ�����܂����B�M�B�̊��q�ƌĂ��ʏ��̊ό��ꏊ�͊��Ə�����܂�܂Ƃ܂��Ă���̂ł����A������茩�ĉ�����̂ŏh�ɖ߂����̂͂Q�������O�ł����B�����ł͂܂����r�[�ɂ���J�E���^�[�ŁA�}���َq�Ƃ����̂��ĂȂ�����Ƃ����`�ɂȂ��Ă��܂��B�}���َq�͂����̃p�C�Ɣ~�̃V���b�v�Ђ��i�H�j�ŁA���̂����̃p�C�͂����������̂ł����B�����ŋL�������܂��A�H�I������畔���ֈē����Ă��炢�܂��B�ٓ��̓G���x�[�^�[�̒����܂߂đS�ُ��~���ŁA��͂�X���b�p�͂Ȃ��ł��B�����ɂ͎O���قƓ����悤�ɑ��܌C�����p�ӂ���Ă��܂����B���́u�����̓��v�͎l�N�O�ɑS�ى��z���ĐV���������炵���A����܂ł́u�e�̓��v�Ƃ��������ȏh�����������ł��B���܂͂U�K���Ă̗��h�Ȍ����ɂȂ��Ă��܂����A�������͑S���łP�V���Ə��Ȃ߂ł��B�����A�`�F�b�N�C���������͂Ȃ����t�����g�S�̂��Z�������ŁA��u�A���K�͗��ق��������Ǝv���܂����B���̓��͖l�̗\�Ō�̋q���ŁA�\���͓̂����炢�O�������̂ő����Ȑl�C�ȂȂƎv���܂����B���傤�Ǎg�t�A�����̎������������炩������܂���B�U�K�̍ŏ�K���嗁��ɂȂ��Ă��āA�����͈ꕔ�����邾���ŁA�قƂ�ǂ̋q���͂T�K����ɂȂ�܂��B�ڂ����ʂ��ꂽ�̂͂S�K�̒[�̕����ł����B���L����ʂ�A�h�A���J����ƈ����̓��ݍ��݂�����A���ݍ��݂��オ���č�����Ƀo�X�E�g�C���E���ʂ��܂Ƃ܂��Ă���܂��B�o�X�͂�⋷�ڂ̃��j�b�g�A�g�C���͂��ׂ̗ɂ���A�V�����[�g�C���ł����B�o�X�E�g�C���ƌ��������`�ɐ��ʂ�����A���ʑ䎩�̂͂ӂ��̑傫���ł������A���̉��ɖ̑䂪����傫�ȋ����u����āA���ʂ̋��ƍ��킹�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B���ݍ��݂��オ�������ʂ̂ӂ��܂��J����ƂP�Q�����̑傫�Ȑ����`�̘a�����L����܂��B�����Ƀe���r��u�������ƁA���̊Ԃ������Ǝd���Ĕz�u����Ă��܂��B���̊Ԃ͋��ڂł����A����ނ��̉Ԃ��܂Ƃ߂đ傫���������Ă��܂��B���܂ōs�������ł��A�����Ɋ�����ꂽ�ԂƂ��Ă͂��Ȃ荋�ŁA�͂Ȃ₩�Ȃ��̂ł����B���łɂ����̓��r�[�ň��݂܂����̂ŁA���߂Ă̂����o���͂���܂���B�����A�e�[�u���̏�ɂ͂���݂Ƃ����̂��A�u����Ă��܂����B���߂̃T�C�Y�̋C�Â���������܂����B�a���̐�ɂ͂������Ƃ����L���������A�֎q����r�u����Ă��܂��B�S�炢�̍L���͂������Ǝv���܂��B������͕ʏ��̊X���݂ƁA�����̎R�A�͂邩�������̉��c�̒��̊X���݂��]�߂܂��B���̕����ɍ����r���͂܂������Ȃ��A�S�̓I�ɂ��Ȃ茩���낷��ۂ��܂��B���c�̊X���݂͖�i�Ƃ��Ă��Ȃ��Ȃ��Y��ł����B�����͗����I�ɂ͂�⍂�����̗��ق̕��ނɓ���Ǝv���̂ł����A�①�ɂ͋�̂��̂��u����A�����̍D���Ȃ��̂����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�������������قƂ��Ă͒������Ǝv���܂����B�����Ƃ��Ă͖��邭�Ă��������Ȃ̂ł����A�I�b�Ƌ������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A�������ق̂��������Ƃ����Ƃ���łƂǂ܂��Ă��銴���ł��B |
 �����C�͐�قǏ������悤�ɍŏ�K�̂U�K�B�j���̌��͂���܂���B�����C�̓�����ɂ͑������Ԃɂ͒u���Ă���܂��A�[���߂��ɂȂ�Ɓu�M�q�݂v�Ƃ������ݕ����u����Ă��܂��B����قNJÂ����������A�����������̂ł��B�Â��n�̈��݂��̂��u����Ă����̂͋v���Ԃ�ł����B�����A�����╁�ʂ̐����u���Ă���ƁA�Ȃ������Ǝv���܂����B���̗M�q�݂͖�⒩�͒u����Ă��炸�A���Ȃ莞�Ԃ�������悤�ł��B�����̗␅�|�b�g�͗[�H��ŁA������������Ԃ��炠��Ƃ����Ǝv���܂����B�嗁��͖��邢�A�������ɂ��ӂꂽ���̂ł��B�ؘg�̗����͂V�A�W�l�͓��ꂻ���ł��B��͂W��������܂����B�V�F�|�r���O�W�F�����u����Ă��܂����B�V�F�[�r���O�n�̂��̂��u����Ă���Ƃ���͔��ɏ��Ȃ��̂ŁA����͕]���ł���Ǝv���܂��B�I�V�͑嗁�ꂩ��o��`�ŁA�̎l�p�����D�ł��B����������l�̍L���ł��傤���B���D�ɓ���Ǝ���̒|�_�ɂ��������Đ���ꂽ�������܂��A�����オ��Ɠ�����������邹��������A��������̒��߂Ɠ������̂ƁB�k���ω������̌i�F�����߂��܂��B���ɖk���ω��̉E�̍����ʒu�ɂ����t���͐^���ʂɗǂ������܂��B���̘I�V�̓x�����_�^�̈��ʼn���������܂��̂œ��D�ɓ����Ă��ĊJ�����͂��܂肠��܂���B���̓��̖�͐��������Y��ŁA���̘I�V��������Ȃ�̐������邱�Ƃ��ł��܂����B�����A��͂肱�ꂪ���ƂƂ������̏�ɊJ�����I�V��������ȂƂ����C�����܂����B�I�V�͂P�Q���܂łƂ����f�菑��������܂������A�I�V�֒ʂ���h�A�Ɍ��͂�����܂���̂ŁA�������ł������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����͑嗁��͌�����Ƃ����C�����܂��B�������Ȃ��܂��L�����܂��B�I�V�͓�����`���Ă݂��Ƃ���A���Ɍ��������ł����̂ŁA��������Əz�̂����ł͂Ȃ��ł��傤���B����������Ɠ������������ł͏z���Ă��邩������܂���B�ł��A���f�L�͂܂����������A�������猾���Ă������͈����͂Ȃ��Ǝv���܂��B���������傤�ǂ��������ł����B �����C�͐�قǏ������悤�ɍŏ�K�̂U�K�B�j���̌��͂���܂���B�����C�̓�����ɂ͑������Ԃɂ͒u���Ă���܂��A�[���߂��ɂȂ�Ɓu�M�q�݂v�Ƃ������ݕ����u����Ă��܂��B����قNJÂ����������A�����������̂ł��B�Â��n�̈��݂��̂��u����Ă����̂͋v���Ԃ�ł����B�����A�����╁�ʂ̐����u���Ă���ƁA�Ȃ������Ǝv���܂����B���̗M�q�݂͖�⒩�͒u����Ă��炸�A���Ȃ莞�Ԃ�������悤�ł��B�����̗␅�|�b�g�͗[�H��ŁA������������Ԃ��炠��Ƃ����Ǝv���܂����B�嗁��͖��邢�A�������ɂ��ӂꂽ���̂ł��B�ؘg�̗����͂V�A�W�l�͓��ꂻ���ł��B��͂W��������܂����B�V�F�|�r���O�W�F�����u����Ă��܂����B�V�F�[�r���O�n�̂��̂��u����Ă���Ƃ���͔��ɏ��Ȃ��̂ŁA����͕]���ł���Ǝv���܂��B�I�V�͑嗁�ꂩ��o��`�ŁA�̎l�p�����D�ł��B����������l�̍L���ł��傤���B���D�ɓ���Ǝ���̒|�_�ɂ��������Đ���ꂽ�������܂��A�����オ��Ɠ�����������邹��������A��������̒��߂Ɠ������̂ƁB�k���ω������̌i�F�����߂��܂��B���ɖk���ω��̉E�̍����ʒu�ɂ����t���͐^���ʂɗǂ������܂��B���̘I�V�̓x�����_�^�̈��ʼn���������܂��̂œ��D�ɓ����Ă��ĊJ�����͂��܂肠��܂���B���̓��̖�͐��������Y��ŁA���̘I�V��������Ȃ�̐������邱�Ƃ��ł��܂����B�����A��͂肱�ꂪ���ƂƂ������̏�ɊJ�����I�V��������ȂƂ����C�����܂����B�I�V�͂P�Q���܂łƂ����f�菑��������܂������A�I�V�֒ʂ���h�A�Ɍ��͂�����܂���̂ŁA�������ł������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����͑嗁��͌�����Ƃ����C�����܂��B�������Ȃ��܂��L�����܂��B�I�V�͓�����`���Ă݂��Ƃ���A���Ɍ��������ł����̂ŁA��������Əz�̂����ł͂Ȃ��ł��傤���B����������Ɠ������������ł͏z���Ă��邩������܂���B�ł��A���f�L�͂܂����������A�������猾���Ă������͈����͂Ȃ��Ǝv���܂��B���������傤�ǂ��������ł����B |
 �H���͗[�H�͕����ł��B���i�������u����Ă��܂����A�����͂��܂肠��܂���B�܂��e�[�u���̏�ɂ͐H�O���A�O�̘Z��Ɛ�t�̗��Ԑ������B���̖p�t�Ă��̓��ƁA�����̓y�r�������o�Ă��܂��B�y�r�����ɉ�������H���J�n�ɂȂ�܂��B�H�O���͂������Ŏv�����قǂ̓N�Z�͂���܂���ł����B�O�͂ǂ�����������A�܂����Ԑ������������Ǝv���܂��B�������A���ƌ����Ă������̓y�r�����ł��B�|�݂ƍ���̃n�[���j�[�͉��Ƃ������܂���B���ɂ����������̂ł����B�ォ��^�ꂽ������̌ܓ_����́A�ܓ_����ƌ����Ă��ʂ͂킸���ł����A������������̂��̂��Ǝv���܂��B�����Ă������̂��̂��Ă��Ȃǂ̔���A���q�̕����A�|�̕��Ƃ��ĊI��a����i��������܂��B�^��ł���ԍ����͂��傤�ǂ������ŁA�������傠��܂���B�M�B���̖p�t�Ă����ƂĂ������������̂ł����B�Ō�̂��т͏������тł���܂��喞���̖��ł����B�f�U�[�g�̓������Ƃ�Ƌ���ł�����ǂ������Ǝv���܂����A��ɂ���Ăڂ��͉�����H�v�������̂��H�ׂ��������C�����܂����B�S�̂ɔ��ɖ����ł����H���ł����A�~�������Ή����������Ă������̂��~���������ȂƂ����Ƃ���ł��B�I�[�\�h�b�N�X�ȗ������������������������Ƃ����Ƃ���ɂƂǂ܂��Ă��銴���ł��B�H�����ɏ��������A�ɗ��܂������A��������̈��A�͋v���Ԃ�ł����B���H�͐H�����ŁA�ꕔ���Ƀe�[�u���������悤�ȍ��ɂȂ��Ă��鏬�����̈֎q�Ȃł��B�S�̓I�ɂ�邬�̂Ȃ����H�ł��B�ʂ͂���قǑ����͂���܂��A���Ȃ�����Ƃ������Ƃ������Ă���܂���B�Ă����͍��B�����������̂ł����i�i�ɂƌ��������ł͂���܂���ł����B�����肨���������͉�������̕ɏ������C�����܂��B�T���_�Ɨ��Ă��͔��ɂ����������̂ł����B��W���[�X�͂��Ȃ�Â����̂ŁA������̃W���[�X�Ȃ�ł��傤�B�C�N�����낵�̃C�N���͔��ɂ����������̂ŁA�ꗱ�ꗱ�H�ׂĂ������������`����Ă��܂��B�܂��A�����͒��H�̂����䂪�������Ƃ������ƂŁA�m���ɂ��̂��������ɂ����������̂ł����B����܂łɂ������������͂�������H�ׂĂ��܂����A�g�b�v�O���[�v�ɓ��閡�ł��B���̑��A���������A�R�Ɗ��̎ϕ��A�L�̒ώρA�ǂ���Ƃ��Ă����������Ǝv���܂��B�����A�f�U�[�g�Ƃ��ĉ�������Ί����������̂ł����A���ꂾ�����c�O�ȋC�����܂����B���̏h���]���̂����h�ł��B�i�s�a�́u�����x�X�O�_�ȏ�̏h�v�ɓ�N�A�����ē����Ă��܂��B�����A�{���ɂǂ�������Ă����_�������A����䂦�S�̂̕��ς������Ȃ�Ƃ��������ŁA���ɂ����A�Ƃ��������ɂ͂�⌇���邩������܂���B�����͐V�����U�K���Ă̂��̂ŁA���������V�ق��D�݂̐l�ɂ͂����ł��傤���A�Â��������D�݂̐l�ɂ͌h�������ł��傤�B�嗁�������Ƃ������������Ȃ��A�H�������Ȃ肢���܂����A���ƈ�̃p���`�ɂ͌����܂��B��ԓ���������̂̓T�[�r�X��������܂���B���}�̎Ԃ͑���������̊�]���ԂȂ炢�ł��o���Ă���銴�����������A�t�����g�̎Ⴂ���������̏Ί�͉����A���͂������肵�����̂ł����B��������̋C�������]�ƈ��ɂ����Ɠ`����Ă���C�����܂��B��������̓`�F�b�N�A�E�g�̎����R�[�q�[�����߂Ă���܂����B�����͂�◿���͍��߂ŁA���̗����Ȃ炱�ꂭ�炢������O�E�E�Ǝv��ꂪ���ł����A���ۂɂȂ��Ȃ�����Ȑ��₳�������̂ł͂���܂���B��ʂ̗��s�҂����S���Ĕ��܂�A�����ł���h�Ƃ��Ă͍œK���Ǝv���܂��B �H���͗[�H�͕����ł��B���i�������u����Ă��܂����A�����͂��܂肠��܂���B�܂��e�[�u���̏�ɂ͐H�O���A�O�̘Z��Ɛ�t�̗��Ԑ������B���̖p�t�Ă��̓��ƁA�����̓y�r�������o�Ă��܂��B�y�r�����ɉ�������H���J�n�ɂȂ�܂��B�H�O���͂������Ŏv�����قǂ̓N�Z�͂���܂���ł����B�O�͂ǂ�����������A�܂����Ԑ������������Ǝv���܂��B�������A���ƌ����Ă������̓y�r�����ł��B�|�݂ƍ���̃n�[���j�[�͉��Ƃ������܂���B���ɂ����������̂ł����B�ォ��^�ꂽ������̌ܓ_����́A�ܓ_����ƌ����Ă��ʂ͂킸���ł����A������������̂��̂��Ǝv���܂��B�����Ă������̂��̂��Ă��Ȃǂ̔���A���q�̕����A�|�̕��Ƃ��ĊI��a����i��������܂��B�^��ł���ԍ����͂��傤�ǂ������ŁA�������傠��܂���B�M�B���̖p�t�Ă����ƂĂ������������̂ł����B�Ō�̂��т͏������тł���܂��喞���̖��ł����B�f�U�[�g�̓������Ƃ�Ƌ���ł�����ǂ������Ǝv���܂����A��ɂ���Ăڂ��͉�����H�v�������̂��H�ׂ��������C�����܂����B�S�̂ɔ��ɖ����ł����H���ł����A�~�������Ή����������Ă������̂��~���������ȂƂ����Ƃ���ł��B�I�[�\�h�b�N�X�ȗ������������������������Ƃ����Ƃ���ɂƂǂ܂��Ă��銴���ł��B�H�����ɏ��������A�ɗ��܂������A��������̈��A�͋v���Ԃ�ł����B���H�͐H�����ŁA�ꕔ���Ƀe�[�u���������悤�ȍ��ɂȂ��Ă��鏬�����̈֎q�Ȃł��B�S�̓I�ɂ�邬�̂Ȃ����H�ł��B�ʂ͂���قǑ����͂���܂��A���Ȃ�����Ƃ������Ƃ������Ă���܂���B�Ă����͍��B�����������̂ł����i�i�ɂƌ��������ł͂���܂���ł����B�����肨���������͉�������̕ɏ������C�����܂��B�T���_�Ɨ��Ă��͔��ɂ����������̂ł����B��W���[�X�͂��Ȃ�Â����̂ŁA������̃W���[�X�Ȃ�ł��傤�B�C�N�����낵�̃C�N���͔��ɂ����������̂ŁA�ꗱ�ꗱ�H�ׂĂ������������`����Ă��܂��B�܂��A�����͒��H�̂����䂪�������Ƃ������ƂŁA�m���ɂ��̂��������ɂ����������̂ł����B����܂łɂ������������͂�������H�ׂĂ��܂����A�g�b�v�O���[�v�ɓ��閡�ł��B���̑��A���������A�R�Ɗ��̎ϕ��A�L�̒ώρA�ǂ���Ƃ��Ă����������Ǝv���܂��B�����A�f�U�[�g�Ƃ��ĉ�������Ί����������̂ł����A���ꂾ�����c�O�ȋC�����܂����B���̏h���]���̂����h�ł��B�i�s�a�́u�����x�X�O�_�ȏ�̏h�v�ɓ�N�A�����ē����Ă��܂��B�����A�{���ɂǂ�������Ă����_�������A����䂦�S�̂̕��ς������Ȃ�Ƃ��������ŁA���ɂ����A�Ƃ��������ɂ͂�⌇���邩������܂���B�����͐V�����U�K���Ă̂��̂ŁA���������V�ق��D�݂̐l�ɂ͂����ł��傤���A�Â��������D�݂̐l�ɂ͌h�������ł��傤�B�嗁�������Ƃ������������Ȃ��A�H�������Ȃ肢���܂����A���ƈ�̃p���`�ɂ͌����܂��B��ԓ���������̂̓T�[�r�X��������܂���B���}�̎Ԃ͑���������̊�]���ԂȂ炢�ł��o���Ă���銴�����������A�t�����g�̎Ⴂ���������̏Ί�͉����A���͂������肵�����̂ł����B��������̋C�������]�ƈ��ɂ����Ɠ`����Ă���C�����܂��B��������̓`�F�b�N�A�E�g�̎����R�[�q�[�����߂Ă���܂����B�����͂�◿���͍��߂ŁA���̗����Ȃ炱�ꂭ�炢������O�E�E�Ǝv��ꂪ���ł����A���ۂɂȂ��Ȃ�����Ȑ��₳�������̂ł͂���܂���B��ʂ̗��s�҂����S���Ĕ��܂�A�����ł���h�Ƃ��Ă͍œK���Ǝv���܂��B |
| �O�����������߂̓��֍s���Ă��܂����B�ڂ��͒߂̓��֍s���Ȃ��̎����Ǝv���Ă��܂����B�J���͌����ɓ�����ጩ�̒߂̓��A��̂�������ł̘I�V�̓������y���ނ��Ƃ��ł��܂����B�ڂ����s���ق�̈�T�ԑO�͂܂��S�R�ς����Ă��Ȃ������悤�ł��B�s���Ă݂�ƒ߂̓��͈ӊO�ɍs���₷���ł��ˁB��������H�c�V�����œc��Ήw�܂łR���ԁB�������犄�Ɩ{���̂���������̃o�X�œc������̃o�X��܂łS�T�����炢�������ł��傤���B���炩���ߘA�����Ă����Ώh���瑗�}�̃o�X�����łɑ҂��Ă��Ă���܂��B���̓��A�c������荞��q�͂قƂ�Ǔc������ō~��A���̂܂ܒ߂̓��̑��}�o�X�Ɉړ����܂����B�������̂Ȃ��ł��߂̓����Ƃтʂ��Đl�C�����邱�Ƃ��v�킹�܂����B���}�o�X�͓r���A�߂̓��̕ʊقł���u�R�̏h�v�֊��A��������{�ق̂����C�ɓ���ɍs���h���q���悹�āA�����ŏh�ւƌ������܂����B�h�̖�̂Ƃ���ŎԂ��~��A�܂����������Ď������̂Ƃ���܂ōs���܂��B���̎��͒��������肾�������A�Ⴊ�ӂ��Ă����肵�Ă���قNjC�ɂƂ߂Ȃ������̂ł����A�A��ɉ��߂Ă悭����ƁA���̓��̍����ɕ��Ԍ������{�w�ƌĂ��������̂ł����B�ڂ��̕����́A�������̉��̖،˂�����Ă����̓�������オ��A�V�{�w�ƌ����Ƃ���ŁA���̑��ɂ����{�w�ƌĂ��Ƃ��낪��������A���q�����͂���قǑ����͂Ȃ��Ǝv���̂ł����A����͓���g��ł���悤�ł��B�����グ��ꂽ�L����ʂ�K�i���オ���āA�V�{�w�̌����ɓ���Ƃ����ɁA������Ƃ����k�b�R�[�i�[�̂悤�ȂƂ��낪����A�{��V�����u����Ă��āA������肭�낰��悤�ɂȂ��Ă��܂����B�����͐V�{�w�̂R���Ƃ��������ŁA�����˂ɂȂ��Ă��܂��B�����˂��J����ƈ����̔̊Ԃ̏オ����̂����E��ɃX�e�����X�̗����䂪�u����A���̉����g�C���ɂȂ��Ă��܂��B�g�C���̓V�����[�g�C���ʼn��K�ł��B�����A���L�܂̏L�������߂ŏ��������܂����B�߂̓��͎��Ɣ��d�Ƃ������ƂŁA�����Ƀe���r���①�ɂ��Ȃ��̂ł����A�G�A�R���͂���A�g�[�͂悭�����Đ\��������܂���B�������A�~��͒g�[�������܂��B�①�ɂ��Ȃ��Ɨ␅�D���̂ڂ��͍����Ă��܂��̂ł����A�����䂩��o�鐅�͔��ɗ₽���A�①�ɂŗ�₵�Ă������̂Ƃ܂������ς��܂���B�܂��A���̐��͔��ɂ����������̂ł����B���łɂ����ƁA�e�����C��ɑ̂���ɂ��������߂鐅���o�Ă���̂ł����A���̂��q���h�̐l�ɕ������Ƃ���ɂ��ƁA���̐������߂邻���ł��B������������₽���Ă����������ł��B�����C�ɓ����Ă̂ǂ���������A���̐������߂����킯�ł��B�����ɂ͑��ɋ��ɂ�ߕ��I�Ȃǂ͂���܂���ł������A�e�B�b�V���͂���܂����B�ߕ��I�̑ւ��ɁA�����̃R�[�i�[�ɒu���^�C�v�̑傫�ȃn���K�[�|�����u����Ă��܂����B�̊Ԃ̏オ����̂ӂ��܂��J����ƁA�W��̘a�����������̊Ԃ����Ă��܂��B�����A�c�O�Ȃ���Ԃ͂���܂���B�����͊i�ʐV����������܂��A�Â����ʂɊ��������܂���B�L���͔̊ԂłR����̍L��������܂��B�ڂ����܂ߐV�{�w�̋q����g�����̂ŁA��g�����̈ē��ŁA�ו������₨���o���͂���܂���ł����B�����A���߂̋C�Â����͂���B����͂����Ɨ������\�����肳��Ă����͗l�ł��B�}���َq�͓����\���Ƃ����A���̔�������\���ł��B���̒��̔�̏�̕��������ɂ͔�͂Ȃ��A�����Q���ۂ�����̂������Ă��܂��B�ǂ������̍����Q�̕�����������\���Ă���悤�ł��B���̊O�ɂ͍��܂Ō������Ƃ��Ȃ��悤�ȑ傫�Ȃ�炪������A�Ђ����ɍ~�葱����̌������ɓ��{�w�̌�����������ł��܂��B���̕����͓�K�̂͂��Ȃ̂ł����A���Ƃ����߂��ɒn�ʂ�����܂��B |
 �A���ł��̂ł�����K�v�͂���܂���B������Ƃ��낢�ł��炨���C�Ɍ������܂��B�܂��s���͉̂��Ƃ����Ă������̘I�V�ł��傤�B���������̏h�̌������o��ƁA���������Ō������ɂ����C������ł��܂��B�����ȋ���n�������ʂɔ����ƍ����B�E�̏������s���ƍ����̘I�V�ƒ��̓��B���ɍs���Ə�����p�̘I�V�ɂȂ�܂��B�I�V�ȊO�͂��ꂼ��j���ʂ̓��D������܂����A���������l���x�̋������̂ł��B�����j���p�̔����͂����炩�L�����̂ł����B�����̘I�V�͏����ɖʂ��Ă��āA�^������ɉ������������������E�ߒI������܂����A�������̂ŁA���̎����͐Ⴊ�����Ă��܂��B�j���Ƃ����̓��̒E�ߏ�����o����悤�ɂȂ��Ă��āA�݂�Ȃ�������o���肵�Ă��܂����B���̍����̘I�V�͊O���猩��Ǝv������苷�����������܂����A�����Ă݂�ƈӊO�ɍL�����l�ł����ꂻ���ł��B���H�̐H�����ɁA���̘I�V�ɂ�������̐l�������Ă���|�X�^�[�������Ă���܂������A���m�ɐ�������ł͂���܂��A�S�l���炢�͓����Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̘I�V�͌����u�Ԃɂ�[���Ƌ��Ԃ悤�ȐV��͂���܂��A������������Ă���ƁA���̗ǂ������킶��Ɗ�����悤�ȘI�V�ł��B�����̌����߂������ł������������܂�A���D�ɓ�����Ă����̉������肩����Ԃ��Ԃ��ƖA�������Ă��܂��B�܂��A��ł������������܂�邠����̉�������M�߂̂������͋����N���o���Ă��܂��B�����ɖʂ������̔��Α��͂Ȃ��炩�ȎΖʂŐႪ�ς����Ă��܂����A�܂��^�����ł͂Ȃ��Z�W������Ƃ��낪�A�������ĉ��s�������������܂��B�܂��ɉ����Ɉ�ꂽ�I�V�ł��B����͂Ƃɂ������q�����Ȃ������Ƃ������ƂőI�̂ŁA�����ڂ����������Ƃ��ň�ԑ����Ă��P�O�l������Ƃ������Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̂����������āA�{���ɂ��̉����ɏ\���Ђ���邱�Ƃ��ł��܂����B�A���ō��v�P�O���Ԃ��炢���̂����C�ɓ������Ǝv���̂ł����A���̂����Ɛ肵�Ĉ�l�œ��ꂽ���Ԃ��Q���ԋ߂���������������܂���B���Ԃ���������Ƃ͎v���̂ł����A��͂�邪����������Ƃ��̔��n�F�̐��E�����̒߂̓��̘I�V�ɂ͈�Ԏ����������ł��B�����͒�����Ă��镔�������ԗ���钆�̓��̓����ӂ�͂��ʂ�߂ł����A�ł��ʂ邷����Ƃ������Ƃ͂���܂���B�����ɂ����Ƃ��Ă��\�����܂�Ǝv���܂��B�����ƔM���̂������Ȃ璍�����ɋ߂Â��ΔM�߂ɂȂ�܂��B�Ɋւ��Ă͎�_���Ƃ������ƂŁA����ڂ͖{���ɏ_�炩�Ȃ����Ƃ��������������̂ł����A����ڂ̖�͂܂�ő����̂����̂悤�ɖڂɐ��݂Ă��Ȃ�ڂ��ɂ��Ȃ�܂����B�Ƃ��낪�O���ڂ̒��ɂȂ�Ƃ܂����Ƃ̂����ɂ��ǂ����悤�Ȋ����ɂȂ艽�Ƃ��Ȃ��Ȃ�܂����B����͂�����ƕs�v�c�ł����B�I�V�ɓ���Z��ɂȂ��Ă����̂ŁA���̂����C�͋삯���ɂȂ��Ă��܂��܂������A���D�݂͂ȏ��������̂́A���ꂼ��͂Ɉ�ꂽ�������Ǝv���܂��B�j���͔����ƍ����̒E�ߏ��͓����Ȃ̂ł����A���̒E�ߏ��ⓒ�D�����͋C�̂�����̂ł����B�����̊O�̂����C�Ƃ͕ʂɗ������q�͓���Ȃ�����������̂ł����A�����ɂ̓V�����[����������Ă��܂��B�����A���D�͂�͂菬���߂ŁA���邷�������������͋C�͂��܂芴�����܂���ł����B�����ȉƑ����C�Ƃ������������܂����B �A���ł��̂ł�����K�v�͂���܂���B������Ƃ��낢�ł��炨���C�Ɍ������܂��B�܂��s���͉̂��Ƃ����Ă������̘I�V�ł��傤�B���������̏h�̌������o��ƁA���������Ō������ɂ����C������ł��܂��B�����ȋ���n�������ʂɔ����ƍ����B�E�̏������s���ƍ����̘I�V�ƒ��̓��B���ɍs���Ə�����p�̘I�V�ɂȂ�܂��B�I�V�ȊO�͂��ꂼ��j���ʂ̓��D������܂����A���������l���x�̋������̂ł��B�����j���p�̔����͂����炩�L�����̂ł����B�����̘I�V�͏����ɖʂ��Ă��āA�^������ɉ������������������E�ߒI������܂����A�������̂ŁA���̎����͐Ⴊ�����Ă��܂��B�j���Ƃ����̓��̒E�ߏ�����o����悤�ɂȂ��Ă��āA�݂�Ȃ�������o���肵�Ă��܂����B���̍����̘I�V�͊O���猩��Ǝv������苷�����������܂����A�����Ă݂�ƈӊO�ɍL�����l�ł����ꂻ���ł��B���H�̐H�����ɁA���̘I�V�ɂ�������̐l�������Ă���|�X�^�[�������Ă���܂������A���m�ɐ�������ł͂���܂��A�S�l���炢�͓����Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̘I�V�͌����u�Ԃɂ�[���Ƌ��Ԃ悤�ȐV��͂���܂��A������������Ă���ƁA���̗ǂ������킶��Ɗ�����悤�ȘI�V�ł��B�����̌����߂������ł������������܂�A���D�ɓ�����Ă����̉������肩����Ԃ��Ԃ��ƖA�������Ă��܂��B�܂��A��ł������������܂�邠����̉�������M�߂̂������͋����N���o���Ă��܂��B�����ɖʂ������̔��Α��͂Ȃ��炩�ȎΖʂŐႪ�ς����Ă��܂����A�܂��^�����ł͂Ȃ��Z�W������Ƃ��낪�A�������ĉ��s�������������܂��B�܂��ɉ����Ɉ�ꂽ�I�V�ł��B����͂Ƃɂ������q�����Ȃ������Ƃ������ƂőI�̂ŁA�����ڂ����������Ƃ��ň�ԑ����Ă��P�O�l������Ƃ������Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̂����������āA�{���ɂ��̉����ɏ\���Ђ���邱�Ƃ��ł��܂����B�A���ō��v�P�O���Ԃ��炢���̂����C�ɓ������Ǝv���̂ł����A���̂����Ɛ肵�Ĉ�l�œ��ꂽ���Ԃ��Q���ԋ߂���������������܂���B���Ԃ���������Ƃ͎v���̂ł����A��͂�邪����������Ƃ��̔��n�F�̐��E�����̒߂̓��̘I�V�ɂ͈�Ԏ����������ł��B�����͒�����Ă��镔�������ԗ���钆�̓��̓����ӂ�͂��ʂ�߂ł����A�ł��ʂ邷����Ƃ������Ƃ͂���܂���B�����ɂ����Ƃ��Ă��\�����܂�Ǝv���܂��B�����ƔM���̂������Ȃ璍�����ɋ߂Â��ΔM�߂ɂȂ�܂��B�Ɋւ��Ă͎�_���Ƃ������ƂŁA����ڂ͖{���ɏ_�炩�Ȃ����Ƃ��������������̂ł����A����ڂ̖�͂܂�ő����̂����̂悤�ɖڂɐ��݂Ă��Ȃ�ڂ��ɂ��Ȃ�܂����B�Ƃ��낪�O���ڂ̒��ɂȂ�Ƃ܂����Ƃ̂����ɂ��ǂ����悤�Ȋ����ɂȂ艽�Ƃ��Ȃ��Ȃ�܂����B����͂�����ƕs�v�c�ł����B�I�V�ɓ���Z��ɂȂ��Ă����̂ŁA���̂����C�͋삯���ɂȂ��Ă��܂��܂������A���D�݂͂ȏ��������̂́A���ꂼ��͂Ɉ�ꂽ�������Ǝv���܂��B�j���͔����ƍ����̒E�ߏ��͓����Ȃ̂ł����A���̒E�ߏ��ⓒ�D�����͋C�̂�����̂ł����B�����̊O�̂����C�Ƃ͕ʂɗ������q�͓���Ȃ�����������̂ł����A�����ɂ̓V�����[����������Ă��܂��B�����A���D�͂�͂菬���߂ŁA���邷�������������͋C�͂��܂芴�����܂���ł����B�����ȉƑ����C�Ƃ������������܂����B |
 �V�{�w�́A�[�H�������ŁA���H����L�ԂɂȂ�܂��B�[�H�͏����Ȃ��V�`���ŁA��x�ɕ����ĉ^��A����Ɍォ�疼���̎R�̈�炪�o����܂��B���i�����͂���܂������Ɛ������Ă���܂��B��x�ڂ͂���قǔM���Ȃ����́A��x�ڂ͔M�����̂Ƃ������ƂȂ̂ł����A��x�ڂɂ��h�g���^���̂ɁA�ݖ��͓�x�ڂȂ̂ł��B�܂�������r�[���𒍕����Ă��^���͓̂�x�ڂł��B����͘A�����Ĉ���ڂ�����ڂ������ł�������A��������ȕ��Ɍ��܂��Ă���̂��Ǝv���܂��B�ڂ��͐H���̑O�ɂ܂��A���Ƃ����Ă����オ��̃r�[���h�ł�����A���a���������������ł��B����ڂ͓��ڂ��^���̂����Ƃ����������̂ŗǂ������̂ł����A����ڂ͂��������Ԃ������������ŁA���̊ԂقƂ�ǔ��������ɑ҂��Ă��܂����B����ڂ̍ŏ��́u�ӂ��A����܂��A�݂��̎��v�Ƃ����R�؎O�_�Ƃ��āi�H�c���܂��j�̂��c�q�̂��̂����Q�����A�⋛�̎h�g�A���̂��̃z�C���Ă��A�R�����̃W�����ł����B���ڂ̓��C���̎R�̈����������⋛�̉��Ă��A�������B�����̎ϕ��Ƃ������C���A�b�v�ŁA���̊⋛�͓����ƂقƂ�Ǎ����H�ׂ��邨���������̂ł����B�R�����̃W�����̓z�C���Ă��Ɠ������M�ɏo����z�C���Ă��ɂ��ĐH�ׂ�̂��Ǝv���܂������A���Ȃ��ł��������ƌ����A���̃W�����̈ʒu�t�������ꕪ����܂���ł����B�R�̈��͎������銴���ŁA�����������Ǝv���܂����B�R�̖��t�����悭�ʂƂ������ƌ����A���O�ɂ����炸�Ȃ��Ȃ��撣���Ă���h���Ɗ����܂����B �V�{�w�́A�[�H�������ŁA���H����L�ԂɂȂ�܂��B�[�H�͏����Ȃ��V�`���ŁA��x�ɕ����ĉ^��A����Ɍォ�疼���̎R�̈�炪�o����܂��B���i�����͂���܂������Ɛ������Ă���܂��B��x�ڂ͂���قǔM���Ȃ����́A��x�ڂ͔M�����̂Ƃ������ƂȂ̂ł����A��x�ڂɂ��h�g���^���̂ɁA�ݖ��͓�x�ڂȂ̂ł��B�܂�������r�[���𒍕����Ă��^���͓̂�x�ڂł��B����͘A�����Ĉ���ڂ�����ڂ������ł�������A��������ȕ��Ɍ��܂��Ă���̂��Ǝv���܂��B�ڂ��͐H���̑O�ɂ܂��A���Ƃ����Ă����オ��̃r�[���h�ł�����A���a���������������ł��B����ڂ͓��ڂ��^���̂����Ƃ����������̂ŗǂ������̂ł����A����ڂ͂��������Ԃ������������ŁA���̊ԂقƂ�ǔ��������ɑ҂��Ă��܂����B����ڂ̍ŏ��́u�ӂ��A����܂��A�݂��̎��v�Ƃ����R�؎O�_�Ƃ��āi�H�c���܂��j�̂��c�q�̂��̂����Q�����A�⋛�̎h�g�A���̂��̃z�C���Ă��A�R�����̃W�����ł����B���ڂ̓��C���̎R�̈����������⋛�̉��Ă��A�������B�����̎ϕ��Ƃ������C���A�b�v�ŁA���̊⋛�͓����ƂقƂ�Ǎ����H�ׂ��邨���������̂ł����B�R�����̃W�����̓z�C���Ă��Ɠ������M�ɏo����z�C���Ă��ɂ��ĐH�ׂ�̂��Ǝv���܂������A���Ȃ��ł��������ƌ����A���̃W�����̈ʒu�t�������ꕪ����܂���ł����B�R�̈��͎������銴���ŁA�����������Ǝv���܂����B�R�̖��t�����悭�ʂƂ������ƌ����A���O�ɂ����炸�Ȃ��Ȃ��撣���Ă���h���Ɗ����܂����B����ڂ͑S�̓I�Ƀ��j���[�͕ς��܂����A����ڂƓ������̂��o����܂��B�R�̎O�_�͊�����g���S�������ŁA�����̎R�̈��������悤�ɏo����܂����B��͂��ׂĕς���Ă��܂����B�h�g�̓T�[�����ɁA�⋛�̉��Ă��͊⋛�̖��X�c�y�ɁA���͂Έ�낤�ǂ�ɂƌ����������ł��B���̑��A���Ɩ�̐������킹�A�@���Ƃ��̂��̎ϕ��A�Ƃ��肽��ۂ��o����܂����B�ڂ��͊⋛�̖��X�c�y�͏��߂Ă������Ǝv���܂����A����͂��������A�����Ƃ��ׂĂ��ƐH�ׂĂ��܂��܂����B�܂����肽��ۂ��������������Ǝv���܂��B�����A����ł��Ȃ薞���ɂȂ��Ă��܂����������A�R�̈��͍���قǂ��������͊������܂���ł����B�����肫�肽��ۂ���i���������ŁA���̕��Ƃ���������ȏ�ɂ����������ς��ɂȂ�܂����B�v�X�̒�������Ԃł��B ���H�͓����̑O�̍L�ԂŁA����͂���Ȃɗʂ͑����͂���܂���B��ʓI�Ȓ���H�ň���ڂ̋��͓����̊ØI�ρB���̑��ɔ[���ƃT���_�A�؊��卪�Ƃ��Ⴋ���Ⴋ�����H���̎R����ɓ������ł����B�������͂悭����e�[�u���ł�����������̂ł͂Ȃ��A��Ɉ������Ă�����̂ł��B����ڂ̋��͍��̐�g�ŁA�[���A�R�͍���Ɠ����ł����B���̑��ɁA�ڋʏĂ��A�����A�ق���Ƃ��₵�̂��ܘa�����o����܂����B���̒��ł͈���ڂ̓����̊ØI�ς������������̂ł����B���̑��͓��ɂ���Ƃ������̂͂���܂���ł����B �߂̓��̐H���ɂ��ď����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�S�̂ɊÖ�����ɂ���Ă���i�H�j�Ƃ������Ƃł��B���̏ے��I�Ȃ��̂�����ڂ̈ʒu�t���s���̎R�����̃W�����ł��ˁB�܂����̒Е��͍����ƈꏏ�ɂ����܂�Ă��邻���ŁA�Ö�����������̂ł����B�S�̓I�ɍ����������g���A��i��i�͂͂���قNJ����Ȃ��Ƃ��Ă��A���ꂪ�ςݏd�Ȃ�Ƃ��Ȃ�d�ʊ���������悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ڂ��͈���ڂ̗[�H�͊낤���o�����X�Ȃ���Ȃ�Ƃ����݂Ƃǂ܂������������܂������A����ڂ͈�i��i�͂����������̂̃g�[�^���Ƃ��ăI�[�o�[���Ă��܂����̂ł͂Ȃ����A���ꂪ�������ɂȂ������̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂����B���Ɋւ��Ă͂ڂ��͂܂����Ƃ͎v���܂���ł������A���A�ׂŐH�����Ă����l�͗ǂ��]���͂��Ă��܂���ł����B����ڂ̂ق���Ƃ��₵���Â��A����͊Â����Ƃ��������ł����B �����͂W�O�O�O�~���甑�܂�Ă������H���͕ς��Ȃ������ł��B���̂����ƃ{�����[�������Ղ�̐H���A�����ĉ���h�Ƃ��Ă̕��͋C�B�l�C�̗��R�����������܂��B�h�̐l�������邱�ƂȂ��ڂ��Ă���܂����B�H���̖��t�������̒n��̂��̂��p���ł���Ȃ����ꂪ�Ƃ₩���������Ƃł͂Ȃ��̂�������܂���B���̒n��̓c�ɗ����ɓO���悤�Ƃ����S�ӋC�͏\���`����Ă��܂����B���{���\���鉷��̈�Ƃ��Ă��܂ł����̐S�ӋC��Y�ꂸ�A���̏h�̕��͋C����葱���Ăق����Ɗ肢�܂��B |
| �@ |
| �����͓c��̊ό������˂ēc��Ή���́u�ԐS������͂܁v�Ƃ����h�ł��B�h�͊m���T�N�O�Ƀ��j���[�A�������Ƃ������ƂŁA���炵�F�������ߑ�I�ȂT�K���Ă̌����ł����B�h��������������ƍ��߁A�Ƃ����^�C�v�̗��قɂ悭����`���Ǝv���܂����B���r�[�ł��������݁A���炭�҂��ĕ����Ɉē����Ă��炦�܂����B�����͏�ł͂Ȃ��J�[�y�b�g�ł����A��͂�ŋ߂̗��قɂ悭����悤�ɁA�X���b�p�͂͂��Ȃ��V�X�e���ɂȂ��Ă��܂��B���łɉו��͕����ɉ^��Ă��āA�ē������Ă����͕̂����W��̒�������ł����B���̒�������͔N�͎Ⴛ���ł������������Ă��āA�������������肵�A������̎���ɂ������Ɠ����Ă���܂����B�����͎l�K�̂S�P�R�����ŁA�L��������ł�͂�S�P�R�ƕ����ԍ���������A�e�[�u���ƈ֎q���u���ꂽ������������܂��B���̗��ق̍ő�̃E���͂��ꂼ��̕����ɐ�p�̃_�C�j���O���[��������Ƃ������ƂȂ̂ł��B���̃_�C�j���O���[���Œ��[�̐H�������邱�ƂɂȂ�܂��B�����^�C�v�ɂ���Ă͂��̂悤�ɘL�����͂��h�A�̊O�ɂ���ꍇ������A���邢�͎厺�Ƃ͕ʂɃ_�C�j���O���[���Ƃ��ē��������̒��ɂ���ꍇ������悤�ł��B�����̓h�A���J����ƈ����̏オ����Ƃ�͂�����̓��ݍ��݂�����܂��B���ݍ��݂̂������Ƀg�C�����A���ʂɐ��ʏ��Ɨ���������܂��B�g�C���̓V�����[�g�C���ł��B���ݍ��݂��オ���ĉE�ɂP�S�炢�̕���������A���ۂɉΔ��ƍ��z�c���u����Ă��Ĉ֎q�͂���܂���B�����ɂ͏��̊Ԃ�����̂ł����A�c�O�Ȃ��珰�̊Ԃɂ����Ƀe���r���u����Ă��āA��������܂���B���߂̏h�ɂ��Ă͏�������̔z��������Ȃ������ȂƂ����C�����܂��B�������Ԃ͂���܂����B������͐^���ɉ��Ɏg���낤�ƍl���Ă��܂��悤�Ȃ��Ȃ�L���L�ꂪ�A�E��ɂ͓c����]�߂܂��B�`�����݂͂���܂���B�����Œ�������͂܂������ƌ}���َq���o���Ă���܂��B�}���َq�͎R�����g������ƒ����Q�͂��ڂ����Q�Ƃ������ƂŁA�����Ƃ�Ƃ�����i�Ȗ��ł����B�A���j�e�B�Ƃ��ẮA�X���b�p�̂Ȃ��h�̏�Ƃ��āA���܌C�����������Ă��܂��B�܂��A���߂͑S�T�C�Y�����炩���ߗp�ӂ���Ă��܂��B�܂��A�����p�̈Ⴄ���̗��߂��H��ɗp�ӂ���܂����B |
 �����C�͂��ׂĈ�K�ł��B�嗁��͊��ƍL�߂Ő�̐����\�����萴���ŋC�����̂������̂ł��B�V�F�|���B���O�t�H�[�����������Ă���̂̓J�~�\���h�̂ڂ��Ƃ��Ă͂��ꂵ���Ƃ���ł��B�����͓c��Ή���i���͏��ɂ��Ɛ����ɂ͓c��p�[������j�Ƃ������Ƃł����B�ǂ�������̈��������Ǝv�����̂ł����A�������ł͂Ȃ����ݓ��Ƃ������Ƃł����B�ǂ����狂��ł���̂��܂ł͕����܂���ł����B�����������ł͂���܂��A���f�L�͂Ȃ�������L�̏L������������悤�ȋC�����܂����B���̓��͂قƂ�ǔ���q���Ȃ��A�嗁���I�V�͏�ɑ݂������Ԃł����̂ŁA�������܂���������Ă͂��Ȃ����������܂����B����͂S�Q�x�Ƃ������Ƃł������A���ݓ��ł��̂ŕ������Ă���Ǝv���܂��B�܂��A�I�V��Ƒ����C���ӂ��߂ĂQ�S���ԓ����ł���̂͂Ȃ��Ȃ������Ǝv���܂��B���ݓ��Ƃ������Ƃ������̂ŁA�I�V��Ƒ����C������Ȃ̂��O�̂��ߕ����Ă݂��̂ł����A�������ł��B�I�V�͑嗁�ꂩ��o��^�C�v�Ŏ������Ɉ͂܂�A�����炵�͂܂���������܂���B�����A���ɓ����q�����Ȃ������������A���Ƃ������̂�т�Ɠ���܂����B�Ƒ����C�͈����A�a���̎��̊Ԃ��t�������h�Ȃ��̂ł��B�����ŁA�������Ă���l�����Ȃ��Ƃ��͂��ł�����܂��B�����ɏ����ȃz���C�g�{�[�h������A�������オ���̂̎��Ԃ����Ȑ\������悤�ɂȂ��Ă��āA�ʔ����Ǝv���܂����B �����C�͂��ׂĈ�K�ł��B�嗁��͊��ƍL�߂Ő�̐����\�����萴���ŋC�����̂������̂ł��B�V�F�|���B���O�t�H�[�����������Ă���̂̓J�~�\���h�̂ڂ��Ƃ��Ă͂��ꂵ���Ƃ���ł��B�����͓c��Ή���i���͏��ɂ��Ɛ����ɂ͓c��p�[������j�Ƃ������Ƃł����B�ǂ�������̈��������Ǝv�����̂ł����A�������ł͂Ȃ����ݓ��Ƃ������Ƃł����B�ǂ����狂��ł���̂��܂ł͕����܂���ł����B�����������ł͂���܂��A���f�L�͂Ȃ�������L�̏L������������悤�ȋC�����܂����B���̓��͂قƂ�ǔ���q���Ȃ��A�嗁���I�V�͏�ɑ݂������Ԃł����̂ŁA�������܂���������Ă͂��Ȃ����������܂����B����͂S�Q�x�Ƃ������Ƃł������A���ݓ��ł��̂ŕ������Ă���Ǝv���܂��B�܂��A�I�V��Ƒ����C���ӂ��߂ĂQ�S���ԓ����ł���̂͂Ȃ��Ȃ������Ǝv���܂��B���ݓ��Ƃ������Ƃ������̂ŁA�I�V��Ƒ����C������Ȃ̂��O�̂��ߕ����Ă݂��̂ł����A�������ł��B�I�V�͑嗁�ꂩ��o��^�C�v�Ŏ������Ɉ͂܂�A�����炵�͂܂���������܂���B�����A���ɓ����q�����Ȃ������������A���Ƃ������̂�т�Ɠ���܂����B�Ƒ����C�͈����A�a���̎��̊Ԃ��t�������h�Ȃ��̂ł��B�����ŁA�������Ă���l�����Ȃ��Ƃ��͂��ł�����܂��B�����ɏ����ȃz���C�g�{�[�h������A�������オ���̂̎��Ԃ����Ȑ\������悤�ɂȂ��Ă��āA�ʔ����Ǝv���܂����B |
 ���āA��p�̃_�C�j���O���[���ł̐H���ł��B�[�H�͏����Ȃ��i�����ƁA��������̒��J�Ȑ���������܂����B�H�O�������蓤���Ƃ����ς�������̂ŁA���蓤���Ē��ɂ��Ĉ�N�Q���������̂������ł��B�܂��������肻�̂��̖̂��ł����������̂ł����B��������������Ƃ������Ƃł��B�����͍ŏ��Ɋ⋛��齁A�R���A�݂��̎����܂�Â��A�Ȃǂ̒n�̂��̂����S�̒�����A�ԑ���I�܁A�g���Ȃǂ̎����������W�߂����M���o����܂��B���ɓg���Ɏ|�݂��Ïk����Ă悩�����Ǝv���܂��B�܂��A�I�܂���{�����ł������A�����������̂ł����B�݂��̎��͖ʔ����H���ŁA�����ŏ��߂ĐH�ׂ��̂Ȃ犴�S����̂ł��傤���A�߂̓��œ���A�����ĐH�ׂĂ������߁A���H���C���ł��ꂪ�����c�O�ł����B�����Ă����肪�ڂ���C�V�Ɗ����Ɠ����A���̂�������ƂĂ����������Ǝv���܂����B����ɁA���o�̍��^���A�͂��͂��̏������Ƒ����܂��B���̂͂��͂��͗��������Ă�����̂ŁA�H�ׂ�Ƃ��肱��Ƃ��Ȃ�傫�ȉ���������̂ł����B���߂ĐH�ׂ܂����B�����̂͂ƂĂ����������Ƃ����Ƃ���܂ł͂����܂��A���̐H���͂��Ȃ胆�j�[�N�Ȋ����ł��B�����āA�H�c���̕����Y�̘a���X�e�[�L�A����͂��Ȃ肢���܂��B�����A�����Ă�������Ƌ}���Ɏ|����������悤�ȋC�����܂����B���A�ɋ߂������ŐH�ׂ������悳�����ł��B���̑��Ɋ`�Y�A���݂����̂��肽��ۓ�A�����Ă��тɂȂ�܂��B������̂��肽��ۓ�������������̂ł��B�f�U�[�g�͉ʕ��̐��荇�킹�ł����A����͏����C���p�N�g�ɂ͌����Ă��������ł����B�S�̓I�ɗ[�H�͒n�̂��̂��g���A�������̍H�v�������邨���������̂ł����B�����A�Ƃє����ĂƂ������̂͏��Ȃ������悤�ȋC�����āA����͎c�O�ł����B��������ɂ��ƏH�c�̓암�͖��t�����Â��Ƃ������Ƃł������A���̏h�͊Â��ɂ��Ă͂��܂芴���܂���ł����B�������A���H���_�C�j���O���[���ł��B���H�̍ő�̓����͏Ă����ł��傤�B�Ă����͊⋛�������ł����B���������ɁA�Ɠ��̕����������Ă����������̂ł����B���̑��ɊC�ہA���炱�A�֎q�̎ςт����A�ق���̂��Z���A���炷�A���Ă��A��̎ϕt�����t���A����Ƀe�[�u���ɂƂ��Ɣ[�����p�ӂ���܂��B�f�ނ��ᖡ������Ƀ��x�������������������̂ł����A��͂�S�̂ɏݖ����g�����̂������_�A����ł��т��i��ł��܂��_����_�ł��傤���B ���āA��p�̃_�C�j���O���[���ł̐H���ł��B�[�H�͏����Ȃ��i�����ƁA��������̒��J�Ȑ���������܂����B�H�O�������蓤���Ƃ����ς�������̂ŁA���蓤���Ē��ɂ��Ĉ�N�Q���������̂������ł��B�܂��������肻�̂��̖̂��ł����������̂ł����B��������������Ƃ������Ƃł��B�����͍ŏ��Ɋ⋛��齁A�R���A�݂��̎����܂�Â��A�Ȃǂ̒n�̂��̂����S�̒�����A�ԑ���I�܁A�g���Ȃǂ̎����������W�߂����M���o����܂��B���ɓg���Ɏ|�݂��Ïk����Ă悩�����Ǝv���܂��B�܂��A�I�܂���{�����ł������A�����������̂ł����B�݂��̎��͖ʔ����H���ŁA�����ŏ��߂ĐH�ׂ��̂Ȃ犴�S����̂ł��傤���A�߂̓��œ���A�����ĐH�ׂĂ������߁A���H���C���ł��ꂪ�����c�O�ł����B�����Ă����肪�ڂ���C�V�Ɗ����Ɠ����A���̂�������ƂĂ����������Ǝv���܂����B����ɁA���o�̍��^���A�͂��͂��̏������Ƒ����܂��B���̂͂��͂��͗��������Ă�����̂ŁA�H�ׂ�Ƃ��肱��Ƃ��Ȃ�傫�ȉ���������̂ł����B���߂ĐH�ׂ܂����B�����̂͂ƂĂ����������Ƃ����Ƃ���܂ł͂����܂��A���̐H���͂��Ȃ胆�j�[�N�Ȋ����ł��B�����āA�H�c���̕����Y�̘a���X�e�[�L�A����͂��Ȃ肢���܂��B�����A�����Ă�������Ƌ}���Ɏ|����������悤�ȋC�����܂����B���A�ɋ߂������ŐH�ׂ������悳�����ł��B���̑��Ɋ`�Y�A���݂����̂��肽��ۓ�A�����Ă��тɂȂ�܂��B������̂��肽��ۓ�������������̂ł��B�f�U�[�g�͉ʕ��̐��荇�킹�ł����A����͏����C���p�N�g�ɂ͌����Ă��������ł����B�S�̓I�ɗ[�H�͒n�̂��̂��g���A�������̍H�v�������邨���������̂ł����B�����A�Ƃє����ĂƂ������̂͏��Ȃ������悤�ȋC�����āA����͎c�O�ł����B��������ɂ��ƏH�c�̓암�͖��t�����Â��Ƃ������Ƃł������A���̏h�͊Â��ɂ��Ă͂��܂芴���܂���ł����B�������A���H���_�C�j���O���[���ł��B���H�̍ő�̓����͏Ă����ł��傤�B�Ă����͊⋛�������ł����B���������ɁA�Ɠ��̕����������Ă����������̂ł����B���̑��ɊC�ہA���炱�A�֎q�̎ςт����A�ق���̂��Z���A���炷�A���Ă��A��̎ϕt�����t���A����Ƀe�[�u���ɂƂ��Ɣ[�����p�ӂ���܂��B�f�ނ��ᖡ������Ƀ��x�������������������̂ł����A��͂�S�̂ɏݖ����g�����̂������_�A����ł��т��i��ł��܂��_����_�ł��傤���B���̗��ق́A�V�[�Y���I�t�̂��̎����ł������͍��~�܂肵�Ă��܂��B�����ݓ��ł��邱�Ƃ��l���Ă��A���̒l�i���Ɗ����Ƃ����������ʂ����܂���B���̓��͂��܂肨�q�����Ȃ������̂��A���̂��Ƃ���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�S�̓I�ȃ��x���͍����Ǝv���܂����A���ɉ�������ꂼ�Ƃ�����тʂ������̂Ƃ������̂�����܂���B�����Ĉ����킯�ł͂Ȃ��̂ł����A�������������ɓ��ݍ���łق����Ƃ�����ۂ������܂����B���オ�菈�̗␅�Ȃǂ̃T�[�r�X���Ȃ����A�A��̉ו��^�т�����܂���ł����B�߂��ɒ߂̓��Ƃ����l�C�̉���h������A����ɂ��̗����őR����ɂ́A�����Ɠw�͂��K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |
| �u���Ă��ȗ�]�v�ւ͒������̊���w����^�N�V�[�łQ�O�����炢�ł��B���܂ŁA�s�������悭�����炸�A���ƂȂ��h�����Ă����̂ł����A����Ȃɍs���₷���Ƃ��낾�Ƃ͎v���܂���ł����B����͗��ٌn�̂łс[����A�u���{�̏h�v�̃L�����y�[�����̏����d����āA�����s�������Ƃ͎v���Ă����u���Ă��ȗ��v�ɏo�����邱�Ƃɂ��܂����B �`�F�b�N�C���͂R���Ȃ̂ł����A�����̓`�łQ�������O�ɂ͏h�ɒ����܂����B���炭�A��ɖʂ������邢���r�[�Ō}���َq�̌I�r㻂Ɛ��������������Ȃ��玞���߂����܂��B�I�r㻂͌I�����̂܂ܓ����Ă���^�C�v�̂��̂ł͂Ȃ��āA���肱��ł�����̂ł����B��i�ȊÂ��̂����������̂ł��B���Ȃ݂ɓ���ڂ͏����߂̂����\���H�ł����B���r�[�̑O�ʂ̒�ɂ͐Ⴊ���悭�ς���A�����̂�����ɂ͎l�\���𒆐S�ɑ����̒����K���悤�ł����B�P�T���قǂ��ĕ����ֈē�����܂����B�|���͂ł��Ă��āA���炭������g�߂Ă����悤�ł��B���̎��̈ē��̒�������͗��������Ă��āA���ɂ������肵�������̐l�ł����B �ē����ꂽ�����́A�H���Ƃ����A�V�قւ̊K�i���オ���������̂Ƃ���ɂ��镔���ł��B�h�A�̉��̕ǂ̏���I�ɓ���̐��l�`�����傱��Ə����Ă��āA���ɂ��镔���������ẮA�V�ق̂��ꂼ��̕����̃h�A�̉��ɏ���I������悤�ł��B�ؖڂ̂����h�A���J����ƍL�����ւƏ�O�����~���ꂽ���ݍ��݂�����܂��B���ݍ��݂��オ���āA���ւ̉E�艡�ɓ�����Ƃ���ɂ͍L�ڂ̃g�C��������A���ɂ͏����Ȏ�ƁA�ǂɐ��Ԃ̓������ԕr�����Ă��܂��B�������V�����[�g�C���ł����B�g�C���̂���ɉE��ɐ��ʂ̃h�A������A�������L�ڂ̐��ʏ��Ő��ʑ�͓����܂��B����ɂ��̐悪���C�ŁA���������������̐F�̗����ł����A��⋷�ڂȈ�ۂ��܂����B���ݍ��݂̉����J����ƁA�P�O��̎厺�ɂȂ�܂��B���̉E��ɓ���̒��ւ��̕����������āA�����Ɏp�����u����ߑ��I������܂��B��p�̒��ւ��̕���������Ƃ���͋v���Ԃ�ł����B�厺�͍���̒I�ɃC���^�[�t�H�����u����A�d��ꂽ��Ɉ�����̏�̏��̊Ԃ�����܂����B���̏��̊Ԃɂ͉Ԃ͂Ȃ��A���F���u����Ă��܂����B�e���r��G�A�R���A���ɂ͔��Α��̉E��̕ǂɖ��ߍ��܂��`�ɔz�u����Ă��邨�����ŁA�\��Ƃ͂����A����ȏ�̍L�������������܂��B�厺�̂���ɐ�ɂ͎l����̍L��������A�@�育�����@���Ă��܂��B�L���͈�ʂ̃K���X���ŁA�J�[�e���E�H�[������������悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̊O�ɂ͂��̕����p�Ƃ��������̑傫�Ȋ�Ƃ���ɑg�ݍ��킳�ꂽ��Ԕ��قǂ̊_�����z�u����Ă��āA����ɂ͐Ⴊ�ς���A�����ɓ����ĊO�߂Ă���ƁA�܂������Â��Ȏ����߂��Ă����܂��B��ɂ͎����������`�����A�����𑖂�Ԃ̉e����u�����܂����A�`�����݂͂Ȃ����ɗ��������܂��B�S�̓I�ɐ\�����Ȃ������ł����A�S�łȂ��̂��A��⊦���A�g�[�����Ɋ���������C�������t���Ă��銴���Ȃ̂��C�ɂȂ�܂����B�܂��A�e�B�b�V�������ʏ������ŁA�����ɂȂ������̂��s�ւł��B�����A���ʏ��̃P�[�X����{�b�N�X�����O���ĕ����Ɏ����Ă��Ă�������A�����̑|���̌�͕����̃{�b�N�X�͂��̂܂܂ŁA���ʂ̃P�[�X�̒��ɂ��V�����e�B�b�V���{�b�N�X��������Ă��܂����B���߂͕z�c��~���Ƃ��ɐV�������̂��ꖇ��[����܂��B�ē����̃T�C�Y�̋C�����͂���A����͂����Ɠ���ڂɂ��\�����肳��Ă��܂����B�܂��A�o�X�^�I���͈�l�ɂ��O������܂����B�����ɓ����Ă���̉��߂Ă̂����o���͂���܂���B |
| �����C�̓t�����g���班���������Ƃ���ɒj��������ňʒu���A�[�H�̎��ԑтɒj����ւɂȂ�܂��B�I�V�����ꂼ��ɂ��Ă��܂����A�����A�ŏ��ɒj���p�̂����C�̕��͑嗁�ꂩ��o��^�C�v�A������́A�ŏ������p�̕��͒E�ߏ�����嗁��A�I�V�ƕʁX�̌���ʂ��ďo��`�ɂȂ��Ă��܂��B�嗁����I�V���ŏ��j���p�̕����傫�߂ŁA���ꂼ�ꏬ���ꂢ�Ȋ����ő傫�ȑ�������Ă��܂����A���ɂ���Ƃ����������͊������܂���B�嗁��͑傫�����͓���ڂɂ͗����̊O�ɂ��������ӂ�o�Ă��܂������A�����͂��ӂ�o���͂Ȃ������C�����܂��B���ߏ����p�̕��͓���Ƃ�����o��������܂���ł����B�t�ɘI�V�͍ŏ��j���p�͊╗�C�ŁA����o�����Ȃ��^�C�v�̂悤�ł����B���̃^�C�v�Ɋւ��ẮA�ĂȂǒ���t���ς��O�ɏo�čs���Ȃ��̂ł́H�@�ƁA�����^��Ɏv���Ă��܂��܂��B���ߏ����̕��̘I�V�͕O�̂����C�ŁA������͓������Ƃ���ɗ����̉����炨���������悭���ӂ�o���܂��B�����A������͎l�l����Ƃ��Ȃ肫�����������܂��B�╗�C�̕��͂U�l���炢�͑��v�ł��傤�B�����̘I�V�Ƃ������ʒu�ɂ�����Ɉ͂܂�Ă��Č����炵�͂���܂��A��ɂ�����x�̃X�y�[�X�����邽�߂���قNj����Ȋ����͂��܂���B�╗�C�̕��͓��D�ɂ���Ȃ������߂��܂����A��͏����̎��ԑтɂȂ��Ă��܂��܂��B�Ƃ������Ƃł����͗�������ł͂Ȃ��z�A���z�Ǝv���܂����A���f�L�͂܂���������܂���B�܂��A���̉Ԃ͂Ȃ��A�����͂��ʂ���Ƃ��銴���̂��̂ł����B��₵����ς��C�����܂����A�������̂ł͂Ȃ��ق�̂킸���Ƃ����Ƃ���ł��B�����͓������I�V���ڂ��ɂƂ��čœK�̉��x�ŋC�����悭����܂����B����̑O�̒j���̒g���̂��������Ƃ���ɁA�����̓������␅�@���u����Ă��܂������A����ڂ̒������ɂ͓����Ă��炸�A��̂P�O�����ɂ͂�����ɂȂ��Ă��ė��������̂܂܂ł����B�S�̂ɐS�z��̍s���͂��Ă���h�Ȃ̂ŁA���̕ӂ̎蔲����͂�����Ƃ������Ƃł�����������ۂ��������Ă��܂��A�ɂ������������܂��B |
| �H���͈�K�̐H�����ł��������܂��B���ꂼ�ꂪ���ɂȂ��Ă��āA���̋q�̎p�����Ȃ���H��������Ƃ������Ƃ͂���܂���B�A�������̂ł����A���������K���j���[�̓��̂悤�ł��B���̓��͂����ƁA�u�@���̂������v�Ƃ������i���������Ă��܂����B�S�̓I�ɋᖡ���ꂽ���̂��Ǝv���܂��B���ł�����̍��̑�a�ς͔��ɏ_�炩���A�݂Ƃ̎�荇�킹�����Ƃ���������i�ŁA����͂����̖����������Ƃ������Ƃł����B�����炭�����o�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���N�G�X�g����ƁA�A���̏ꍇ�A���̓����H�ׂ���Ƃ������Ƃł����B�܂��A��t���̂���������̂���Ƃ����H�������ɂ悭�āA���܂łɐH�ׂ����Ƃ̂Ȃ������̂��̂ł��B�H�O���͓���Ƃ��~���ŁA�H���̑O�ɔ~���z�����o����A��𐮂���Ƃ����̂��ς��������ł��B������͏����̐��K���j���[����̐ɂ��炷�݂������̂Ǝh�g����ɂႭ��|���X�ł����������̂ŁA���Ȃ�Â��Ă��܂����A���̂��炷���݂͂���قnj��ʂ��Ă���Ƃ͎v���܂���ł����B�������܂����Ƃ������Ƃ͂���܂���B������́A����ڂ͍g���Ɣn�h���ɕς��A����͔��ɂ��������Ǝv���܂��B���ɁA�n�h���͏㓙�Ȃ��̂ł����B�Ƃ������ƂŎh�g�͓���ڂ̕����ǂ������ł��ˁB�����̐|�̕��͏t�̎R�ɕ����X�����Ă����������̂ŁA�t�̍�����y���߂܂����B��̂��̂��D���Ȑl�ɂ͂��ꂵ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����Ɛ�ɂȂ�ƁA����ɎR�̎�ނ�������Ƃ������Ƃł����B���ɂ͕S�����ɂ݂�����Q���������������A�喐�̗M�q���̏Ă����A�C�V���̎ϕ��Ȃǂ����сA���ꂼ�ꂪ�����������̂ł��B���т͎R�����Ђ��ŁA���̕����������肵���A���ɍ������̂ł����B�f�U�[�g�̓C�`�S�̃V���[�x�b�g����̂Ƃ������̂ŁA�����ł��܂��B�^�ԃy�[�X�����悢���̂ŁA�S���ňꎞ�Ԕ��͂䂤�ɂ�����܂��B����ɕ����֖߂�ƁA��H�̂��Ύ��i���①�ɂɗp�ӂ���Ă��܂��B�H������V�ɂ͂��������܂���ˁB ���H�͂�͂�H�����ł����A���Ƃ͂��������Ɉē�����܂����B�������т��A�������I���ł��܂��B�Ă����͉��̋����������Y��Ă��܂��܂������A��銱�������ɂ����������̂ł��B���͉��ŏo�`���ݖ��x�[�X�̂��̂ł͂Ȃ��A�����Ƃ����̂����������̂ł����B�Е������ς�炸���������`���͑卪�ƈ��̏`�œؓ��������ĂƂĂ����R�ł��B���炩�炨�o�ɂ������ē����̂ł����A��l�ʼn��t��������{�����[�������Ղ�Ȃ��̂ł����B���̑��ق���ɂƂ�덩�z�����������́A�����̒ώρA�Ȃǎ�ނ����������悭�A���ɏ[�����������x�̍������H�Ƃ����܂��B�l�I�ɂ́A�W���[�X��f�U�[�g������ƍō��������̂ł����A�~���肷���ł��傤���B�H��ɖ������R�[�q�[�A�g���̃T�[�r�X������܂��B ����ڂ̗[�H�͂܂������ς��܂����B�����悤�ɔ~���z���Ɣ~���̐H�O�����o����܂��B����ڂ͓畨�Ɖ��̂ǂ��炩���I�ׂ�Ƃ������Ƃł������A��͂����H�ׂĂ݂����Ƃ������Ƃʼn���I�����܂����B���i�����͂���܂��A�����͂��킵�����Ă���܂��B�������̓����C���̎��Ɉē����Ă��ꂽ�������肵���������S�����Ă���܂����B�O�̘Z��͍�����p���[���������C�����܂������A��t���̌ӓ������͂����������̂ł��B���t�̂���Ԃ���Ԃ��e�[�u���ʼn��g�����̂Ƃ��ďo����܂������A�ɂ��������̂�̗���ׂ������ɓ��t���L���Ȃ������ĐH�ׂ�Ƃ�������ł��B�w���V�[�ł����A���t�̗ʂ�����قǑ����Ȃ��A����Ƃ����C���p�N�g�͂���܂���B���t�����A���ׂ��������ǂ�̂悤�ȁA�����Ƃ���ɂႭ���g�����Ƃ�����������A���������Ǝv���܂����B�����܂��͊��̂��˂̓����������̂�����̂ł����B������͐�ɏq�ׂ����̂ŏ\���ɖ����ł��܂��B���ƁA������������i�o����܂������A���܂�C���p�N�g���Ȃ������̂��A�ʐ^�����Ă��v���o���܂���B���͑傫�Ȋ⋛�̉����Ă��B��l�ň���̊��蓖�Ăł����A���Ȃ�傫�Ȋ⋛�Ȃ̂ŁA�ʓI�ɕs���͂���܂���B�⋛�͂��ꂱ���S��ȏ�H�ׂ��Ǝv���܂����A�����ɂȂ������̂͏��߂Ăł����B�ق��ق����Ă��������̂ł����A�����悭���Ƃ��Ȃ��ƁA��������������ς��Ȃ��Ă��܂��܂��B���Ōł߂�Ƃ����Â����������Ă��܂����A���ʓI�ɂ͋��Ă��̕�����₨���������ȂƂ�����ۂ������܂����B�|�̕��͖����g�����T���_�ŁA������̓{�����[�������Ղ�ł��B���̑��A�����n�̏Ă����͂��܂�C���p�N�g������܂���B�܂��A�R�̓V�n�����o����܂����B�������A���̓V�n���͂ǂ������킯�������Ă܂����͂���܂��A����قǂ̊����͊������܂���ł����B���т́A�Ƃ�낲�͂�ŁA�Ƃ��͔��ɂ����Ղ�Ƃ������̂ł����A�����`���ڂ��ɂƂ��Ă͊Â߂ŁA�Ƃ���D���Ȃڂ��Ƃ��Ă͖������͍��ЂƂƂ����Ƃ���ł��B�f�U�[�g�͂�A���A�C�`�S�A�������̃t���[�c���荇�킹�ł����B�S�̓I�Ɉ����͂Ȃ��̂ł����A��͂��ӂƔ�ׂ�ƃ{���e�[�W���������Ă��܂��B�܂��A���̓����①�ɂɍ���Ƃ͂����������Ύ��i���p�ӂ���Ă��܂����B �ڂ̒��H�͍��̗[�H�Ɠ������ł����B�܂��������I�����܂����B�����ƌ��������A���͐����܂���ł������A������͕i�������Ȃ���ۂ��܂����B���C���͓������ŁA�����ȊO�̖�̋�������Ƃ�����Ă���{�i�I�Ȃ��̂ł��B�������͂悭���H�ɏo����܂��������܂Ŗ{�i�I�Ȃ��͍̂��܂łɂȂ������C�����܂��B���̂ق��ɁA�����������ڂ��A��������g�������́A�_�炩�߂̂��ܗg���A�⋛�̈�銱���A�Ƃ��A��̎ϕ��Ȃǂł����B�������ď����Ă݂�Ƃ��������i���͂���܂��ˁB���̓��͂����̖��X�`�ŁA��͂肽���Ղ肠��܂��B�⋛�̈�銱���͂�͂�A�ƂĂ������������̂ł������A�S�̂̃o�����X�₻�ꂼ��̕i�ɂ��ẮA��͂����ڂ̒��H�̕����]���ł��܂��B ���̏h�͈ē��̒������������肵�Ă������Ƃ����߁A�]�ƈ��S���ɋ��炪�s���͂��Ă���Ƃ�����ۂ��܂����B�����A�Ⴂ�l�ȂǗ����̓��e������ł��Ȃ��Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�����܂������A�����ƕ����Ă��āA���̌サ������t�H���[���Ă��܂����B�S�̓I�ɕs���͂Ȃ��̂ł����A�������悤�ɁA�����̔�����������Ă����̂��ӊO�Ŏc�O�Ɏv�������ƁA�����̒g�[�̕����Q�Ă���z�c�����邱�Ƃ��l���Ăق������ƂȂǂ�����܂����B�܂��A�H�������������̂ł����A�H�I������Ƃ��̃g�[�^���Ƃ��Ă̖������ɂ�⌇����C�����܂����B����́A���邢�͎R�▐�Ȃǂ̑f�ނɑ����̕肪�������邹����������܂���B�܂��A��������͂�����������ڂ̐H���̃p���[��������h�Ƃ�����ۂ��ʂ����܂���B�A�E�g�͂������^�N�V�[�܂ʼnו����^��ł���A���̏]�ƈ��Əh�̂���l�����J�Ɍ������Ă���܂����B |
| ����̐V�����s�̃��C���͉���˂ŁA���n����ƐV�䍂����Ȃ̂ł����A�����Ȃ肱���ɍs�������A���̑O���ɏ��{�Ɉꔑ���悤�Ƃ������ƂőI�̂��A�i�s�a�̕]��������قLj����Ȃ����̏h�ł����B���{�����ԉ���s���̃o�X�ɏ��A�P���P�T�����ɏ����ꂢ�Ȋ����̏h�ɓ������܂����B�{���͂R���̃C���炵���̂ł����A�����͂i�s�a�̊��łQ���̃C���ɂȂ��Ă��܂����B������܂肵�����r�[�ŁA���Β��Ƃ������\���Ƃ����̂��o����A�����̏������ł���܂łƂ������Ƃł��炭�҂�����܂����B���̂Ƃ��Ή����Ă��ꂽ�̂͏����������悤�ł��B���炭�҂��āA�P���R�O�����ɕ����Ɉē�����܂����B �����͂T�O�R�����ł����B�h�A���J����ƁA�����̓��ݍ��݂̐��ʂɒI������A���킢�炵���t�����������Ă��܂����B���ݍ��݂́A�E�̃h�A���J����ƍL�߂̐��ʎ��ɂȂ�܂��B���ʑ�ƌ��������`�ɁA�h�A������A�J����ƃV�����[�g�C���Ƃ��̉��Ƀo�X�^�u������܂����B�������͍̂L���������Ƃ��Ă���̂ŁA�ꉞ�z�e���`���Ȃ̂ł����A�o�X�^�u�Ƃ�����藁���Ƃ��������ŏ������A���j�b�g�o�X�ɋ߂��`�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B���ʂ��o�āA���ݍ��݂̍��̉����J���ĂU��̎��̊Ԃɓ���܂��B���̊Ԃ̐悪�O�~�~���̂S������̍L���ɂȂ��Ă��Ĉ֎q���u����Ă��܂��B���̊ԂƍL���ɕ��Ԍ`�ŗׂɂW��̎厺������܂��B�厺�̑��ƌ������������ǂɏ��̊Ԃ�����A�Ԃ��������Ă��܂����B����ɂ��܂荂���r���͂Ȃ��A�܊K����ł����������낷�����ʼn����܂Ō��n���܂��B�������猩�グ�銴���ɂȂ�̂ł����A���̋߂��Ɋ��Ə����`�����݂͂���܂��B�����͐V�����A���̊Ԃ̕ǂ�A�厺�̑��̉��ɂ͒I�̂悤�Ȃ��̂��߂��炳��Ă��āA�E���i�ɂȂ�̂�h���ł��܂��B���߂̋C�Â����͂���A�܂����߂̑��ɍ얱�߂�����܂��B�얱�߂̓S���̓��������₷�����̂ł����B�܂��A���ɂ͒������̕t�����J�M�̂������������ȋ��ɂ��l�g�ݍ��킳�����^�C�v�̂��̂ŁA�F�B���m�ł̏h���Ȃǂɂ͂����Ǝv���܂����B |
| �����C�͑嗁�ꂪ�j���ʂɂ��ꂼ�����ƁA�嗁�ꂩ��o��`�̘I�V����͂������Ă���Ƃ�����ʓI�Ȍ`�ł��B�����͒j���̌�ւ͂���܂���B�����炭�j���Ƃ��܂����������悤�ȍ��Ȃ̂��Ǝv���܂��B�����͑|���̎��Ԃ������āA�Q�S����OK�Ƃ������Ƃł����B�o�X�^�I���͒E�ߏ�ɂ��u����Ă��܂����B�嗁��͖��邭�Đ����Ȋ����ŁA�D�Y�Ό��ƓD�Y�V�����v�[���������Ă��܂��B�V�F�[�r���O�t�H�[��������A����͌������Ƃ���܂���B�I�V�͒����`�ؘ̖g�̂����C�łS�E�T�l���炢�����ꂻ���ȍL���ł��B�����̏�ɂ͉���������A�������������͂܂�Ă��܂�����A���]�Ȃǂ͂܂���������܂���B�����͓K���ŁA����̓����������A���̉Ԃ��Ȃ��A���ɂ����ɓ����͂Ȃ��������܂������A�����͂ق�������邵�Ă��܂����B�����C�͌������肩�����z���Ƃ����Ƃ���ł͂Ȃ��ł��傤���B��̎��̂�����������g�p���Ă���Ƃ������Ƃł����B�����A�����ɂ͂��̂悤�ȕ\�����Ȃ������̂ŁA�����̂����C�͉���ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B����菈�ɂ͉������Ƃ����W���[�X�����ł����߂�悤�ɒu����Ă��܂��B�W���[�X�ނȂǂ�u���Ă���Ƃ���́A��͈������߂��肷��Ƃ���������̂ł����A�����͈�������߂�悤�ł��B�嗁��̂ق��ɉƑ����C���O����A��������ň���L���ɂȂ��Ă��܂��B�h���q�͖����̈�Ɋm���A��������Ƃ������Ƃ������Ǝv���܂��B���̖����̉Ƒ����C�͂T�K�ɂ���A�I�V�Œ��߂��������̂ł��B�܂��A�L���������Ƃ��Ă��āA��g�ꎞ�Ԃ܂łƂ������ƂȂ̂ŁA���Ƃ����������Ă����܂��B |
| �H���͌��̐H�����ŁA���i����������A������������̂ł����B��i���̉��Η����ŁA�H�O���͂����A��t�������q�����A�O�͊Ñ�̗M�q�ĂȂǘZ��ށA�z�����������̓y�r�����A�����肪��⋛�̂������Ƃ������́A���̑����Ȃ����g������������A�������̎�ł����A�M�q���A��F�c�y�Ȃǂ�������o����܂��B���C���Ɉʒu�Â����銴���ŁA�M�B���̂���Ԃ���Ԃ�����܂����B�e�[�u�����̂ɓd�������킪�g�ݍ��܂�Ă���悤�ŁA�����e�[�u���̏�ɂ����ɂ����u���������ł������������Ă��܂����B���т́A�����тŁA����͏����ł͂Ȃ��V���W�ł����B�f�U�[�g�̂Ԃǂ����[�X�ŏI���ł��B�S�̓I�ɐ�������Ă��Ă��������[�H���Ǝv���܂��B�����A��͂�A�������тʂ���Ƃ������̂͂Ȃ������C�����܂����B ���H���[�H�ƑS�������ꏊ�ł��������܂����B�n���̗L�@�����g��������C�ۂ̂����ʓI�Ȓ���H�ł����A�������т̑��ɂ����̎��̓�������V�̒�������t�t������A�T�[�����̎h�g����������A�������͎����łɂ�������Ă��������č������ƁA�ق�̂�����ƕω������Ă����ۂ��܂����B�u���[�x���[���[�O���g�̃f�U�[�g������A�S�̓I�Ɏ蔲���̂Ȃ��o�����X�̂Ƃꂽ���̂ŁA�]���ł��钩�H�������ƌ����܂��B ���́u�ʂ̓��v�̑傫�ȓ����́A�[�H��Ɂu�ԍ��v�Ƃ��������Ŗ��ӂ̂悤�Ƀ~�j�R���T�[�g���J�����Ƃ������ƂŁA���̖���n�[�v�i����Ă̓Ɠ��ȃn�[�v�j�̉��t������܂����B�܂����A�c�͕̂����ɗ��Ȃ����낤�Ǝv���Ă����̂ł����A�c�̂������ɗ��Ė����̑吷���ɂȂ�A��������������ƕ��͋C���Ⴄ�Ƃ����Ă��܂������A����Ȃ�ɐ���オ��܂����B���i�͂����Ƃ������蒮�����͋C�ɂȂ�̂ł��傤�B�~�j�R���T�[�g�Ƃ͂����ꎞ�Ԕ����炢�̎��Ԃ�����čs���܂��B���y�̍D���Ȑl�ɂ͂�����������܂���B�����̎�l�̓t�����g�ɂ���Ƃ��͈��z�������̂ł����A�R���T�[�g�̓r���̃A�g���N�V�����ɉ̎�Ƃ��ďo�������Ƃ��͕ʐl�̂悤�Ȋ����ŁA���̈��z�̂Ȃ���l���Ƃ͂܂������C�Â��܂���ł����B�S�̓I�Ɉ�ۂ͂����̂ł����A����������قǂ͈����͂���܂���B�S�̂̃o�����X�͔��Ɏ��Ă����ۂȂ̂ŁA�����ӂ���������������ł��܂������Ǝv���܂����A�t�ɓ��ɂ���Ƃ����ˏo�������̂��Ȃ��̂ŁA������ƂƂ����l�����邩������܂���B���̕ӂ̌��ˍ�����������Ɋ����܂����B�@ |
| �@ |
| �ʂ̓����`�F�b�N�A�E�g���܂����B���{����o�X�ł��悢��ړI�n�̉���˂������܂��B�ȑO���炸���ƁA�����ւ̓g�����[�o�X�Ƃ��P�[�u���J�[�Ȃǂɉ������芷���Ȃ���s���Ȃ��Ǝv������ł��܂����B�������̂Ƃ���Ƃ̊��Ⴂ�������̂ł��傤���B�e���r�̉���ԑg�ŏ��{���璼�s�̃o�X���o�Ă��邱�Ƃ�m��A�܂��A���̓r���ɓ����悤�ɉۑ肾�����u���n����v��ʂ邱�Ƃ�m��A���̓�̉����V�����s�̒n�ƌ��߂��̂ł����B �m���A�o�X�̏��v���Ԃ͓Ԃ�������Ȃ������Ǝv���܂��B�ʂ��Ă݂����������[�g���l�����āA�o�X�͉���˂̒n�ɒ����܂����B�����ƎR���̊����Ŏ��͉͂����Ȃ��Ƃ��납�Ǝv���Ă����̂ł����A����ȂɎR���ł͂Ȃ��Ƃ��������ňӊO�ł����B���ʃo�X������Ƃ͂����A���͏��Ȃ��̂Ńo�X��ɒ������̂͂P�Q���S�T�����ł����B�C���̎��Ԃ͂Q���ŁA�ǂ����Œ��H����낤�Ǝv�����̂ł����A�ڂ��������~�肽�A�����قɋ߂��Ƀo�X��̋ߕӂɂ͂܂���������炵���X������܂���B�Ƃ肠�������قɉו���u�����Ƃ������ƂɌ��߂܂����B�����قɂ͕����Ă��s����炵���̂ł����A���J���~���Ă��ĉו�������Ƃ������ƂŁA���Ԃ͑����̂ł����d�b���Č}���ɗ��Ă���邩�������Ƃɂ��܂����B�A������Ƃ����}���ɗ��Ă��ꂽ�̂ŏ�����܂����B�����قɂ͒��H��H�ׂ�Ƃ���͂Ȃ��A���r�[�Ŕ����Ă��鉷�Ȃǂ�H�ׂāA���ǂ��ꂪ���H����ɂȂ��Ă��܂��܂����B���r�[�ɂ͈͘F���̕���������A���̈͘F���[�ŕS�����Ə����Ȃ��\�������������܂����B�R�O�����炢�o��������ł��傤���B�����������ֈē����Ă���܂����B�����̂͂����肵���A�������肵����ۂ��钇������ł����B�����ɂ́A�܂��}���َq�̖��`�Ƃ������َq��A�����z�A���~�Ȃǂ��u����Ă��܂����B �����͖{�ق̂Q�P�Q�����Łu�}���x�v�ƌĂ�镔���ł��B�h�A���J���A�����̓��ݍ��݂ɏオ���Ă����������ʏ��ɂȂ��Ă��܂��B���ʏ��̉��̃h�A���g�C���ŁA�V�����[�g�C���ł����B���ʏ��̌���g�C���ɂ͑������Ă��ĊO�̖��邳�������Ă��܂��B���ݍ��݂��瓪���Ԃ��Ȃ��悤�Ɉ�i�オ��ƁA���ʂɎl����̔̊Ԃ������Ē��Δ����u����A���̒��ɒY���p�ӂ���Ă��܂����B���_������悤�Ő������̂悤�Ȃ��̂��u����Ă��܂������A�ʓ|�������̂ƁA��Ȃ��̂Ƃʼn͓_���܂���ł����B���̔̊Ԃ̍����ɏ����ȑ�������A�E���̘a���ɂ͂܂����������Ȃ��̂ŁA���ǁA���͂����ƁA���ʏ��ƃg�C���ɂ��邾���ł��B���̏����ȕ����ŁA���܂肢�������ł͂Ȃ��̂��Ǝv���܂������A���͂��̑����瑄���x��]�ނ��Ƃ��ł���̂ł����B�h�̖��������قƂ͂����A�����瑄���x��]�ނ��Ƃ��ł��镔���͏��Ȃ��炵���A�����x��������ƌ����_�ł́A�ǂ��������͂��������������炵���̂ł��B���̑�����̔`�����݂͂قƂ�ǂȂ��A�����̓��H���炿����ƌ����邩�Ȓ��x�ł��傤���B�̊Ԃ̉E��Ɏ厺�ƂȂ�\��̏�̊Ԃ��ʒu���Ă��܂��B�^�ɑ傫�Ȋۑ��̗����ʂ���Ă��āA���̗��͉E���������Ԃ�Ⴍ�Ȃ��Ă��āA�C�����Ȃ��Ɠ����Ԃ���̂ŁA�\�����ӂ��Ă��������ƒ�������Ɍ����܂����B�ǂ����A��������͂������������Ԃ����o��������悤�ł��B�K���ɑ؍ݒ��ɓ����Ԃ��邱�Ƃ͂���܂���ł����B�\��̊Ԃ̈�ԉ��Ɉ��~����̏����ȏ��̊Ԃ�����A�Ԃ��������Ă��܂����B���������Ƃɗ����͂��̉Ԃ͑ウ���Ă��āA���܂łɉ�����A�����܂������A�Ԃ��������̂͏��߂Ăł͂Ȃ������ł��傤���B���邢�́A�ׂ̕����̂��̂Ƒウ��������������܂��A���̂�����Ƃ����S���������ł����ꂵ���Ǝv���܂����B�����͌Ö��Ƃ��ڒz�������_�ɉ��������Ƃ��������̂�����̂ŁA���|���ł���Ȃ�������_���Ȋ��������܂��B�G�A�R���͓V�䖄�ߍ��^�̂��̂ʼn��̐Â��Ȃ��ƂƁA���R�Ȓg�����͔��ɍD�������Ă܂����B�����S�̓I�ɂ݂�A�S�̂̍L��������قǂł͂Ȃ��A���ɔ�тʂ��Ă��炵���Ƃ����قǂ̕����ł͂���܂���B |
| �����C�̐��͑����j���ʂ̓�������ƁA�j���ʂ̘I�V����A�����̘I�V����ɑ݂���̘I�V���l�Ƃ������C���i�b�v�ł��B�j���̓���ւ��͂Ȃ����|���Ԃ������ĂQ�S���ԓ���OK�ł��B�����ɂ���ĈႤ�̂�������܂��A���̎��͘I�V�͂�≷�߂ł����B�嗁��͓����������A�傫�����͂�≷�߂ŁA���������͂��M�߂Ƃ������Ƃ���ł����B���ׂČ�������Ǝv���܂��B���̉Ԃ͂Ȃ��A����̓������قƂ�ǂ��܂���ł����B �嗁��͒E�ߏ������������ӂ�Ɏg������ۂ̂������̂ŁA�傫�ȃK���X����ʎ���Ă��Ė��邢��ۂ��܂����B��͎͂l���炢�̏����߂̗����ł����A�������������ċC�����������Ǝv���܂����B�嗁��͌����̒��ɂ���̂ł����A�I�V�͂��ׂāA�嗁��̓�����̂����肩��ʘH��ʂ��ĊO�ɏo��`�ɂȂ��Ă��܂��B���ɉ����Ă���������ł��āA�ŏ��ɂ��鑄���̓����j�������ň�Ԍi�F���悭�A�悭�A�G����e���r�Ȃǂ̎�ނɏo�Ă���I�V�ł��B�J�����͔��Q�ŁA�Ō�̓��͐�̉��ɓ���`�����������x�̕���]�ނ��Ƃ��ł��܂����B�͌��͂��܂萅�ʂ͂Ȃ��A�傫�Ȑ����낲��Ɠ]�����Ă��Čk���Ƃ��������ł͂���܂���B�܂��A���̎��͓���Ƃ������͂ʂ�߂ŁA�����Ă���o��܂Ō��܂ł����ɂ����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ���Ԃł����B�ƌ����Ă��A��������オ�����r�[�ɁA�Ԃ���Ɗ����Ƃ����Ƃ���܂ł͍s���܂���B�����Ƒ͉̂��܂��Ă��܂��B �݂���̘I�V�͎l����A������Ɋ|�����D�ŁA���łɒN���������Ă��邩���Ȃ���������������ł����B�݂���ɂ͑�̃J�M�͂����āA�|���邱�Ƃ͂ł���̂ł����A�Ȃ����J�M�̂Ȃ��Ƃ��������܂����B |
| �����̗[�H�͈�K�̑啔���̐H���ǂ���ł����B���i����������܂����A�Ⴂ�j���]�ƈ��̔��ɂĂ��˂��Ȑ���������܂��B�A���̗����̂����A�������{���̗����Ƃ̂��Ƃł����B�H�O���͎R�Ԃǂ����Ő�t���E���t�����A�m�i�V�̐��n�������A�I���̋e�Ԙa���A��ˋ��̎h�g�̎O�_�ł��B�����Ƃ��đ�M�ɎR�𒆐S�Ƃ������̂��A�����ۂݒ��x�̑傫���̗e��ɓ�A���ƍ����g�������i�A�������g������i�������A��l�ł��ꂼ��̂��M�Ɏ�蕪����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�����āA�⋛�̓y�r�����ɉ�������܂��B�ォ��A�ӂ�ӂ����A�⋛�̉��Ă��A���q�����̂悤�Ȋ����̂Ȃ߂��̐����A�g�����Ƃ��āA�C�V���A�a��I�A��ǂ��o����A���C���̔�ˋ��̂����Ă��ɂȂ�܂��B��������ˋ��̂����Ă����������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A�C�V���̓V�n���͐�i�ł����B�⋛�̉��Ă��͂ق�̏������������c���������ł��B�f�U�[�g�͊`�V���[�x�b�g�ł����B�S�̓I�ɍH�v���������闿���Ŕ��ɂ��������Ǝv���܂����B�������͈�N���O����Ƃ̂��Ƃł����̂ŁA����ȑO�ɍs�����l�͂�����x�s���Ă݂Ă�������������܂���B�铒������̏h�̒��ł͗����͂��Ȃ肨���������ɓ���܂��B�ʂ��猾���Ă��A�S�̓I�Ƀo�����X���悭�Ƃ�Ă���Ɗ����܂����B���̌�A�����ɖ߂�Ɩ�H�Ƃ��āA�����̗t�ɕ�܂ꂽ�ő����т��p�ӂ���Ă��܂����B ����ڂ̗[�H�́A����ڂ̑啔���̐H�������班���s�������̐H�����ɂȂ�܂����B�A���p�̌����̏�ł��i�����͂���܂���B�H���̐��b�͍���Ɠ����Ⴂ�j���̏]�ƈ��ł�͂蒚�J�ȉ��ł����B�ǂ����A�j���̏]�ƈ��͂܂��������z�̂Ȃ��p�^�[���ƁA���J�ȃp�^�[���̗��ɒ[�ɕ������悤�ȋC�����܂��B�H�O���̓��������ɕς��A�O�Ƃ��ĕP�|�A�����卪�A�Ȃ��̗t�A�o���������A�����Ԃ����A��͂��蕪������悤�ɑ�M�ŏo����Ă��܂��B���̓��́A������Ƃ��ă}�O���A�J���p�`�A�����̂������Ȃǂ̋�������܂����B�n�{�̓�����ɉ�������A�ォ��A�⋛�̗g�����̂����A���t�Ƒ��̒��q�������^��Ă��܂��B���̓��̃��C���͔�ˋ��̖p�t�Ă��ŁA����̂����Ă��Ɠ��l�����������̂ł����B�f�U�[�g�͂������A�`�A�Ȃ��Ƃ����ʕ��̐��荇�킹�ł��B���̓��̗������\�������������̂Ȃ̂ł����A�i������⏭�Ȃ��Ƃ�����ۂł��B�ƌ����Ă����\���Ȃ���t�ɂ͂Ȃ�̂ł����B���̓��̖�H�͉����ȂƎv���ĕ����ɖ߂�ƁA�c�O�Ȃ��炱�̓��͖�H�͂���܂���ł����B ���H�͂��ꂼ��̗[�H�Ɠ����Ƃ���ŁA����ڂ͑啔���A����ڂ͌��ł����B����ڂ̒��H�͉��͂�����̂̊C�ۂ�[���͂Ȃ��A��ʓI�Ȓ���H�Ƃ͂ق�̂�����ƈႤ���������܂����B���傤�䖡�ŐH�ׂ�������̂ł͂Ȃ����H�ł��B���͈��̊J���ŁA���̑��p�t���X���Ă������́A�R�̌Ӗ��a���A���铤���A���Ƃ�����ǂ��̎ϕ������ׂ��A�ɂ͑��Ŗ��X�`���|�����Ă��܂��B�S�̓I�Ƀo�����X�����Ă��Ă��������A�蔲���̂Ȃ����H�Ɗ����܂����B�������ƈǐm�����̃f�U�[�g����A�g�}�g�W���[�X����Ƃڂ��Ƃ��Ă͐\�����̂Ȃ����H�ł����B ����ڂ̒��H������ڂƓ��l�o�����X�̎�ꂽ�H���ŁA��͂薞���ł��܂����B�g�}�g�W���[�X�͂����W���[�X�ɕς��A����͂��Ȃ�Â����̂ł����B�����Ԃ��A���Ă��A�p�t�o�^�[���X�Ă��A���̂����̏����A���̋����������A������̊J��������܂��B�Е��������������̂ł��B�f�U�[�g�̓��b�h�O���[�v�t���[�c�ƃL�E�C�̐��荇�킹�ł����B �ē��̒�������͏ڂ����I�m�ŁA�H���W�̒j���ׂ͍₩�A����ڂ͉Ԃ��ウ���Ă����ȂǁA�铒�̏h�ɂ��Ă͍s���͂��Ă��đ@�ׂƂ�����ۂ������܂����B�����C�͋G�߂̊W������炵���A���͑S�̓I�ɉ��߂Ȃ̂��ڂ��Ƃ��Ă͎c�O�ȂƂ���ł��B���ق̏]�ƈ��ɂ��ƁA�Ă͔M�߂������Ƃ������ƂȂ̂ŁA��Ԃ��������Ƃ����͈̂ĊO����̂����m��܂���B�����͂��ׂĂ��ō���Ă��Đ��X�����A�����͌Ö��Ƃ����㕗�ɍ�蒼�����Ƃ������ƂŁA�������������z�E�����̐��̌��z�Ƃ�����悤�ł����A�Â��Ƃ����܂��������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̕��������Ă݂������������܂����B |
| �@ |
| �V�����s���A���悢��ŏI�ړI�n�ƂȂ�܂����B�����ق��o�āA�V�䍂���[�v�E�F�[�ʼn����̖k�A���v�X�̎R�X���y���݁A���̏h���ꏊ�̕��n����u���������v�������܂����B���n����͐���s���Ă݂�������n�������̂ł����A��͂�V�䍂�Ɠ������R�ōs���ɂ����Ǝv���Ă����̂ł��B����A�V�䍂�ׂ�ɓ������ēr���̃o�X��ɕ��n�����邱�Ƃ��m�F���āA���̑g�ݍ��킹�ɂ����̂ł����B �����̓`�F�b�N�C�����ԑO�ɓ������āA�������Ɖ߂����̂ł����A�������ɂ��̓��͐V�䍂���[�v�E�F�[�ɏ�������߁A���n������̃o�X��ɒ������̂�2������ɂȂ�܂����B����ł��C���̎��ԂƓ��������炢�ɂ̓o�X��ɒ�������ł��B�h�ɓd�b������Ƃ������Ă���܂����B���������͉���X�̈�Ԏ�O�Ɉʒu���Ă���h�̂悤�ł��B���i�����������錺�ւ��烍�r�[�ɓ���ƁA�����ɕ����Ɉē�����܂����B�ē����ꂽ�����͂����тƂ��������ŁA�t�����g�̂����߂���������ɏオ�����Ƃ���Ɉʒu���镔���ł��B�a���̃h�A���J���A�オ��Ƃ����L���ɖʂ����E��Ɏl����̕���������܂��B�^�Ɏl�p���Y������悤�ȃX�y�[�X�����Ă��܂��B�����͈ꖇ�̏�q�ŘL���Ɗu�Ă��Ă��邾���Ȃ̂ŘL���̐����ʂ��ł��B�ł�����A���̕������g���Ƃ������Ƃ͑S���Ȃ��ƌ����Ă����ł��傤�B��������炢�̓��ݍ��݂ɏオ��ƁA����ɐ��ʏ��ƃg�C��������܂��B�g�C���̓V�����[�g�C���ł������A���ʏ��̃X�y�[�X�����Ȃ肫���Ȃ��Ă��܂����B���ݍ��݂̐��ʕӂ�Ɉʒu����ӂ��܂��J����Ə\������̘a�����Ђ낪��܂��B���̂ӂ��܂�����̂ŁA������߂�Ύ����ł̐��͂���قǘL���ɂ͕������Ȃ����낤�Ǝv���܂��B�L����֎q�Ȃǂ͂Ȃ��A������͒���␅�Ԃ����߂��܂��B�ꉞ�A���̕����͈�K�Ƃ������Ƃ炵���̂ł����A�ΖʂɌ����Ă���̂�����͂��傤�Lj�K���������낷�����ɂȂ��Ă��܂��B���̑�����E�������ƃ��r�[�̃K���X�������A���r�[�̒[�ɗ������l����͕����̑����̂����肪�ǂ����������ł��B�������Â��������~���ڒz������I�ɍ�蒼�����炵���A�����̒��͑����قɏ������Ă��܂��B�����A�����ققǂ̓��_���ł���܂���B�����̒��قǂɏ��Ԃ�ȏ��̊Ԃ�����܂������A�Ԃ͊������Ă��܂���ł����B�܂��A�ؑ��Ȃ̂ɁA�g�[���~�߂Ă��Ȃ�������قNJ�������܂���ł����B�}���َq�͏��Ԃ�ȉ����\���ŁA�l���Ă݂���A�}���َq�ʼn����\���Ƃ����͈̂ӊO�ɏ��Ȃ���������܂���B���߂ƍ얱�߂̗����o���Ă���āA�T�C�Y�̋C����������܂����B�����A���̍얱�߂͍��ɃS�����܂����������Ă��Ȃ����̂ŁA�������邸��Ɨ����Ă��Ă��܂��A���܂ŏo���ꂽ�얱�߂̒��ōł����ɂ������̂������C�����܂����B |
| ���������ɂ͊ٓ��ɓ�������Ƃ��ꂼ��ɘI�V�A����ƉƑ����C������A�j���̌�ւ͂Ȃ����|���Ԃ������Ă��ł������ł��܂��B�܂��A���N���O�ɂ��̊ٓ��̂����C�̑��ɁA�����Čܕ��قǂ̂Ƃ���Ɂu�����̓��v�Ƃ������I�V�̂����C���ł��āA�����͒��̂V���P�T�������͂W�����܂łƂ������Ƃł����B�ٓ��̂����͂������̌���������ĉ��x���߂����Ă���Ƃ̂��ƂŁA���x�Ǘ����ނ��������ƎᏗ�����b���Ă���܂����B�����͑��������߂ŁA���C���������Ă��邹���������Ă������Â����������܂����B�̗����ŁA�m����ɋ���Ă����Ǝv���܂��B�����͒E�ߏ��Ƀ��L�b�h�ƃw�A�g�j�b�N���Ȃ��̂��[���������Ȃ��Ǝv���܂����B������ɃV�F�[�r���O�t�H�[���͂���܂����B�I�V�͑嗁�ꂩ���d�̖̔����J���ĊO�ɏo��`���ł��B���������Ă��āA�[���ł��������̂ł����A����������܂薾�邭�Ȃ���ۂ��܂����B�����A���̕��A��������̂ɂ͂�����������܂���B�뉀�^�̘I�V�Ŏ��͂ɖؗ��������܂��B�S�̂ɂ��������L���A�Q�O�l�ȏ�͓����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�I�V�̓����͂ʂ�߂ł����A�����ɋ߂Â��ΔM���Ȃ�܂��B �h��������Čܕ��قǂ́u�����̓��v�͈ꉞ�I�V�Ƃ��������̂悤�ł����A�����Ɋ��S�ɕ����Ă��Ĕ��I�V�Ƃ��������ł��B�������A�J��������ɂ���܂��ꂸ�ɂ�����肨���ɂ���āA�t�ɂ��ꂪ�C���������C�����܂����B�����̓��͂��M�߂̓K���Ƃ����Ƃ���ł��傤���B�͖{�قƈقȂ��Ă��āA�܂��ł��Ă���قnjo���Ă��Ȃ��̂ɁA�������S�̂ɉ����̂��߂ɗ������Ă��܂��B�����Ɍk���߂�A�������ł��邨���C�ł��B�{�ق̂������A�����̓����������肾�Ǝv���܂��B����������̉Ԃ͂Ȃ��A����̓��������܂肵�܂��A����������A�Ꮧ�����ǂ���炱�̂����̓��̕����I�ɂ����߂Ƃ��������ł����B �݂��蕗�C�͎O����A�����������ʘH�̓�����ɁA�ǂ̂����C���J���Ă��邩�������v�ŕ\�������悤�ɂȂ��Ă��܂��B���ɓ����̎��Ԃ����߂��Ă���킯�ł͂Ȃ��A������̗ǎ��ɔC����Ă���̂́A���Ԃɒǂ�ꂸ�ɂ������ł��Ă����Ǝv���܂����B�݂��蕗�C�́A���ǂ��̂����̈�ɂ�������܂���ł������A�����ƘI�V�����Ă��闧�h�Ȃ��̂ł����B |
| �����̗[�H�͑啔���̐H�����ŁA�����̒��ɂ������̈͘F��������A���ꂼ��̈͘F�����͂�ł̐H���ɂȂ�܂��B�͘F���̎���ؘ̖g�̕����ɕi�������ׂ���`�ł��B���i�����͐�p�̑�ɋ��ݍ��܂�Ă��āA�����g���܂킵���Ǝv�����̂ł����A�����ċA���Ă������Ƃ̂��Ƃł����B�������A�R���̏����A�����̓y�r�����ȂǂƏ�����Ă��邾���ŁA�f�ނɂ��Ă͏ڂ���������Ă��܂���B�Ȃɒ������Ƃ��ɁA�����ɂ͎O��ނ̋���������Ă���̂ł����A����͂��łɏĂ��������Ă��āA���ł��H�ׂ�����̂̂悤�ł��B�����m�炸�ɏĂ���̂����炭�҂��Ă�����A����܂�Ă��Ă���ƍd���Ȃ��Ă��܂��Ƃ������Ƃł����B�⋛�̋��Ă��͂ӂ�����Ƃ��Ă��������A���ȊO���ׂĐH�ׂ�����̂ŁA�����ق��ǂ��Ă��Ă��܂����B���̂ق��̋����̂͌ܕ��݂Ƃ��Ⴊ�����ŁA���ꂼ��ق��ق����Ă����������������܂����B�H�O���͎R�Ԃǂ����ŁA�Ȃ߁A�����ǂ�A���тȂǂ̎R�̂��̒��S�̑O�Ȃǂ�����A���C���͔�ˋ��̖p�t���X�Ă��ł����B�قƂ�ǂ����̂��̂�H�ׂ���̂ł����A�V�n�������͗�߂Ă��܂����B��߂Ă��Ă�������Ƃ������������������ɐɂ����Ǝv���܂����B�Ō�̐H���ɂ͔�ˋ��̂����i�����薞���ł�����̂ł����B�f�U�[�g�͂Ԃǂ��A�`�Ȃǂ̉ʕ��̐��荇�킹�ł��B�r���ł���l�������̐^�ŁA���A�����Ă��܂������A�����͂��ɂ��������̂��A���e�͂��܂��ۂɎc���Ă��܂���B�����Ƃ��Ă͑O�̂Ȃ߂��������������炢�œ��Ɉ�ۂɎc����̂͏��Ȃ��Ǝv���܂������A�������̂����Â��̂ŁA���������o�I�ɂ��y���݂ɂ����C�����܂��B���ꂪ���̈�ۂɑ����e�����Ă��邩������܂���B ����ڂ̗[�H�͌��̐H�����ɂȂ�܂����B����Ɠ��l�̑�ɏ�������i����������܂������A����͑f�ނ��������菑����Ă��܂����B�펯�I�ɂ͑f�ނ������ꂽ������̕������K�̐H���Ƃ����C�����܂����A����͑啔���ł݂�ȓ������̂�H�ׂĂ����C�����܂��B�Ƃ������Ƃō���͂ǂ��炪�A���p�̐H�����������Y��Ă��܂������߂悭������܂���B�����A�[�H�Ɋւ��Ă͂���قǍ����Ȃ��悤�Ɋ����܂����B��͂�͘F�����͂�ł̐H���ł��邱�Ƃɂ͕ς�肠��܂���B�H�O���̓}�^�^�r���ł�����Ƃ����̂�����̂ł��B���̓������Ă�������A�u�A�}�S�v�u�G�����M�v�u�ɂイ����v�̎O�{�ł�͂����Ɠ��l�����������̂ł����B���̑��A�s�҂ɂ�ɂ��⒩�N�l�Q�Ȃǂ��g�����O�A�⋛�Ɨ������̂��z�����A��ˋ��̃^�^�L�̂�����A�����̖p�t�Ă��A�V��q�������Ȃǂ������������A�ǂ����݂�L�m�V�^�̗g�����A���n�卪�̃`�[�Y�����Ȃǂ�����A���C���͔�ˋ��̂����Ă��ł����B���т͂킳�ђ��Ђ��ŁA�f�U�[�g�̓������Ɛ��N���[���̒��ɉʕ��̏��Ђ������Ă�����̂ł��B���̓��͌��ŕ��������邩���������ŁA������ڂł��y���ނ��Ƃ��ł��܂����B��������Ƃ�������{�����[�������Ղ�Ŗ����ɂȂ�܂��B�S�̓I�ɂ��������A�f�ނ��������낢���̂��g���Ă��܂��B�����A��͂�A����Ɠ��l�A���ꂾ�Ɗ�������悤�Ȃ��̂͂Ȃ������C�����܂��B ���H�͂��ꂼ��O���̗[�H�̏ꏊ�Ɠ������ł����B����ڂ͖p�t�̏�ɖ������ڂ����𗎂Ƃ��ďĂ������̂ɖ��X�������ĐH�ׂ���́A���̏Ă����A�Ȃ߂����낵�A�R�A�T���_�A�卪���g���������A���q�����A���ȂǂŁA��ʂ̒���H�Ƃ͏�����̈قȂ�����ۂ�^������̂ł����B�g�}�g�W���[�X���t���Ă��Ă����������̂ł��B ����ڂ�����ڂƓ��l�A��ʓI�Ȓ���H�Ƃ͈���������̂��̂ł��B���̓��̓��M���ׂ����Ƃ́A�ʂ͏��Ȃ��̂ł�����ˋ��̖p�t���X�Ă����������Ƃ������Ƃł��傤�B���̑��������A���Ă��A���̏Ă����A���q�����A⡂̎ϕ��A���Z���A����ȊO�ɏ�������B�͘F���̎���ɕ��ׂ�ꂽ�l�q�͂ƂĂ����H�Ƃ͎v���܂���B��i��i�̃{�����[��������A�r�[���𗊂����������ĐH�א�̂ɂT�O�����������Ă��܂��܂����B�g�}�g�W���[�X�͑��ς�炸�t���Ă��āA����ɁA���̓��̓I�����W�ƃu�h�E�̃f�U�[�g������܂����B����ځA����ڂ̂ǂ��炪���K�̒��H���͕�����܂��A�����炭����ڂ̕��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B ���̓��������́A�嗁�ꂪ������Ɣ��Â��������������Ƃ�A�����̃G�A�R�������������ł���A���C��̉������邳�����ƁA�L���Ə�q�ꖇ�Ȃ̂ʼn����ʂ��ɂȂ邱�ƁA�����̕ǎ��ɂ͂���Ă���Ƃ��낪���邱�ƁA�E�ߏ�Ƀe�B�b�V�����Ȃ��A�w�A�g�j�b�N���Ȃ��ȂǁA�ׂ�������ƌ��_�����X�ڂɕt���̂ł����A���ّS�̂̎�������������镵�͋C��V���������̓��̉��K���A�H���̗ʂ����߂ŁA�{�����[��������Ƃ��ꂵ���Ƃ����l�ɂ͂����Ă��ł��邱�ƂȂǁA���͓I�ȂƂ�����������ɂ���܂��B |
| ����̋��͕��n�̉���X�̍ł����Ɉʒu���A�傫�Ȗ���������Ă��̏h�ɒ������̂͂Q���Q�O�����ł����B��X���ł����������炵���A�R�������珇���ē�����Ƃ������ƂŁA��ԑ傫�ȃ\�t�@�[�ɂǂ�����ƍ������낵�܂����B���Ȃ����̋q���ۂۂƂ���ė��āA�R�����ɂ͂��łɂS�g���炢�̋q���W�܂��Ă����ł��傤���B�������Ɉē������Ƃ������ƂŁA�܂���X�̖��O���Ă�܂����B �ē����ꂽ�̂͑傫�Ȗ傩�猺�ււƌ������O�̏����ƕ��s����A�n��L���̂悤�ȂƂ�����s������ԉ��A�R�����Ƃ��������ł����B�����˂��J���A����̏����ȓ��ݍ��݂��オ���ĉ��������ƁA�P�O��̕������L����A����ɂ��̐�ɂ͈͘F������ꂽ�l�����̎��̊Ԃ��T���Ă��܂��B������������L���ɓ�����炵���A�֎q�̑���ɁA�͘F���ɍ��z�c����u����Ă��܂����B�܂��A�P�O��̕��ɂ͂܂��x�����������Ă��܂����B�[�̕����ł��̂ŁA�p�����ɓ�����킯�ŏ\��̘a���̓����ĉE���A�l�����̕����̐��ʂƉE���ɂ��ꂼ�ꑋ������܂��B���������ʒu���瓹�H�����������낷�����ł��B���H�ɍł��߂������Ƃ������ƂɂȂ�܂����A����ɖ����Ă���̂ŁA����قǓ��H����̔`�����݂͈ӎ����Ȃ��ŗǂ������ł��B�͘F���̕����̍����ɐ��ʂƃg�C�����������������`�ɔz�u����Ă��܂��B�g�C���̓V�����[�g�C���ł����B�a���̍����ɏ��̊Ԃ�����A�Ԃ��������Ă��܂����B�����ԕr�ɉԂ�����Ƃ�����Ԃł͂Ȃ��A�����Ɗ������Ă��܂��B�N���[�[�b�g�́A�㉺�t���T�C�Y�̈�ԕ��ł��Ȃ��Ƃ�̂�����̂ł��B���̑O�̐���������̂��炢�̂��̂���������A����Ȃ��������̂ł����B���̂���̋��������̗��������������͂��Ȃ肢���Ǝv���܂��B �}���َq�Ƃ����̓��r�[�ő҂Ԃɂ��������܂����B���َq�͂�����ׂƂ��������ȕς�������َq�ł������A�����ł̉��߂Ă̂����o����A�}���َq�Ȃǂ͂���܂���ł����B�����҂������������܂������A�Ȃ����[�H��A�H�������畔���ɖ߂��Ă݂�ƕ��n��b�Ƃ������َq����u����Ă��܂����B���ɉ��̃��b�Z�[�W���Y�����Ă��Ȃ������̂ŁA���̂��َq�̈ʒu�Â����悭������܂���ł����B �����͂悭����^�I���n�ł͂Ȃ��g���̂ẴX���b�p���p�ӂ���Ă��܂����A���̃X���b�p���A�ǂ������A�f���ŗ����Ă��g������������������̂ł����B �����C�̓t�����g���ԂɁA���̕����Ƃ͔��Α��ɂ���A�Q�S����OK�ŁA�j���̌�ւ͂���܂���B������̂Ƃ���ɗN������|�̊ǂɒʂ�������̂��鐅���ݏꂪ����܂����A�Ђ��Ⴍ����u���Ă��邾���Ȃ̂ŁA���܂���ދC���N����܂���B������ɂ���C������������܂����A�����͐������A���݂₷����D�悵�Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���Ȃ݂ɐ��͗₽���Ă����������̂ł����B �嗁��͖̗������������D�ŁA����قǑ傫���͂���܂��A�K���ɌÂтĂ��āA�������Ƃ����C�����ɂȂ�܂��B�嗁�ꂩ��̔����J���ďo��`�̘I�V���C�́A�L�ڂ̓��D�̏�ɋ��₪�n����A���̉����炨�������D�ɗ��ꍞ��ł���Ƃ������ɕx���̂ł����B���������ɍs���ɂ́A��ɐA����y���͐ς��Ă��邻�̋���̉�����������߂Ēʂ�Ȃ���Ȃ�܂���B�ڂ��͈�����̋���̌��������ɂ͍s���܂���ł������A�ق��̐l�͂��������s���Ă��܂����B���̂���̋��͂ƂĂ��铒�̏h�Ƃ͂����Ȃ��悤�Ȃ������ȏh�ł����A�������ɓ������܂߂Ă��̂����C�͔铒�̕��C�Ƃ��������ł����B�����͑嗁�ꂪ��⍂�߁A�I�V�͂���߂Ƃ����Ƃ���ł��傤���B�嗁��ɂ���I�V�ɂ��댹������̂悤�ł��B�E�ߏ��ɁA�����|���V�[�Ƃł������ׂ��A�G�߂ɂ��A������K���ɂ��邽�߂̕��@�����킵�������������\���Ă��܂����B |
| �H���͌��̐H�����ɗp�ӂ���A�����Ƃ��i���������Ă��܂��B�H�����̕����̐^�ɂ͍ג����͘F�������A�����͂��̒[�̖̕����ɒu����܂��B�������[�������Ȃ��Ă���̂ŁA���������̂悤�ɕK�v�ȏ�ɔw�����ۂ߂Ă����ޕK�v���Ȃ��̂͏�����܂��B�͘F���ɂ͒Y���������A�������闿���͂��ׂĂ��̒Y���g���܂��B�����ق������悤�Ɉ͘F���̐H�����ł������A�͘F���͒Ⴍ�A�������K�X�ł����̂ŁA���̕ӂ͂���̋��̕��������ł��ˁB �͘F���ɂ͐H�O���̔~���C���ƁA������A���킢�A�ő��Ȃǂ��g�����U�i���炢�̐��荇�킹�ł���t�R�O�����ׂ��A�̂��ɂ͂��܂��̉��Ă��̋����h�����Ă��܂����B�O�͂��ꂼ�ꂿ����Ƃ����H�v�̂�����̂Ŋy���߂܂����B���܂��͂������������̂ł����A�����ӂ���Ƃ��������Ɍ����A����͑O���̑����ق̂��܂��ɌR�z�͏オ��܂����B���̌�A�����͉����ȃe���|�ň�i���^��A���͐�t���ŏt���̍K�[���[�Ƃ������́A���̎|�݂����g�|�ň������Ă������������̂ł����B�����āA���o�����炰�^��ƏĂ��⋛�̂����܂��ŁA����͏o�`�̖��Ɩ��炰�ƏĂ��⋛�̃n�[���j�[���f���炵���A��i�̂��z�����ł����B�����Ă̕~�R���̐얐�������ؘa���̂�����͂��ꂪ������H�Ƃ����Â������̂ŁA�������������Ƃ͎v���܂����A�얐�����Ɉ�������ł��܂��������͖Ƃ�܂���B�ł��A�R���̂�����Ƃ��ẮA��̂������������܂���B�����ŁA�u���~�n���Ŏ�������̂ŁA���j���[�ɂ͂Ȃ��̂ł����v�ƌ����Ē����������Ă��Ă��ꂽ���̂��A�ӂ��̂Ƃ��̓V�n���ł��B�ӂ��̂Ƃ���������l��������Ă���A���ꂪ�Ƃ��Ă������������̂ł����B�R�̗g�����͂������������������̂Ƒ��ꂪ���܂��Ă��܂����A����͖{���ɂ������������ł��ˁB����Ӗ��A���̔�ˋ�������������������������܂���B�����Ă͂��̔�ˋ��̒Y�ΏāA��ˋ��Ƃ����Ɩp�t���X�Ă�����ʓI�ł����A����͑O���̑����ق����̂���̋��������ł͂���܂���ł����B�����͖ԏĂ��ŁA�ԏĂ�����ˋ��̂��������ɕς��͂Ȃ��A���̔Z���Ȗ������\���܂����B���̎��Ƃ��Ă͑O���̑����ق�菟���Ă����Ǝv���܂��B�����ẮA�╨�͂��тƍ��g�̎ς����蓒�t�N���[���Y���A��ˋ���H�ׂ�����A�����ς肵�����t�̖��ŗ����������܂��B����������������̂ł��B�Ō�̉������T�N�T�N�H�c�q�ƏĂ�⡂̂����B�܂��ɃT�N�T�N�Ƃ����H���ŁA�Ă�⡂������݂̂Ȃ����ɂ����������̂ł����B����Ɍܕ��݂������Ă��Ă���܂��B���͂�͏t�L���x�c�̂��͂�Ƃ����A�t�L���x�c�����Ăƈꏏ�ɐ������߂��炵�����̂ŁA�L���x�c�̊Ö������͂�ɂ悭�ڂ��Ă��܂����B�f�U�[�g�̓T���[�[���[䕃\�[�X�����ł������A���̃f�U�[�g�͏��X�C���p�N�g�Ɍ������悤�Ɏv���܂��B�H���͑S�̓I�Ƀe���|�ǂ��A���e�����ɖ����ł�����̂ł����B�����A���ʏo���̕����V������������]�v�]���������Ȃ����Ƃ������Ƃ�����Ǝv���܂��B ���H�������ꏊ�ł��B���̖p�t���X�A���X�`����̓c�ɏ`�A�ϕ��Ȃǂ��e��ڂ���ꂽ���M�A������̂���������A���̈�銱�A���g���A�g�}�g�W���[�X�A䕂ƃp�C�i�b�v���̃f�U�[�g�A�Ƃ������C���i�b�v�ł����B�c�ɏ`�͋��R�ŁA���܂�h���Ȃ��܂�₩�Ȗ��̂����������̂ŁA�ϕ��Ȃǂ̂��M�����ꂼ�ꂨ�����������Ǝv���܂��B�����A�����ł����������ŏĂ����������A�O���̑����قɔ�ׂč���̈�ۂł����B�������A�H���Ɋւ��Ă͗[�H�E���H�Ƒ����I�Ɍ��āA���Ȃ荂���]�������Ă������Ǝv���܂��B �������Ȃ��Ȃ��A�����C���Ȃ��Ȃ��A�H�����Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ薞���x�̍����h���Ǝv���܂��B���������̃��r�[�ł݂̂Ȃ���̘b�������Ƃ��Ȃ����ɓ����Ă��܂������A���Ȃ肢�낢��ȏh�ɔ��܂��Ă���l���W�܂��Ă���悤�����A�o�鎞�ɂ͊������Ă���l�����܂����B�ڂ������ʂɉ������Ȃ�����ė��ĉ߂������Ȃ瓯���悤�ȍD��ۂ������ċA���Ă������Ǝv���܂��B |
| ���́A�����Ƀ`�F�b�N�C������܂Ŏ��̂悤�Ȃ�����������܂����B �O���̑����ق��`�F�b�N�A�E�g�����̂͂P�O���ŁA���̑O�Ɠ��l�ɐV�䍂���[�v�E�F�[�ɏ�낤���ƁA�����ق̎ԂŃ��[�v�E�F�[�̂Ƃ���܂ő����Ă�������̂ł��B�ł��A����Ă͂��邪�A�u���[�X�J�C�ł͂Ȃ��A�Ƃ肠�������n�ɍs���Ă��܂����ƁA�m���P�P��������̃o�X�ŕ��n������������Ƃɂ��܂����B���\��̃o�X�͕��n����̒��܂œ��炸�A������Ƃ����������ꂽ�o�X��ɂ����~�܂�Ȃ��̂ŁA�܂��}���ɗ��Ă��炢�A�h�ɉו���u�����Ă�����āA�`�F�b�N�C�����ԋ߂��܂ʼn���X���Ԃ�Ԃ炵�Ă��悤�A�Ƃ������Ƃŏh�ɓd�b�����܂����B�o���̂͏����ł������A�����b���ƍ��f���������ł����B�ǂ����l�����Ȃ��炵���A�}���ɗ����Ȃ��l�q�ł������A������Ƒ҂��Ă��������Ƃ������ƂŁA���ꂩ�ɗ��炵���A�悤�₭OK�̕Ԏ�������܂����B�����A���̎��A���߂ɏh�ɓ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�h�ɒN�����Ȃ��Ȃ�A�Ƃ����悤�ȓ��e�̂��Ƃ������܂����B���߂ɏh�ɓ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��͎̂d���Ȃ��A���邢�͓�����O�Ƃ��Ă��A�h�ɒN�����Ȃ��Ȃ�Ƃ����̂͑傢�ɋ^��ł����B���̒i�K�ŁA�ڂ��͂��̏h�̓��C���̃X�^�b�t����������Ƃ���l�̓�l���炢�������Ȃ����R���^�̏�����܂�Ƃ����h�Ȃ낤�ȂƎv���Ă��܂����B �o�X�����n������ɒ����ƁA���łɒj�����҂��Ă��āA�ו���a����悤�Ɍ���ꂽ��ł����Ƙb�������Ă��܂����B����A��������Ȃ��Ăڂ��������ꏏ�ɏ悹�Ă��炤��ł��Ƃ����ƁA�����A�����������Ƃł����Ƃ������ƂŁA�Ԃɏ悹�Ă��炢�܂����B���́A���l���̂悤�Ȍ�������A�h�ɂ͌}���ɗ�����l���N�����Ȃ��̂ŁA�N���m�荇���ɂł����̂��낤�Ǝv���܂����B�Ƃ��낪�A�O�n����ɗ��āA������T�������nj�����Ȃ������A�H��������Ƃ�����Ȃ������A�Ȃǂ̘b�����Ă��邤���ɁA���̉����������Ǝv���A���̌}���̐l�ɁA���Ȃ��͂���̋��̂���l�ł����ƕ����Ă݂܂����B���̃J���͌����ɓ�����A�����ł��Ƃ������Ƃł����B�������A��l�ɂ��Ă͂��܂�ɂ��Ή������l���̊����ł��B ���[�̑̒�������Ȃ̂ŁA�����܂ł͂���������Ȃ��č\��Ȃ����A���r�[�ɂ͉����������邩�ƕ����Ă݂�ƁA�Q�����炢�ɂ͓���邪�A�|�������Ă���̂ł��邳���A�Ƃ����Ԏ��ł����B�́`�A�Q���ɂ܂����r�[�̑|�������Ă���h�ł����A�Ƃ��������ł��B�P�Q�����炻�̂Q���܂Ŏ��Ԃ��Ԃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł����A�̒�������̐l�Ԃ��ǂ��������ɁA���̂Q���܂ł��̕��n����ʼn߂������炢�����A�Ȃǂ̋C�z��A�A�h�o�C�X�͈����܂���ł����B�ڂ����l����ɁA���h�Ȉꌬ�Ƃł��鑫���́u�ɓ��v�ł��낮�̂���Ԃ����Ǝv���̂ł����A���̂��Ƃɂ���ؐG��܂���B�O�����ɁA�������ǂ��ɂ���̂�������Ȃ������Ƃ�����b�̎��ɂ��A�u�����ł��ˁA������Â炢�ł��ˁv�Ƃ������Ԏ������ŁA�ǂ̕ӂɂ���A�ǂ�Ȍ����Ȃ̂��Ƃ����������Ȃ��A���̉E���ł��������Ƃ����ڂ��̏d�˂Ă̎���ɁA�����ł��A�Ɠ����Ă��ꂽ�����ł����B ���ǁA�ɓ��Ɉ�l�������[���c���ĉ���X���������Ď��Ԃ��Ԃ��A������x�h�Ɍ������܂����B��͂�ڂ���������ԏ��ŁA���r�[�̑|���͏I������炵���A�Ђ�����Ƃ��Ă��܂����B�܂��A���l���ł���Ă���h���Ǝv������ł���ڂ��́A�o�Ă��ĉ����Ă��ꂽ�����Ɂu��������ł����v�ƕ����Ă��܂��܂������A�Ⴄ�Ƃ������Ƃł��B���̌㕪����܂������A���R���Ƃ͑�Ⴂ�ŏ]�ƈ��͉��l������悤�ł����B�ォ�痈���l���]�ƈ��ɁA�d�b����������Ǐo�Ȃ������A�Ƃ������Ƃ������Ă����̂ŁA��͂�{���ɏ]�ƈ����N�����Ȃ��Ȃ鎞�Ԃ��������悤�ł��B���ꂪ����̂��ƂȂ̂��A���܂��܂��̓������̂��ƂȂ̂�������܂���ł������E�E ��ɂ��q�ׂ��悤�Ɂu�������Ȃ��Ȃ��A�����C���Ȃ��Ȃ��A�H�����Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ薞���x�̍����h�v�ł��邱�Ƃɂ͈Ⴂ����܂���B�܂��A�����炭�ڂ������̂悤�ɁA���i�Ƃ͈Ⴄ�A�����˔��I�ȏo�����ł��N����Ȃ�������A�ق���т������邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł��傤�B okies������܂߂āA���̏h�ɂ�����ۂ��������Ȃ����������̐l�ɂƂ��Ă͂����炭�܂��s�������h�ł���ɈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B�������A���̂���̋��̎�l�ɂ��ĂȂ��̋C����������̂��́A�͂Ȃ͂��^��ŁA�ڂ��͂��̏h�������������đ��^����C�����͎��Ă܂���B �����A�����͂����Ă��A�Ƃ肠������l�Ɗ�����킹���A���ʂɃC����������A�ڂ��ɂƂ��āA��O���҂̏h�̌��ɂȂ邾�낤�Ƃ������Ƃ��܂��A�����Ȃ̂ł��B |
| ����̎R�A���s�̃��C�������捻�u�ŁA�_�����璹�捻�u�ɍł��߂��̂͊�䉷��ł͂Ȃ����Ƃ��������d����A��䉷�班�������Ɉړ����Ă����Ƃ����h���v�����𗧂Ă܂����B��䉷��ɂ��Ắu��䉮�v�Ƃ������ق��A���ٌn�̂łс[����̃��|�ł���^����Ă��܂������A�铒������̏h�ł�����A����ɂi�s�a�̖����x�X�O�_�ȏ�̏h�ɂ����������Ƃ�����̂ő�����ƂȂ�܂����B�h�ɓd�b����ƁA�ʒu�Ƃ��Ă͒����`�Ɗ�䉮�̂��傤�ǒ��Ԃ�����ɒ��捻�u������A���u�ό��ɂ͂���ȂɎ��Ԃ͗v��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��������A�������J�œ���������Ƃ����V�C�\�������A���u�͏o�������Ɍ��Ă��܂����Ƃɂ��܂����B �����`����^�N�V�[�Œ��捻�u�Ɍ������A���u�̊ό���A�҂��Ă��Ă�������^�N�V�[�����āA�h�ɒ������̂͂Q���S�O�����ł����B�����ɏ]�ƈ����o�Ă��āA�g�����N����ו��Ȃǂ��^��ł���܂����B����������Ǘ��������̂��郍�r�[������A�S�ُ~���߂��āA�X���b�p�͂���܂���B�S�ُ�̗��ق͋v���Ԃ�ł��B���r�[�ł̂����Ȃǂ͂Ȃ��A���������Ɉē�����܂����B �ؑ��O�K���Ă̌����ŁA�ʂ��ꂽ�͓̂�K�̒[�́u�����v�Ƃ��������ł����B�P�O��̎厺�ɂU��̎��̊Ԃ�����L�������ŁA�h�A�̂Ƃ���ɂ������ē��}������ƁA���ق̒��ł��L�߂̕����������悤�ł��B�h�A���J����ƁA�������L��������A�������E���Ƀg�C��������܂��B�����͑��t���ŃV�����[�g�C���ł����B���L���̍����ɂ͗①�ɂƐ��ʏ�������ł��܂��B���̘L���ɖʂ��ĉE���̕��������̊Ԃō������厺�Ƃ������ƒP���ȑ���ɂȂ��Ă��܂��B���̎��̊Ԃɂ��傫�ȏ�q��������A�h�̃t�����g�O�ɂ���ؒ�߂邱�Ƃ��ł��܂��B�������A���̕�������������������Ă���\���Ȃ̂ŁA�قƂ�ǂ��̑��͊J���܂���ł����B�Â��ؑ��̌����ł����A�����̒��͂���قNjÂ�������Ƃ�����ł�����܂���B��ŕ����������Ƃł����A�ׂ�K�ォ��̉��͂��������悭�����A���Ȃǂ����e�͕�����Ȃ��Ȃ���A���ꕷ�����Ă��܂��B ���̊Ԃɂ͉Ԃ��������Ă��܂������A�^�Ƀe���r���ł�ƍ����Ă��܂����B���߂̃T�C�Y�̋C�Â����͂���܂����B���z�����o����A�}���َq�͂Q�O���I�����g�����������`�̃[���[�َq�ŁA�[�H��ɂ͂Ƃ��Ƃ薲�������Ƃ������َq���o����܂����B���̂��َq�Ɋւ��Ă͂��܂�L�����Ȃ��̂ł����A�����闋�������̂悤�Ȃ��̂ł͂���܂���B�厺�̑����͎O����̍L���ŁA������́u���ȂΉ��@��䉷��v�Ƃ������킢�炵���Q�[�g��A�ڂ̑O�̉ԉ��Ƃ������ق̎���ꂳ�ꂽ���ցA���̍��̎G�݉��Ȃǂ������܂����B���̉���X�̒��߂͂Ȃ��Ȃ��������悤�Ɏv���܂����B�������A����X�̂悤�Ɍ�����̂͂��̕ӂ肾���ŁA���ق��O�������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�����Ԃ��ƕ����Ă݂��̂ł����A���̒ʂ�ŁA���Ȃ�̗��j�����鉷��ɂ�������炸�A�{���ɏ����ȉ���n�ł����B�Ȃ�ł��́A����������炵���A����ȍ~���Ă��܂����Ƃ������Ƃł����B |
| �����C�͍ŏ������p�́u�����̓��v�ƒj���p�́u�j���̓��v�̓����̂W�������Ɍ�ւ��A�Q�S���ԓ��邱�Ƃ��ł��܂��B�ŏ��j���p�́u�j���̓��v�͂��̉��N���O�ɏo��������ŁA��������̘b�ɂ��ƁA����l���S���Ȃ�O�Ƀx�b�h�ōŌ�܂ł��́u�j���̓��v�̐v�H�ɐS���ӂ��Ă����悤�ł��B ���̂���l�̎v���̂�����������̓��g�����_���Ƃ��������ŁA�������ǂ������ŋK�����������𗧂āA�X�e���h�O���X�̍ג������������ʂɉf����A�V��̍�����������������ł����B�l�p�����D�̐^������Ɏl�p���[���Ȃ��đ����̂��̂����玞�����ȖA���オ���Ă��܂��B�������炨�����N���Ă��邻���ł��B�������̂͂��܂�傫���Ȃ��̂ŁA����ł��鎞�͊y���߂Ȃ��ł��傤���A�Ă��鎞�͂̂�т�Ǝ����߂������Ƃ��ł��邢�������C�ł��B���ʂ����悭�A���C���܂������������Ă��Ȃ��̂��ڂ��ɂƂ��Ă͍D��ۂł����B ���ߏ����p�̌����̓������̏j���̓��Ɠ����悤�Ȋ����ŁA�X�e���h�O���X������܂������A���D�̍L���͏j���̓��̓�{���炢�������Ƃ������܂��B��͂�������[���Ȃ��Ă��đ������炨�����N���Ă��܂��B�����A�j���̓��قNjC�A�͗����オ���Ă��Ȃ������ł����B����������C�������炸�A���܂ł������Ă��邱�Ƃ��ł��܂��B�����͌����̓��Ƃ͔��Α��̏�̒i�ɘI�V���C�����Ă���̂ł����A�������������͂܂�Ă��ĊJ�������قƂ�ǂȂ����Ƃ�A���C���S��������Ȃ������ł��\���C�������������ƁA����ɁA�����I�V�͑����N�o�ł͂Ȃ����낤�Ƃ������ƂŁA���܂�I�V�̃����b�g��������ꂸ�A�قƂ�Ǔ��邱�Ƃ͂���܂���ł����B �����͗����Ƃ��K���ŁA�������L�B���̉Ԃ͂Ȃ��A��������ɂ��ƒ��h����ɂ������Ƃ������Ƃł����B���\�Ƃ��Ă͒������ł��ˁB �����̊O�̘L���ɓ����̗₽���������p�ӂ���A�v���Ԃ�ɃL���̂����A�����������������ނ��Ƃ��ł��܂����B |
| �[�H�͕����̂����߂��ɂ�����̐H���ǂ���ł������A�����ɂ���Ă͕����o���̏ꍇ������悤�ł��B���i�����͂������̂ł����A�����͂���܂���ł����B�܂������̗������e�[�u���ɕ��ׂ��A���шȊO�̌�o�����l�i�Ƃ����\���ł��B���C���ƂȂ�̂��A�n���̃~�j�X�e�[�L�ŁA����͏��߂���e�[�u���ɂ���A������̍D���Ȏ��Ɏ����ʼn�����Ƃ����`���ŁA����Ȃ�{���ɐH�ׂ������ɐH�ׂ���̂ōD�s���ł��B�H�O���͂Ȃ��A�O�̔��j�V�A�����݁A���������A��ǁA�@���̗g�����A��������i�Ȃǔ��i�ƁA���t���̌Ӗ������A�|�̕��̏��t�K�j�A�֎q�E�g���\���E⡁E�������Ԃ�̎ϕ������ׂ��Ă��܂����B�����ォ�犨���A���ځA���A���G���̎h�g�ƁA���炭���āA�����C�V�ƎO�t�ƕ��ƌu�G���̗g�����A�Ñ�����̗t�ŕ�Ă����A���L��y�r�����ɂ������̂����ɉ^��Ă��܂����B�݂�Ȕ��ɂ����������������܂����B�V�N�ȋ��͂������A�Z���ȌӖ������A�����C�V�ƌu�G���̗g���������Ɉ�ۂɎc��܂����B�������͓����̔��F���ɂ����炵�����Ƃ𒇋��������Ă���܂����B�^�ѕ����e���|�悭�i�݁A������݂������ɐ\��������܂���B���ɖ������܂����B�f�U�[�g�͂��і݂�䕂Ŏc�O�Ȃ��炱��͂���قǂ̃C���p�N�g�͂���܂���ł����B �H���̌㔼�ɏ��������A�ɗ��āA���낢��b�����Ă���܂����B��������ɂ��ƑS��������Ă���Ƃ̂��Ƃł����A�A������ł̂łс[����̘b�ł͂łс[�����܂������͗��Ȃ������Ƃ������Ƃł����B�Ƃɂ����A��������̈��A�Ƃ����ƌ`���݂̂ŁA�����ɗ������낤�Ƃ������������܂����A�����̏�������͂��Ȃ蒷���Ԙb�ɕt�������Ă���܂����B�铒�̏h�ɉ������Ă���A��������̂��q�����������Ƃ�A�����҂ł��̊�䉮��I�Ԑl�����Ȃ��炸����ȂǂƂ������Ƃ������Ă���܂����B ���H�������ꏊ�ł��B���A�R�Ƃ�����ǂ��̎ϐZ���A������Ƃ���ݖ��X�A�����I�݂̂���A�������A�O���[�v�t���[�c�W���[�X�A�Ƃ��������i�b�v�ŁA�{�����[���͂���قǂ���܂��A�o�����X�̎�ꂽ�����������H���Ƃ����܂��B ���̏h�̗B��̌��_���A�K���ׂ̕����̉����悭�ʂ��Ă��܂����ƁB�����C��H���͐\��������܂���B�����̋C�z����s���͂��Ă��܂��B ���̊�䉷��͎R�A�̉���̒��ł����Ȃ�Â����j�����悤�ŁA�ꎞ���͑������W���Ă����炵���̂ł����A���͗��ق͎O�������A�{���ɂЂ����肵������ɂȂ��Ă��܂��܂����B�`�F�b�N�A�E�g�̌�A���H���w�߂��Ŏ�����̂ł����A�H��g�C���ɗ��������[�͂��̃g�C���ɂ��Ȃ�̃J���`���[�V���b�N�����l�q�ł��B����Ȃ���Ƃ����ċ����������C�o���̂��Ȃ��A�ЂȂт��n��̒��ŗ��قƂ��Ẵ��x���̍�����ۂ�������̂͑�ςȂ��Ƃ��Ǝv���܂����A���̐S�ӋC���킷�ꂸ�Ɋ撣���Ăق����h�ł��B |
| �@ |
| �ڂ͎O������̗��ّ勴�B�O������͐Ėؕʊق����߁A�����h�������炵���̂ł����A�����͉��Ƃ����Ă�okies����̒ǂ������ŁA���ّ勴�Ɍ��߂܂����B�������A�i�s�a�̖����x�X�O�_�ȏ�̏h�ɓ��������Ƃ�����Ƃ������Ƃ��A�d�v�ȃ|�C���g�ł��B���ق����߂Ă���A���ٌn�̂łс[������h�����Ă������Ƃ�������܂����B��͂�]���͍��������悤�ł��B �����͑q�g�w���瑗�}�����Ă����̂����ꂵ���Ƃ���ł��B�C���^�[�l�b�g�Ő\�����̂ł����A�w�ւ̓������Ԃ������莟�悲�A�����������Ƃ̃R�����g���Y�����āA�m�F�̃��[�����A���Ă��܂����B�d�b������Ɣ��ɑΉ��̂����l���o�āA�����������ɕ��������̂ł����A���̐l�͂��̏h�̎x�z�l�Ƃ������Ƃł����B�`�F�b�N�A�E�g���̑Ή�������A�������q�����������ł͂Ȃ��A������̗���ɗ����čl���邱�Ƃ̏o����l���Ɗ����܂����B ���ّ勴�͑O���̊�䉮�Ɠ������ؑ��̎O�K���Ăł��B�������A�O�ρE�����Ȃǂ̋Â�������͊�䉮���������Əd���������������܂��B���̌����͍���L�`�������Ɏw�肳��Ă���Ƃ������ƂŁA��������Ȃ����闧�h�Ȃ��̂ł��B�����A���̗��ّS�̂����n����Ί݂̗V�������U�����܂������A���ّS�̂̎p�����ꂳ�ꂽ���������̂ł����B �}���̎Ԃŗ��قɓ��������̂͂Q���P�T������B�O����i�O����j�ɖʂ����i�F�̂������r�[�Ŗ����ƌ}���َq�ł����\���I�����̂��і݂����������܂��B���̂��ƁA�����ɕ����ֈē����Ă���܂����B���̗��ّ勴�̂����C�͌����̒[�ƒ[�̓�ӏ��ɕ�����Ă���̂ł����A���܂����̂͂��̘I�V���C���̒[�ɍł��߂��S���Ƃ��������ł����B �h�A���J����Ɣ���قǂ̋����X���b�p��E���X�y�[�X������A�̂����ꂽ�܂d��̉����J���A���̍T���̊ԂɒE�����������銴���ł��B���̓��͉������Ă��Ă���̂ŁA�T���̊ԂƌĂт܂������A�����I�ɂ͓��ݍ��݂ł��ˁB����ɂ��̍T���̊Ԃ̉����J���A���i�ނƘZ��̎厺�ɑ����Ă��܂��B�����͘Z��Ɣ��ɋ����̂ł����A���傤�Lj����̗��h�ȏ��̊Ԃ�����A���̊Ԃ̘e�ǂƂ����A�V��Ƃ����A�����̑�������Ȃ�Â������̂ŁA���ɂ��������ł��B����Ɠ��l�ɓ�K�Ȃ̂ł����A��䉮�̂悤�ɏ��ׂ̕�������������Ƃ������Ƃ�����܂���ł����B�����̏�̏�Ƀe���r�╶�����u����A�ꏊ���Ƃ��Ă���̂ł����A�L���͂R����ŗ��h�Ȉ֎q���u���������肵���������܂��B�g�C���͍L�����ɂ���A���ʂ��L���ɕt���Ă���Ƃ����A�̂Ȃ���̍\���ł��B�����A�V�����[�g�C���ł���ȂǁA�s�ւ͂���܂���B ���̊ԂƍL���̋��̕ǂɏ����ȏ�q�����炦���A���̏�q�̑O�ɂ��ł₩�ȉԂ��������Ă��܂����B�����ł̂����o���͂���܂��A�����ɂ͓Ȃ̎����݂ƎO��ނ̒����̂����������p�ӂ���Ă��āA������������������̂ł����B������̓��r�[�Ɠ����悤�ɎO����̗���ƁA���ꂩ��A���傤�Ǖ����̐^�������̑Ί݂��J��ꂽ���n���l���ڂɓ���܂��B�����A���C�Ɉ�ԋ߂������Ȃ̂ő��̉E�����́A�I�V�̉����ȂǂɎ��E�����������Ă��܂��Ă��܂��B���\����Ă���Ƃ͂����A�Ί݂���̔`�����݂͂���A���ւ��鎞�Ȃǂ͏�q��߂�K�v�͂���܂����A�S�̓I�ɂ͗����������D�܂�����ۂ̕����ł����B |
| ���[�ɕ�����Ă��镗�C�̂����A�����ɋ߂����ɁA�嗁��̈�ł���u�ӂ��ׂ̓��v����ɓƗ������I�V���C�A����ɗL���̉Ƒ����C�������܂��Ă��āA�ӂ��ׂ̓��ƘI�V���C�͖�̋㎞�ɂ�������̒[�ɂ����A�̓��ƌ�ւɂȂ�܂��B�ŏ��͂ӂ��ׂ̓��ƘI�V���C���j���p�ł����B�ӂ��ׂ̓��͂��̖��̒ʂ�Ђ傤����^�ŁA�傫���~�Ə������~�̗������Ȃ��������邢�����C�ł��B��≷�߂ł����A�傫���~�����������~�̕�����≷�x�������悤�ł����B���̊O�̎O���쉈���̂Ƃ���ɏo�邱�Ƃ��ł��A�����ɂ͓����̒Ⴂ�Q��������܂��B��l�p�Ȃ̂Œ����ԓƐ肵�Ă�������E�ł����A�������̉����x�����Ȃ��̂ŁA�ʂ铒�D���̐l�ɂ͂�����������܂���B�I�V�͂��������O����̐쉈���ɍ���Ă���̂ł����A�`�����ݖh�~�̂��߂̈͂��������͂�߂��炳��A�i�F�͑S�������܂���B�����A�I�V�̊������������̂ق��Ƀ��h����̓����������~�X�g�T�E�i�̂悤�ȕ���������A���̓�����ӂ肩��͌i�F�߂邱�Ƃ��ł��܂��B�����A����͑Ί݂���������Ă��܂��Ƃ������ƂŁA�����͂��̃~�X�g�T�E�i�͖邵�����p�ł��Ȃ��ł��傤�B�����͂�≷�߂Ƃ������Ƃ���ł��傤���B �����̖����͊�A�̓��łƂɂ������C���h�Ȋ����̊╗�C�ł��B��̓��A���̓��A���̓��Ƃ����O��ނ̎��R�̂܂܂̗����ɕ�����A��̂ł��ڂ�����������C�A�Ƌ��ɁA�V�N�Ȃ������N���������Ă��܂��B���̓��Ɖ��̓������W�E����A��̓����g���E����ł��̃g���E����̓g���E���̊ܗL�ʂ����E��Ƃ̂��Ƃł����B��������̓�����ԍ����A���E���̏��ɉ�����悤�ł��B���̗����̃��C���h�����Ȃ��Ȃ��Ȃ̂ł����A�����Ƒ̂���������������Ă��āA�������̐Ό����͊�̊���ڂɗ��ꍞ�ނƂ������Ƃ����C���h�����ӂ�鑢��ɂȂ��Ă��܂����B�����A���̌�̐Ό����͂ǂ��Ȃ����Ⴄ�낤�ƁA������ƋC�ɂȂ�܂������A�܂��A���R�l�����Ă���̂��낤�Ǝv���܂��B����̌����ڂɂ��āA�ڂ��͓��ɂ͊����Ȃ������̂ł����A���i�͂قƂ�NJ��������Ȃ����[���A��������͊����������Ƃ������ƂŁA������ʂ��������ċC�ɓ������悤�ł����B �H���͒��[�Ƃ������ŏo����܂��B���C����A���Ă���Ƃ��łɃe�[�u���ɔ������F�̃e�[�u���N���X���������Ă��܂����B�v�X�Ƀe�[�u���N���X�̖@�����v���o���܂������A�m������͔����e�[�u���N���X�̖@���������ȂƎv�������܂����B���i�����͂Ȃ��A���ɒ�������̐���������܂���B���߂Đ��������ł��������肵�Ăق����Ɗ����܂����B�܂��A�e�[�u���ɂ͐H�O���̃��}�������ƑO����A�ނ����A�����q�@���A�C�V�A�ق��邢���Ȃǂ̋�퐷�肪���ׂ��܂����B���ɂ��̂ق��邢���͐�i�ł������A����Ɍ��炸�ǂ�������������̂ł����B�����Ĉ�i���^��܂��B�܂����낵�X�e�[�L�Ƃ���������卪���낵�A�O���[�v�t���[�c�H�ȂǂŏĂ������́B�{�����[��������A���������ł��܂��B�����Ă̂��o���������������̂ł����B���̎���������ɓ�����A���ڂ̏Ă�������ł��̗��ق̔���̗������Ǝv���܂��B�Ă����ɕ��ڂ̑�����悹�A�y���Ă��Ă��������A�Ă�����ԂƂ����������̂��̂ł��B�����ȕ��ڂł����A���������ꏏ�ɏo����܂����̂ŁA�����炭��l�ň���������̂��Ǝv���܂��B�H�����̂��邨���������̂ł����B�����Ă��A�Ȗݓ���̒��q�����B�Ȃ̖��̂������肵���Ȗ݂������Ă��܂��B�Ȃ̃N�Z�̋��������������钼�O�̂Ƃ���Ŏ~�߂Ă������Ƃ����▭�ȂƂ���ɂڂ��͖������܂����B������H����������܂��B�����āA���R���̕�ݗg���ł������i�Ƃ���������܂���B�Ō�̊��Ƌ��̏Ă���������͂Ȃ��A�������тɂ��Ԃ������������������Ă��܂����B���i���炢�H�ׂĂ݂����Ǝv���܂������A��i���̃{�����[���͂���A�������͏\���������܂��B�ǂ���A����͐H�ׂ����Ƃ�����Ƃ������}�Ȍ����ł͂Ȃ��A�H�v�̋Â炳�ꂽ�����ŁA�y���݂Ȃ��炨�������H�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B�f�U�[�g�̓X�C�J���T�C�R���^�ɐ����P���Ȃ��̂ł����A���̃X�C�J�ɂ�������Ƃ����H�v������܂����B�����A�ڂ��Ƃ��Ă̓f�U�[�g�ɂ����������Â������̂��~���������C�����܂����B |
| ���H�͋������ŁA�e�ɉ��h�̂悤�Ȃ��̂�����܂��B��̂�A���炷���낵�A������A�@���A����ɂႭ�A���炱�̘Z�i���O�̂悤�ɍג����M�ɏ������悹��ꂽ���́B���t�H�������������ƏĂ��C�ہB���Â��R���B���B���B�Ƃ���Ă���蒃�q�����B�Ƃ����������ʓI�Ȓ��H�Ƃ͈ꖡ�������H���������������키���Ƃ��ł��āA��͂薞�����܂����B �������̒m�v�n�y�ꂳ��͂R�N�O�Ɍ���̖��H�ɑI�ꂽ�l�ŁA���N�����J�͂���͂����Ƃ������Ƃł��B�v���Ԃ�ɁA�����𖡂킢�ɂ����ł�������x�s���������قƂȂ�܂����B ���̗��ّ勴�́A����L�`�������̌����ƈӏ��̋Â炳�ꂽ�����A�ꂩ�炨�����N���o�鎩�R�̂܂܂̊�A�̓��A����̖��H�̍��H�v�̋Â炳�ꂽ���������H���ƁA�����ł�����̂��O���������ނ܂�Ȃ�h�ƌ����Ă����ł��傤�B�������A�w����̑��}������A�C�z��̂���x�z�l������Ƃ����T�[�r�X�ʂɉ����A�����͎��Ƀ��[�Y�i�u���Ƃ������ƂŌ������Ƃ�����܂���B��䉮�Ƃ͂܂��������A����͎O������Ƃ��������ق̂���������Ŗ��������Ă̌��ʂȂ̂ł��傤���B �����A�ڂ������܂�������ł͓��ɕs���ȓ_�͂Ȃ������̂ł����A��������̈�l���܂��Ⴍ�s����ł��������ƁA�z�c��~���ɗ����̂����Z���̃o�C�g�H�Ǝv����悤�ȃL���s�L���s�R�l���ŁA�ԓx�͑S�R�����Ȃ������̂ł����A���̗��قɂ͕s�ލ����̎Ⴓ���ӂ�銴���Ɉ�a�������������ƁA�Ȃǂ�����܂����B�܂��A�łс[����⑼�̐l�ɂ��C�ɂȂ�_���������������悤�ł��B �ǂ����A�q�̋ꌾ�̈��ɐ����ɑΏ����A���{���ւ�h�̈�ɂȂ��悤�A�������������������Ă����ė~�����Ɗ肤�A���������h�ł��B |
| �@ |
| �O���ڂ͂܂���Ԃňꎞ�Ԃقǐ��i���ĕĎq�w�ɍs���A��������o�X�ŊF������Ɍ������܂��B�R�A�Ƃ����ƁA�ڂ��̒��ł͎O���ƊF���Ƌʑ����r�b�O�R�ŁA����͂��̎O�̉���ɓ��邱�Ƃ����Ăł������A�c�O�Ȃ���ʑ��͎���ɂ��ύX�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�F���͂ǂ��ɂ��悤�Ǝv�����̂ł����A�����Ă��鉽�N�����́u�����x�X�O�_�ȏ�̏h�v�Ƃ����{�́A�K���Ɏ��o��������Ɂu�F���e�T�Ɓv�Ƃ������ق��ڂ��Ă��āA�F������͌��\��K�͗��ق��������ł͋q�������܂����Ȃ����̗��ق������̂ŁA�����Ɍ��߂��̂ł��B ���ق̓o�X�₩�炠�܂藣��Ă��Ȃ��悤�ŁA�܂��~���Ή��Ƃ��Ȃ邾�낤�Ǝv���Ă����̂ł����A�o�X��͊ό��ē����̋߂��������̂ŁA���łɓ������ƒ��ɓ���A�q�˂�ƁA�}���ɗ��Ă��炢�܂��傤�ƁA�ē����̐l�����قɓd�b�������Ă���܂����B �Ⴂ�������}���ɗ��Ă���A�h�ɒ������̂͂P�������߂��������ł��傤���B�F������͓��{�C�ɖʂ�������n�ŁA���̏h�̓��r�[���炷����̍��l�����n�����Ƃ��ł��܂��B�V�C���ǂ������̂ŁA���l�������U�����悤�Ƃ������ƂŁA���炭�����A�h�ɖ߂����̂��Q�����炢�ł����B���r�[�Ŕ~���z�������������A�����ɕ����Ɉē�����܂����B �����͂S�O�R�����́u�����C�v�Ƃ����Ƃ���ł����B�����˃^�C�v�̃h�A���J����ƍL�ڂ̌��ւƓ����̔̊Ԃ̓��ݍ��݂�����܂��B�オ���č��Ƀg�C��������A�V�����[�g�C���ł����B���ݍ��݂̉E�ɂ͍L�ڂ̐��ʂ�����A���ׂ̗����C�ɂȂ��Ă��܂��B���ݍ��݂̐��ʂ̘a�����P�O��ŁA���̐�ɂQ�D�T����̏�̍L���������Ęa���p�̈֎q���u����Ă��܂��B���邢�����ŁA�S�ʂɑ傫��������K���X������͉��₩�ȓ��{�C�ƁA�������̂�≺�Ɉ��ɕ��Ԕg�����u���b�N�A�����āA�g�����u���b�N�̎�O�̋�ǂ̗t���t���ɂ����悤�ȍ��l�A�������ꂾ���������܂��B���̓��̐�i�Ɖf����A���ɂ������߂̕����ł��B���O���ɂ͓���������������炵���̂ł����A����Ă͂�����̂́A���̓��͉����Ƃ������ƂŌ����܂���ł����B���̕����̌i�F�̑f���炵���Ƃ���́A�ǂ������̑����^�k�������Ă���̂ł͂Ȃ����ƒP���Ȃڂ��͍l����̂ł����A���̓����ޗ[�������̍����Ɍ����A�����̒��������̉E���Ɍ��������Ƃł��B�G�߂ɂ����Ǝv���܂����A�p�����ł��Ȃ��̂ɁA�C�ɖʂ���������ʂ����Ȃ�������A�������[����������Ƃ����̂͒������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���ꂾ���ł����]�̕]���͓��`�ɂȂ�܂��B���z�����̔��Α�������Ă��邽�߁A�����ɂ��Ă������ɂ��Ă������̒��܂Ő[���������܂Ȃ��̂����ɂ����_�ł��B�ɍs�������̎R���ق͒������[���������݁A�Ƃ͂������Ȃ菋���v�������܂����B���̋e�T�ƂŖk�����̑��̎v��ʃ����b�g�����߂Ēm��܂����B |
| �����̊�䉮�A����̗��ّ勴�Ƃ������A���a���̌Â������̗��������������Ƃ͗l�ς��̕����ŁA�ŏ��͔�����Ȉ�ۂ����̂ł����A���炭������A���̋����̂Ȃ����邢����������͂���ł������̂��Ɗ������n�߂܂����B �Ԃ͌��֘e�̌C����̏�Ə��̊Ԃ̓��Ɋ������Ă��܂����B�t�����g�ō��z�������̂ł����A�����ʼn��߂Ă̂����o��������A�}���َq�̎��\�������������܂����B����ɁA��ŌW�̒��������A�ɗ��āA�u���Ȃ̔��e�v�Ɩ������o���Ă���܂����B�����A�����C�ɂ����ƍs���Ă������߁A���̒�������̈��A�����̂͂T���߂��������̂ŁA�ڂ��́u���Ȃ̔��e�v�͗[�H��̃f�U�[�g�ւƉ��܂����B�����A�t�����g�ō��z�������Ƃ����A�����ɒ����Ă��������Ă�������Ƃ������i�肪���������̂͂�����Ǝc�O�ł��B�ǂ��炩�ł͂����ڂ肪�~�����Ƃ���ł��B�܂��A���߂̋C�Â����������A���ǁA��ŃT�C�Y�Ⴂ�������Ă��Ă��炢�܂����B����ɁA�������C���^�[�t�H�������̊Ԃɒu����Ă��܂����B�������A�����̃L�[�͓�{����A���������Ă��܂����A����͂��ł��D���Ȏ��ɂ��ꂼ�ꂪ�����C�ɍs����̂Ŕ��ɂ��肪�����A�]���������Ǝv���܂��B �����C�͒j������K�A��������K�̂��ꂼ��C���ɂ���j�����͂���܂���B�����͖钆�̈ꎞ�܂ʼn\�ł��B�C�ɖʂ��������C�͍��w�K�ɂ���̂���ʓI���Ǝv���܂����A�����͈�K�Ɠ�K�Ȃ̂Œ��߂͂��܂�ǂ�����܂���B�嗁��͊C�ɗՂޑ����ɓ��D������A���邭���D������ƍL�߂ł�����肵�Ă��܂��B�I�V�͑嗁�ꂩ�炳��ɊC���ɏo��`�ł����A��K�ł��̂Ŏ������������͂܂�Ă��邽�߁A�����̊O�ŗ����オ��Ȃ��ƊC�������܂��A��������ƊO�̓�������Ă���l�Ɩڂ������Ă��܂��\��������A���������Ȃ��ł��B ���C��ɂ���f���ɂ��ƁA�����͌���̉��x���������߉������Ă�����̂̑嗁����I�V��������ł���A�z��߂͂��Ă��Ȃ������ł��B�͉��h�����������ꖡ�����銴���ł����B �E�ߏ��ɂ̓t�F�C�X�^�I�������R�Ɏg����悤�ɒu����Ă��܂����B�܂��A�����S�I�ɑI�ꂽ�Ƃ����u�V�̐^����v�Ƃ����V�R�����������␅�@���ݒu����Ă��܂����B�����������ł����B |
| �H���͕����ł��������܂����B���i�����͂���܂���ł������A�����͂���܂����B�v���o���܂܂ɕ��ׂ�ƁA�H�O���̔~���B�����̂���Ԃ���ԁA�������̔�����B�������|�B�O�V�_����i���A�I�̎ς�����A�T�[�����������j�B��t���̎ԊC�V�̏Ă����A��̔��q�A�����H�@�������킹�B���q�����A������̒n�܁A�ߑ�A�ÊC�V�A�A�I���C�J�A�j�V�K�C�Ȃǂł����B��̂ɂ����Ă��������Ǝv���܂��B���ɂ������̔����₨����͂������ɑN�x���悭�A�ƂĂ������������̂ł����B�������A�S�̓I�ɂ͑O���̗��ّ勴�قǂ̃C���p�N�g�͂���܂���B�f�U�[�g�̓L�[�E�C�A�m�i�V�A����̑g�ݍ��킹�ł����B �����A��䉮�◷�ّ勴�����ق�̏������������̊��ɂ́A�ŏ��ɂقƂ�ǂ̗����������ė��Ă��܂��`�ŁA���Ƃ���o���ꂽ�̂͂�����ƒ��q�����A���ꂩ�炲�т�f�U�[�g�W�̂��݂̂̂ŁA���̕ӂ����Ɏc�O�Ɏv���܂����B��i��i���J�ɏo���ꂽ��A�H���̈�ۂ͂���w�悭�Ȃ����Ǝv���܂��B ���H�������ŁA���͂͂��͂��̈�銱�ł����B��������l������t���܂��B���ꂪ��������Ă��ĂȂ�Ƃ���i�ł����B�͂��͂��͈ȑO�H�c�ɍs�����Ƃ��ɉԐS������͂܂ŏ��߂ĐH�ׂ��̂ł����A�ӊO�ƍd���Ă��育�肵���H���ɒ���āA����Ȃ��̂��Ǝv���Ă��܂����B�ł�����A�����͂��͂��ƒm�������ɂ͂������肵���̂ł��B�������A����͑S�R����āA�|�݂��͋�����������A���ɂ����������̂ł����B���̑��A���̎M�̘e�ɒ|�ցB��̎ϕ��B�Ђ����B�C�J�\�[�����B���Ă��B�C�ہB�������Ƃ������C���i�b�v�ł����B�f�U�[�g�̓I�����W�ŁA���ރ��[�O���g�����Ă��܂����B��Ԃ̒��H�Ƃ����܂������������S�̓I�ɍD��ۂł����B �����͖��Ӄ��r�[�Ńt���[�g�̃R���T�[�g���s���Ă��܂��B�t�����g�S���̏]�ƈ����t���[�g�̃v���̉��t�Ƃł�����炵���̂ł��B���̂��Ƃ͍s���Ă݂ď��߂Ēm�����̂ł����A�[�H��Ɏv��ʊy���݂邱�Ƃ��ł��܂����B�ڂ������Ƃ͂悭������܂��A���̐l���o�X��܂ő���̎Ԃ��^�]���Ă��ꂽ�Z�����Ԃɏ����b�����Ƃ���A�ĂȂǂ̓��[���b�p�����ɍs���Ƃ������Ƃł����B �[�H���ɁA��������ɏ����̘b����o�����̂ł����A�����͏����͗���ɂ��Ă��Ă��Ȃ�����ǁA�Ꮧ���Ȃ�`�F�b�N�A�E�g�̎��ɂ��邾�낤�Ƃ������Ƃł����B�`�F�b�N�A�E�g�̎��ɂ�����͂������肻�̘b���Y��Ă��܂������A�Ꮧ���̕����琺�������Ă���܂����B��������̘b�ɂ��ƁA�܂������͂��Ă��Ȃ����̂̎Ꮧ�����K���Ƃ��Ă��łɊ������̂悤�ł��BH�o�ɏo�Ă���ʐ^�Ƃ͏�����ۂ͈Ⴄ�̂ł����A������ɂ��斾�邭���^�Ȋ����̂��鏗���ŁA�ق�̈ꌾ�����b���܂���ł��������ɍD��ۂ������܂����B �F�����̂����ǂ������Ȃ̂��悭�m��܂��A�����Ɨ[���̗�����������A���͂邩����C���̌i�F�A������̉���A���������C�̍K�A�����ɍX�Ȃ�H�v�Ɠw�͂������āA��w���W���Ă����悤�Ꮧ���ɃG�[���𑗂肽���Ǝv���܂��B |
| �@ |
| ���悢��R�A���l���ڂɂȂ�܂��B �Ďq�ɖ߂��Ă���ɗ�ԂŐ��i�B���]����^�N�V�[�ɏ��勴�قւƌ������܂����B �勴�ق͂i�s�a�̖����x�X�O�_�ȏ�̏h�̏�A�ŁA����A���̓��܂łɖK�˂��O�̗��ق��X�O�_�ȏ�ɓ�������O�ꂽ�肵�Ă���̂ɑ��āA���N�̂悤�ɖ���A�˂Ă��邱�Ƃ�A�l�b�g�Ō��Ă݂�Ƃ��̂X�O�_�ȏ�̒��ł����N�͏�ʂɈʒu���Ă������Ȋ����Ŕ��ɋ������������̂ł��B�ꎞ�͐_�����ʑ�����̕��������߂Ƃ������ƂŁA�������F���ɂ��悤�Ǝv�����̂ł����A�Ȃ������̓������������ŁA����������̉����Ǝv���đ勴�قɌ��肵���̂ł����B�������A�p���t���b�g������������A�d�b�Ŗ⍇���������ł͂��܂薞���x�X�O�_�Ƃ�����ۂ��Ȃ��̂��s�v�c�ł����B ���]�勴�߂��ɂ���勴�قɉו���a���āA�����߂��݂̂Ȕ��ő�߂���H�ׁA�������珼�]��ւƕ�������A�x��߂�������āA�܂��勴�قɖ߂����玞�Ԃ͂��傤�ǃ`�F�b�N�C���̂R�����P�O�����x������Ƃ���ł����B ���r�[�Ŗ����Əo�_�O���Ƃ���������Q�Ȃǂ��O�w�ɏd�˂����ɂ��������}���َq�����������A���������]�Ɗ�����������A�����ւƈē�����܂����B �����͂T�K�̂T�O�Q�����u�����Łv�Ƃ��������ł����B�勴�ق͌����ɂ���ĂU�K���ŏ�K�̏ꍇ������̂ł����A�u�����Łv�̂��錚���ł͂��̊K���ŏ�K�ł����B�h�A���J���A���ɓ���ƍ��^�C���̌��ւɓ����̔̊Ԃ̓��ݍ��݁A�オ�����E���˂�����ɐ��ʂƂ��̍������ڂ̕��C�ŁA���C�̎�O�ɂ���g�C���̓V�����[�g�C���ł��B���ݍ��݂̐��ʂɂӂ��܂����Ă��A�J����Ə\��̘a���A����ɂ��̐�̑����ɓ�������炢�̍L��������܂��B�①�ɂ͍L���̒[�Ƃ����Â��^�C�v�̕����ł��B������͖ڂ̑O�̑勴������ǂ��āA�����E���ɏ��]�勴�A����Ɏ����Α勴�Ƒ����A���̐�̎����܂ň�]�̉��Ɍ��n����A�O���̊F���C�݂Ƃ͂܂������������߂̂������i���L�����Ă��܂��B���̌i�F���{�[���ƒ��߂Ă���̂��ǂ������ł��B �����A�����̑��삪�{���ɗތ^�I�Ȋ����ł��肩�Â��Ƃ����A����Ƃ����������⊴������v�f���Ȃ����ƁA����ɕ����ł̂����o�����Ȃ��ȂǁA�܂������ɓ������i�K�Ŗ����x�X�O�_�ȏ�Ƃ�������͂����ς�Y���Ă��܂���B�܂��A�^�I��������В��|�[�`���t���Ă��Ȃ��̂��ӊO�ł����B�������葫�܂�����܂���B�������A�Ԃ͌��ւ̌C���̏�Ə��̊ԂɊ������A�܂��A���߂̋C�Â����͂���܂����B |
| �����C�Ɋւ��Ă͒ʏ�͂R����������͂��ł����A�ǂ���������炩�u�����͂S������v�ƍ������܂����B���R�̐����͂���܂���B�ǂ����I�V���Ȃ����A�`�F�b�N�C���������Ԃ������قǂ͑����Ȃ��Ƃ������ƂŁA�ʂɂS���ł����܂�Ȃ��̂ł����A���R�����킸���k���������������I�Ȋ����ň���I�ɍ�������͔̂[���������܂���B ���̂����C�ł����A���q�ׂ��悤�ɘI�V���Ȃ��A�܂��A�n����K�ɂ���̂������̓����ł��B���Ԃ͂Q�S���܂łŗ����j����ւƂȂ�܂��B���̑嗁����Â��^�C������ŁA�̂Ȃ���̑嗁��Ƃ�����ۂł��B�����͍L���P�O�l���炢���ꂻ���ł����B��̈����L�߂Ɏ���A�ׂƂ̎d�肪�݂����Ă���̂ŁA�������Ƒ̂���Ƃ͂ł��܂��B�n���ɂ���̂ł����A���Ȃ��Ő^���ÂƂ����킯�ł͂Ȃ��A��ʂ���������̑��ɉ����āA�ꃁ�[�g�����炢�̕��ŏォ��@�艺�����A�ォ���������Ă���d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B�����ɐA���Ȃǂ��A�����Ă��āA����A���̂������Œn���̕NJ��͂��܂芴�����܂���B�������邾���ő啪��ۂ��Ⴂ�܂��B�E�ߏ�ɂ̓n���h�^�I�����p�ӂ���Ă��܂����B �����͓K���ŁA�G�߂ɂ���ĉ������Ă���悤�ł��B�\���ɂ��Ɖ��f���ł����Ă���炵���̂ł������f�L�͂��܂���ł����B����ɕ\���ɂ��Əz��߂ƕ����z�p���Ă���Ƃ̂��Ƃł����B �����͒����J�E���^�[�ɍ����Đ�̗���߂��铒���̕������ʂɂ���A�E�[�����������Ē������ނ��Ƃ��ł��܂��B�����A���ʂɂ��̂��߂ɌW�̐l���t���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�����ŏ���ɕ����ɓ����ė␅�@���璍���ň��ނ̂ł��B���̓���菈�͊m���S�����炾�Ƃ������Ƃł������A���̓��̂����C�̊J�n���ԁA�S�����傤�ǂɕ��C�ɏo�������ڂ��͕��C�ɓ���O�ɁA�����̕������Ăǂ�Ȋ����Ȃ낤�ƁA������Ɣ`���Ă݂��̂ł����A�S�����߂��Ă���̂ɏ]�ƈ��̈�l���܂����Q�����Ă��܂����B �����C����オ��ƁA��K�̃��r�[�̂Ƃ���ł��Ղ̉��t�����Ă��܂����B���傤�ǂ����ɂ��������炵���l�ƈꌾ�A���t�����킵���̂ł����A�����S��������V���܂ł͂��Ղ����t����Ƃ������Ƃł����B |
| �[�H�͕����ł��B���ʂ͕����ł̐H���ƂȂ�ƁA�e�[�u���ɒu����Ă������ق̐�������p���t���b�g�Ȃǎ�X�̂��̂����ꂢ�ɕЕt�����A����ɒ��J�ȂƂ��낾�ƃe�[�u���N���X���~����܂��B�������A�����ł͐��������̓e�[�u���̋��ɕЊ�ꂽ�����ł����B�����ŕ����̋��Ɏ����čs���܂������A����͏펯���^���܂��B �[�H�͂��i�����͂Ȃ��A�ڂ�������������܂���B�H�O���͕t�����A��t���̖�ƊC�̕��̘a�����O��ƑO�̊����[�X�g���ߌ킪���Ζ~�ɕ��ׂ��A�������̂���Ԃ���Ԃ��~�̊O�ɗp�ӂ���܂��B���̌�͈�i���^��A�܂��ÊC�V�A����ς��H�����A�C�J�̂�����B�����āA���q�����B���ɁA�������̕Ăł���͂����������̂ł����B����ɑ������̂ǂ���̎ϕt���������������������܂������A����������Z�����ȂƎv���܂����B���̌オ�������i�ŁA儏`�̐H���Ƒ����܂��B�f�U�[�g�̓p�C�i�b�v���ƃu�h�E�ł����B��͂�C�̂��̂����������A�S�̓I�ɖ����̂������̂ł������A�Ⴆ��L���Ƃ��������̂͊������܂���ł����B ���H�͐H�����ɕς��܂��B��̂ӂ��ߎρB�Ђ����B������ȂǎO��ނ̓������e��B�C�ہB�Ԃ�̏Ƃ�Ă��B�C�J�h���B�J�j�T���_�B�ȏオ��̖~�ɐ����ďo����܂��B�z�e���̘a��H�̂悤�Ȋ����ł��B�����g�������̂��Ȃ��A�܂��Ԃ�̏Ƃ�Ă��͂�͂薡���Z���ڂł����B�܂����������Ƃ͎v���܂����A���ɂ���Ƃ�������ۂ͂���܂���B�f�U�[�g�̓I�����W�ł����B ���̑勴�ق͍��s�����R�A�̎l�̗��ق̒��ł͍ł��]���ł��Ȃ��h�ł����B���C�̊J�n���ԂɊւ��邱�ƁA����菈�Ɋւ��邱�ƁA�[�H���̃e�[�u���Ɋւ��邱�Ƃ��]���ł��Ȃ��傫�ȗv���ł����A����ȊO�ɂ��������悤�ɋC�ɂȂ�Ƃ��낪����������܂��B�i�s�a�̖����x�X�O�_�ȏ�̏h�ɓ����Ă��邱�Ƃɑ傢�Ȃ�^����������Ȃ��h���ߋ��ɂ���������܂������A�����������ł����B�[�H�̎��ɒ�������ɂi�s�a�̖����x�X�O�_�ȏ�ɓ����Ă���Ƃ����b����o���ƁA��͂肪�����肷�邨�q������Ƃ������Ƃł����B�m���ɕ�����|�[�`�̂��Ƃœ��������r�[�ɂ������肷�邾�낤�ȂƎv���܂����B�i�s�a��ʂ��Ƃ�������������悤�ł����A���̕����͂ǂ��Ȃ�ł��傤�B�����킯�ł͂���܂��A����Ȃɋɒ[�ɂ����悤�ȗ\���͂��܂���B�A������A�i�s�a�̑����ł�����Ƙb��ɂ���ƁA�����͕]�����������A�ӊO�ɂ����C�̕]���������Ȃ��Ƃ������Ƃł����B�ɂ킩�ɐM�����Ȃ��C���ł��B�I�V���Ȃ����A�n���ɂ��邵�Ƃ������Ƃłi�s�a�̐l������Ђ˂��Ă��܂����B�i�s�a���Ӑ}�I�ɖ����x�𑀍삷��Ƃ������Ƃ͂��蓾�Ȃ����A�m���ɖ������ăA���P�[�g�ɓ������l������̂ł��傤���E�E �}�C�i�X�̗v�f����������܂������A�t�����g�ŏo�_��Ђւ̍s�����������˂��Ƃ��A�N�z�̒j�������ؒ��J�ɏ抷�w��s���������ɏ����ċ����Ă���܂����B�͂�����Ƃ͕�����Ȃ��̂ł����A�ǂ������̏h�̂���l�̂悤�ȋC�����܂��B���̑Ή������Ȃ當��Ȃ��ɖ����x�X�O�_�ȏ�̏h�ł��傤�B���̒j���̋q���v�����C������S���������Ă����Ƃ����Ǝv���܂��B�܂��A���[�͎�����]�ޕ�������̌i�F���������C�ɓ������悤�ł����B |
| �_�ސ쌧����k�ւ͈ꉞ�S���s���Ă���̂ł����A�܂��܂��s���Ă��Ȃ���������������܂��B�ڂ��ڂ��Ƃ��̕ӂ����߂Ă��������ȂƂ������ƂŁA����͏��̎O�d���ɍs�����Ƃɂ��܂����B���Ƃ����Ă��{��ňɐ��C�V����x�H�ׂĂ݂����A�Ƃ������[�̋�����]������܂����B���������č���͉���͓�̎��A�C�̍K�����C���̗��s�ł��B �Ƃ͂����A��͂艷����ɉz�������Ƃ͂���܂���B�i�s�a�̃p���t���b�g�����Ă݂�ƁA���H�̗��قɉ���̃}�[�N�����Ă��܂����B���ł��q����������قǑ����Ȃ��A�i�s�a�̕]�����������������A�z�e���m�V�ɂ��Ă݂܂����B���H�ɘA�������̋߂��ł����ꔑ�Ƃ������Ƃōŏ��͉��������u���Β��ɗ\���̂ł����A�C���^�[�l�b�g�Ō����N�`�R�~������Ȃ̂ŏh����T�ԑO�Ɂu�C�̍K�̃t�����`�v�Œm��l���m��u���ό��z�e���ɕύX���Ă��܂��܂����B ���É��ŐV��������芷���Ē��H�w�ɂ͂P���Q�O�����ɓ������܂����B1�����o���̌}���̎Ԃ�����Ƃ������Ƃł������A�}�C�N���o�X�����ꂽ�̂͂P�������肬��̎��Ԃł����B��Ԃɍ��킹�ĎԂ��o���ꍇ�A�������ɂ͗]�T�������đ҂��Ă��Ăق������̂ł��B�Ԃɂ͂P�T�l���炢�̐l��������荞�݂܂������A���̎��j���͂ڂ���l�A�����ɐl�C�̏h�ȂȂƎv���܂������A��Œ�������ɕ����Ă݂��Ƃ���A���̎Ԃ����܂��܂Œj�����͂���Ȃɋɒ[�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł����B �w����߂��̂��Ǝv���Ă�����A�h�͎ԂłR�O���߂�������Ƃ���ɂ���܂����B�Q������Ƀ`�F�b�N�C���B���g�����ꏏ�̃o�X�Œ����܂����̂ŏ��Ƀ��r�[�ő҂�����܂��B���ƂȂ����҂��Ă���ƁA�����̂Ƃ���\����܂��Ə]�ƈ�������Ă��āA�L�O�̎ʐ^���B�邽�߂ɂ킴�킴�Ȃ��ړ����ď���̂Ƃ���ɍ��炳��܂��B�͂́`�A�������̂悤�ɋL�O�ʐ^�������ȂƎv���ĕ����Ă���ƁA�Ȃ�ƗL���Ƃ̂��ƁB�����`�F�b�N�C�����Ċ��������q���A�����̏����̂��߂ɂ킴�킴�Ȃ��ړ�������Ƃ�����펯�ɂ͂�����܂������A�݂�Ȃ��ƂȂ����Ȃ��ړ����A���ԂɎʐ^���B���Ă��܂��B�����ǁA�f�W�J����N�ł������Ă��鎞��ɁA����Ȏʐ^���q�Ȃ��Ȃ����낤�ȂƎv���܂����B���̌�A�����Ə����ȍ����َq�����������A�����ɕ����ֈē�����܂����B �����̓t�����g�O�̃��r�[�͌C�̂܂܂Ȃ̂ł����A�����������r���ɌC��E���Ƃ��낪����A���������͏��~���̘L���ɑf���ƂȂ�ς�����`���ł��B�O�K���Ă̌����̓�K�Ƀt�����g������A�����������G���x�[�^�[�͂Ȃ��̂ŁA���̓�K�����K���̏��~�肪�K�v�ɂȂ�܂��B |
| �ʂ��ꂽ�����͂R�P�����́u�܌��v�Ƃ��������ł����B�����ł̂����o���͂���A�}���َq�́u��J�̋��v�Ƃ����������`�̂��َq�ł��B���߂̋C�Â����������āA���߂��������Ɨ������̓��ނ��p�ӂ���܂��B�T�C�Y�̐\��������������炵���A����ڂ����������̂��u����Ă��܂����B�������t���Ă��āA�S��ނ��炢�����]�̐V�����Ă���܂��B���������Ȃ̂Œn���̒����V���ɂ��Ă݂܂����B���̊Ԃɂ͂܂��ڂ݂̕S������������Ă��܂����B�Ƃ��낪�A�����ɂ͂��̕S���������Ƒ�ւ̉Ԃ��J�����Ă��āA�A���̉�X�ɂ������荇�킹�Ă����C����������܂����B�ŏI���ɂ͐���������߂����悤�Ȋ����ɂȂ��āA�S�����đ����ȂƎv���܂����B�␅�����߂���p�ӂ���Ă��܂��B ���L������e�����̃h�A�O�������������`�ɂȂ��Ă��܂��B�}���V�����Ō����A���R�[�u�Ƃ��������ŁA�L�����畔���ւ̏o���肪���ڌ����Ȃ��悤�ɔz������Ă��܂��B�����˂��J���ĕ����ɓ���Ƃ܂������̓��ݍ��݂�����܂��B���ݍ��݂̍����ɂ͗①�ɂƐ���������ł��܂��B�����A���̐����̎��͒Ⴍ��������ł���A���ɂ悵���̂悤�Ȃ��̂��~����Ă��āA�ǂ̂悤�Ɏg���̂����悭������܂���ł����B���ݍ��ݐ��ʂ̂ӂ��܂��J����ƘZ��̍T���̊Ԃ�����܂��B�������̕����͏������̂Ŏ����T�炢�ł��傤���B���̐�ɖ�������̏�q������A��q���J����Ƃ���ɐ�̎O����̍L���ɑ����Ă��܂��B�T���̊Ԃ�ʂ��č��ɂ���P�Q��̎厺�ɓ���܂��B�厺������E��̍L���ɏo����悤�ɂȂ��Ă���̂ł����A�L���Ƃ̋��������Ƃӂ��܂Ŏd���Ă��܂��B�厺����͐��ʏ��A���C�A�g�C�����W�܂�����s�ɒ��ڍs����悤�ɂȂ��Ă��āA���������ɔ����t�����Ă��܂��B�܂�A���ׂĂ�ߐ�Ύ厺�͍L��������Ɨ�������̕����ɂȂ�Ƃ������ƂŁA����͂Ȃ��Ȃ��̑��肾�Ǝv���܂����B��E�O�N�O�Ƀ��j���[�A�������Ƃ������ƂŁA���͌��̊C�Ξւ�ӂ���Ȃǂ̂����鍂�����ق̕����Ɠ������炢��������܂���B�厺�ƍL���̑�����͑O���̉����ƑO�̏��R�A�����ɊC�������܂��B�`�����݂͂���܂���B |
| �����C�̓��r�[��������O�ŗ����p�̃G���x�[�^�[�ɏ��A�n���ɍ~��܂��B�n���Ƃ����Ă��ΖʂɌ����Ă���`�̌����ł��̂Ō����炵�͏\���ɂ���܂��B�������Ԃ͖�̂P�Q���܂łŒ��͂U������j������サ�܂��B�嗁��͖��邭�A�^�Ɏl�p������������A�E�̕ǂɉ����Ċ╗�C���W���O�W�[�ƕ��ʂ̂����C�̓�Ɏd���Ă��܂��B���ꂼ��̗����͂���قǑ傫������܂���B���邢�����Ȋ����̑嗁��ł��B�I�V�͂��̑嗁�ꂩ��o��`�́A�l�l���炢�̊╗�C�ŁA�ڂ̑O��̖X�ɕ����A�E�����ɂ͂͂邩�ɊC�����n���܂��B�����A�ǂǂƐ����悭�������痬��o�邨�����z�ł��邱�Ƃ���Ă��܂��B�ŏ������̕��̘I�V�͑S�̂��X�̗t�Ɉ͂܂�Ă��āA�����炵���Ȃ�������ƈÂ߂ł��B ���̑嗁��̑O�ɓ���菈������A�J�E���^�[�ɒu���ꂽ�␅�@�ŗ₦�������������������ނ��Ƃ��ł��܂��B�����̌W�̒��������āA���̒�������ɂ��Ƃ����̂����͋߂��̓쐨���R���狂�ݓ����ĉ^��ł���Ƃ������Ƃł����B���C��̕\���ɂ������A�z�E���f�����Ə�����Ă��܂����B�������J���L�L�͂���܂���B�ŋ߂͉��f�����ł��J���L�L�̂��Ȃ��Ƃ��낪�����悤�ł��B �����͋��ݓ��Ƃ͌��������������܂�A�����Ȃ��Ȃ������܂���B�����A����肪�ׂ��������ł��邱�Ƃ�A�����������������������ł��邱�ƁA�嗁��̗����͂����ł��Ȃ��̂ɁA�I�V���C�͓��̉Ԃ������C�����s���Ȃ��̂����V���Ă��邱�ƂȂǁA�^�ѓ��ł���Ƃ�������ς�����������̂��A�C�ɂȂ邱�Ƃ�����������A������ŗ�^�Ƃ����C�ɂ͂Ȃ�܂���B�����̓V�����[�Ȃǂŗ������ɏo�Ă���̂ł����A�������ɂ����ł͗����Ă��܂����B����炪����̂��Ƃ��Ǝ������ł���̂Ȃ�A�Ȃ��Ȃ����������ł���Ƃ͌�����Ǝv���܂��B |
| �[�H�͕����ł��B�����C����オ���Ă���ƃe�[�u���ɔ����e�[�u���N���X���~����A���Ζ~�Ƃ��̏�ɒu���ꂽ���A�e�̂����ڂ肪�[�R�Ƃ����������܂��ŐÂ��ɗ�����҂��Ă���Ƃ�������ł��B�������҂����������̂�����܂����B �[�H�����肢�������ԂɁA�n�߂Ă��\��Ȃ����Ƃ����m�F�̓d�b�����炩���߂����Ă��痿�����^��܂��B�H�O���͔~���ŁA�܂��O�̋G�߂̒����O��i�����̉��h�A�O�����s�[�X���A��܂����j���^��A�����Ă�����̋G�߂̋��퐷��i�J���n�M�̎p������̂�n�������傤��Ƌ��ɐH�ׂ���́A�������A��A�C�V�A���j�ł��̃J���n�M���̂ŐH�ׂ����͉��Ƃ��������f���炵�����̂ł����B�܂��A���̑��̋������邩��ɐV�N���̂��̂Ő\��������܂���B�܂��A�J���n�M�͎p����ł�����{�����[���������Ղ肠��܂��B�����āA�҂��Ă܂����ɐ��C�V�̐�������B�܂�����Ɏ葫�����C�V���C�ɂ��Ȃ���H�ׂ�A�Â��Ղ�Ղ�Ƃ������̐g�͂����Ղ�Ƃ����ď\���Ɋ��\���܂����B�喞���ł��B�����Ă������̒��q�����ŁA�����͗x��H�����悭�o����܂����A�x��H���͖��Ƃ��Ă��������Ǝv�����Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A���̑O�͂ǂ���������������d���Ƃ��납��n�߂����͊i���ɋ߂����̂������Ă�����ꂽ�����ł����B����ɔ�ׂāA���̔����̂��������B�������i�ł����B�����Ă��G�߂̎O��̎ϕ��i���ڂ���A�卪�A�C�V�̐������킹�j�Ƒ�̍������ŁA���̍������������������̂ł��B�����Ă̂��т̕��ƍ������킹���Ƃ������т����߂���f���炵���A���̌�ɁA��t���̌����ʎq�Ȃ߂��R���\���[���[���o�Ă��܂������A���ԂȂǂ����܂��Ȃ��ɂ���������������̂ł����B�����A��t���ɂ��Ă͏o�Ă���̂����т����߂�̌�ƁA�����Ԃ�x�������̂͂ǂ�������Ȃ̂�������܂���B����ɔ��g���̏t���A�킩�߂ƊL�̋G�߂̐|���Ƒ����A���Ȃ肨�Ȃ��������ς��ɂȂ�����Ⴢ��Ă����悤�ł������A�Ō�̐H���͔������т��A�߂��Ԃ̎G����I�ׂ�Ƃ������Ƃł����B�߂��Ԃ̎G���𗊂݂܂������A�܂��܂�����������������̂ł����B�f�U�[�g�̃t���[�c�[���[�������܂��B�Ƃɂ����C�̍K�̃{�����[�����_�ŁA���̒`���������ł����������ς��ɂȂ�H���ł��B�ق�̂�����Ƃ��̍������ق��A����ȍ����ȐH�����ڂ��͍D���ł��B�H���̎��͂��i�����͂Ȃ������̂ł����A���i�����͂Ȃ��̂��Ƃ�������ɒ�������Ŋȗ��Ȃ��̂������Ă��Ă���܂����B�Ō�̃��X�^�C���Ƃ��������̎��Ԃɏ��������A�ɗ��܂������A�q���͂قƂ�lj��炵���A�Z�������ł��܂�b�͂ł��܂���ł����B����Ƃ��������̏�������ł����B �����̒��H�������ł��B��T���_�A�C�J�\�[�����A���Ă��A���ƃI�N���̘a�����A�������A�C�ہA�ɐ��C�V�̖��X�`�A�f�U�[�g���������ƃ��C�V�i���C�`�j�Ƃ������ɕ��ׂ��A�������҂����ȂƎv���Ă悭����ƁA�Ă���������܂���B�����Ǝv���āA�Ă������Ȃ����Ƃ��w�E����ƁA��������́A����Ă镗���Ȃ��A�����Ƃ��������̂ō����͕t���Ȃ������|�̈Ӗ��s���̐����ł����B���܂łŘA���̎��ł���A�ǂ�ȂɈ������قł��꒩�H�ɏĂ������o�Ȃ��������Ƃ͈�x���Ȃ������Ǝv���܂��B�[���ł��܂���ł������A����Ȃ��̂��Ɛ[���Njy�͂��܂���ł����B���͗ǂ��A�Ă���������Ε���Ȃ��ł��B |
| �����͂��ɐ��Q��֏o�����A�A���Ă����̂͂R���߂��ł����B�t�����g�ŃL�[�����A����m�����镔���֍s���ƁA�Ȃ�ƃh�A���J���������B�M�d�i�͂Ȃ��Ƃ͌����A�o�b�N����X�̂��̂������̒��ɒu�����ςȂ����Ƃ����̂ɂł��B����ɂ͊J���������ӂ�����܂���ł����B���Ɉُ�͂Ȃ������̂ʼn��������܂���ł������A����͈ꌾ�t�����g�Ɍ����Ă����ׂ��������Ǝv���܂��B�h�A���܂��Ă���Ȃ�܂������A�S�J��Ԃł����B�S�J�Ƃ����A�L���̑����肩�A�����̃h�A�܂őS�J�ł����B����ۂǕ���ʂ��̂��D���ȏh���ƌ����܂����A���Ԃ̓`�F�b�N�C�����Ԃ̂R�����߂��Ă��܂��B�q�����鎞�ԂɂȂ�O�ɂ͕߂Ă����ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B�S�J�̂������ŕ����ɂ̓n�G���R�C�������Ă��܂����B����ȏ�Ԃŗ[�H�ȂǐH�ׂ�������܂���B���[�͗[�H�O�̕��C�ɏo������O�Ƀt�����g�ɓd�b�����āA�߂�܂łɎ���Ă����Ăق����|��`���Ă��܂������A�[�H�O�̖Z�����Z�����ԂɁA���������n�G�����͓̂�����낤�ȂƎv���Ȃ���A���Ă���ƁA�����Ɉ�C�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�������ʂȃn�G���ŐV����ł�����̂ł��傤���B�����Ă݂���̂��Ǝv���܂����B�܂��A����ڂ̌}���َq�͍���ƕς�炸��J�̋��ł����B �����C����A���Ă���ƁA��͂����Ɠ����������e�[�u���N���X���|�����Ă��܂��B�܂��A���炩���߂̓d�b�������Ă��痿�����^��Ă��܂����B�����͐H�O���͂Ȃ��A��t���̑������̖����q�a���ƁA�������t������̂͒������̂ł����V���������A�����āA�����肪�����̓C�T�L�̎p����ɁA��A�T�[�����A�ÊC�V�Ƃ������C���i�b�v�ł����B����̊̂̂悤�Ȓ����͂Ȃ��������̂̂�͂�V�N�ł����������ł��B�����āA�W���̂������̎p�����A�����āA�ϕ����ԋ��i�킪�j�ϕt���ł����A������Ɩ����Z���C�����܂����B�����Ă�����̈ɐ��C�V�ɑ���鸂̓��Ă��ł��B����̊��͂��̈ɐ��C�V��鸂���I�Ԃ��Ƃ��ł���̂ł����A�A���Ƃ������Ƃŏ������ɐ��C�V�A����ڂ�鸂Ƃ����̂ł��B����鸂����̂������肵�������������̂ł����B�����Ă������̃l�[�Y�Ă��ŁA���̃l�[�Y�Ƃ̓}���l�[�Y�̂��ƂŁA�����̏�Ƀ}���l�[�Y�������ăO���^���̂悤�ɏĂ������̂ŁA�ڐ悪�ς���Ă������������Ǝv���܂��B�����āA�m�M���������̂����ł����B�Ō�ɏ��㋍�̐ΏĂŁA����ڂ͓����o�܂����B�ΏĂƌ����Ă����̂悤�ɕ������Ȃ��Ă��āA���ʂ݂̐����ɐɓ����������Ƃ������Ƃ�����܂���B�Ӗ�����ŐH�ׂ�̂ł����A���̌Ӗ����ꂪ�h���̂��c�O�ŁA���������Â��Ă������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�h�����ē��̎|�݂�ł������Ă��܂����悤�ȋC�����܂��B���łɂ��Ȃ肨���������ς��ɂȂ��Ă����̂Ɛh���Ӗ�����ŁA���㋍�Ɋ����Ƃ����Ƃ���܂ōs���Ȃ������̂��������Ƃ���ł����B�S�̓I�ɂ͍���̕����C���p�N�g�������Ǝv���܂����A�������A���̓����قƂ�ǂ��������āA�\���ɖ�����������܂����B���͂�͍���Ɠ����A�߂��Ԃ̎G����I�сA���̓��̃f�U�[�g�̓o�j���̔Z���ȃA�C�X�N���[���ł����B�����A�������ƐH�ׂĂ������ߎ��Ԃ��x���Ȃ����̂��A�f�U�[�g�̃A�C�X�N���[����H�ׂĂ邤���ɕЕt���ɗ����̂͂��������܂���B���̓������i�����͂Ȃ������̂ł����A����Ɠ��l�̂��̂���Ŏ����Ă��Ă��炢�܂����B |
| ����ڂ̒��H�͂������Ă����͕t���Ă��܂��B�������Ă����X�Ƃł��ĂԂׂ����̂��o����܂����B����͂�����p�t���X���������ɂ܂Ԃ��ďĂ��ĐH�ׂ�Ƃ����������̂��̂ł��B���ꂩ��A�̂�����ρB�����āA�n���T���_�B���̒��ɂ�䕂�������Ă��āA�����̓f�U�[�g�M���t���Ă��Ȃ��̂ł��̑ւ�肩�Ǝv���܂��B�C�ہB���B�T�[�����̎h�g�Ƃ���A����ɃJ���C�̈�銱���T���̊ԂŌW�̐l���Ă��Ă���Ă��܂��B����͏Ă��������ނ��t���Ă��܂����B��������A��͍���ɉ����̂ɂƎv�킸�ɂ͂����܂���B�Ɨ������f�U�[�g���Ȃ��̂��c�O�ł������A�T�[�����̎h�g�͂������������ł����A�X�Y�L���J���C���\�������ł��܂����B �����قǁA�����Ƃ���ƍ���̂Ƃ��낪���ɒ[�ɕ݂���h�����Ȃ��Ǝv���܂��B�����Ƃ���͂܂������ł����B�S�̓I�ɍL���A�厺���璼�ڐ��ʏ��֍s������A�L�����Ɨ����Ă�����A�������悤�ɗ������������P���~���炢�����h�̃��x���ɂ͏\���s���Ă����Ǝv���܂��B�����Ă̂����Ƃ���́A�H���Ƀ{�����[��������f�ނ������Ƃ������Ƃł��B�������A���N���Ȃǂɂ͐H���̃{�����[�����t�]������Ă��܂����������܂����A�C�̍K�̏h�Ƃ��ẮA�ڂ����s�������܂ł̃x�X�g�R�ɓ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���h�ȂǂŁA�u�����A���̒l�i�ł���ȂɁv�Ƃ����̂��s�u�Ȃǂł悭����Ă��܂����A����̏����ꂢ�ȏh�o�[�W�����ƌ����Ă����ł��傤�B�Ƃɂ����A���������ŁA�C�̍K�����\�������Ƃ����l�ɂ͂����Ă��̏h�ƌ�����ł��傤�B�������A�ŏ��̒��H�ɏĂ������Ȃ��̂͑�^��ł������B ��������ɂ��Ă͈�T�ɂ͌����܂��A�S�����Ă��ꂽ���������̎Ⴂ��l�́A�ӂ��͂Ȃ����i���������Ƃ�����Ȋ�������ɍH�ʂ��Ď����Ă��Ă��ꂽ���A�ɐ��_�{�֍s�����߂̃p���t���b�g���������猾���o���ē͂��Ă���܂����B�]���������Ǝv���܂��B �����_�̂P�͂܂��`�F�b�N�C���̎��ɗL���Ŕ���t���邽�߂����ɁA�����������x�݂����q�ɂ킴�킴�Ȃ��ړ������ʐ^���B�邱�Ƃł��B���̎ʐ^�͂R�킠��A���ꂼ�ꂪ�P�O�O�O�~�����܂��B�S�������Ƃ���ƂR�O�O�O�~�������ł��B���̓��͎̓q�����܂��̂悤�ȂP���~�D�̏ё������ɂ��ꂼ��̋q�̊炪�����Ă���Ƃ������̂ł��B����Ȃ��̒N�������̂��A����������͂��Ȃ����낤�Ǝv���Ă���ƁA���[���O���Ƃ��S�������Ă��܂����E�E�E����͂Ƃ������A�ŋ߂͂���Ă��鎩���őI�ׂ�J���[���߂̃����^�����L���ŁA�m���ꖇ���P�T�O�O�~���炢�����Ǝv���܂��B����̂Ȃ疳���̃T�[�r�X�ł���ׂ��Ƃ����L���ł��Ă���Ƃ������������܂����B ���̂Q�͏������悤�ɓڂ̏h�ɖ߂�Ɖו����u���ꂽ�܂ܕ������J���������ɂȂ��Ă������ƁB���̂��N����Ȃ��ėǂ������Ǝv���܂��B ���ƁA�����C�Ɋւ��ẮA��������ł��Ȃ��Ƃ��낪�S�ɂ킾���܂��Ă��܂��B �ƁA�]���̂Ԃ�̑傫�����̃z�e���m�V�ł����A��͂�S�̓I�ɂ͗ǂ���ۂ������c���Ă��܂��B�ʐ^�B�e�������Ȃ�A���������C����������ɂȂ����炩�Ȃ�̂����߂̏h�ɂȂ��ł����B |
| �@ |
| �ɐ��u���̎O���ڂ́u�u���ό��z�e���v�ł��B�����͒m��l���m��u�C�̍K�t�����X�����v�̃z�e���ŁA���{�̃t�����X���������ۂɂ͊O�����Ƃ̂ł��Ȃ��z�e���炵���̂ł����A���͂����m�����̂́A���̗��s�����܂�����A���łɎu���Β��ɐ\�����ゾ�����̂ł��B�m�����̂͂ق�̋��R�ŁA���ƂȂ��Ă͂��ꂪ���������̂��v���o���Ȃ��قǂ����ۂ��Ȃ��������������̂ł����A���ׂĂ݂�ƁA���̓`���I�ȗ������ł��鍂�����V�Ƃ����l�����̃z�e���Œn���̐H�ނ����ɓƑn�I�ȃt�����X������n��グ���Ƃ������Ƃ�������܂����B���̒��ő�\�I�Ȃ��̂��u�ɐ��C�V�̃N���[���X�[�v�v�Ɓu��鸂̃X�e�[�L�v���Ƃ������Ƃł����B�����������͉��N���O�ɂ��̃z�e�����������̂ł����A���̖��͒�q�̗����l�ɂ���Ă܂��p����Ă���炵���Ƃ������Ƃł����B �u�u���ό��z�e���v�͉���ł��Ȃ����A�嗁�������܂���B����ɂЂ������u�u���Β��v�͉���ł���g�o������ƃ��P�[�V�������������Ȃ��Ȃ��ǂ������Ŗ��͓I�ł��B�����A�����܂Łu�C�̍K�t�����X�����v�ɂ��Ēm���Ă��܂��ƁA����͐���H�ׂĂ݂Ȃ���Ȃ�܂��Ƃ����C�ɂȂ��Ă��܂����B����ɁA�\����Ō����u�u���Β��v�̕]�����v�����قǂɂ͖F�����Ȃ����Ƃ�����A�v�����ė\����u�u���ό��z�e���v�ɕύX���Ă��܂��܂����B �u�u���ό��z�e���v�ɂ͌����w����R�O���Ɉ�{�قǂ̑��}�����������悤�ł��B�P�Q���O�Ɍ����ɒ������̂ŁA���傤�ljw�O�ɗ��Ă������}�Ԃɉו��������^��ł��炢�A�H���Ɖp��p�߂���ɏo�����܂����B �p��p�߂��肩��A������X���܂��w�O�Ɏ~�܂��Ă������}�Ԃɏ�荞�݁A�z�e���ɓ��������̂͂Q���R�T�����ł����B�w����z�e���܂ł͎ԂŌܕ��������炸�A��������ɁA���ꂾ����������Ă����v�������ȂƎv���܂����B�����ɕ����Ɉē�����܂����B �����͂S�Q�Q�����ŁA�R�Q�u�̃c�C���B�����I�[�\�h�b�N�X�ȕ����̂���ł��B�����Ă����E��ɃN���[�[�b�g�A���Α������ʁE�V�����[�g�C���E�o�X�̃��j�b�g�ł�����Ɨ����̕����������ȂƎv���܂����B��������Ƀc�C���̃x�b�h�A���Α��ɗ①�ɂ�h���b�T�[���p�f�X�N���u����A�E���̃R�[�i�[�Ƀe���r���Ɨ����Ă���܂��B���Α��̃R�[�i�[�ɂ͓�l�|���̃\�t�@�ƃe�[�u�����������瑤�Ɉ֎q����r�u����Ă��܂����B�x�����_���Ȃ��A�����ǑS�̂̕��̂Ȃ����������̂Ȃ̂ŁA�O�̉p��p�ɕ����Ԑ^�삢�����̌i�F���v�������͊y���߂܂���B�܂��A�����̒��x�Ȃǂ����N����o�����̂ŁA�����ɓ������r�[�Ɂu�킟���I�I�v�Ƃ���������������������͈̂������܂���B�����A���̑���ɁA���������������ł���Ƃ������Ƃ͂ł��܂��B�����̏h�������͍��߂ł����A�ł����̂��Ȃ�̕������[�H�̐H���ɂ��Ă��銴���Ȃ̂ŁA�����Ɋւ��Ă͂��܂荂�]�݂�����͍̂��Ƃ������̂Ȃ̂ł��傤�B�z�e���ɂ͌}���َq�Ȃǂ͒u���Ă��Ȃ��Ƃ��낪�����Ǝv���܂����A�����ɂ́u�ւ̌ˁv�Ƃ����������܂Ԃ��ꂽ�����Ȃ��َq���u����Ă��܂����B |
| �z�e���ɂ͂����h�����邾���łȂ��A�z�e������T������y���݂Ƃ������̂�����܂��B���̎u���ό��z�e���ɂ͂܂��L��Ȓ낪����A�������ƎU�����Ď����߂������Ƃ��ł��܂��B��ɂ̓v�[��������A�ւ͌����Ă�����́A�p��p�߂���̑D�̐�p�D���������悤�ł��B�܂���K�ɂ͏������Ȃ�����h�[���n�E�X���W�߂��~���[�W�A���̂悤�ȂƂ��������A���X���L�����̂ł��B����ɏオ��ƂR�U�O�x�A�ǂ������Ă��C�ƗƓ��̌i�F���L����܂��B�܂��A�G�������|�����A���X�g�����̃��E���[���ɂ͓��c�k���̊G������Ƃ������Ƃł��B�S�̂ɖڐV�����͂Ȃ����̂́A�`���̃z�e���Ƃ��Ă̂ǂ����肵�����̐[���������܂����B �[�H�͈�K�̂��̃��X�g�����A���E���[���ł��B�H�����Ԃ����x�߂̂V���ɂ����̂ŁA�����̐l�����łɐȂɒ����Ă��܂����B�����̃��j���[�́A�ɐ��C�V�̃T���_�@�ɐ��C�V�h���b�V���O�A�ɐ��C�V�̃N���[���X�[�v�A�{���̋��̃|�A���A�V���[�x�b�g�A鸃X�e�[�L�@�u�[���m���[�b�g�\�[�X�A�f�U�[�g�A�R�[�q�[�ƂȂ��Ă��܂��B����ɂ���ɏ��㋍�̃X�e�[�L���t���R�[�X������炵���̂ł����A���܂�~�����Ă͂����Ȃ��Ƃ����Ɖ䖝���܂����B �ɐ��C�V�̃T���_�͈ɐ��C�V�̊k���e�ɕt�������h�Ȃ��̂ŁA�^�ɖ�ؗނ��A��������͂�ňɐ��C�V�̐�g�����ׂ��Ă��錋�\�{�����[���̂�����̂ł��B��g�͂ǂ̂悤�ɏ��������̂������܂���ł������A�����Ȃ��Ă��܂����̂ł����炭䥂ł��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A�Ղ�Ղ肵�������͂����Ǝc����Ă��܂����B��ɂ͉��F���ۂ��h���b�V���O�A�ɐ��C�V�̐�g�ɂ̓I�����W���ۂ��F�̃h���b�V���O���|�����āA���̃I�����W�F�̕����ɐ��C�V�h���b�V���O���Ǝv���܂��B���̃h���b�V���O�Ɋւ��ẮA�ǂ�Ȗ����������A������ƋL�������ł��܂����A�����������M�ł��������Ƃ͊ԈႢ����܂���B���̈ɐ��C�V�N���[���X�[�v��鸃N���[���X�[�v�Ƃ̂ǂ��炩��I�Ԃ��Ƃ��ł���̂ł����A��͂��]�̂���ɐ��C�V�N���[���X�[�v�̕��ɂ��Ă݂܂����B���̃N���[���X�[�v�͈ɐ��C�V�̊k�t���ŏo�����ꍇ������悤�ł����A����͊k���Ȃ������ɃX�[�v�����ł����B�����炭�O�̈ɐ��C�V�̃T���_�Ɋk���g���Ă���̂ŁA�k���������Ƃ�������̂��Ǝv���܂��B�J�b�v�ɂȂ݂Ȃ݂ƒ����ꂽ�X�[�v�̕\�ʂɁA�܂�ʼnp��p�̓��X�̂悤�ɔZ�����F�̕�����������ł��܂��B����͐����������Ă��܂����̂ł����A�����炭�X�[�v�̏�ɉ������ׂĂ���ɏĂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ƃɂ����ɐ��C�V�̎|�݂��Ïk���ꂽ�Z���Ȗ��ŁA�Ȃ�قǂƂ��Ȃ炸�ɂ͂����Ȃ���i�ł��B���ꂪ���̃z�e���̖��������̈���Ƃ������Ƃ��\���ɔ[���ł��܂��B�����Ă��{���̋��̃|�A���@�t���[�c�\�[�X�ŁA�m�����̓��̓C�T�L�������悤�ɋL�����Ă���̂ł����A�L���Ⴂ��������܂���B�ӂ���ƏĂ��������������̂ł������A�ɐ��C�V�̃N���[���X�[�v�̌�ł͂���قNj���Ȉ�ۂ͎c���܂���B�������A���̂��ƍ�鸂̃X�e�[�L�ƂȂ邱�Ƃ��l����ƁA�ނ��낱�̋������͂��̂悤�Ɍy�������̕��������̂�������܂���B |
| �������̃V���[�x�b�g�̌オ���悢��鸃X�e�[�L�@�u�[���m���[�b�g�\�[�X�ł��B��������t�B�����̃X�e�[�L�Ƃ̂ǂ��炩��I�Ԃ��Ƃ��ł��܂����A����I�Ԑl�͑���鸃X�e�[�L���L���ł��邱�Ƃ�m��Ȃ����A���邢�͂���������H�ׂ����Ƃ�����Ƃ����l�ł��傤�B�������A�ڂ��͏��߂���鸃X�e�[�L���ړI�ł��B��Ŏʐ^������ƁA�^��Ă���鸂́A�i�s�a�̃Z�b�g�����̊W���炩�A���邢�͂��M���傫�������̂��A����قǑ傫��鸂ł͂Ȃ������悤�ł��B�ʐ^����Ō��āA����H�Ǝv���܂����B�������A���̏�Ō����Ƃ��͂��̑��݊��䂦�ɂł��傤���A�������������Ƃ͊����܂���ł����B���̌��݂̂��邱�ƁA鸂̌`�e�Ƃ��Ă͂���������������܂��A�܂��ɊہX�Ƒ������Ƃ��������ł��B�i�C�t�����Ă��艞��������܂��B�ł����������_�炩�����������A�m���Ƀi�C�t�������Ă����܂��B�������A����͊ہX�Ƒ����Ă��܂�����A���ׂ点�ăt�[�e���̓Ђ���̂悤�ɔ�����肵�Ȃ��悤�ɐT�d�ɐ�܂����B���ɓ��ꂽ�u�ԁA���ĐH�ׂ����Ƃ̂Ȃ����������ɍL����܂��B���܂ł̘a�H�ŐH�ׂ��x��Ă���鸂͊m���ɂ���������������ǁA���ĒP���Ȗ��������낤�Ǝv�킸�ɂ͂����܂���B���G�ŏd�w�I�Ȏ|�݂����|�I�ȗ͂������ĉ����Ă��āA�ڂ���ł��̂߂��܂����B����́A鸂���鸗����ƌ����Ă�������������܂���B����鸗����́A�m���Ɉ�x�H�ׂĂ݂鉿�l����Ǝv���܂����B�f�U�[�g�̓A�C�X�N���[���̂��M�ɉ����������Ԃ��F�̉ʕ����U�炵�����̂ł������A鸂Ɉ��|���ꂽ�������A���܂�L���Ɏc���Ă��܂���B ���܂ŁA�m�H�̒��H�ł̓{�����[�����܂߁A������������ꂽ���Ƃ����܂�Ȃ������̂ŁA���̃t�����`�͂���Ƃ��āA��͂蒩�H�͘a�H�ɂ��邱�Ƃɂ��܂����B�����ɂ́u�l�ؖȁv�Ƃ����a�H�̃��X�g����������܂��B��̃z�e���̒��̘a��H�Ƃ����̂͌��܂肫���Ă��܂����A��������͂�A���炩���߂��ׂĂ����ׂ�ꂽ���~����^��Ă��������ł����B�ق���̂��Z���A�����A���g���Ƒ卪�̎ϕ��A�T���_�A����ɁA���A�����A���Ⴑ�A�����킪�������ڂ������M�A�C�ہA���̊����A���̉��ɗ��Ă��A��̂��~�ɍڂ��Ă͂�����̂́A�l���Ă݂�ƕi���͂���A���ꂼ��ɋC�̔z��ꂽ�����������̂ł������A��͂肱�������`���ƒ�H���Œ�H�𗊂悤�ŗ��������܂���B�����ƍL���X�y�[�X�ł������ƐH�ׂ����C�����܂��B�܂����͊J���̓����J�b�g���Đg���ɕ����A�d�˂Ă��M�ɏ悹�邭�炢�̑傫�ڂ̂��̂ł������A���̏��Ƃ����_�ł͑��͘p�ߕӂ̂��̂ɂ͂��y�Ȃ��C�����܂����B �Ƃɂ����C�̍K�t�����X�����ŗL���ȓ`������z�e���ł���A�z�e���Ƃ��Ẳ��̐[�������������Ă��邪�A�����A�����Â�������������A����ȃz�e���ł��ˁB���q�������ǂ̂��炢�Ȃ̂��悭������܂��A�[�H�̃��X�g�����u���E���[���v�ł̓e�[�u�����ɔ䂵�āA����قǖ��܂��Ă����킯�ł͂���܂���B�܂��A�C�̍K�̃��j���[���A���ʂ̃t�����`���X�g�����ɔ�ׂ�Ƃ��Ȃ艿�i�̍������̂ł�����A���̈ɐ��ߕӂ̐l���������ł͂Ƃ��Ă��x�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƍl�����܂��B�܂�A���̃z�e���ƃ��X�g�����͑S������q���W�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��h���Â����Ă����ł��B���̓`���I�ȗ������Ńl�[���o�����[�̂��鍂�����V���̋��������A�ǂ̂悤�ɗ��j���p���A����ɔ��W�����Ă����̂��A���̃z�e���ƃ��X�g�����͏d�v�ȋǖʂɗ�������Ă���Ɗ������ɂ͂����܂���B |
| ���R�����A���y�����[�g�֍s���Ă��܂����B �������A����͂������̏�蕨�̏��p����A�ו��������Ă̈ړ��Ƃ������Ƃ��l���āA�l�I�ɂ��ꂱ��Ɠ���Y�܂���̂����ɂȂ�A�c�A�[�ɎQ�����邱�Ƃɂ��Ă��܂��܂����B�c�A�[�̌��_�Ƃ��ẮA�x���C�������A�E�g�̂��ߗ��قł������ł��Ȃ��A���������̊ό��n�ł����Ԃ̎��R�������Ȃ��A���ق����R�ɑI�ׂȂ��Ȃǂ��낢�날��̂ł����A�����������Y�܂���킸��킵������̉����I�킯�ł��B �z�[���y�[�W�ŗ��s�L�\����Ă������������������Ⴂ�܂����A���s���̏o�������Ƃ��Ă��o���Ă����Ȃ����A�����̂���ρA�Ƃ������ƂŁA�����̂悤�ɗ��ق̓��e�ɂ��ڂ��āA�����܂��B �Ƃ����Ă��A���̕��߂Ă̒c�̂ł̏h���ł��̂ŁA�����̂悤�ɗ��قɂ������؍݂��邱�Ƃ��ł����A����ɗ��s��Ђ��c�A�[�����̂����̂����炭�炢�����̗��قɂ����Ă���̂����s���Ȃ̂ŁA�����̕Ƃ͒P���ɔ�r�͂ł��܂���B���̂��Ƃ����炩���߂��f�肵�Ă����܂��B �܂������́A�V�����Œ����ցA��������z���ʂ̃o�X�ʼnF�ތ��Ɍ������܂��B�g���b�R��Ԃŏ��ނ܂ʼn������č����k�J�̌i�ς��y����A�܂��o�X�Ŏ�����ւƌ������܂����B �h�������̂́u�t�H�b�T�}�O�i�����쉷��v�́u�z�e��������v�ʼn�X�̕����͂S�O�U�����ł����B�h�A���J����Ɣ���قǂ̋������ւ�����A��O��̓��ݍ��݂ւƏオ��܂��B���ݍ��݂̎�O�A���ւ̉��ɂ͌��ւƏ����ȕǂŎd��ꂽ���ʏ�������A��������ڂł��B����Ƀg�C�������ׂ̗ɂ���A�V�����[�g�C���ł����B���ݍ��݂̐�ɂP�O��̘a��������A���̐�̂R����̍L���ւƑ����Ă��܂��B���̍L���͈�i������`�Ńe�[�u���ƈ֎q����r�u����Ă��܂����B�a���̍����ɔ������̃X�y�[�X������A�e���r�u���ꂪ�Ɨ����Ă���̂͂����̂ł����A�c��̏��̊Ԃɓ����镔�����A�����̂Ȃ������̔~���Ƃ��������̂Ƃ���ŁA�����Z�b�g�u����Ɖ����Ă��܂����B�Ԃ͂Ȃ��A�␅���Ō�܂ł���܂���ł����B �����A�i�F�͂��Ȃ�ǂ��A�P��̗���ׂ͍����̂́A�L���͌��ƁA���̓y��̎�O�ɂ͂��̏h�̒r�A�����ĉ����ɂ͎R�����n����Ƃ����S���炮���̂ł����B�������A�`�����݂�����܂���B�����A�ꕔ�̃z�e���̂悤�ɁA�����ǂ̉����̔������炢�����Ȃ��A�����ӎ����Ĕ`���Ȃ��ƌi�F���ڂɓ���Ȃ��Ƃ����Ƃ��낪���Ƃ��c�O�ŁA���������̌i�F��������Ă��Ȃ��\���ƂȂ��Ă��܂����B�����ɂ͌}���َq�̂Ƃ�남����Ƃ����A�˂��Ƃ�Ƃ����������\�����u���Ă���܂����B |
| �����C�͂Q�S���ԓ����n�j�ŁA�j�����͂���܂���B�L�X�Ƃ����嗁��ŁA���Ȃ�̐l�������ꂻ���ł��B���ɖʂ������̓��D�̉������̉���菭���Ⴍ�Ȃ��Ă��āA�������炨��������o�Ă��܂��B���D�ɂ͑����ʂ̂��������ꍞ��ł��܂����A���̃z�e���̌��֑O�ɂӂӂƗN���o�鉷��̓��ʂ���l����ƁA������̂������Ǝv���܂��B�����A�������Ă��邩�͕\�����Ȃ������̂ł悭������܂���B�܂��A���������Ԃ����Ԃ������̂ŁA�l���r��邱�Ƃ��Ȃ��A�ʐ^���B�ꂸ�A�����̂悤�ɂ͂������Ƃ͓���܂���ł����B�����͗𔒂Ŕ��߂��悤�Ȃ�≩�F�݂��������F�����Ă��܂��B�Ȃ߂Ă݂�Ɖ���ŁA�o�`�����h���������܂����B �I�V�͑嗁�ꂩ��o��`�ŁA���̑嗁��̃K���X���ƕ��s�ɍג�������ꂽ�╗�C�ł��B���͂���قǍL���Ȃ��̂ł����A������x����������܂��̂ŁA��������L�߂̂����C���ƌ�����ł��傤�B�P�O�l���炢�͓��ꂻ���ł��B�I�V�̑O�ɏ����Ȑ��H������Ă��āA���̐悪�y��̂悤�ɍ��������Ă��܂��B��ւ̊J�����͂���̂ł����A���߂͓y��ɂ��������Ă��܂��Ă��܂��B���̂�����́A�߂��̃z�e�����x����t�̘I�V�ƂȂ����悭���Ă��܂����B �H���͑啔���̐H�����ł��B��X�͒c�̂Ƃ͂����l�q�̏W���̂ł��̂ŁA�S�������Ă̊��t�Ȃǂ͂Ȃ��A�����炭���̌l�q�Ɠ����H�����������Ǝv���܂��B ���i�����͂Ȃ��A����������܂���B��X�̗[�H�͂V���J�n�������̂ł����A�J�j������ɂ�������炸�A8��15���ɂ͏I�����Ă��܂��܂����B���̃J�j�͍g�Y���C�K�j�Ƃ������ƂŁA��l�Ɉ�ς��t���Ă��܂������A���邩��ɔ��ɕn���ȃJ�j�ŁA�Ă̒�A�ǂ��̐g�������Ă��܂����B���ɂ͋��X�e�[�L�ƁA�䂸���炰�Ȃǂ̑O�؎O�i�B������̓L�X�Ɩڑ�A�ÊC�V�ƉG���B�G���̉��h�Ƃ�����C�����g�������̂�����܂����B�炪����܂������A����͓��e�A���Ƃ�����ł����B���̑��ɂ̓T�U�G�ƃo�[�i�L�̃K�[���b�N�o�^�[�Ă��A�ĉ֎q�̎ϕ��A�C�N�T���_�A�����āA�Ō�ɒ|���ɓ������O���^���̂悤�Ȃ��̂��o���ꂽ�̂ł����A�ʐ^�����Ă��ǂ�Ȃ��̂��������v���o���܂���B�f�U�[�g�̓t���[�c�ǐm�����ŁA����͂Ȃ��Ȃ������������̂ł����B �H������V�̉�X�͈�E�Ƃ��H���O���[�h�A�b�v�v�����ɂ����̂ł������A���̓��̐H���͂ǂ��ɂ��O���[�h�A�b�v���ꂽ�����͂��܂���ł����B��������ɕ�������A�l�q�̓��e�Ƃ͈قȂ��Ă���Ƃ������Ƃł����B��������Ă����̂͊C�̋߂����Ǝv�����̂ł����A���̊��ɂ͂��������o�Ȃ��������A���̏h�͂i�s�a�ł͈ꉞ���������̏h�ɓ����Ă���悤�Ȃ̂ł����A�S���[���ł��܂���ł����B ���H�͓������Ńo�C�L���O�ł��B�S�̂ɕi���͑����Ȃ��A���������������ʂ̊����œ��M����ׂ��Ƃ���͂܂���������܂���ł����B ���f�肵���悤�ɂ��̗��قɋ��z��������|���Ă���̂��s���Ȃ��߁A�Η����Ƃ��������̕]���͂ł��܂��A�����₨���C�͂܂������ł���Ǝv���܂��B���ɕ����̒��߂́A���������Ƃ͂����Ȃ��Ȃ��̂��̂�����܂��B�����A�H���Ɋւ��Ă͑傢�Ȃ�^�₪����Ƃ����Ƃ���ł��B������x�l�ōs�����Ƃ����ƁA�s���Ȃ��Ǝv���܂��B |
| �@ |
| �����͂W���ɏo�������R������������������ϕ����_�������Ə��p���ŁA�ڂ̑咬����u�����ό��z�e���v�ɔ��܂�܂����B �����͂S�T�P�����ł����B����ꂽ�����̘L�������������ɓ���ƁA�����̒��͋��ԈˑR�Ƃ��Ă��܂����B����̌��ւ���A�̊Ԉ����̓��ݍ��݂ɂ�����܂��B���ݍ��݂̂�������ɂ͐��ʑ䂪�ނ��o����Ă��āA���̑������ւ̂Ƃ���ɂ܂ł͂ݏo�Ă��܂��B�����̃h�A������Ă����E�ɂ̓g�C��������A���~����͈�x���ւŃX���b�p�𗚂��āA�g�C���ɓ���Ȃ���Ȃ�܂���B�g�C����p�̃X���b�p�͂Ȃ��A�L��������X���b�p�����ׂČ��p�Ƃ͂ǂ��ɂ��s���Ȋ��������܂��B ���ݍ��ݐ��ʂ̉����J���Ē��ɓ����10��̘a���ɂȂ��Ă��܂��B�����ɔ������̍����̂Ȃ����̊Ԃ��z����Ă���̂ł����A���������ׂăe���r�A�C���^�[�t�H���u����Ɖ����Ă��܂����B�������Ԃ͂���܂���B����ɐ�ɂR����̍L��������A�K���X������͗тƉ͌��A�����ɎR�Ƃ����A�z�e��������Ɠ����悤�Ȓ��߂��L�����Ă��܂��B�����A�����͖ڂ̑O�ɗт����邹���ŁA�S�̂̊J�����̓z�e��������̑�����̌i�F�̕����ǂ������Ǝv���܂��B�}���َq�͍����̑��z�Ƃ������َq�������̂ł����A�ǂ�Ȃ��َq�����������܂��ۂɎc���Ă��܂���B �嗁��͓V�䂪�R�������ɎO�p�`�ɍ�������Ă��čL�X�Ƃ��Ă��܂��B���D�����Ȃ�L�����̂ł��B�����͓������Ԃ���̂P�Q���܂łŁA�����͒j����ւƂ����V�X�e���ł����A���D�����̈Ⴂ�Ƃ��������ŁA�\����傫���͒j���łقƂ�Ǖς�肪����܂���B�����͖��F�������L�ł����A�Ȃ߂���ɁA�ق�̂������ȉ������c��悤�ȋC�����܂����B�����A�ق�̂������Ȃ��̂ŁA�C�̂�����������܂���B�����������炭�������肾�Ǝv���܂��B �I�V�͑嗁�ꂩ��o��`�ŁA���邢�͖Ŏl�p�����ꂽ�T�E�U�l������邭�炢�̂��̂ł��B�����X�ň͂܂�Ă��邽�߂���قǂ̊J�����͂���܂��A�����ɓ��������������p�̕��͑O���̒j���p��������̃X�y�[�X���L�X�Ƃ��Ă����C�����܂��B�嗁��A�I�V�Ƃ��K���ŁA���ɔM���Ƃ������Ƃ������Ƃ͂���܂���ł����B |
| �H���͂��̓����O���[�h�A�b�v�v�����Ƃ������ƂŁA���Ƃ������̐H�����ł��������܂����B��������ɕ������Ƃ���A���̓��̗����̓��e�͌l�q�Ɠ������e���Ƃ������Ƃł����B�������Ȃ�����A�������̖��O�̓��������i�������u����Ă��܂����B�܂��A�����̐���������A�����ƈ�i���^��ł���܂��B�ŏ��ɑO�̊⋛�̗��A�g���}���l�A�V�����̎O��ƁA������̐M�B�T�[�����A�⋛�A�ωG���B����ɁA�₵���̖������A�~�j�g�}�g�A�����������o����܂��B�����āA��̂��̂̎������Ⴊ�����A����B���ꂩ��A�ϕ�����⋛�̂����ł���͂����������̂ł����B���̂��̘o�q�����o�āA�Ă������Ă��g�}�g�A�M�B�T�[���������Ђ��A�~�j�I�N���A�G�S�}�������X�A����ɂ���ɕʂ̂��M�ŏĂ��������o����܂����B���i�����̏Ă����̒��ɂ͊m���ɏ����Ƃ���܂������A�����A�����X���C�X�������̂��t���āA���ɒu����Ă��邮�炢�̂��̂��낤�Ƒz�����Ă����Ƃ���A�ق�̂����ۂ��ȏ����ł����܂邲�ƁA�������Ɨ��������M�ŏo���ꂽ�͈̂ӊO�ŁA���̂����������Ă����������������܂����B���̐i�悪�n�h���ł���������������̂ł��B����ɁA�������������A���ԊC�V�A��Z�A���A���t�ŁA������̏����͈�ۂɎc��܂���ł������A�ԊC�V�͔��ɂ����������̂ł����B�Ō�Ɋ��тŁA�f�U�[�g�̓t���[�c�̐��荇�킹�ł����B�S�̂Ɉ�i��i�̃{�����[���͂��܂�Ȃ��A����t�����Ȃǂɂ��Â����Ƃ���͑S������܂��A�葢��̊������ǂ��o�Ă��āA�����������̂ł����B ���H�͂�������o�C�L���O�ŁA�S�̂ɂ��������Ǝv���܂����A���ɔ�тʂ������̂Ƃ����̂͂Ȃ������ł��B �����͑債�����Ƃ͂Ȃ����̂́A�����C�͂܂��܂��A�[�H�͈ӊO�Ƃ����Ƃ������ƂŁA���J���̏h�ɂ͂ǂ��t�������Ă�����܂��A�����������ł͂����߂̏h�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B |
| �����Ƃ����Εʏ������B���̕ʏ�����̋߂��ɏ��������������ɐH�ׂ��鏼������������Ƃ������ƂŁA���N���O����s���Ă݂����Ǝv���Ă����̂ł����A�Ƃ��Ƃ����N�s���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B�{���Ȃ珼���̃V�[�Y���̃s�[�N�ł���P�O�����{�������̂ł����A�P�O���̗��s�V�[�Y���͂����Ɖ����֍s�������Ƃ�����]�������āA����A�Ƃ肠�������������������I�[�v�����Ă��邱�Ƃ����A�X���ɍs���Ă݂悤���Ƃ������ƂɂȂ�܂����B���ʂƂ��Ă͂܂����������������悤�ŁA�����̊��ɂ͏����̃{�����[�������Ȃ��A���܂薞���ł��܂���ł������A�o����ɂȂ�̓{�����[���������A��ςȐl�o�ɂȂ邻���ł��B ����͂��Ă����A�ǂ����ʏ�����ɔ��܂�̂Ȃ�A�ȑO�A�����̓��ɔ��܂��āA����X����������ɔ��ɋC�ɂȂ����A�������{�X�ƗՐ�O�����ʑ��ɔ��܂��Ă݂悤�Ǝv���Ă��܂����B���Ȃ�O�ɉԉ��ɔ��܂������Ƃ�����̂ŁA���̓ɔ��܂�A�ʏ��̍s���Ă݂����������ق͂��ׂďh�����邱�ƂɂȂ�܂��B �����͗Ր�O�����ʑ��ł��B�ʏ�����̊e���ق̕ʏ�����w�ւ̌}���͗��يX�����̑�^�o�X�A����͂��ꂼ��̗��ق̎ԂƂ����V�X�e���ɂȂ��Ă���悤�ł��B�Q�������O�ɕʏ�����w�ɒ������̂ł����A�}���̍����o�X�ɏ�����O�g���ׂĂ̏h����͗Ր�O�����ʑ��ł����B �S�ُ��~���̗��قŁA�ŋ߂͂₯�ɏ��~����������ۂł��B�O�g���ꂼ�ꂪ���r�[�̈֎q�ł�����Ƒ҂�����A�����ƂƂ���Ă�����������܂����B�Ƃ���Ă�͐|�ݖ��ƍ����̂ǂ��炪������������܂��B�܂��A�����Ŋe���������̍D���ȕ��̃|�[�`��I�Ԃ��Ƃ��ł��A����͂Ȃ��Ȃ������A�C�f�A���Ǝv���܂����B�|�[�`��I�ׂ�̂͏��߂Ă������Ǝv���܂��B����ɁA�����͗�ɂ���āA�D���ȕ��̗��߂��I�Ԃ��Ƃ��ł��܂��B ���̈֎q�ł͐�q���A���܂ő҂�����̂��A�Ƃ��炢�炵���l�q�ł����B�����A�`�F�b�N�C�����Q������ł�����A�܂������߂��������ł��B���̂����ɉ�X�̔ԂɂȂ�A�����������Ă���j���������ֈē����Ă���܂��B��q��������A�O�g��������ɓ���������ŁA������ƖZ�������ȕ��͋C�ŁA�ē��̒j���͊����ӂ��ӂ��A�Ƃ����������ł����B �ē����ꂽ�̂͂P�R�P�����u�����܁v�Ƃ��������ł��B�O���猩�āA�ؑ��l�K���Ă̗��h�Ȍ����̐��ʎO�K�����ɂ�����̂����A�������ĉE���̕������Ǝv���܂��B���L����������Ĕ������̌��ւƔ���̓��ݍ��݂��ق�̂킸���Ȓi���ő����Ă��܂��B���̓��ݍ��݂ɏオ��ƁA�����E��̕ǂɏ�����P�T�Z���`�ギ�炢�̂Ƃ���ɕ����オ���������Ńh�A������A�������J����ƁA���ʂƃg�C���Ɨ�������̉��������j�b�g�o�X�ɂȂ��Ă��܂��B�g�C���̓V�����[�g�C���ł����A���邩��ɁA�̂Ȃ���̘a���Ƀ��j�b�g��Ƃߍ��݂܂����Ƃ��������ł��B�Â������Ȃ̂ŁA���������`�ɂȂ�̂͂�ނȂ��̂ł��傤�B�����A���������Ă���̂ł����A�ڂ��͕����̃o�X�͂���Ȃ��Ǝv���̂ł����E�E���ݍ��ݐ��ʂ��l�����̍T���̊ԂɂȂ��Ă��܂��B���ʂɃK���X��������A�O�̌i�F�������܂��B�T���̊Ԃɓ���ƁA�X�O�x�E��ɂW��̎厺�������Ă��܂��B�厺�̐��ʂɂ͂�⋷�ڂ̍L���ɋ�̏����ȗ①�ɂƁA�֎q����r�u����Ă��܂��B���߂̋C�Â���������܂����B ���̍L���ɖʂ����������̏h�̐��ʂɓ�����炵���A���l���̐l������ɊO�̓��H���炱����̎ʐ^���B���Ă��܂��B���̑����璭�߂�ƁA�E��͉���X�ŗ��ق̃r���Ȃǂ���������ŎG�R�Ƃ��Ă���̂ł����A���̔����ʑ������يX�̈�ԉ��Ƃ������ƂŁA�����͎R�⏬���������A�̖X�̔������i�F�ł��B�O�̌l���͔`�����݂�����̂ł����A��������Ă���̂ŋC�ɂ͂Ȃ�܂���B�厺�̉E���Ɉ����̏��̊ԂƁA�e���r�u���ꂪ����Ă���܂��B���̊Ԃɂ͂����ƉԂ��������Ă��܂����B���r�[�ł��łɂƂ���Ă�Ƃ��������̂ŁA�����ł̂����o���͂Ȃ��A�}���َq�̎��\�����u����Ă��邾���ł��B �����A�Â��ؑ��Ȃ̂ŁA�����͏��������Ƃǂ��ǂ��Ɖ������܂��B���̊K�ɂ͂��������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ォ��̉��͂܂��������Ȃ������̂ŁA�`�F�b�N�A�E�g����܂ŁA���̎O�K���ŏ�K���Ǝv���Ă��܂����B�`�F�b�N�A�E�g��A�O���猚���߂Ă��A�ŏ�K�̑��肪�ǂ����Ă��Ⴄ�̂ŁA���������ȁ`�Ǝv���A�O�̂��߂ɊK���𐔂�����l�K�܂ł����āA�����܂����B�����܂���ł������A�l�K�͑����h���̕����ł͂Ȃ��C�����܂��B�����͌Â��Ȃ�����K���X�𑽗p�����������O�ς����Ă��܂��B�������炵���l����������Ɏʐ^���B���Ă��闝�R��������܂����B�ڂ����ꖇ�B���Ă��܂����B |
| �����C�͒j���̌��͂Ȃ��A�钆�̂P�Q������Q���܂ł̐��|���Ԃ������Ă��ł�����邻���ł��B�����̂����C�̍ő�̓����͗��������~���ɂȂ��Ă��邱�ƂŁA���Ȃ�̂ɓ������l���̂�܂����قɂ���Ȃ����C���������悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��Ƃ����Ƃ���ł����A�L�����قƂ�ǂ���܂���̂ŏ��߂Ă̌o���Ƃ��������ł��B�ŋ߂͓��D�̒��܂ł����~���Ƃ����Ƃ��������݂����ł����A�������ɂ����܂łł͂���܂���ł����B�����A���̏�̗����͓����҂����Ȃ��ĐÂ��Ő����Ȃ����C�ɂ͎������Ǝv���̂ł����A�����̂悤�ɁA����p�X�|�[�g�̊Y�����قŁA���s��Ђ̓��߂���v�����̗��قł�����悤�ȁA���ɓ����҂̑��������C�ɂ͍���Ȃ��Ǝv���܂��B�ŏ��A�`�F�b�N�C����ɓ��������͂����ł��Ȃ������̂ł����A��Q��O�ɓ��������͗����̏��炩�ɍ����ۂ����ꂽ����������܂����B���ɋC�ɂȂ�܂��B�܂��A�`�F�b�N�C����̂܂��R���O�̒i�K�ŁA���@���}�b�g���т���т���ł������A���[�̌��t�ɂ��ƁA�����̒E�ߏ��͎U���������̖тő��̓��ݏ�������قlj���Ă��āA���܂łň�ԉ���Ă����E�ߏ��������Ƃ������Ƃł����B�j���̒E�ߏ��̃e�B�b�V������Ă��܂����B�����ɃV�F�[���B���O�t�H�[�����������̂͗ǂ��Ǝv���܂��B �����̓��D�͂R�E�S�l���x�̏����Ȃ��̂ŁA��͂肻�ꂾ���̗������������ɂ͏���������C�����܂��B���̓��̓����͔������Ă��āA�����ɂ̓R�b�v���u����Ă��܂��B���ނƁA��i�ȗ��L���Y���܂��B�I�V�͓�������o��`�̊╗�C�ł�����͂S�E�T�l�Ƃ��������ł��傤���B������͓����ł����A��͂蓒���ɂ���R�b�v�Ɍ�������Ƃ����͂܂������ς��Ȃ��悤�ł��B��͓̂����ɓ������������Ƃ������܂ł̂ڂ��̈�ۂ������̂ł����A�����͈Ⴄ�悤�ł��B�����͓����������ł����̂ŁA���������́A�����҂������������߂̂����̗Ƃ����C�����܂��B�I�V�͎�����Q�E�R���[�g���̍����Ŋ��S�Ɉ͂܂�Ă���A���ꂵ���قǂł͂���܂��J�����͂���܂���B���C��̓�����e�ɔ������u���Ă���܂��B�F�͔����̂ł����A���͂͂����肵�Ă��܂����B �܂��A�S���������Ȃ̂��͕�����܂��A�݂��蕗�C�Ɉ�������œ��邱�Ƃ��ł��܂����B����͗\�ԂɂȂ��ăt�����g�܂ōs���ƁA�킴�킴�ē��̐l���␅�������Ĉē����Ă����Ƃ����D��ȃT�[�r�X���t���Ă��܂����B�����C�͊ۂ��`�̓����C�ŁA��藧�Ăē����͂Ȃ������C�����܂��B �H���͂ڂ������͌��̐H�����ł��������܂������A�����ɂ���Ă͕����ł̐H���ɂȂ�悤�ł��B���i�����͂���܂����A�����͂���܂���ł����B�^��ł���͎̂Ⴂ�l���������̈�l�ɕ����Ă݂��Ƃ���A���o�C�g�������ł��B�H���̓��e�ɂ��Ă̏ڂ��������͖�����������܂���B�H�O���͉��c�Y�̐ԃ��C���ł������������܂����B���ʂ������Ɛ��ݖ����B�O�����I�ώρA���߂��L�n�ρA�v�`�Ԃǂ��A�I�a��ρA�R�����a���B���z�������A�H�̖��o�y�r�����B�Đ���ʼn��G���Ӗ��a���A�H�֎q���ՐX�āA�M�B�T�[�����h�g�A�g���ʔK�����N���[���\�[�X�ρA�H�����M�q�Ă��B��̕��͏�����p���v�L���X�[�v�d���B���������Ր�O���C�r�g���i���C�r��̓Ƃ������Ƃ������ŁA��Ńl�b�g�Œ��ׂ���A�x�m�{���Y�n�̂悤�ł��B�����������̂ł����B�j�p�ϋʁY�e���Q�B�ւ�蔫�����̂��\���B���H���ɏ�c�s���V���A���R�k�ꂳ�O�����߂����Ă���������̊��тɂ������́B�~�o���M�B�������X�d���āA�����^���B�f�U�[�g�����ԉʃ~���N㻁B�ȏオ���i�����ɏ�����Ă��܂����B��i��i�̃{�����[��������قǂȂ��̂ŁA���ƈ�E��i�~�����������������܂������A���ꂼ�ꂨ���������������܂����B�����A���C���̏����珉�߁A���ʂɃC���p�N�g�̂�����̂͂Ȃ������ł��B�������̂��ẮA�������薡�키�̂�Y��ĐH�ח����Ă��܂����̂ŁA���Ƃ������܂���B���Ƃ��Ƃ��Ă̖��͂��܂蕪����Ȃ��ق��ł�����E�E�������͂R�O��ł܂������֗��ĂR�N���炢�Ƃ�����������̘b�ł����B�ŏ��ɐH�O���A�O�Ƃ��ʂ������ׂ��A�����Ĉ�i���^��Ă��܂����A�y�[�X�͂��Ȃ葁���A�ŏ��̂S�O���ł��ƈ�i���c���݂̂ɂȂ��Ă��܂��܂����B�������т̊��т͐����オ��܂ŁA�S�O��������Ƃ������Ƃł������A�H���̍ŏ��ɁA��_���܂��傤���ƕ����Ă����̂ŁA���قƂ��Ă�����ȂɐH�����Ԃ����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�B |
| ���H����ӂƓ������ł��B���͈��̊ØI�ςʼn��Ƀs���h�̎ϒő����u����Ă��܂��B���т͔��Ƃ�ƒ����̑I�����ł��A���X�`���ܖڂƑ��̑I�����ł��܂��B���̑��ɂ̓T���_�B�Ђ����Ɠ��̌Ӗ��悲���B�����̂��Z���B�������B��W���[�X�B���J�쓤���X�̓����̗�z�B���̒��J�쓤���X�Ƃ����̂́A�ʏ�����ł͗L���ȓ����X�炵���ł��B�ł߂̖��x�̔Z�������Ƃ������������܂����B�������������̂������������ł��B�f�p�Ń{�����[���͂���܂��A�@�ׂȖ��ŁA�S�̂ɂ����������������܂����B ���̕ʏ�����X�̍ʼn��ɂ���A�Ր�O�����ʑ��͕ʏ�����ł����Ȃ�R���̂��闷�ق��Ǝv���܂��B�ؑ��l�K���ẮA�O�ς͂Ȃ��Ȃ��f���炵���G���g�����X���������܂��B���̍��͒�̂��̉Ԃ������炵���A�Ԍ���Ƃ��������ǂ��������A���̍��͏h�������������Ȃ�悤�ł��B���r�[���̃M�������[�ɂ͂��̏h��K�ꂽ�����l�̐F�������[�łȂ��قǂ̑����̐��������Ă��āA���̓`���Ɗi���������������܂��B �������A���݂͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���B�����������������ݒ�̕���������A�������p�X�|�[�g�̏h�Ƃ������ƂŒN�ł��C�y�ɔ��܂��A���邢�͓����悤�ɂȂ����̂͂���͂���ł����Ǝv���̂ł����A�������悤�ɁA�E�ߏ�������A���������Ă���������Ȃ��Ȃ�ƂȂ�A���������h�͍ŏ��ɕ����l�Ɍh������Ă��܂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����v���Č����������A�F���ɂ͍ŋ߂̂��̂��قƂ�ǖ����悤�ȋC�����܂����B�܂��A�Ⴂ�A���o�C�g�炵���j���̏]�ƈ������ɑ����A���ꂾ���Ŋi���͊i�i�ɗ����Ă��܂��܂��B�ē����Ă��ꂽ�j�����Z�������ŁA�����������������������ŗ�������������܂���B ���̗Ր�O�����ʑ��̐i�ނׂ����͂ǂ����������Ȃ̂ł��傤�B���͖������ɓ��荞��ł��܂����C�����āA���l���Ȃ��珫�����l���Ă��܂��܂��B�܂��͗�������f��A�]�ƈ������ڂ��āA�V�܂炵���������������߂����Ƃ���n�߂�̂��ڂ��͈�Ԃ��Ǝv���̂ł����B ����̏h���͗����Ƃ��i�s�a�̊����̂ł������A���̗Ր�O�����ʑ��ƁA���̂������{�X�Ƃł�5000�~�̗�����������܂����B�����ɔ��܂��Ă݂āA�m���ɂ���Ȋ������ȂƂ����C�����܂����B�������{�X�ɂ͐F���͂܂����������Ă��炸�A�ǂ̒��x�̕����l�����Ă���̂��͕�����܂��A���݂�������A�K���{�X�̕��ɗ���ł��傤�B |
| �@ |
| �Ր�O�����ʑ����o�āA����X���P�E�Q�����S�������֖߂�A�����E���ɓ���Ƃ������{�X�ł��B���̗��ق��Â������ł����A�����ڂ͐V���������ł��B�ׂ���������ŁA�{�قƎl�G���Ƃ����ʓ@�ɕ�����Ă��܂��B�Ր�O�����ʑ��̃`�F�b�N�A�E�g���P�P���������̂ŁA�������{�X�ɂ͂P�P���P�O�����ɒ����Ă��܂��܂����B�ו���a���A�������{�X�ŏ��������̌}���̎Ԃ�҂��肾�����̂ŁA�t�����g�ɐ����|���A���̎|�������܂����B���Ԃ����Ԃł��̂ŁA�{���Ȃ烍�r�[�͏o���̐l�ō��G���Ă���͂��Ȃ̂ł����A�q�͒N�����炸�A���邭������肵����Ԃ��L�����Ă��܂��B�����̃`�F�b�N�A�E�g�͂P�Q���Ȃ̂ŁA���邢�͂܂��݂�ȕ����ł�����肵�Ă���̂�������܂���B�t�����g����͒j����l�����o�Ă��ĉ����Ă���A������̌������Ƃ������ɗ������āA���������Ɋm�F�̓d�b�����܂��傤���ƌ����Ă���܂����B���v������ƒf��܂������A���Ɋ����̂����Ή��ł����B ���������ł�����肵�A�k���ω����Q�q���āA�����t�̑O��i�ݏ������s���Ƃ����ɂ������{�X�O�ɒ����܂����B�܂��P���T�O���ł����B�������{�X�̃C���̎��Ԃ͂R���Ȃ̂ł����A���r�[�ŏ����ȗ���Ɩ��������������A���炭����ƈē����Ă��炦�܂����B��قǂ��������Ɋ����̂����j���]�ƈ����ē����Ă���܂����B�����������̓J���[���߂�I�ׂ�悤�ł��B �����͕ʓ@�̎l�G���������ŁA�ʓ@�ɒʂ���ʗp���ł�����𗚂��A������n���������ڂ̑O�������l�G���̌��ւł��B�����ł������E���ƁA��͂肱������S�ُ��~���ɂȂ��Ă��܂��B������̎����Ⴄ�炵���A�����ʑ��ɔ�ׂāA������͂�����Ƃ����������܂����B �ʂ��ꂽ�͎̂l�G���̊K�i���オ���Ă����A�P�P�P�����́u�����i���j�v�Ƃ��������ŁA���ƂŃp���t���b�g���m�F����ƁA�������{�X�ł͈�ԏ����ȕ����̂悤�ł��B�̈����˂��J����ƁA�̊Ԉ�����̌��ւ�����A���̂܂�l�����~����Ă��铥�ݍ��݂ɏオ��܂��B���ݍ��݂̉E�ɂ͍L���g�C��������A���͉��ɃV�����[�g�C���̕֊�Ƃ��̎�O�Ɏ������̒j���p���֊�����Ă��܂����B���֊킪�������̂͏��߂Ă������C�����܂��B���ݍ��ݍ����ɂ̓V���N����ʂ���L�����ʏ��Ƃ��̉��Ƀ{�f�B�V�����[��������܂����B���C�̑ւ��Ƀ{�f�B�V�����[���������̂����߂Ă������C�����܂��B�����Ƃ���ɖ�������j�b�g�o�X��������A���͕����ŗ��������Ƃ����l�̂��߂ɂ̓V���[���[��������A�Ƃ����͈̂�̂�����̂悤�ȋC�����Ċ��S���܂����B ���ݍ��ݐ��ʂ̉����J����Ɣ���̎厺�B���ʂɑ������葋����͉��̗���̉����⑼�̗��ق̉����Ɛ�Ƃ��������ŁA�i�F�͂���قǂ̂��Ƃ͂���܂��A�`�����݂�����܂���B�厺�̍����ɓ�����̍L���̏��̊Ԃ�����A�ԕr�̑��ɂ͉����u����Ă��炸�A��Ԃ��������Ǝg���Ă��܂��B�Ԃ͎�O�̐�p�̃X�y�[�X�Ƃ������Ƃ���Ɋ������Ă��܂��B�厺�̑��̉��ɁA����������A�C���^�[�t�H���Ȃǂ͂��̉��́A��ɂȂ��Ă��镔���ɒu����Ă��܂��B�厺�̉E���ɕ��Ԍ`�łU��̎��̊Ԃ�����A�e���r�͂�����ɒu����Ă��āA�z�c�����̕����ɕ~����܂����B���Ԍ`�����炱����ɂ��L����������A�S�̓I�ɖ��邢�J�����̂��镔���ł����A�L����֎q�͂���܂���B �����ł̉��߂Ă̂����o���͂���܂��A���߂̋C�Â����͂���܂����B�܂��A�Q�����p�ɍ얱�߂����Ă��܂��B�①�ɂ͐\�����ł����B�����ɂ����Ă������}���َq�͔����̏Ĉ�̓����������\���ŁA�炪�����Ƃ�Ƃ��A���̂�������͉�������⋭�߂ł��B �����͐V���������ł����A���̎l�G���͌��Ă��Ă���P�Q�N���o���Ă���Ƃ������Ƃł����B�ڂ��Ƃ��Ă͈֎q�������̂��c�O�ł����A��͂肻��Ȃ�́A���炦�̂��������ł��B |
| �����C�͖{�قɘI�V�Ɗ╗�C�̓����A�l�G���ɑ嗁�ꂪ�����A�܂��͘I�V���j���A�{�ق̊╗�C�������ɂȂ��Ă��܂��B��̂W���ɂ��̂��ׂČ�ւ��A�����͂Q�S���܂ł������Ǝv���܂��B�����͊m���A�l�G���̂����C�̕��͑ւ�����܂܂ł������A�{�ق̂����C�͂܂����ɂ��ǂ��Ă����ƋL�����Ă��܂��B �l�G���ɂ���嗁��͂ǂ�������ʂ𗎂Ƃ����A���������������C�łU�l���炢�͓��ꂻ���ł��B�����q�����Ȃ���������Ɠ��邱�Ƃ��ł��܂��B�D�Y�Ό����A�O�V�����v�[���A�ԉ����V�F�[���B���O�t�H�[��������܂����B��̊Ԃɂ͎d�肪����A�E�ߏ��̃h���b�T�[���Ɨ�����������肵�����̂ł��B�����A���h���b�T�[�Ȃǂ̐������Ȃ��̂ŁA���ݍ����Ɨ]�T���Ȃ��Ȃ肻���ł��B �I�V�͂��ꂾ�����Ɨ����Ă��܂��B����E���ŘI�V�ɏo��ƁA���D�͓����A���S�ȘI�V����A���̘e�ɃK���X�Ɉ͂܂ꂽ���������̂��̂������܂��B�������A�ǂ������l���炢��������Ȃ������Ȃ��̂ŁA�K���ɑ��̐l�Ƃ����������Ƃ��Ȃ���������ǂ������̂ł����A�c�̂Ȃǂƈꏏ�ɂȂ�����ߌ��ł��傤�B���Ȃ݂ɁA�������{�X�͗������͈�ؔF�߂Ă��Ȃ��悤�ŁA�i�s�a�̕ʏ����߂���̏h������O��Ă��܂����B �l�����͂܂�Ă���I�V�ł����A���̈͂�ł�����̂��A���R�̗̖X�ŁA���������Ȃ荂���Ƃ���܂ł���̂ŁA�����������グ��A���፷�̂���i�F�Ƃ��Ă͍��܂łň�Ԃ�������܂���B �{�ق̊╗�C�ɂ͒Z���Ԃ�������Ȃ������̂łقƂ�Lj�ۂ��c���Ă��Ȃ��̂ł����A���ƍL���āA�����Ȃ����͋C�ł����B���D�͓�������C�����܂��B �܂��A���̂������{�X�ɂ��݂��蕗�C������A��͂�S�����ǂ����͕�����܂��A����͖����œ���܂����B�����ƘI�V�̗��������Ă��闧�h�Ȃ��̂ł��B�I�V�͊╗�C�Ő�قǓ������Ɨ��������̂����L�����̂ł����B ����̎��ɂ��ẮA�ǂ̓��D���ꉞ���D���炨���͂��ӂ�Ă���̂ł����A���z��������Ȃ��Ƃ����C�����܂��B�����A�܂��������f�L�͂��܂���B���L�͑O���̔����ʑ��������炩�Ɏキ�A�����͔����ʑ��̕��������悤�Ɏv���܂����B�܂��A����p�̃R�b�v�Ȃǂ͌�������܂���ł����B �����̓������␅�|�b�g���l�G���͓��オ�菈�ɁA�{�ق͘L���ɒu����Ă��܂����B |
| �[�H�͖{�ق̌��̐H�����ł��������܂����B�H����������������̂Ƃ���ɁA�������R�[�i�[������A�������O��ނ̂����̗������������Ă���܂��B���̎O��ނ̂����͐H���̎��ɒ����ł�����̂ł�����A���̎��Ɏ����Ŗ����m�F�������������S���Ē����ł���킯�ŁA����͂Ȃ��Ȃ�������悾�Ɗ����܂����B ���i����������A��������������܂����B�H�O���͕ʏ��̔����C���Ƃ������Ƃł����A����̉��c�̐ԃ��C���̂ق����������������C�����܂����B�����́A��t��������݂̂���a���Ɛ��������ÊC�V�B�O�������̕S�����c�q�A�H�������v�Ă��A�^�c�ۓ�@�H���̎q�A�����Ƙ@���̐Z���B�z�����������y�r�����B�����̂��������Ђ��B�����肪�M�B�T�[�����A��e�ԁA���������^�^�L�B�ϕ����e�ԓ�Z�A���c��֎q�A�q�������ØI�ρB�Ă������O�̂�������I�Ԃ��̂ň�͏����̋��������A������͐�Ȏq�������̉��Ă��A������͐^�c�ۂ̋��Ă��ŁA�l�����͓�l�Ƃ��A�����̋���������I�т܂����B�����đ�̂��̂��������肫�̂���B�|�̕��̊I�e�Ԋ����ōŌ�ɏ������сB�f�U�[�g�͂Ԃǂ��ƃ}���S�[�v�����H�ƂȂ��Ă��܂��B �ŏ��ɐH�O���ƑO���e�[�u���ɕ��ׂ��A�����ď����̓y�r�����B��t���̐��������C�V�B�����Ђ��B������E�E�Ƃ������ň�i���^��Ă��܂����B�S�̓I�ɂ����y�[�X�ŁA�������Q���Ԃ����ĐH�������܂����B��͂�A�����̕ʏ�����Ƃ������ƂŁA�����������g���A�y�r�����A������A�������т̎O�i�͑O���̔����ʑ��Ƌ��ʂ��Ă��܂����B�ǂ�����ƂĂ������������̂ł������A��͂藿���̈Ⴂ���A�������{�X�̕����{�����[�����܂߂Ă��ゾ�����C�����܂��B�����̋������������킢�[�����������ґ�Ȃ��̂ł����B�S�̂ɖ����̍s���[�H�ł����B ���H�������ꏊ�ŁA�K�̉ԁA���炱�A�C�ۂ̒ώρA�Ƃ����O�_�̏��M�B�����̎ϕ��H���߂����B�卪�A����ɂႭ�A�~�Z�̐������킹�B���̈�銱�ƊC���H�̕t�������B���B��T���_�B���Ɛ������B���̂������͒��J�쓤���X�̂��̂ł͂Ȃ��A���̗��ٓ����̂��̂��Ƃ������Ƃł����B���J�쓤���X�Ƃ͑ΏƓI�ɁA����͊Â��Ăӂ�ӂ킵�����̂Ŕ��ɓ����̂��邨�����������ł����B��T���_�̓h���b�V���O���C�ɓ���܂����B����ɁA��W���[�X���t���܂��B����Ƃ��������F�͂Ȃ����̂ł����A�S�̂ɂ������������̍s�����H�ł��B���r�[�ŃR�[�q�[�̃T�[�r�X������A����Ńf�U�[�g���t���Ă����當��Ȃ��ł����B �P�Q���`�F�b�N�A�E�g�ŁA�ڂ������͂P�P�������܂ł����̂ł����A���̃`�F�b�N�A�E�g�̋q�Ƃ��قƂ�Ǐd�Ȃ炸�A���r�[�ɂ͔����ʑ��̃C����A�E�g�̂��킴�킵�������Ƃ͑ΏƓI�ɁA���ɂ�����肵�����Ԃ�����Ă��܂����B�l�ɂ���Ă͈٘_�����邩������܂��A���݂̂Ƃ���͕ʏ���̍������قƌ����Ă����ł��傤�B�����A�A���o�C�g�́A�Ⴂ�]�ƈ��̑��������ʑ��ɔ�ׂāA�����͗��������Ă��āA������x�N��̍s�����j���]�ƈ��������C�����܂����B�����̕��͋C�A�������͔����ʑ��̕��������Ǝv���̂ł����A�������Ɗ����ɂ͂������{�X�ł��B���̂������{�X�ɂ͔����ʑ��̌����A��̂悤�ɓ��ɓˏo�����Ƃ���͂Ȃ��̂ł����A���Ƃ����āA��������鏊���قƂ�nj�������܂���B |
| �U�N���Ԃ�̊�茧�ւ̗��֍s���Ă��܂����B�{���͎����Ƃ��Ă͊��Ȃ畽��ɍs���Ă݂��������̂ł����A���[�������_��ɍs�������Ƃ������ƂŁA�ŏ��͂��̓�ӏ������v�������l�����̂ł��B�������A�ǂ������ԓI�ȗ]�T���Ȃ������Ȃ̂ŁA����͎���ɉA���̑���ɎO���̏�y���l�Ɉꔑ�A�����ď����_��ɋ߂��q����ɓƂ������Ƃɂ��܂����B�q����͑O��u�l�G���v�ɔ��܂��Ă��āA�T�^�I�ȏ����D�݂̏h�Ƃ������_�ŁA�ڂ��Ƃ��Ă͐���ĖK�������h�Ƃ����킯�ł��Ȃ������̂ł����A����A��ɔ��܂肽�������ΎR���̗���ȊO�́A�ǂ������ɂ���Ƃ����h���v�������炸�A���Ƃ����ČΎR���̗���ɘA������Ƃ����Ƃ���܂ł͓��ݐꂸ�A�Ƃ����Ȃ�䂫�ŁA���Ljꔑ�͂܂��l�G���ɔ��܂邱�Ƃɂ��Ă��܂��܂����B��y���l�́u��y���l�p�[�N�z�e���v�����āA�q����́u�l�G���v���u�ΎR���v�Ƃ������ɂȂ�܂����B |
| ��y���l�͉���ł͂Ȃ��̂ł����A�܂��O���̊C�̍K�A�����ď�y���l�̊ό������C���̖ړI�ɂ��邱�Ƃɂ��܂����B�u��y���l�p�[�N�z�e���v�͉���ł͂Ȃ����̂́A�I�V���C�͊C�������Ă���Ƃ������ƂŁA���̊C�����C�Ƃ͂����Ȃ���̂��A�i�g���E���͂��Ȃ�����Ă���͂������A����Ƃ͂�͂�Ⴄ�̂��A�Ƃ������Ƃɂ�����������܂����B ��������{�Â܂Ńo�X�Ō��������̂ł����A���̃o�X�̌㔼�͉��Ƃ����삩������܂��A�k�������������Ƒ���܂��B�������قǂ̌i�F�͂Ȃ��̂ł����A����ɋ߂������ɐ삪����Ă��ĖO���܂���ł����B �{�Â��痷�ق̌}���̎Ԃŏh�ɒ����܂����B���̓��͌��������������Ƃ������ƂŁA���̏�y���l�p�[�N�z�e���͂��̒n��̂��̂悤�ȏh�ł���悤�ł��B���̑O�̒c�̗��s�͕ʂɂ��āA��X�Ƃ��Ă͋v�X�̋��嗷�قł��B���r�[�Ȃǂ͂���Ȃ�ɍL�X�Ƃ��Ă��܂����B �`�F�b�N�C�����Ԃ͂Q���炵���̂ł����A���������̂��R������ł����̂ŁA�����ɕ����Ɉē����Ă��炦�܂����B �ē����ꂽ�̂͂T�O�P�����ŁA�ŏ�K�̈�Ԓ[�̕����ł��B�p�����ɂ�����܂����A���͈�ʂɂ�������܂���̂ŁA�p�����Ƃ��Ẵ����b�g�͂���܂���B�t�ɁA��y���l�p�[�N�z�e���͊C���Ə��ё��̕����ɕ�����Ă��āA�������C���̕����̕��������Ǝv���܂����A���̕����͈�Ԓ[�ɂ��邽�߁A���������C�ʼnE���������тƂ��������ɂȂ��Ă���A�����Ȉʒu�Â��ł��B �����L�ڂ̌��ւ��߂ɓ��銴���œ��ݍ��݂ɏオ��ƁA�E���ɐ��ʂƃg�C���Ɨ������R�̎��^�ɕ���ł��܂��B���ݍ��ݐ��ʂ̕����͂P�O��ʼnE���ɏ��̊Ԃ�����A�Ԃ͊������Ă��܂���ł������A�e���r��C���^�[�t�H�����u����Ă��܂���B���ʂɂR����̍L��������A�֎q����r�u����Ă��܂��B�L���̉E�ׂɂ͕ǂŎd��ꂽ�A�p���̂���P�D�T��̃X�y�[�X������܂��B������͊C�Ə��т������A�Ȃ��Ȃ��̌i�F�ł��B�`�����݂�����܂���B�␅�͏��߂���u����Ă��܂����A���߂̋C�Â����͂���܂���ł����B�}���َq�͂����ߋʎq�Ƃ����A�Ђ悱�݂����Ȃ��َq�ŁA�Ȃ��Ȃ������������̂ł����B���̖����ł��傤���B�����́A�V���������̂��A������Ƃ����т�Ă������ȂƂ��������ł��B |
| �����C�͑嗁�ꂪ�����̕��������ŁA�嗁�ꂩ��o��`�̘I�V���C�����C�ł��B�嗁��̒j�����͂���̂ł����A��T�ԂɈ�x�̌�ւƂ������ƂŁA���j�̂��̓��͌�ւ������肾�����悤�ł��B�Ȃ��A��T�ԂɈ�x�Ȃ̂��͂悭�킩��܂��A�Ƃɂ������߂Ẵp�^�[���ł����B �嗁��͑�^���قɂ悭����`�́A�傫�������Ƃ������̈�ʂɉ����ĂP�O�l���炢���ꂻ���ȓ��D������A���̔��Α��̈�ʂɂ����Ɛꂪ����ł���Ƃ������̂ł��B�����A�������ɂ͑傫�Ȓ�����{����A�킸��킵����ۂ�^���Ă��܂��B�������A�z�ʼn��f�L�����܂����B �嗁�ꂩ��o��I�V�͎l�p���╗�C�ŁA�S�l���炢�̂���قǍL���Ȃ����D�ł��B���̊C���������Ƃ��������́A�Ȃ߂�Ƃ�͂�Ɠ��̖������܂��B��͂蕁�i�̉���Ƃ͂܂��Ⴄ���G�Ȗ��ŁA�������������Ă���Γ����悤�ɂȂ�A�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��̂��A�Ƃ������Ƃ��悭������܂����B���D����͗т����߂��A�����オ��ƌ����̕��ɊC�������܂��B �H���͕����ł����B���i�����͂Ȃ��A����������܂���B�ŏ��ɃO���X�ɓ������Ԃ����ݕ����o����A���R�A�H�O�����Ǝv���܂������A���͂���͎��h�W���[�X�ł����B���h�ɖI�����������Â����̂ŁA����͐H������ł��ˁB�ŏ��ɂقƂ�Ǐo����Ă��܂��`�ŁA�ォ��o���̂͂��ƁA�ǂ`�A�f�U�[�g�����ł����B�����A��⊘�т̉�������̍D���Ȏ��ɂ��邱�Ƃ��o�����̂ŁA�}�C�y�[�X�ŐH�ׂ��܂����B �����炪�P�Ƃŏ��M�ɏo����A�{���̒��q�����A�C�V�̍��Ђ��͊Â����ł��������������̂ł����B�킩�߂ƃ`���E�U���̐|���X�a���A�C�N���o�^�[�Ă��ł́A����сA�����A���y�A���߂��A�C���A�ʔK���f�ނł��B��͂�A����т����������ł��ˁB�������A����т͂��Ȃ菬�Ԃ�ŁA�{���ɂ���т��ǂ����^�킵���v���Ă��܂������A��������ɂ��Ƃ���т������ł��B������͂Ԃ�A���̐Ԑg�A�ÊC�V�A�G���A�����̎h�g�ŁA�G���ƊÊC�V�����ɂ������������Ǝv���܂��B�m�M������A���g���ƃp�v���J�ƊL����卪�ɃI���[�u�I�C���ƃ^�[�����b�N�����������̂ŁA������ƍ���̂Ƃ��������܂����A�܂������������ł����B�킩�߂��i���ɂ킩�߂����肱��ł���j�͂����炪�����Ă��Ă��������Ǝv���܂����B�畨�̓J�j�ƃT�[�����Ƒ��̊C�N����Ԃ���ԂŁA�Ӗ�����ł������������܂����B�O�̊��V�⍕���������������̂ł����B�O�͑���䪉ׂƂ��ƈ�i����܂����B�H���̍��̊��т͂������������̂ł����A�ǂ�(���j�`�͖��̃����n�����Ȃ��č���̋C�����܂����B�f�U�[�g�̃`���R���[�g���[�X�����������Ǝv���܂��B�S�̂ɂ��������Ƃ͎v���܂����A���ɂ���Ƃ�����тʂ��������Ȃ��A�܂�����̂��̂���������Ƃ����Ƃ���ł��B ���H�̓o���P�b�g���[���Ńo�C�L���O�ł��B�o�C�L���O�Ƃ����ƁA���Ă͑S���H�ׂ悤�Ɖ��M�������Ă��āA�P���Ԃ��炢�����Ē������ɂȂ��ċA�����̂ł����A�ŋ߂͂ǂ����p���[���������Ă��܂��āA�K���Ɏ����Ă��ďI���ɂ���悤�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�����̎�ނ͑������Ȃ����Ȃ����Ȃ��Ƃ����Ƃ���ŁA�����܂��܂�������Ǝv���܂����A���M���ׂ����Ƃ͉����Ȃ��Ƃ��������x�������Ǝv���܂��B ����ł͂Ȃ��C�����C�Ƃ����̂����̏�y���l�p�[�N�z�e���̈�Ԃ̓����ł��傤���B�����A��͂�C�����C�͈�a��������A���܂������肵�����C���ɂ͂Ȃ�܂���ł����B�O���̊C�̋߂��̏h�Ȃ̂ŁA�������ɊC�̍K�͂��������A�{�����[��������܂��B�������A���������������}�����Ă��邹�����A���邢�́A����̗��s��Ђ̊��̂������A����͂Ƃ������M���ׂ����̂͂���܂���ł����B�����������͂Ȃ��̂ł����A�����猩����i�F�̂����A�C�����������Ȃ������̂��c�O�ł��B����̏h�������ʼn���ł͂Ȃ����Ƃ����Ă���ƁA���̓��e�̓R�X�g�p�t�H�[�}���X�����ʂ����Ƃ͌����܂��A���Ƃ����Ĉ������Ȃ��Ƃ������Ƃ���ł��傤���B��������A�����Ƃ����߂ɂȂ�͂��ł����A����Ȗ����Ȃ��Ƃ������Ă����傤������܂���B |
| �@ |
| ���āA��y���l���琷���ɖ߂�A�Ȃ�����́u�l�G���v�Ɍ������܂��B�l�G���ւ͂U�N���O�ɑ��R���t�Ƒg�ݍ��킹�čs���Ĉȗ��ŁA��������i�s�a�̖����x�X�O�_�ȏ�̏h�ɂ悭�����Ă��܂����B���̎��̏h����̊ȒP�ȃ��������ɂ́u������͊����ɖ������^�C�v�̏h�B���܂�q�����܂��Ă��Ȃ������B�H���͂��������������A����̎R���t�̈�ۂ��������̂ŁA�C���p�N�g�ɂ�⌇�����B���H�͂Ȃ��Ȃ��ǂ������B�}���َq�̂���݂�ׂ����悢�B�v �Ə�����Ă��܂����B�쎡�̖������͂����肳��ɂQ�N���O�ɍs���Ă����̂ł����A�ǂ������̍��A�����D�݂̏�����܂肵���h�̑�\�ɂ��Ă����悤�ł��B�T�^�I�ȏ����D�݂̏h�ŁA�����C�͂����������Ƃ͂Ȃ��A�����Ƃ��Ă͂��܂�ĖK����C�̋N���Ȃ��h�Ƃ�����ۂ����c���Ă��܂���ł������A���ɔ��܂肽���h�����ɂȂ��A�܂��A�O�[�͔��܂��Ă��܂���̂ŁA����A������x�l�G���ɔ��܂��Ă݂邩�Ƃ����C�ɂȂ����̂ł��B |
| �Ȃ�����̃o�X��܂ŘH���o�X�ōs���A�h�̌}���̎Ԃɏ�芷���܂��B�Ȃ��̂����߂��A���������������Ƃ���ɁA�m���ɁA�����D�݂̏�����܂肵���h�Ƃ����O�ς̎l�G��������܂��B �R�����C�����Ԃł����A�R���P�T�����ɓ��������̂ŁB�����ɕ����Ɉē����Ă��炦�܂����B �����͂R�O�Q�����́u���������v�ł����B���ւƔ̓��ݍ��݂����킹�ĂP����Ȃ����炢�̋���������ŁA���ݍ��݂��オ�����E���ɐ��ʁA�o�X�A�g�C���������܂��Ă��鑢��ł��B���ʂ͋����̂ł����ׂ��①�ɂɂȂ��Ă��āA���̏�̃X�y�[�X�����܂����p���Ă��܂��B���ʂ̑ΖʂɃg�C���ƃo�X������ł��āA�g�C���̓V�����[�g�C���ł������ڂŁA�o�X�͂e�q�o�̂��̂ł����B ���ւ��琳�ʂ̉����J����ƁA�P�O��̘a���ł��B�E����ʂ��m������Ə��̊ԂɂȂ��Ă��āA���̊Ԃɂ͉Ԃ��������A����ȊO�͈����܂���B��͂肱�����������̊Ԃ�����ƂȂ��Ƃł͑傫����ۂ��������܂��B�a���̐悪�L���ł����A�L���̍��������d���A�����Ƀe���r���u����Ă��܂��B���������ĉE���̍L�������͑�̂Q�D�T�����ƁA���ڂł��B �����猩����̂́A�O�̏��R����������������ō��ꂽ���̏h�̒��ԏ�ŁA�����͎O�K�Ƃ͂����A���\�A���ԏꂩ��͕����̒��܂Ō��ʂ������Ȉz�ł��B���ԏꂪ�Ȃ���A���R�̊����ł܂������̂ł��傤���A���E�̂قƂ�ǂ����ԏ�̂��̌i�F�͂��������܂���B���̓�K�̉�������������o���āA�Β�̂悤�ɑ����Ă���̂ł����A�`�����ނ悤�Ɍ��Ȃ��ƌ����Ȃ����A���̎E���i�Ȍi�F�ɂ͏Ă��ɐ��Ƃ������Ƃ���ł��B �S�̂ɕ����͋��������ł���A�܂��A6�N���O�ɔ�ׁA��͂肢�������Â��Ȃ������Ƃ�A�܂�łς��Ƃ��Ȃ����̊O�̌i�F�ƍ��킹�āA�����͐ݒ肳�ꂽ�Q���~�ȏ�̗����ɂ͌�����Ȃ���ۂł��B�P�U�O�O�O�~���炢�ł��A�͂邩�ɂ�����肢�������̂Ƃ���͂���܂��B �}���َq�͍��������݂�ׂ��ŁA����͑��ς�炸�ƂĂ������������̂ł����B���߂̋C�Â����͂���A�␅�����߂���p�ӂ���Ă��܂��B |
| ���C�͒j���͈�K�A�����͓�K�ŁA��ւ͂Ȃ��A�Q�S���ԓ����ł��܂��B������������܂肵���A��ʌ^�̂����ӂ��̑嗁��ŁA�����`�̗����͂T�E�U�l�Ƃ����������ł����B�E�ߏ��ɂ̓o�X�^�I���Ɨ␅�@���u����Ă��܂��B���オ�菈�Ƃ����͓̂��ɂ���܂���B �I�V�͑嗁�ꂩ��o��`�̐Ε��C�ł����B��ɂ����炩�̉��s��������̂ŁA�͂܂�Ă���̂��͏����͗���������C�����܂����B�嗁��ƍ��킹�āA�����������Ⴟ�Ȃ����C�������C�������̂ł����A�ӊO�ɂ����ł��Ȃ��A����͂���ȂɈ����v���܂���ł����B������O��̑O�������������ł��傤���B�����͂�⍂�߂̓K���ŁA�������ȗ����L�����܂��B�Â����ł����B �[�H�͕����ł��B�܂���������ɁA�e���r�͂����ɂȂ�܂����ƕ�����܂����B�����ꂽ�̂͏��߂Ă������Ǝv���܂��B�Ƃł̓e���r�����Ȃ���H��������̂ł����A����ł͈�e���r�����Ȃ����Ƃɂ��Ă��܂��B�u�������A���܂���v�Ɠ����܂������A����Ɠ������l�ɂ̓e���r�Ɍ����ē���ׂĔz�V���邻���ł��B�����ȏ�̋q���e���r�����邻���ŁA���ɂ͂܂�������b�����A�e���r�����Ă���q������Ƃ������Ƃł��B ����͂��Ă����A�H���͂��i�������������������܂��B�_�����̂������Ƃ����^�C�g�������Ă��܂����̂ŁA���ւ�肾�Ǝv���܂��B�H�O�����u�M�q�̘I�v�Ƃ����A�M�q�ɏĒ��Ɛ�����ꂽ���̂������ŁA�����ς肵�Ă����������̂ł����B�����́u�`�̔��a���v�́A�ƂĂ��Â��`���g�������a���ɃN�R�̐Ԃ������悹�����̂ŁA���̊`�̊Â��������Ă��܂��B�o�́u�����ƏH�I�e�Ԋ����v�ɂ́A�������݂Ă��Ă����������t�c�q�������Ă��܂��B�I���ƂĂ����������̂ł����A�ɂ��ނ炭�͂��̎I�̋����ɏ����������Ă��錙��������܂����B�h�g�́u���喼���E���g�i�������j��d�ˁE�k��L�E�����O�C�V�v�͐V�N�ŗ₦�Ă��ĂƂĂ������������̂ł����B���ł��k��L�Ɣ����O�C�V�͓��ɗǂ������Ǝv���܂��B�Ăɓ��������ւ���A�u���������i�E���L�n�ρE�����[�X�ρE�����E�ԑ��A�݂����ԁE��������ؒЂ��v�ƐF�Ƃ�ǂ�Ŋy���߂܂����B����͓��Ɋ����[�X�ς����Ȃ肨���������̂ł����B���悪�u�����Ă��v�ł���͖ڑ�A�⊪�C�V�A�x�[�R�������A�ۏ\���A�Ò����h�q�A���n�ʎq�A����_�������ŏĂ������ł����A�e�f�ނ���������āA�S�̂̃n�[���j�[��������������̂ɂȂ��Ă��܂����B�����Ă��ɂȂ��Ă���̂ŁA�f�ނ̎|�݂��ƂĂ������Ă��āA���{�������ꂽ���t�̍��肪�����ɍs���n���Ă��܂��B�����͉���~���߂������ł͑S���Ȃ��A��������̐����ɂ��ƁA���ɔM���������A�e�펩�͉̂ɂ����Ȃ��ŏ����Ă��ɂ���Ƃ������Ƃ������̂ł����A�ڂ��̒m���Ă��������Ă��͒��ɉ���~���߁A�e�킲�ƉɊ|���ď����Ă��ɂ�����̂ŁA��������̐����͖{�����Ȃ��H�Ƌ^�킸�ɂ͂����܂���ł����B�������A�o���ꂽ���̂�����ƁA�m���ɐ����̒ʂ�̋C�����Ȃ��ł͂���܂���B���ł��ڑ����Ă��͔��ɂ��܂������Ă��ɂȂ��Ă��܂����B���������Ƃ��āu�哤�̊����v���o����A����͂��傤�������Q���������Ă��Ă����������̂ł����B�ϕ��́u�n�鏒�\�������g���v�����������̂ł����A����܂łقǂ̃C���p�N�g�͂���܂���B�ւ�蔫�́u���јa���i�k�㋍�j�S�Ă��o�^�[�E�Ӗ�����v���㎿�̓��̂����������̂ł����B�H���͂���߂Ⴑ�̓�������тƁA������̖��X�`�ŁA��������ꂼ�ꂨ���������������܂����B���َq�Ƃ��āA�u�ь�A�����A�M�q�̃V���[�x�b�g�v���o����܂����B �ŏ��ɐH�O���A�����A���ւ�̎O�i���^��A���Ƃ͈�i���o�����Ƃ����`�ł��B�S�̂�1���ԂS�O�����x�ŁA�ŏ��͉����������̂ł����A�Ō�ɂ��ԉ��т����̂��c�O�ł����B |
| ���H�������ł��B�����̓����͉��ƌ����Ă��A���H�ɂ����i����������Ƃ���ł��傤�B���Z���̘I�n���t�͏����E�O���ȂǂŁA���̓��Ɏs��ɏo�����̂��g�������ł��B�Ă����́u�͂��͂��̈�銱�v������ł��B���������̂ł����A����͂T���ɊF������̋e�̉ƂŐH�ׂ������|�݂��Z�������C�����܂��B����d���ɂ́A������A���ˁA�����A�l�Q�A�u���b�R���[�������Ă���A�����̐������������͌��Y�哤�i��Y�j���g�p���������ŁA�v�����݂����ȐH���ł����B�������菃���̃T���_�Ɛ��n���ŁA�������̉���ʎq�i�����_��́u�_�ꂽ�܂��v���g�p���č�������́j�͂������A�����������Ă��������Ǝv���܂����B�M�̏Ă��C�ۂƁA�������u�����̐��������������i�r������j�v�A�����āA���X�`�����쌴��儏`�i���̒n���X�ƐԂ̗����X�̍��킹���X�d���āj�ŁA�����̖��X�`���v���o���܂����B���т͊�茧�Y�ĂЂƂ߂ڂ�P�O�O���̕Ă������ł��B���َq�u�G�̕��v�͗m���̐ԃ��C���Ђ��t�����{���[�Y�W�����H�Ƌ��ɂ́A�܂��܂��Ƃ����Ƃ���Ń��[�O���g���������Ă��܂����B�S�̓I�Ƀo�����X�̎�ꂽ���ɂ����������H���Ǝv���܂��B�킴�킴���i�������o�����������āA���H�ɂ����L�������Ă���Ƃ��������ł����B ���̏h�́A�������悤�ɗ����̊��ɂ͕����͗ǂ�����܂���B�ŏ����[�͂��Ȃ�s�������ŁA�����������D�݂̏h���Ƃ����ƐM�����Ȃ��悤�ł������A�H�������Ĕ[�������悤�ł��B�܂��A�S���̎Ⴂ��������́A�����͏��Ȃ��̂ł�������ׂ����Ƃ͂�����Ƃ���l�ŁA���Ⴖ��˂̂��X�ׂĒn�}���R�s�[���Ă���܂����B�z�c��~�����Ԃ�����A���̏h���ꏊ�̌ΎR���܂ʼnו��������^��ł��ꂽ��A�q�̗���ɗ����Ƃ��ł���h�ł��B�������債�����Ƃ̂Ȃ����ɂ́A�����̃O���[�v��s�[�^�[�������悤�ł��B�m���ɁA�H���͕]���ł���Ǝv���܂��B������H�ׂɂ����ł��������h�ɂȂ�܂����B�܂��A�����C�͑O�����قǂł͂Ȃ��A����Ȃɂ͈����Ȃ���ۂł����B�����������Ƃ��Ȃ���܂茾�����͂Ȃ��Ȃ�̂ł����A���̕����Ƃ����\���ɂ͓�����L�������łȂ��A�O�̌i�F���܂܂�Ă��܂��̂ŁA��������Ƃ��Ȃ�悤�ɕς���̂͑�ς�������܂���B�Ƃɂ����A����ł������̌��_��H���ŕ₢�A�����I�ɂ͍D����ۂ��c��܂����B |
| �@ |
| ���悢��A���N�̊��̗����ŏI�͂ƂȂ�܂����B �l�G���ɉו�������A�����_��ł�����肵����A�ŏI�ړI�n�́u�ΎR���v�����܂��B���́u�ΎR���v�͉��l���̂g�o�ŘI�V���L���Ƃ������Ƃ�A����ɗ��ꂪ�ǂ��A�����֍s���Ȃ痣��ɏh�����ׂ��Ƃ������m���Ă��܂����B��������ٌn�̐l�����łȂ��A����n�̐l�����Ȃ�h�����Ă���̂������̓����̂悤�Ɏv���܂����B ����͂R�������Ȃ��A�����t���̘I�V������̂͂��̂����̂P���݂̂ŁA���Ƃ̂Q���͓����C���������ɕt���Ă��Ȃ��Ƃ������ƂŁA���܂�Ȃ瓯������ł��I�V�t���̕����A�Ƃ����̂������̏펯�̂悤�ł����B�������A������s���̂����s�V�[�Y���̂P�O���ŗ\��̓d�b�������̂�����قǑO�ł͂���܂���ł�������A�I�V�t���̕����͎���͂����Ȃ��A����̕�������ꂽ�����ł��ǂ������Ǝv�����Ƃɂ��܂����B �`�F�b�N�C���͂R���Ȃ̂ł����A���߂ɏ����_�����ɂ����̂ŁA�Q���P�T���ɓ������܂����B�������A�R���ɂȂ�܂ŕ����ɂ͓���Ȃ��Ƃ������Ƃł����B�m���A�����C�ɂ͓����Ƃ������ƂŁA����܂��ƌ���ꂽ�Ǝv�����̂ł����A�L���͊m���ł͂���܂���B�����A���߂��ɂ��炦��킯�ł͂Ȃ��A�܂��m���ɒ��ւ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��ʓ|�������̂Œf��A���֑O�ɂ��鑫���ɓ����Ă��܂������A������Q�O���������Ă�����O���܂����B���։��̍��|�`���̈͘F�������鏬�����ŋx��ł���ƂR���ɂȂ蕔���ւƈē����Ă��炦�邱�ƂɂȂ�܂����B ����ւ͊O�̗���p�̖���������Ă܂������s���܂��B�����͎O���������̉E�[�́u��h�i����j�v�Ƃ��������ł����B���ւ����ƁA���ւƓ��ݍ��݂����킹�ĂR��قǂ̋�Ԃ�����܂��B���̉����J���A��͂�R�������炢���肻���ȘL���ɏo��ƉE���ɂ��̕����̔���ł���傫�ȓ���������܂��B���̑傫�ȓ����͂������ŁA���X�ЂΑ��肾�����ł��B�P�S�������闁���̑��������̂V�̓��D�ɂȂ��Ă��܂��B���D�̉E���͐Q���ɂȂ��Ă��āA�S�ʂɎ��ꂽ�傫�ȑ����璭�߂���䏊�̕��i���f���炵�����̂ł����B�����S�̂��ŏo���Ă��āA�ƂĂ��������������C�ŁA���ʂ̔铒�̏h�̑嗁��ƌ����邭�炢�̕��͋C�������Ă��܂��B�����C�̓�����ɔ铒������̒����������Ȃ�܂����B�����t���̉�������Ƃ��ẮA���܂łň�ԗǂ������C�����܂��B�܂��A�E�ߏ����V���N����ʂ�����ʂƂȂ����Ă��đS�̓I�ɍL�X�Ƃ��Ă��܂����B ���̐��ʂ̎�O�Ƀg�C��������A�������L�X���Ă��āA�g�C�����Ɏ�������Ă��܂��B�������V�����[�g�C���ŗ����{�^���t���ł����B �L���̍���͂U��̑O���ƂW��̎厺�������A����ɂ��̐�Ɍ炢�̔̊Ԃ̍L�����݂����Ă��܂��B�L���ɂ͓�r�̈֎q���u����A����ɍ����Ē��߂�L�X�����䏊�̌i�F�͑f���炵���A��O�̂��݂������傤�Ǎg�t���Ă������Ƃ������āA����Ɍ�������R�̃V���G�b�g�Ƒ��܂��ĉ��Ƃ������Ȃ��������i�F�ł��B�������A�`�����݂Ȃǂ͂Ȃ��������璭�߂�i�F�Ƃ��Ă͓���̕��ނɓ���܂��B���H�̎��ɂ͔���������H�A���̌i�F��w�i�ɔ��ŁA����܂��S�Ɏc��܂����B��������ɂ��Ɣ����ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł����B �����A�����S�̂Ƃ��Ă͍L���ĐV�����̂ł����A�����̏��̊Ԃɂ͉Ԃ��������Ă��炸�A�|�b�g���u����Ă������A���ɒ��x�Ɋւ��Ă�����ƌ��������̂��Ȃ������C�����܂��B�����ȕ����Ƃ��������A�����L�������Ƃ��������ł����B �}���َq�͌I�Ɣ��Q�̏Ă��َq�Ƃ����葢�芴���ӂ����̂ŁA���������A�H���̃f�U�[�g�����҂�������̂ł����B���߂̋C�Â���������A���߂͓���܂����B |
| ���C�͖�P�Q����ւłQ�S���ԓ��邱�Ƃ��ł��܂��B�I�V�͊m���Ɍ�ւ������̂ł����A�����Ɋւ��Ă͓���C���Ȃ������������A��ւ��������͂悭�o���Ă��܂���B ���C�͘I�V�Ɠ�����������Ă��āA�I�V�͖{�ق̗���ɋ߂��[�̂ق��ɓƗ����Ă���܂��B�����͖{�ق̌����̒��ɓ����܂��B�{�ق̗�����Ɉ�A����Ƃ͔��Α��̖{�ق̈�Ԓ[�Ɉꂩ���ł��B������͌䏊�̌i�F�͂����̂ł����A���������̂ł��B�{�ق̒[�̕��ɂ��镗�C�͌i�F�����ꂾ���A�Â������ł��B���ǁA�I�V���C�ȊO�͕����̓����ɓ���܂����B�{�ق̓�̕��C���A�����̓����̂ق�������ۂǖ��͓I�������̂ł��B �I�V�͒j�����ꂼ�ꂩ�Ȃ�L���╗�C�ł��B�ŏ��j���p�́A�����Ί_�ƍ����Ɉ͂܂�āA���̎l�p�����̂قƂ�ǂ����D�ɂȂ��Ă��܂��B���ʂ̐Ί_��`���Ă��������ꍞ�ނƂ����A�Â�������ŁA�����̐l�������ꂻ���ł��B�����A���D�ɂ����Č��n���ƁA�������邵������ł����C�ɓ����Ă��銴�������܂��B������Ǝ�ꂽ�C�z�������āA�����ɂ���Ȃ���A�Ȃ����r��̌����v���o���Ă��܂��܂����B�����͏ꏊ�ɂ���ĉ���������M�������肵�܂������A�S�̓I�ɓK���ł͂Ȃ��ł��傤���B �钆�̂P�Q���Ɍ�ւ������́A����قǎ�ꂽ�����͂Ȃ��A���D�ȊO�ɒ�炵��������������A�����A����ꂽ�X�y�[�X�������āA�ŏ��j���p�̘I�V��肸���ƈ�ۂ͗ǂ����̂ł����B�����A����͕����̕��C�����ɋC�ɓ������̂ŁA�ڂ��ɂ͒������I�V�ɂ͂���قǒ����Ԃ͓���܂���ł����B�����̂����C�͗�����ŁA�I�V�������A�����肾�Ǝv���܂��B �H���͕����łł��B���i����������A����������܂����B�u���̂������v����t���ɓ�������̂��Ǝv���܂����A�}�������Ƃ����ܓ����̓��ނ��r㻂����������悤�Ȍ`�ŕ���ł��܂��B�}���͊Â݂����邿����ƕs�v�c�Ȉ�ۂ̂��̂ŁA������̂����܂̓����̗����Ƃ��ɂ��َq�݂����Ȋ��������܂����B�u�n�{���X�v�̏����ƁA�O�ɓ�����u�R��̍K�v�͂��ݑ��Ƃق������A�R�݂̂��A�I�̏a��ρA�⋛�̈�銱���̂T��ނ��ق�̏��������M�ɍڂ����Ă��܂����B�ق������͐����ۂ��č���ł������A�݂��͂��Ⴋ���Ⴋ���Ă��������A�I�̏a��ς������������̂ł����B��Ɠ암������{�̗₵��Ԃ͍���A���������A������Ƃς��ς����Ă��銴���ł����B�싛�̂�����́A�R���ƍg���Ɗ⋛�Ƃ������C���i�b�v�ł������A�R���͏������č��ꖡ�������A�����̓p���`���ア�Ɗ����܂����B�⋛���������܂���B�S�̓I�ɒ��肪�Ȃ��A��X���������̋������ł����B�����܂ł��ŏ��ɏo����A���̌�͈�i���ł����B�u�����ƒZ�p���̒Y�Ώāv�͎��������јa���ŏ_�炩���Ă����������̂ł����B�Z�p���͏��߂ĐH�ׂ܂������A�T�V�̓������_�炩���ăW���[�V�[�ȍ��јa���Ƃ͂܂������Ⴂ�A���肪�d�������Ȃ̂ł������킢�L���ŁA���݉���������A���ނقǂɖ����N���o�Ă���Ƃ����������̓Ɠ��̋��ł����B�t�������͖k������Ƃ������Ⴊ�����ł��B�u�H��̓����\���v�͂܂��܂��Ƃ������Ƃ���A�u�n��ƎR�̗g���v�ɂ��ẮA�ő��E�����͂������������̂ł����A�݂��̉�͂���Ȃɂ��������͊������A�����E䪉ׂ͂܂��܂��Ƃ������Ƃ���ł����B�u�⋛�̉��Ă��v�͔��ɂ��������A���ȊO�͂��ׂĐH�ׂ���Ƃ�����Ԃ̕���̂Ȃ����̂ł����B�u�������сv�������������������܂����B���҂����f�U�[�g�́u�H�̗�َq�v�͎R�����̃��[�X�ŁA�����������̂ł����B��������ɕ����ƁA�H���͖{�قƗ���Ƃ͎�Ⴄ�����������ł��B�{�قƂ͗����͂��Ȃ�Ⴄ�Ǝv���̂ŁA���̊��ɂ͐H���ɂ͂����������͂��Ă��Ȃ��悤�ł��B �H���Ɏg�����|���͗[�H��ɊG�t�������Ď����A�邱�Ƃ��ł��܂��B�l�Ȃǂ͂���Ȋ��ł��Ȃ��Ɛ�ɂ��Ȃ����ƂȂ̂ŁA����͂���Ŋy�������̂ł����B |
| ���H�������ł��B�ь�W���[�X���o�܂������A�g���R�Ƃ������炲�Ɛ��������̂������ŁA�s���N�F�łԂԂ������Ă��邨�������W���[�X�ŁA������������W���[�X�͏��߂Ăł����B�[���Ƌ���������܂��B���̋����͏���䋍���ł͂Ȃ������ł����A�����������̂ł����B�傫�Ȃ��M�ɏ������ڂ������̂��Z��ނ���܂����B���Ⴋ���Ⴋ���Ă���ƁA�̌s�Ȃǂ��Ӗ��Řa�������́A���A�⋛�̊ØI�ρA�����̎ϕ��A����ݖ��X�ŁA�Z�����͔̂Z���A�������͔̂����ƁA���̃����n���������ėǂ��Ǝv���܂����B���ɂ͐哤�̊����ƁA�Z���ł����������܂����t���܂����B�ܕ��˂��̔������������тɖ��X�`�ŁA���X�`�͂�����Ɩ������������ł������A���̐h�����̂�H�ׂ���ň��ނƂ������������܂����B�Ō�ɐH��̃R�[�q�[���t���܂��B�f�p�ł����A�n�̑f�ނ���������Ă��������������H�������Ǝv���܂��B �����͏����͂��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł������A���̂����A�ڂɓ������]�ƈ��͂قƂ�ǂ������������C�����܂��B����̎Ԃ̉^�]�������ł����B�t�����g�╔���W�̏������݂Ȕ��ɒ�p���ł��B�����A�R���܂ł�������Ƒ҂�����ꂽ�͎̂c�O�ł����B�܂��A���[�����߂̐��𗊂����A�����ɂ͓����Ă���Ȃ������悤�ŁA������Ǝێq��K�̂Ƃ��낪���邩������܂���B�����炩�̗Z�ʂ𗘂�������ƁA�����Ǝv���̂ł����B �]���́A�L���I�V�͂ڂ��ɂƂ��Ă͂���قNj�����ۂ̂�����̂ł͂���܂���ł������A�����̒��߂ƕ����̓����͓��ꋉ�ł��B����ŗ������O���̎l�G�����݂������猾�����Ƃ͂Ȃ������̂ł����A�����̂��ƂȂ���A���܂������Ȃ����̂ł��B�܂��A�r�[���������̂����M���̂Łi�����炩���������Y��܂������j�A�|���̊G�t�����y�������̂ł����B�q�ɑ���Z�ʂ�����������Ջ@���ς��ƁA�[�H�̃��x���A�b�v�����������]�܂�܂��B���ꂳ�����Ȃ�����A���ɃR�X�g�p�t�H�[�}���X�̍����h�ɂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B |
| �铒�̏h�̃X�^���v���̎O���ڂ��悤�₭��t�ɂȂ����̂ŁA�\��ʂ�u����̋��v�ɂ����҂ōs�����Ƃɂ��܂����B�����A�����Ȃ艜��˂܂ł͉����̂ŁA�ǂ����őO�����邱�Ƃɂ��āA���낢�댟���������ʁA���{����̃o�X�H���̓r���ɂ���A�N�`�R�~�◷�ٌn�y�[�W�ł����]���́u������G�v���O���̏h�Ƃ��Ă͍œK�ł͂Ȃ����Ƃ������_�ɒB���܂����B ������G�̓`�F�b�N�C�����Ԃ��Q���Ȃ̂ł����A�o�X���~��ďh�ɒ������̂͂Q�������炢�ł����B���邢���r�[�ŋ������ƕ��̒Е������������A�����ɕ����ւƈē�����܂����B�����̓X���b�p���Ȃ��A�t�����g�̏��̓t���[�����O�ł����B�����͂Q�O�P�����́u�ɂ���v�Ƃ����Ƃ���ł����B�J�[�y�b�g�~���̊K�i���オ���ď��L���ɏo����A�����߂銴���̒[�̕����ł��B�͗l�������ꂽ�X�`�[���̃h�A���J����ƁA�R����̔~���̓��ݍ��݂�����܂��B���ݍ��݂��͂����ʂ��A�����˂��J����Ɩ����肪�t���^�C�v�̃g�C���ŁA�V�����[�g�C���ł��B�������A�g�C�����Ɏ�͂���܂���B�g�C���̉E�ׂ����ʏ��ň����̍L���̂���L�ڂ̐��ʑ�ł����B�j���p�Ə����p�̃A���j�e�B�̕r���R��ނ����сA����ɒܐ�����Ă��܂��B�����p�ɕ��L�̃w�A�o���h���p�ӂ���Ă����̂͏��߂Ă������ł��傤���B��p�̃^�I������|�����Ă��܂����B ���ʏ��̐�̉����J����ƁA�P�O��̘a���ł��B�^�ɑ傫�Ȗ��|���̂������ł�ƒu����A�������Ƃ��Ă��Ă����ŐH�����������C���ɂȂ�܂����B�����͍ŋ߁A�o�������肾�����ŁA�����D���̏��[�����ł��܂����B���̐�ɂR����̃J�[�y�b�g�~���̍L��������A�������肵���֎q����r�A���̕��������āA�n�̎��^�ɕ���ł��܂��B���Ƌ����̂ŁA�n�̎��ɂ��Ȃ��ƁA�Ђ��������č���Ȃ��̂ł��B������́A���̕����̐Β�ƁA���ɒj���p�I�V���C�̐�̕����A���̐�̈���Ɖ����ɓ��ƖX�A�R�̎Ζʂ��݂��܂��B���Ɍi�F�������Ƃ����قǂł��Ȃ��A�܂��܂��Ƃ������Ƃ���ł��傤���B �L���ɂ́A�[�ɑ傫���ď�v�����ȃ^�I���|�����u����Ă��܂����B�L���̉E�����A��������炢�̉��σR�[�i�[�Ƃ��������ɂȂ��Ă��āA�����ȋ���ƃX�^���h���u����A�オ�����ȑ��ɂȂ��Ă��܂��B�����̉E��O�ɂ͑傫�ȁA�R�[�g���]�T�Ŋ|������m�����ꂪ����A���̐�A�E�蒆�قǂɂP�D�T����̏�̏��̊Ԃ�����܂����B�����̂Ȃ��^�C�v�ŁA���̊Ԃɂ͂��킳�����Ђ�̊G�ƁA�����ƉԂ��������Ă��܂����B ���̊ԂɑΖʂ���A�����̍����ɂ͕ǑS�̂ɂ������̒I���d���A�����ɂ����Z�b�g�A�e���r�A���ɁA�①�ɁA�|�b�g�A�R�[�q�[���[�J�[�Ȃǂ��ׂĂ��[�߂��Ă��āA���Ȃ荇���I�ȕǂ̑���ɂȂ��Ă��܂��B�①�ɂ͋�Œ��ɐ����������|�b�g�����������Ă��܂����B�}���َq�͊��������Ƃ������ڂ̃h���C�t���[�c�ł����B�������ڂ̃h���C�t���[�c�͂��������Ö����Ïk���ꂽ�����ŁA���������͕��ʂł��B���ɓ��M���ׂ��}���َq�ł͂���܂���B�����ł̂����o���͂���܂���ł����B |
| ���߂́A���r�[�Œj���Ƃ��D�݂̕��ƃT�C�Y���I�ׂ܂��B�j���͎�ނ����Ȃ��̂ł����A�j�����I�ׂ�̂͏��߂Ăł͂Ȃ������ł��傤���B�L�[�������A���邭�A�����ꂢ�ł������ł���A���̗����̕����ɂ��Ă͐\�����̂Ȃ������Ƃ����Ă����Ǝv���܂��B �����̂����C�Ɋւ��Ăł����A�嗁��ɓ�����Ƃ���́A����̂͐�ƘI�V�݂̂ŁA�����C�݂͑���̈�݂̂ɂ�������܂���B�݂��蕗�C�̓`�F�b�N�C�����̗\�ŁA�������O�A������Ƃ�������ł��B���̏h�͂ł��Ă��炻��قǔN�����o���Ă��Ȃ��̂ɁA�O�̗����͍ŋߑւ������肾�����ŁA�V�����O�̂��������������ɏ[�����Ă��܂����B �嗁��͒j����オ�Ȃ��A�P�P���܂łł��B���̑嗁��͕ς���Ă��āA����Ƃ܂��ʘH�����˂��Ƃ���ɐꂪ�܂������菰�g�[�������Ă��܂��B������ʂ��āA������̃h�A�Ŏd���Ă���O�ɏo��ƁA�������I�V�ɂȂ��Ă���Ƃ�����ł��B�ł�����A�I�V�݂̂̑嗁��Ƃ͂����A�M�C�Β��Ƃ͂������āA�����̒��ő̂�S�z�͂���܂���B�܂�A��ʓI�ȗ��ق̑嗁�ꂩ��o��^�C�v�̘I�V�ɁA�����������Ȃ������ł��傤���B �I�V�͓��A�╗�C�Ɩ��t�����Ă���̂ł����A�S�����A�ł͂Ȃ��āA���A�����͍ŏ��̂R���[�g���قǂŁA�������o��A���Ƃ͈�ʓI�ȘI�V�ł��B��������Ȃ�͂܂�Ă��܂��Ă���̂Ōi�F�͂悭����܂���B�W�l����P�O�l���炢���ꂻ���ȍL�߂̘I�V�ŁA��≷�߂̓K���Ƃ����Ƃ���ł��傤���B�ǂ��Ղ�ƐZ�����āA�������Ɠ����Ă����邨���ł����B���F�A�����œ��̉ԂȂǂ͂���܂���ł������A�������ɉ���̓��������܂����B���̓�����̈������Ƃ̂��Ƃł��B�����ǂ���͂Ȃ��A���r�[�Ƀ|�b�g�ɓ������␅���u����Ă��܂����B |
| �H���͈�K�̑啔���̐H�����ł��������܂��B���̃��j���[���G�ŕ\���ꂽ�A�G����̂��i�������e�[�u���Ɉꖇ�u����Ă��܂����B���̂������A���ɐ����͂���܂���B�ŏ��ɒu���ꂽ�̂͐H�O���ƑO�݂̂ŁA��͂����肩�炨�i�����̏��Ԃǂ���Ɉ�i���^��܂����B�S�̓I�ɂ��傤�ǂ����y�[�X�ł����B �H�O���͂����ŁA����͂���قǃA���R�[�����������A�Â��͂���܂��������ς肵�Ă��܂����B�O�̂����A�싞�悤����͂����Ă�Ƃ������A�˂Ƃ��Ƃ����Â���������́A������L�̗L�n�ς����������A�T�[������{���i�͂��͂�����ƒ��܂��Ă��Ă��̃T�[�����������������̂ł����B�I�̂����g���͊O�����Ⴋ���Ⴋ���Ē��̌I���_�炩���˂��Ƃ肵�Ă��܂��B�q�������z�y���Ђ������Ⴋ���Ⴋ���Ă����������̂ŁA���̑��A�߂����_�O�Ă��A����C���ρA������܂����B�O�؍D���̂ڂ��ɂƂ��Ă������̍s���O�ł����B������͑喐�̐̂�����i�喐�̗��j�Y���ŁA�喐�͐싛�ɂ��Ă͂������肵����������������A�L�݂��S�R�Ȃ��A����͑�������������������̂ł����B���̂�����́A�܂ɂ��A�卪�Ɛl�Q�ł������\�������̂ȂǁA�F�X��̍��H�v���Â炳��Ă��āA�y���߂܂����B�����Ă̏������͒n��������z�C�����������Ɛ��|���|�ŐH�ׂ���̂ŁA���Ȃ肨�������Ƃ����܂��B�ĕ��͊⋛�̉��Ă����A�⋛�̗M�q���Ă��̂ǂ��炩��I�Ԃ��̂ŁA�ڂ��͗M�q���Ă���I�т܂������A����͊⋛�ɏݖ��̂����h���āA�U��M�q���������̂ł��B�������肵�����ŁA�K���̐�܂őS���H�ׂ���A��i�ł����B�����́A�����̎�ł������ŁA�ׂ߂Ŏ��������������āA�������������邨�����ł����B�n���͐M�B���̃T�[���C���̐h�����傤���X�i���h�q������ō�������Ɛ����X�j�Ă��ł��B�����������肵�Ă���̂ł����A���ꂪ���̎|���ƌ����ɒ��a���Ă��܂��B�����̂��̖̂��������Ɋy���݂����l�ɂƂ��Ă͈٘_�����邩������Ȃ��̂ł����A��̗����Ƃ��Ă͕���̂Ȃ����̂ŁA�������i�ƌ����܂��B�g�����͕S�����̂����g�����ق��ق����Ă��������A�n���̍���l�Q�͏�����܂�Ƃ܂Ƃ܂��Ă��܂����A�|�̕��͏H�֎q�̖��ƃW�����|�̎_���Ƃ��▭�ȃo�����X��ۂ��Ă��܂��B�ނ�����т͏�i�Ȗ��ŁA�W�����������L���Ƃ��������ł��B���̂ނ�����т���H�̂��ɂ���ɂȂ�̂ł����A���̎��ɕK�v�Ȑ����Ă���܂��B�Е����݂�Ȃ����������̂ł����B�Ö����͋G�߂̉ʕ����Ƃˊ`�ŁA����͏_�炩�߂����A�ł������̐▭�̌ł��ŁA�����������̂ł��B����ƒn���̖����A�C�X�������܂����B �����͗����̓��e���ς��͕̂s����������ŁA���̎��X�̐H�ނ̕ω��ɍ��킹��悤�ł��B�A���͂n�j�Ȃ̂ł����A�O�A���͔��Ƒ��k���Ă���Ƃ������Ƃł����B�H���͖��R���Ƃ����������Ǝv���܂����A�{�����[������⏭�Ȃ��̂����_�ł��傤���B�Ƃ͂����A�S�̓I�ɔ��ɂ��������H���ŁA���Ԃ��Q���Ԃ��炢���������Ǝv���܂��B�{�����[�������Ȃ��������̂́A���邢�́A�����Ƃ��̗������̗�����H�ׂĂ݂����Ƃ����C�������A�����v�킹���̂�������܂���B |
| ���H�������ꏊ�ł����B��W���[�X���o����A�喐�̏Ƃ�Ă��A�Z�����̒Е��A�R���Ђ��A�E�C���i�[�A���g�A�ώς̍ڂ������ׂ����M����O�ɒu����܂��B�C�ہA����ɗ��́A���A�����A���Ă��̎O�킩��I�ׂ܂��B����I�̂ł����A����͏o�`�������ŗ��Əo�`�Ƃ̃o�����X�����ɂ������̂ł����B���C�����卪������A�_�炩���d�オ���Ă��܂����B���ł��Ӗ������⏬���ƃG�����M�̃o�^�[�����߂������������̂ł����B���ƁA���̖��X�`�ƃf�U�[�g�͂�ł��B�܂��A���H���Ɋ�]���āA�����ɐH��̃R�[�q�[�̗p�ӂ����Ă���܂����B�[�H�قǂ̋��͂���܂���ł������A�Ӗ������ɂ͂��̕З������A�Ƃ�����A�����������H�ł����B �[�H�̂Ƃ��A��������Ə����b���ł����̂ł����A���̏h�͂T�N�O�ɂł��������ł��B�ŋ߂͌Ö��ƕ��̈Â��h���͂��Ȃ̂ł����A�����͂��̋t���s���āA�V�������邭���Ă���Ƃ������Ƃł����B����͓`���̂���Ƃ���ɂ͂��Ȃ�Ȃ��̂ŁA���ق̐V�����A���ꂢ����ۂƂ��Ɠw�͂��Ă���悤�ł��B���̂W��������Ɩ��O���o��������x���ƌ����Ă��܂����B ���āA�S�̓I�ɔ��ɍD��ۂ��������̗��قȂ̂ł����A��A�z�c��~���Ƃ��A�傫���x�����L���ɉ�����邽�߁A���̐�̍L���̈֎q���A�҂����艟���t�����āA����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂��傫�Ȍ��_�ł��B�܂��A�����̑嗁�ꂪ�Ȃ��Ƃ����̂����_�Ƃ܂ł͂����܂��A��_�������܂���B����ɁA�����܂������A�[�H�̃{�����[�������������ق����Ƃ���ł��B�������A�C�ɂȂ�͈̂ȏ�̂R�_���炢�őS�̓I�ɂ͌��_�̏��Ȃ��h�Ƃ�����ł��傤�B���M���ׂ��͗[�H�̂��������ŁA��i�]�����R���������͍̂ŋ߂ɂ͂Ȃ����Ƃ������Ǝv���܂��B�܂��A��������̋q�ɑ���p�������ɂ����ł��ˁB�[�H���̂�����̎���ɂ����Ȋ�������ɓ����Ă��ꂽ���A�W�g�̋q�̊�����ׂĊo���悤�Ɠw�͂��Ă���_���f���炵�����Ƃł��B�܂��A�T�N�����o���Ă��Ȃ��̂ɂ����O�̗����Ɏ�����Ă���_���猩�Ă��A���ق̕ێ�Ɋւ���S�\�����������肵�Ă���ƌ����Ă����ł��傤�B���ɃR�X�g�p�t�H�[�}���X�̂����h�ł���ƌ����܂��B |
| �@ |
| ���悢�悠�̂���̋��ł��B �O��́u����̋��v�̕ɂ��������悤�ɁA�T�[�r�X�ʂł̂Ђǂ��]���͂��������̂́A�����E���C�E�H�����ǂ��A�s�����i�K�ł��łɁA����̂����҂͂������ȁA�Ƃ����\���͂���܂����B���ǁA�P�O�X�^���v�����܂����i�K�ŁA��͂�A�u����̋��v�ɂ��悤�Ƃ������ƂɂȂ�A���߂͂P�P���͂ǂ����ȂƎv�����̂ł����A�\������Ă݂�Ƃ��łɂ��Ȃ�̕��������܂��Ă������Ƃ������āA�ꌎ�����ĂP�Q���ɂ��邱�Ƃɂ��܂����B���̂��������A�����ɂ����҂̗\����\�肵�Ă������Ɏ��܂����B �O��͑O���̐V�䍂�����炷���ɍs���āA���Ȃ葁�����Ԃɒ����Ă��܂������߁A�Ђǂ��ڂɂ������Ƃ������Ƃ�����A����͂�����Ɨ���Ă���u������G�v�ɂ��Ă݂��̂ł��B�o�X�ŕ�������܂ōs���A�y���H�������Ă܂��o�X�ŕ��n����ɒ����܂����B�O������x���Ƃ͂����A�܂��C���̎��Ԃ܂ŗ]�T������Ƃ������ƂŁA��͂�ɓ��Ɋ���Ă݂܂����B�����ł��炭������肵�A����s�����Ǝɓ��̌��ւɏo���Ƃ��ɂ��傤�Ǘ��ق̊W�҂炵���l�Ƃ���Ⴂ�A�u����ɂ��́v�Ɩ��邭���A���Ă���܂����B���̎��A�ڂ��́u����`���H�v�Ǝv�����̂ł��B���������āA���̐l�́A���̑O�́u����̋��v�̎��l����Ȃ����E�E�ƁB�������A�O��͌}���ɗ��Ă��ꂽ�Ƃ��ɂ�����ƁA������������ŁA���̂��Ƃ́A�Ԃ̒��Ŕw���Ƃ���ׂ��Ă��������ł��̂ŁA�m�M������܂���B���̐l�͏��^�̎Ԃŗ��Ă��āA���[�����̎Ԃ����Ă��܂����B ����͂Q���S�O���ɓ����B���r�[�ł����A�ƑO��Ɠ����u������ׁv�Ƃ����A���ȕ����ł߂č����ł���悤�Ȋ����̌}���َq�����������A���炭���ĕ����Ɉē�����܂����B�O��̂悤�ȁA���r�[�̂��������̋q����A���𐁂����镗���Ȃ��A�܂��A�O��قǂ̐��̋q���������Ă��炸�A�������ʂ̃��r�[�̈�ۂł����B ����̕����͂Q�O�Q�����́u�z�����v�Ƃ����Ƃ���ł����B�O�ʘH�����̒����n��L��������Ă��āA�˂���������O�̕����ŁA�O��͓˂�������̂Q�O�P�����u�R�����v�ł�������A���ׂ̗̕����ɂȂ�킯�ł��B |
| �̃h�A���J���ē���ƁA�������̔̊Ԃ�����܂��B�E��̑�̏�ɉԕr���u���Ă���A�Ԃł͂Ȃ��A�t�̂����}�������Ă��܂����B�オ����ɁA�g���̂Ă̔����X���b�p�ƃ}�W�b�N���u����Ă���͈̂ȑO�Ɠ����ł��B�̊ԂɃX���b�p��E���ŏオ��ƁA�����͂����U���̍T���̊ԂŁA�T���̊Ԃ̐^�ɂ���肪���Ă��܂��B���ʂɑ傫�ȑ�������Ă��āA���H�����̌i�F��̐��ʂɂ͎R�������܂��B���̍T���̊Ԃ̉E���ɂP�炢�̍L�߂̐��ʏ�������A���ʏ��Ɍ����������`�ŁA�V�����[�g�C��������܂��B�T���̊Ԃ̍��ׂɂP�O��̎厺������A�^���x�����u����Ă��܂��B�厺�̉E���ɍT���̊Ԃƕ���ő�������A���l�ɁA�R�A����̓��H�A�G�Ȃǂ������܂����B���Ɍ����������`�łP����̏��̊Ԃ�����A�Ԃ���������Ɗ������A�e�B�b�V���ƃC���^�[�t�H������i�Ⴂ��O�̔̕����ɒu����Ă��āA���̊Ԃɂ̓��K�l�̓����������������u����Ă��܂��B���̊Ԃ̍��Ƀe���r�̒u���ꂪ����A���̉������ɂɂȂ��Ă��܂��B��͂�A�����ł̂����o���͂Ȃ��A�����ɂ͑O�l�A�[�H��ɕ��n��b�Ƃ������ׂ��������َq���u����Ă����܂����B �O��̕����̗l�q�Ȃǂ�������Y��Ă��܂������A��́A�����悤�Ȋ����������Ǝv���܂��B�O��]�������A�N���[�[�b�g�̑傫���ł����A����A�ڂ��͂��܂�C�ɂ��Ȃ������悤�ŁA�����ɂ͂���܂���ł����B�����A�����A�O�l�ɑ傫�������Ǝv���܂��B �Ƃ���ŁA���̕����Ɉē������Ƃ��L������O��������A�������̎ɓ��Ō����Ԃ��~�n���ɒu����Ă��܂����B��͂肠�̎ɓ��̈��z�̂����l�́A�O��̖����z�Ȃ����̎��l�������̂ł��傤���E�E��ł��B �����C�͑O��Ɠ����Ȃ̂Ŋ��������Ă��������܂��B�����A�O��͂��܂�C�ɂȂ�Ȃ������̂ł����A�I�V�A�����C�Ƃ������̒ꂪ���炴�炵�������ɂȂ��Ă��āA���[�͂��ꂪ�ɂ��ċC�ɓ���Ȃ��l�q�ł����B�O��͉�������Ȃ������̂ł����E�E �ڂ��Ƃ��ẮA�����Ă݂�Ίm���ɂ������ȁE�E���x�ł��B |
| �H���͌��̐H���ǂ���ł��B���Ƃ͂����A�ׂ̐��͂��Ȃ�ǂ���������A��g�ňꎺ�̎d��ǃ^�C�v�̂��̂������ƋL�����Ă��܂��B �u��Ì��̂������v�Ƒ肳�ꂽ���i�����Ɛ���������܂����B�H�O���i��˂���C���j�́A�������肵������₩�Ȗ��ŁA������ƃA���R�[������������x�ŁA��t���́i�t���t�����̂��i���ؕ����A���߂��A���炰�A�S�����j�̒��q�����i����g�ƎR���������Ă���j�ł����B�Q���ł߂́A������ƕς�������q�����ł��B�H���Đ���Ƃ����O�́A�t�e�Ƃ��߂��̔��a���͏t�e�������Ă��Ă��������A�������A���܂��̊ØI�ς܂��܂��A�Ȃ߂̊ØI�ς͊Ö��������Ă��銴���A��x�g�������Ƃ͂ق��ق��Ƃ��āA�����������āA���ڂ���͂������Ƃ������������Ƃ����s�v�c�ȐH���ŁA��ˋ��̎�f���i�����������A�Ƃ������Ƃ���ł����B�����������̂͂���̂ł����A�Â����̂̑����O�Ƃ����Ƃ��낪����̋C�����܂����B�Â������������ł��B�������͂����͈��ނ炵���̂ł����A���őO�ɂ���ȂɊÂ����̂����Ԃ̂����ǂ�������܂���B �����Ă̂��o�́A�����X�[�v�d���ĂƂ������̂ŁA���ʒc�q�ɁA�{����̃X�[�v�������ł��B���̂��o�́A�a�H�̘o���Ƃ������A�܂��ɃX�[�v�Ƃ��������ł��B������������ǁA�������ꂽ�Ƃ���͂Ȃ��A���̂��݂͂Ƃ���Ƃ��āA�������������̂ł����A�������Ƃ�����ۂł����B����͐얐�Ƒ�⋛�̂Ȃ߂��ݖ��i�������Ē@�����Ȃ߂����ݖ��Ŗ��������́j�Y���ŁA�Ȃ߂��ݖ��͂��������A�⋛�����������H�ׂ��܂��B�Ȃ߂��ݖ��̏�ɁA�֎q�A�⋛�A�얐���ςݏd�Ȃ��Ă���Ƃ����ς�����`�̂�����ŁA�����������̂ł����B����������A�����ږ������̈�ۂ͖Ƃ�Ȃ��C�����܂����B�ĕ��̂Ђ����Y�ΏĂ͂���������ˋ��ł������ł��B���̑O��������������ۂ����āA�Ȃ��Ȃ������Ǝv���܂����B�⋛�Y�ΏĂ͉����������傤�ǂ悭�A�ӂ���Ƃ��Ă悭�o���Ă���Ǝv���̂ł����A������ƍ����c��܂����B���ւ��݂͂��т������āA��x�g���āA�����������X��h�������̂ŁA���ɂ��������A�Ȃ��Ȃ��̂��̂ł��B�����̃o�X�Z���^�[�Œ��ɐH�ׂ����Ƃ͌��Ƃ����ۂ�̏�o���ł����B���ւ�̍g���[���[�A����Q�|���́A�����ς肵���f�U�[�g�݂����Ȋ����ł��B�g�����̂��Ⴋ���Ⴋ�c�q�Ɣ�t�������̗g���o���́A���ɂ��܈��A��ɘ@���̂��c�q���d�Ȃ����A�����������Ɏ����A��ɐςݏd�˂��ς�����`�̗g���o���ł����A����͂܂��܂����������Ƃ����Ƃ���ł��傤�B���͂�͏Ă����ɂ��蒃�Ђ��ł��B�f�U�[�g�͓�Z�̃��[�X�ŁA��ɖ����Ə���������Ă��܂��B�����͂Ȃ��̂ł����A��藧�ĂĂƂ��������ł�����܂���B �S�̓I�ɂ܂��܂��̗[�H�ł������A����Ƃ������ꖡ�͂Ȃ��C�����܂��B�S�̗̂���Ƃ��Ă��A�ǂ����ȂƂ����Ƃ���ŁA���ꂪ���܂芴�����܂���B �������������Ă���������Ƃň�N�ɂȂ邻���ŁA�O�̗������̉��œ����Ă����l�����i���������ł��B���j���[�͏��X�ɐV�����������̐F���o���Ă���悤�ŁA�]���͂��q����ɂ�肯��Ƃ������Ƃł����B�m���ɁA�ܕ��݂ȂǁA�`���I�ȃ��j���[�͂�������Ɩ����p������Ă���Ǝv���܂����A�����炵�����o�����ƍH�v���Ă���Ƃ��낪�A�܂��Ӑ}�ʂ�ɂ͕\��Ă��܂���B�܂��A���̍H�v�̕������ɂ��^��_�����Ƃ��낪����C�����܂��B�V�����������͂܂��Q�O��Ƃ������Ƃł����B�����͖��炩�ɑO���藎������ۂł��B |
| ���H�������ꏊ�ł��B��˂̃g�}�g�W���[�X���o����܂����A�����������̂ł��B�O�݂����Ȋ����ŁA����܂��ƏĂ������A�����i������ƌł߁j�A����ɂႭ�A����B���A�卪�i�悭�������݂Ă��Ă��������j�̎ϕ�������ꂽ�킪����܂����B���Ƃ�����������ꏏ�ɓ�������ɂ�������ĐH�ׂ����͕ς�������̂ł��B���͈��̈�銱�ŁA����͂��������A���X�`����̓c�ɓ�͓ؓ��Ȃǂ������Ă�����R�̓�ŁA�؏`�݂����Ȋ����ł��B�����L���Ƃ�����ۂ̂��̂ł����B�p�t���X�A���g���A�������A����ƈ��̈�銱���͂��ׂĖԂɍڂ��ďĂ��܂��B������͌ł߂̊Ðh�ςł����A�Â߂̖��t���̏`�ɂ��낢��ȃG�L�X���ǂ��o�Ă��Ă����������̂ł����B�f�U�[�g���������Ɗ`�ł��B���H�͂��������A�����ł��܂������A�l���Ă݂��炱�̓��e�͂قƂ�ǑO��Ɠ����ł��B�G�߂͑O�S���A���P�Q���Ƒ啪�ς���Ă���̂ł����A��������ƁA��N��ʂ��Ă��̓��e�Ȃ̂�������܂���B�����A����͉ƂɋA���Ă��Ă���A�O��̓��e�ׂĂ݂ĕ����������ƂŁA�H�����͐V�N�Ȏv���ŁA���������H�ׂ邱�Ƃ��ł��܂����B�L���͂������Ƃ����̂��A�������Ƃ�������̂ł��B �O��͎��l�̊�����A�]�ƈ��̈�ۂ����������̂ł����A�����A���C�A�H�����e���悭�A����̂����҂̏h�̑I��ƂȂ����킯�ł��B�����A����͋������Ȃ��Ȃ����������A���������C�����i�̊����͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B����͂����A�����܂ł�������̎����̕ω��ŁA���َ��̂ɂ͉��̐ӔC���Ȃ����ƂȂ̂ł����A�B��A�H���Ɋւ��Ă͖��炩�ɑO����͗������Ǝv���܂��B�������ꂽ�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����A��ˋ���ܕ��݂ȂǁA�ȑO����p����Ă��镨�͊m���ɑO�l�ɂ����������̂ł����B �܂��A�O��͔��ɖZ�������Řb���ł����A�c�O�Ɏv���Ă����Ꮧ���Ƃ���Ƙb�����̂ł����A��͂���Ɋ����̂����l�ł����B�]�ƈ��̂ǂ����₽�������́A���ς�炸�Ȃ��͂Ȃ��̂ł����A����[�H�̒S�������Ă��ꂽ�Ⴂ�����́A�悭����ɓ����Ă��ꂽ�Ǝv���܂��B�Ƃɂ����A�Ⴂ�������̐����Ɣ����肢�����Ƃ���ł��B |
| �@ |
| ���āA������������˂܂ōs�����̂����珼�{�ߕӂł����ꔑ���悤�Ǝv���A�ǂ����������ƍl�����̂ł����A�ǂ�������Ƃ������h���v��������܂���B���ǁA�ǂ������łɍs�������Ƃ̂���h�̍Ĕ������ɓ���čl���܂����B�Ĕ��ƂȂ�ƁA������̖��_�ق��A�O��s���Ă��牽�N���o���A�O��̈�ۂ��悩�������A���N���O�Ƀ��j���[�A���������A�Ƃ������Ƃʼn�R���サ�Ă��܂����B ���_�ق́A���{�w����h�܂ő��}���Ă����̂ł����A�ŏ��̌}���̎��Ԃ��R�����x�Ȃ̂ł��B�C���̎��Ԃ��R���ł��̂ŁA�h�ɒ������Ԃ͂R�������܂���Ă��܂��܂��B����͑O��̂Ƃ��������ŁA�ڂ��ɂƂ��Ă̓}�C�i�X�|�C���g�Ȃ̂ł����A�����̃o�X�H���͂Ȃ��A�^�N�V�[���Ɨ��������������肻���A�Ƃ������Ƃō�����R���̌}���̎Ԃōs�����Ƃɂ��܂����B �}���̎Ԃł͑����̏h���q�ƈꏏ�ɂȂ����̂ł����A�h�ɒ����A�C��E���Ŏ����ɏオ��Ɠ����Ɂu�����l�v�ƌĂ�A�����ɒS���̒j���̈ē��W�����āA���̂܂܁A����悠���Ƃ����Ԃɕ����ւƈē����Ă��炦�܂����i�����A����͌�ŏq�ׂ�悤�Ȏ������������̂悤�ł��j�B �����́u���铏�v�̂R�P�O�����u���_�v�ł��B�O�~�~���̘L������A�h�A���J���ē���ƁA�P������̍����傫�ȃ^�C�����\��ꂽ���ւł��B���Ă��������̔Z���̃t���[�����O�i���ɒY��~���Ă��邻���ŁA��C�̏Ɖ��M���ʂ�����炵���j�̎O����̓��ݍ��݂̉E���ɖؐ��̑傫�ȃN���[�[�b�g���u����A����͊J����ƃM�[�Ƃ������̂���N�㕨�ł����B�N���[�[�b�g�̔��Α��A���ݍ��ݍ��̃h�A���J����ƁA�o�X�ƃg�C���Ɛ��ʂ��g�ݍ��킳���������ɂȂ�A���ʂ͏�����ƍL�ڂł��B�h�A���J�����E�����ʂŁA�������o�X���[���ł����A�o�X���[���͐��ʂƂ̋����̕ǂƃh�A�����ׂē����K���X�ł����B���̃o�X���[���̓^�C������Ȃ̂ł����A�^�C�������F���ۂ����邢�������Ȃ��̂Ȃ̂ŁA�^�C�����L�̗₽�������͂܂��������܂���ł����B�o�X���[���̉��A�E��ɃK���X�@�ۂ������łł��������̂�����Ƌ��ڂ̗���������܂����A�o�X���[���S�̂͂��������L���Ȃ��Ă��܂��B���ʂ̍��ׂ��h�A�̂Ȃ������̕ǂƂ���K���X�ƂŎd��ꂽ��ԂŃV�����[�g�C�����������Ă��܂����B ���ݍ��݂̐��ʂ͗m���Ȃ̂ł����A�ς�������Ƃɉ�������܂��B�����J����ƁA���ݍ��݂Ɠ����F�̃t���[�����O�������A�P�O�炢�̍L���ł��傤���B�E���ɉt���e���r�Ɛ^��ǂ��ނ��o���ɂȂ����A���v�̃X�e���I�Z�b�g���u����Ă��܂����B�����n�̂b�c���Z�b�g����A�^��ǃA���v�́A�悭�����Ă���悤�ɁA������������������������ƁA�ڂ����v���܂����B����ꂽ�傫�ȓd�C�X�^���h�����E��Βu����A���Α��ɂ͍L�ڂ̃Z�~�_�u���̃x�b�h�������ł��܂����B�x�b�h�Ɋւ��Ă͂悭������Ȃ��̂ł����A���X�`���[�׃f�B���O�}�b�g���X�Ƃ����A����獂���Ȃ��̂��g���Ă��邻���ł��B�����Ƃ̕ǂɂ͂��ꂼ�����G���|�����Ă��܂��B ����ɂ��̐�̍L���Ƃ������A���ڂ̃��r���O�Ƃ������A�����Ƃ̋��͏�q�Ŏd���A�\�t�@�[�����Ɍ������Ēu����Ă��܂��B�܂��A������I�b�g�}���t���̂ǂ�����Ƃ����֎q����͂葋�Ɍ������Ēu����Ă��܂����B�E���ɑ傫�ȏ���I�ƃR�[�i�[�ɂ̓K�X���̒g�F������܂��B���Α��������p�̎��ƁA�①�ɁA�����̃Z�b�g�Ȃǂ��[�߂�ꂽ��p�ł��B���ʂ��L����ʂ̃K���X�ŁA�O�͐�̗���ƗсA�����A�����Ƀ��X�g�����̃e���X�Ȃ�������ƌ����܂��B�`�����݂͂���܂���B���̍L���Ƃ��������r���O�͑S�̂��U�炢�̍L���ł����A�G�A�R�����Ȃ��Ȃ����R�Ȋ����ʼn��K�Ɍ����Ă��āA�������܂��������������܂���B �h�̌��ւŌC��E���ł���A�S���̒j���������Ƃ��Ĉē����Ă���܂������A�����ł̂����o�������̒j���ł��B�}���َq�͂���̍я��Ƃ����a�َq�ƁA�s�n�a�h�q�`�Ɣ��ɏ����ꂽ�N�b�L�[���u����Ă��܂����B���̃N�b�L�[�͂����������̂ł����B���߂̋C�Â���������A�Q���������Ă��܂��B���߂͂ނ����Ƃ������Ƃł����B���̒S���̒j���͔��ɒ��J�ňꗬ�z�e�����x�����Ǝv���܂��B�L�[�͓����܂����B |
| �����C�͑嗁��Ɨ������A�Q�������ꂼ��j���ʂɂ���܂��B���j���[�A���ŗ������ƐQ�����������悤�ł��B�嗁�ꂪ�ς�����̂��́A�ȑO�̋L�����܂����������܂��Ȃ̂ŁA�悭������܂���ł����B�嗁��Ɨ������͖�ʂ��n�j�ŁA�O�̘I�V�ƐQ���͂Q�R���܂ł������ł��B�[�H���Ԃ�����ŁA�j����ւ��������悤�ł��B�I�V�͒��͖閾������Ƃ������Ƃł����B �嗁��͐����Ŗ��邢�����C�ł��B�������A�S���łS�T�����銄�ɂ͂���قǓ��D���L������܂���B�W�l���炢�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B�W�p�`�̓��D�Ő^���炨�����N��������`�ł����A���ʃM���M���̂Ƃ���܂ł����N���オ��Ȃ��̂ŁA���������Ɋ܂ނ��Ƃ��ł��܂���B�J�����͂P�P�������Ǝv���܂��B �������͔��I�V�̊����ŊJ�������L������A�S�̂��L�X�Ƃ��āA�Ȃ��Ȃ��C���������Ƃ���ł��B�������Ƃ����Ă��A�������L���A�O�ɖʂ�����p��������i�Ɛ[���Ȃ��Ă��܂��B�O�ɖʂ��Ă���̂ŁA�ڂ̑O�̗т߂Ȃ�������Ă����܂��B�������ɂ̓~�X�g�T�E�i���t���Ă��܂����B�Q���́A���������A���}�L�����h�����_����Ă��āA�����������Y���Ă��܂������A���͂��ׂď�����ĕЕt�����Ă��܂����B�����������͂Ȃ��Ǝv���܂��B �^�I���̓o�X�^�I���݂̂��E�ߏ��ɒu����Ă��܂����B �I�V�͂��ꂼ��̑嗁�ꂩ��o��`�́A���������̂ƁA�h�̌�������肽�Ƃ���ɍ����̘I�V�̓��ނł��B�嗁��ɕt������I�V�́A���߂��Ȃ��A���܂�ς��Ƃ��Ȃ����̂ŁA�O��̏h���̈�ۂƕς��܂���B���̘I�V�͑����ȑO�Ƃ͕ς���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����̘I�V�͊╗�C�łU�E�V�l�Ƃ����Ƃ���̍ג��������C�ł��B�E�ߏ����j���ʂ�Ă��܂������A�O��͕�����Ă��Ȃ������悤�ɋL�����Ă��܂��B������̘I�V����ǂƔ��Ɏ�����͂܂�Ă��āA����Ȃ�ɕ���̂���I�V�Ȃ̂ł������߂͂���܂���B�ȑO�͒m��܂��A���A���̘I�V�͉J���~��Ɠ����֎~�ɂȂ��Ă��܂������ł��B �����́A���F�A�����A���L�ŁA���f�L�͊����Ȃ������̂ł����A�z�̂悤�ȋC�����܂��B���̉Ԃ��Ȃ��A���܂�����̊������Ȃ������̂悤�Ɏv���܂����B |
| �[�H�̓t�����`�A���A�n��a�H�̂R��ނ���I�ׂ܂��B���Ƒn�엿���̗������͓����l�������ŁA������������[���̂ł����A���̖��_�قō��A��Ԑl�C�̓t�����`�炵���A�ڂ����t�����`��I�����܂����B�t�����`��]�҂͗\��̒i�K�ő��߂ɓ`���������悢�����ł��B�t�����`�Ƃ͂����A��𑽂��g���A�o�^�[�Ȃǂ͍T���߂ɂ��������Ƃ������Ƃł����B�t�����`�͐�p�̃��X�g�����ŁA�����̒�������Ə��Ȗڂ̂��߂ɂ����ɖ��܂��Ă��܂��悤�ł��B�܂��A�H���̓t���[�^�C���Ȃ̂ŁA�����̍D���Ȏ��ԂɁi�������A��W���܂łɁj��������Ƃ����̂����ꂵ�����̂ł��B���͂��̓��A�[�H�O�ɁA�X�p�[�����O���C���ƃr�[�������\����ł��܂��A������Ƌx��ŁA�ڂ��Ƃ��Ă͒������V���Ƃ����x�����Ԃɏo�������̂ł����A�t���[�^�C���̂������ŁA�����邱�Ƃ�����܂���ł����B �t�����`�Ȃ���A���i����o�܂��B�X�ɃR�[�X�̃��j���[���u����Ă��āA���J�Ȑ���������܂��B�ŏ��́A�u�I�[�h�u���o���G�v�ŁA�ǂ��傤�̃G�X�J�x�V���A�A�{�J�h�ɊI�ƃJ���t�����[�̃N���[���A�J���p���[���[�ƃn�[�u�ƎR�����悹��䕂̎O�_���K���X�̊�ɍڂ��ďo�Ă��܂����B䕂͂���ɒ��̃����Q�ɓ��ꂽ���̂ŁA�����ځA�a�H�̑O�ƌ����Ă��[�����Ă��܂������ł��B�A�{�J�h�ɊI�ƃJ���t�����[�̃N���[���͂₳�����_�炩�Ȗ��Ȃ̂ł������ɃC���p�N�g�͂Ȃ����A�J���p���[���[�ƃn�[�u�A�R�����悹��䕂͊Â��Ă��������̂ł����J���p���̋ꖡ�Ƃ̃o�����X�����ꗝ���ł��Ȃ��Ƃ����O�r����ȏo�����ł����B�@�����Ắu�����Ƌ����v�ŋ����̃\�[�X�͊Ö��������Ă��������A�������̂������������A�v�`�v�`�Ƃ��������̎��Ƃ̐H���̃o�����X���������̂ł����B���́u��x�ő��v�ŁA����͌�x�ő��i�g�����y�b�g���H�j���}�b�V�����[���ƃG�V�����b�g���g�����\�[�X�ŐH�ׂ����ł��B��x�ő����͂Ȃ肨���������̂ŁA�܂��A�\�[�X�Ƃ��悭�����Ă��܂����B����̂���̋��̖ԏĂ��̒ő����A�������肪����ł��邾�������āA����ۂǂ����������̂ł����B�����āA�u�����ۂ�ƃ`�R���v�t�����`�ł悭�o�Ă���A�^�����ڂ傫�Ȃ��M�ɁA�����ۂ�̃X�[�v������A���̂����ۂ�ƏĂ����`�R�������܂������Ă��Ă����������̂ł��B�����ۂ�̉������̒i�K�ł����ƍ��z�o�`���g���Ă���Ƃ������Ƃł����B�����u��߁v�ŁA�Ă�����߂����u����A����ɂ̓I�����W�̖A�A�G�V�����b�g�̃A�b�V���i�����́j�A�n�[�u�̃A�b�V���A�}���l�[�Y�p�E�_�[�������Ă��܂��B�ʁX�ɂ��Ă��������A�����Ă��Ă����������ł��B������\�[�X�ɂ��낢��H�v�������Ėʔ����A���������Ǝv���܂����B �����ŁA�u�M�B�Y�R���ƃO���[�v�t���[�c�̃V���[�x�b�g�v���o����܂������A�܂��ɂ��������Ƃ��������ŁA�Ƃɂ������̒��������ς肷�邱�Ƃ͊m���Ƃ������̂ł��B�Ōオ�u���i���ƍ��z�ŃV���v���ɐ��������̂ɓ~���`�̂����̂悤�ȃ\�[�X�i�R�e�L�[�k�\�[�X�j���|�������́j�v�A�܂��͋���i�x�싍��̒�������т��Ă��������l�߂Đԃ��C���Ŏύ������ň�Ԗ����������肵�Ă���j�A�܂��͎q�r�i�M�B�Y�̎q�r�Ƀn�[�u�̍���̃\�[�X�j�v�Ƃ����O�i�̒������i��I�ԁA���C�������ł��B�ڂ��͎q�r��I�т܂������A�{�����[���������Ă������肵�Ă�����̂ŁA���������A����͂����Ǝv���܂����B���[�͋����I�т܂������A������������ł������������������ł��B����ȊO�ɗ������A�b�v������̂����ɓ�킠��܂������A�����y���ŗ����A�b�v�͒���Ă���̂ŁA�ʏ헿���̒�����I�т܂����B |
| �f�U�[�g�́u�Â��U�f�v�Ƒ肳��A�O��̃`���R���[�g�i�`���R���[�g�ƃR�[�q�[�̓���g�����e���[�k�ƃC�`�S�A�r�X�^�`�I�̃I�C���Ɖt�̏�̃`���R���[�g�A�`���R���[�g�̃A�C�X�N���[���ɃI�����W�̏Ă��َq�A�e���[�k�͑�l�̖��j�̍ڂ������M���o�Ă��܂������A���Ƃ��M�̗]���ɁA�uHappy
Birthday�v�̕����Ƃڂ��̖��O���`���R���[�g�ŏ�����Ă��܂����B���́A�ȑO�A�������Ƃ��ɁA���ɋC�ɓ������|��H���̎��ɉ��C�Ȃ�����ׂ����Ƃ���A����������A����ɓ���܂��Ƃ������ƂŁA�������������̂ł����A�����������͂�������Y��Ă����̂ɁA���ّ��͉��N�Ԃ��L�^�ɗ��߁A�\���Ƃ��̓d�b�ԍ��Ɩ��O���炿���ƌ������Ă����悤�ł��B���̃T�v���C�Y�ɂ͂���܂����B�`���R���[�g�͈�i�Ƃ��������������܂����B�H��̈��ݕ��́A�R�[�q�[�܂��͍g���܂��̓n�[�u�e�B�[���I�ׂ܂��B�ڂ��̓R�[�q�[��I�т܂������A����������������̂ł����B���̑��ɁA�H�����o�����p���������������Ă��āA�܂��A������̃p���̕��̓T�N�T�N���Ă��ă��[�O���g���ۂ��������Ă��ꂼ�ꂨ���������̂ł����B �����̃t�����`�͑n��t�����`�Ƃ��������ŁA���Ȃ�a�̈�ۂ̋����t�����`�ł��B�ŏ��̑O�̂Ƃ��͂ǂ��Ȃ邱�Ƃ��Ǝv�����̂ł����A�S�̂Ƃ��Ă͏\���Ɋy���߂���̂ł����B�V�F�t�͂R�R���炢�ƎႢ�炵���̂ł����A�t�����X�ŏC�Ƃ��A�Q�T�œߐ{�̓����y���̗������ɏA�C�����l���Ƃ������Ƃł��B �Ȃ��A�A�����ēƂ��t�����`���H�ׂ����ꍇ�̓��j���[���ς��Ƃ������Ƃł����B�A��ƁA��H�p�̂��ɂ��肪�����ɒu���Ă���܂����B ���H�͏ꏊ�������A�_�C�j���O�l�G�Ƃ����Ƃ���ŁA�W���`�P�O���܂ł̃t���[�^�C���Ƃ������Ƃł����B�[�H���l�A�D���Ȏ��Ԃɍs���A�������P�O���܂łƂ͂��ꂵ�����Ƃł��B���H�͘a�H�݂̂Ƃ������ƂŁA�a�H�h�̂ڂ��͉��̖�������܂���ł������A���������[�H���O��̒�����I�ׂ�̂�������A�����ł��m�H���I�ׂ����Ԑl�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �����ƃ������A�I�������킹�����ݕ����u����A���͂A�C�ۂ̓����Ă��邨���i�C�ۂ̕������悭�����Ă���j��I�т܂��B�ϕ��͗����A�@���A�l�Q�A��Z�A���₦��ǂ��A�o�����������Ă��āA�ォ�獕�|�̂��|�����Ă��܂��B�_�炩���������ϕ���Ă��Ȃ��▭�Ȏd�オ��ŗ��������ɂ��������������܂����B���͋�L�ŁA�e�ɗ��Ă��ƍ��z���u����Ă��āA���̒L�������������̂ł����B�卪�T���_�����Ⴋ���Ⴋ���Ă��āA���тƂ���ɂႭ�A���g���Ƒf�˓�Z�A����ɂ�����̏����ƌv�O�̏���������܂��B���̑��ɁA�Z���t�T�[�r�X�̃R�[�i�[������A�n���̐V�N�Ȑ����A���̗L�@�͔|�̑哤�ō�����I���W�i���[���A���Ɛ��̓������g���������������ׂ�ꎩ�R�Ɏ�邱�Ƃ��ł��܂��B�����͑哤�̍��肪���Ă����������̂ł����B�f�U�[�g�͂�ƕ����ƃI�����W�����������荇�킹�����̂ŁA�H��ɃR�[�q�[���g�������܂��B�T�[�r�X�̏�����������̘b�ɂ悭�t�������Ă���A���̏����Ƃ������b�����Ȃ���H�ׂ��̂ŁA�H�����W��������X�����܂ł������Ă��܂��܂����B���ɁA��藧�ĂĖڗ��������̂͂Ȃ��̂ł����A�S�̓I�ɂ��������A���낢�ŐH�ׂ�ꂽ���H�ł����B |
| �S�̓I�ɂ��Ȃ薞���x�̍����h���ł����B���Ƃ��Ƃ����̓C���^�[�l�b�g�����v�����Ő\�����̂ł����A���ّ��́A������ł�����������Y��Ă�������̃����o�[�ł��邱�ƂׁA���̃C���^�[�l�b�g�����v������������ɂP�������A��������o�[�����ɂ킴�킴�ύX���Ă����Ă���܂����B����́A�����]�����Ă����Ǝv���܂��B �l�Ɋւ��ẮA�]�ƈ��̈�ۂ��S�����ɂɂ��₩�ł����Ǝv���܂����B�݂Ȃ�������P������Ă���悤�ŁA�ڂ����b�����l�͂��ׂăz�e�����݂̒��J���Őڂ��Ă���܂����B �t�����`���w���V�[�ł���A���j���[�͌��I�łƂĂ����͂�����܂��B�����C���������ƐQ���������ď[�����Ă��܂����B�����ɂ͐^��ǂ̃A���v���u����Ă��āA�ƂĂ��������_�炩�ȉ��ʼn��y������Ă��܂��B��������ɋC�������������Ƃł����B��͑�����A���C�g�A�b�v���ꂽ�傫�Ȗ������āA���ɖ�����镗�i�ŁA����͓_���܂���ł������A�����̒g�F�����炬��^���Ă����͂��ł��B�\���ɂ��낰��ƂĂ����������ŁA�����y���̂悤�ȍL����͂Ȃ����̂́A�������A�����Ă�����肷��̂���Ԃ����̂�������܂���B �������������A���ɏ����q�����ɑ����i�}���̃o�X�͒j������l�����ŁA���ƂP�O�l�ȏオ�����ł����j�̂ŁA���Ԃɂ���Ă͏����p�̕��C���������������炵�����ƂƁA�C�����R���Ȃ̂ɁA�}�����w���R�����A�A�E�g���P�Q���Ȃ̂ɁA���肪�h���P�P�����Ƃ������}�̎��Ԑݒ�ɋ^�₪���邱�Ƃ̓�_�݂̂����_���ƌ�����ł��傤�B����A���}�̎��Ԃ����ł��čl���Ăق������̂ł��B ���_�ق́A�ȑO�͗��قƂ��������������̂ł����A����͊��S�Ƀz�e���ɋ߂��A���ɍs���͂����T�[�r�X�Ő\��������܂���ł����B���͉���������ƁA����ɂȂ�邻���Ȃ̂ŁA����ɉ��K�ȃT�[�r�X�����邱�ƂƎv���܂��B |
| ���́u�������Ɓv�֍s�����͔��ɕ�����Â炭�A�o�X����~��Ă��������x�d�b���čs�������m�F�����̂ł����A���̎��A���ꂩ�璅���|�̂��Ƃ�������ƁA�܂����i�͂��j��Ȃ��Ƃ������e�̂��Ƃ������܂����B�Ƃ肠�����s���āA���r�[�ő҂����Ă��炨���ƁA�`�F�b�N�C���͂R���ł��������������̂��Q���Q�T�����ł����B�����炵���l���t�����g�œd�b���ŁA���ɂ͒N�����Ȃ��悤�������̂ŁA�Ƃ肠�����C��E���Ń��r�[�ɏオ��A�֎q�ɍ��|���đ҂��܂����B�d�b���I����������́A�q���`�F�b�N�C�����ԑO�ɏ���ɏオ�肱�̂��s�������Ȋ����ł������A����͂��܂�C�ɗ��߂��ɁA�ڂ����������s�̃N�[�|���ƃX�^���v�����o���ƁA���̃N�[�|���ŃX�^���v�͉����Ȃ��ƌ����܂����B�����I�Ƌ����A�������s�̃N�[�|���ł���A�ƔO�������Ƃ����ɓP�ꂽ�̂ł����A�N�[�|�����o���q�ɂ͔��˓I�ɂ��̂悤�ȑΉ��ɂȂ��Ȃ����Ɖ����݂܂����B �]�ƈ����o���Ă��āA�S�T�����ɕ����ֈē�����܂������A���̊ԁA�܂������̎c�郍�r�[�ɒg�[�������菗�����b�������Ă����肷�邱�Ƃ͈�Ȃ��A�C�z��S�z��͊������܂���B���̏����͍��ꂾ�ȁE�E�Ƃ�����ۂł����B �ē����ꂽ�̂͂R�K���Ă̂R�K�̏�O�Ƃ����p�̕����ł����B�h�A���J����Ɣ���قǂ̔̊Ԃ̌��ւƁA���̐�ɏ����ȏ����̓��ݍ��݂�����A�˂�������̕ǂɓ��� �u���炵���ʼn悪�|�����Ă��܂��B�L���͂Ȃ��A�Ɨ��������ւł��B���ݍ��ݍ���̉����J����ƂP�O��̖��|���̘a���ɂȂ��Ă��܂��B�a���ɓ���ƉE��Ɉ������`�ŒE�ߏ�������A�����ɗ①�ɂ��u����Ă��܂��B�E�ߏ��ׂ̗����j�b�g�o�X�ŁA��ʂ̃��j�b�g�o�X�̂悤�ɂ͋ɒ[�ɂ͋����Ȃ��̂ł����A�������g�C���E���ʁE�o�X�̃��j�b�g�Ȃ̂ōL���͂���܂���ł����B�g�C���͎c�O�Ȃ��牷�������̂��̂ł����B �a���ɂ��ǂ�ƁA�E��̕ǂɗm�����ꂪ����A����ȊO�͈�ʂ��L�����̊ԂɂȂ��Ă��܂��B�ς���Ă���̂͂��̏��̊Ԃ̔w���̕ǂɓ����镔���S�̂������^�̏�q���ɂȂ��Ă��āA�������J����Ɩk�A���v�X�̎R�X��������̂ł��B�܂��Ɍi�F�������ꂽ���̊ԂŁA���̂悤�ȏ��̊Ԃ������̂͏��߂Ăł����B���̊Ԃ̍����A�a���̐��ʂɂ͏�q�����Ă��A���̐�ɂ�⋷�ڂ̍L���������āA���[���O���̈��قǂ̏�̏����X�y�[�X�ɂȂ��Ă��܂��B�L���ɂ͈֎q����r�u����Ă��܂����B�L���̑�����������̎R��������̂ł����A�ǂ��炩�Ƃ����Ƌ߂��̉ƁX�̉������i�F�̂قƂ�ǂ��߂Ă���ƌ����Ă����ł��傤�B�O�K�Ȃ̂Ŕ`�����݂͂���܂���B �����ł̂����o���͂���A�}���َq�͋��ł����������̂ł������A�����ڂ�͏o�܂���ł����B���߂̋C�����͂���܂����B�����A�����ɂ͋��ɂ͂Ȃ��A�␅���Ō�܂œ͂��܂���ł����B |
| �����C�͒���ɂ���A�j���嗁��ɘI�V�����Ă��܂��B�j���̌��͂Ȃ��A��ʂ��������邱�Ƃ��ł��܂��B �j���嗁��́A�����͂S�l���炢�ŋ��ڂł��B������܂�Ƃ��������ŁA�ؑg�݂̓V��̕��͋C���Ȃ��Ȃ������������Ǝv���܂����B �I�V�͑嗁�ꂩ��o��`�ł��B�嗁��̐�^�̗����ƃK���X��������őΏ̂̌`�ɂȂ��Ă��܂��B�I�V�͎���ň͂܂�Ă��āA�����炵�͂܂���������܂���B���̘I�V�ɂ͂��܂薣�͂͊����܂���ł����B�����͉����A�z�A���f���������L����Ă��܂����A�����͂��Ă��Ȃ������ł��B�܂����f�����Ƃ������Ƃł����A���f�L�͂��܂���ł����B�E�ߏ��̗␅�|�b�g�ɗ₦���Β����p�ӂ���Ă��܂��B �[�H�͑啔���̐H�����łł��B ���i�����͂���܂���ł������A�����͂���܂����B�H�O���͂���܂���B��t���Ƃ������˂��o���ɋ߂������́A�R�ɂ�����߂��g�����������o����A�u����Ă����M�B���ɁA�ŏ������������܂����B�����͂��܂肶������ƏĂ��Ȃ����Ȃ̂ŁA���ǂ��̋����܂����߂ɐH�ׂ邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂����B���̂����ŁA�S�̂̐H���̗��ꂪ���������Ȃ����C�����܂��B�����Ĉ�i���^��Ă��܂��B�u�G���A�n�̂ӂ������̃x�[�R���A�����̊ØI�ρA�ӓ������q�A�C���A�R�Ȃǂ��g�����O���ڂ����ג������M���^�ɒu����A����͓�l�ŏ��M�Ɏ�蕪���ĐH�ׂ܂��B���̒��ł́A�n�̂ӂ��������o�F�̏o���ŁA�O�͑S�̓I�ɂ����������ƌ����܂��B ���ɏo�Ă����̂������̗x��H���ł��B���ɓ��������̂�Ԃŋd���ĐH�ׂ�Ƃ�������̂��̂ł����A���̔��������C�ǂ��āA�܂��d���̂���ςȂ̂ł��B�����̐������\����̂ŁA�����Ō�ɂ͔����Ɗi�����Ă���悤�ȋC�����Ă��܂����B�̂ljz�����y���ނ��̂Ȃ̂ɁA�i���ɋC������A����y���߂Ȃ��������������܂����B���͓��t�h���ŁA����͐�G�肪�悭�ƂĂ������������̂ł����B�����ẮA���낢��ȎR�������ۂ݂̒��ɓ��ꂽ���̂𒆐S�ɁA�傫�Ȃ��M�ɔ��a���ȂǁA������Ƃ������̂��X��ޕ��ׂ����̂ŁA���͂��������y���߂��̂ł����A�傫�Ȃ��M�ɕ��ׂ�ꂽ���̌����ڂƑ��܂��āA�ŏ��̑O����x�o�Ă����悤�Ȉ�ۂ�����܂����B ���������߂̗e��ɏo�Ă�����������g�����������������A��t���̎R���g�������̂�������܂肵�����̂������̂ŁA������ƁA���ꂼ��̏����Ȋ���܂߂āA�����Ƀ����n�����Ȃ������͔ۂ߂܂���B���̎��_���������A�H�����ɏ]�ƈ������̂��q����Ɂu�����̗����͎��̍�݂������Ƃ��q����Ɍ����܂��v�Ɖ���猾����߂��Č����Ă����̂����ɓ����āA�Ȃ�قǂȂƎv���܂����B�����Ă��u�G���Ɖ����������Y��Ă��܂��܂������A���Ԃ�̋��̂���Ԃ���Ԃł����B�u�G���͂������������̂ł����A���Ԃ�̋��͂悭��ʂ��Ă���ƌ����A�ʂ��������̂��|�݂������Ă��܂�����ۂł��B����Ԃ���Ԃƌ����̂Ȃ�A���܂��ʂ��Ȃ��Ă��H�ׂ�����̂��o���ė~�����Ǝv���܂����B�����Ĕn�̂������Ǝ�X�̖��C�ۂŎ芪���ɂ������̂ŁA����͏]�ƈ�������Ă��ꂽ�������ŁA���ɂ��������H�ׂ��܂����B�����Ď葢�蓤���Ƃ܂ĊL�̂��z�������o����A���̂܂ĊL�͂ƂĂ������������̂ł����B ����ɊC�V�O���^�����o�Ă��܂����B�O���^���D���̂ڂ��́A�O���^���ɂ͂��������_�����Â��̂ł����A���̃O���^���̓C���p�N�g�Ɍ����A���̓��̗����̒��ōł��]���͒Ⴂ���̂ł����B�����ăO�����s�[�X���т��o����A�Ō�ɏĂ�⡂ŁY�ł��B⡂͔M�X�ł��������̂ł����A���������݂�����A���������ꂪ�o�����܂łɂ��Ȃ莞�Ԃ��������̂ŁA����܂ʼn����ɉ^��ł����H������������ԉ��т��Ă��܂��A��X���R�O����ɐȂɒ������l�Ǝ��Ԃ������Ă��܂��܂����B���̌�ŁA�ʗ����̎�l�̎�ł��������o����ďI���ƂȂ�܂������A���̋����ł��͂T������Ȃ������̐��ł��Ŏ�l���ł��Ă������̂ł��B������ƁA���������������Ă����ۂ��܂������A�����A�ڂ��͋����ł͂Ȃ��̂ŁA���̋����Ɋւ��Ă̕]���͂��̒��x�ɗ��߂Ă��������Ǝv���܂��B�S�̓I�ɂ͂��������A���͕]�����Ă����Ǝv���̂ł����A�ŏ��ɋ���H�ׂĂ��܂����ƂɂȂ�_��A�O����o�Ă���悤�Ȉ�ہA�Ō��⡂��ԉ��т����Ƃ���ȂǁA�����̑g�ݗ��Ăɑ傢�ɋ^�₪�c��܂����B �Ȃ��A���̗����͎�l�Ɨ������̓�l�����S�ɂȂ��č���Ă���Ƃ̂��Ƃł����B�Ō�̃f�U�[�g���Ȃ������̂ł����A�����ɖ߂�ƃ}���S�X�`���Ɩ�H�̂��ɂ��肪�u���Ă���܂����B�}���S�X�`���͔��ɋv���Ԃ�Ŋ��҂����̂ł����A�ȑO�H�ׂ����̂�薡�͊m���ɗ�������̂ŁA�������肵�܂����B ���H�������Ƃ���ł��B���i��͂���܂���B���C�V�Ƒ卪���낵�̏���������A�����ȍ��Ƃ��܂ڂ��ꖇ�A�R���Ђ������A���₦��ǂ�����ꖇ�̑傫�Ȃ��M�ɍڂ��Ă��܂����B���ɂ�⡂Ƃ��₦��ǂ��̘a�����A�ق���̂��Z���A�ő��̖p�t���X�Ă��A�������A�C�ۂƂ������C���i�b�v�ŁA���܂ɂ���܂����A�����g�������̂͏o�܂���ł����B���ƁA��W���[�X���t���܂����B���ꂼ��͂��������̂ł����A�S�̂Ƀ{�����[���s���ŕ�����Ȃ���ۂ͂ʂ����܂���B |
| �������Ƃ́A�܂��A�`�F�b�N�C�����̏����̑Ή��Ɉ�l��v���܂��B�`�F�b�N�C�����Ԃ��߂��ē������Ȃ�A�܂��Ή��͈�����̂�������܂��A�ʏ�Ƃ͈Ⴄ������Ƃ����Ƃ���ɂ����{���͌���Ă��܂����̂ł��B�`�F�b�N�C�����ԑO�ɕ����֓����Ƃ͌����܂���̂ŁA���߂ă`�F�b�N�C�����ԑO�ɓ��������q�ɂ�������x�̋C�z��͕K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����A�ΏƓI�ɂ����̂���l�̓`�F�b�N�A�E�g�̎��ȂǁA���ɒ�p���ł���͂����Ǝv���܂����B �����C�����͋C�͂�����x������̂ł����A��͂苷�ڂŁA�I�V���܂߁A���C���̖̂��͔͂����ł��ˁB�I�V�̈�ۂ����������ǂ��Ȃ�ƑS�̂��A�b�v����悤�ȋC������̂ł����B�H���͈����Ȃ��Ǝv���܂����A���݂������]�ƈ��������Ă���悤�ɁA�����Ƃ��������̍悪����ł���Ƃ�����ۂ̋����\���ł��B�܂��A���Ԕz���ɖ�肪����܂����B�㔼�����̗����ɂ��������͂����A���ɉ����鎞�Ԃ����炵�������ŁA�啪����������Ă���Ǝv���̂ł����B �����̂����C�͒���ɒ���o���Ă���`�Ȃ̂ł����A���̎����Β�̂悤�ɏ����ꂢ�ɑ����Ă���܂��B�Ǐ������K�i�̏オ����ɂ���A�������������͋C���C�ɓ������l��A���̍�ő傢�Ɍ��\�Ƃ������D���Ȃ烊�s�[�^�[�ɂȂ�l�����邩������Ȃ��ȁA�Ƃ��v���܂����B |
| �Q�O�O�X�N�P�P���ɕđ�̓��̑�u���̏h�@���݂�v�ɘA���ōs���Ă��܂����B���͂��ꂪ�R��ڂ̏h���ŁA�ŏ������̑O�N�̂Q�O�O�W�N�X���A�Q��ڂ��S�����O�̂Q�O�O�X�N�V���ł����B�P��ځA�Q��ڂƂ����T�{���Ă��܂����̂ŁA�ŐV�̂��̂R��ڂ𒆐S�ɍ��܂ł̑����������Ă��������܂��B |
| �P��ڂ̏h���͂Q�O�O�W�N�X���ł������A���̏h�̖���m���āA�}�[�N���n�߂��̂͂���������Ȃ�O�A�s�u�ԑg�u���������C���v�ŁA�����|��ƃP�[�V�[���K�ꂽ�ۂ̗l�q�������Ƃ�����ł����B�E�b�h�f�b�L�̃e���X�������r�[���璭�߂�̒�B�����ĉ������A�����玟�ւƓW�J�����A�đ��g���������̐��X�B�����ɂł��s���Ă݂����Ǝv���܂������A�ڂ��̈����ȂŁA�s�u�ŕ������ꂽ������͐�ɍ���ł��邩��ƁA�������Ȃ�̊��Ԑ扄�����Ă��܂��̂ł��B���͌��́u�����v�̎��������ł����B�u���݂�v�������������Ă��邤���ɁA���ٌn�̐l���������l���h�����āA��������������]���̐����������Ă��܂����B ����͍s���˂Ȃ�܂��Ǝv���ďd�������グ�A�悤�₭�Q�O�O�W�N�X���ɍs�����̂ł����A���̎��ɁA�A�������ꍇ�A���̓��̗�������͂苍���ŁA���e�����ׂĕς��Ƃ������Ƃ��āA����͘A�����˂Ȃ�܂��ƐV���ȉۑ肪���܂�A���N�̂V���ɘA�����ʂ������̂ł��B�����āA����ɂ��̎��ɏ�������G�߂��ꂼ��̏h�̗l�q���A����͋G�߂�ς��čs���Ă݂Ȃ���A�ǂ����s���Ȃ��͂�A���ƁA���̂Q�O�O�X�N�P�P���̍g�t�̋G�߂ɂR�x�ڂ̖K��ɂȂ����킯�ł��B |
| �����ɃG�[�X�i�s�a�́u�D��E�€�v�Ƃ����p���t���b�g�̍ŐV���i2009�D10.1�`2010�D3.31�j�A������܂��B�u���݂�v���ڂ��Ă��āA�����ɂi�s�a���h���҂Ɉ˗������A���P�[�g�̏W�v���f�ڂ���Ă���̂ł����A���݂�́A�q�����R�_�A�H�����T�_�A�嗁�ꂪ�Q�_�A�T�[�r�X���S�_�A�����x���T�_�ƂȂ��Ă��܂����B���ׂĂT�_���_�ł��B���̃A���P�[�g���ʂ͂ڂ��̈��ڂ̏h�����̎����Ƃ����������߂��̂ł����A���ڂ��ׂ��́A�X�̍��ڂł͐H���ȊO�ɂT�_�̕]�����Ȃ��A�������Q�_�A�R�_�Ƃ����Ⴂ�]�����ڂ�����̂ɂ�������炸�A�����]���Ƃ������ׂ������x���T�_�ł��邱�Ƃł��B�����ɐH�������ׂĂ��J�o�[���Ă��邩��������܂��B �ڂ��̑���ڂ̏h�����̈�ۂ��܂��ɂ���Ȋ����ł����B���ڂ́u�Ђ߁v�Ƃ����A���݂�ł����Β��Ԃ��炢�̉��i�т̗m���ɏh�������̂ł����A�����͍L�����̂̂����Ƃ��������ŁA�|�b�g���z�e���`���́A�����Ő������ĕ����������Ȃ��̂����A��������������œ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂȂǁA������Ƃ悻�悻���������������Ă��܂�D���ɂȂ�܂���ł����B �嗁������ɕs���ł����B���݂�͑嗁�ꂪ�I�V�t�̂��̂ƘI�V�Ȃ��̂��̂Ƃ̓����̂ł����A���̓��A�܂��j���p�Ɋ��蓖�Ă�ꂽ�̂��I�V�Ȃ��̕��ł����B�R���N���[�g�ł����ςȂ��ŁA�{���͂������ȗ���Ȃ̂ł��傤���A�ꂪ�O�����Ȃ��A���̂�����낪�̉��̗����Ƃ̎d��ǂɂȂ��Ă��Ĕ��ɋ����������܂����B�܂��������R�l���炢�̍L���ŁA�e�̃X�y�[�X���Ȃ��A�Ƃɂ����������ꂵ�������͔ۂ߂܂���B�����͒����C�̂ڂ����A�����͒����Ԃ����Ȃ��Ƒ��X�ɏo�Ă��Ă��܂��܂����B ����Ȗ�ŁA�H���̎��Ԃ܂łɂ͂��Ȃ�s��������Ă����̂ł��B�Ƃ��낪�A�[�H�ɍs���Ă݂�ƁA�����玟�ւƏo�Ă���A�H�v���Â炵�������̐��X�B���܂ŕ��������Ƃ��Ȃ��悤�ȋ������ʂ��g���Ă���̂ɂ�������炸�A�����̒����ł͏I���Ȃ��A��̌����Ƃ��Ċ������ꂽ�����B�H�אi�݁A�Ȃ�ւ��čŌ�̃f�U�[�g��H�I����ċC�Â��ƁA��قǂ܂ł̐ςݏd�Ȃ����s���͂����̂悤�ɂ����ς�ƈ�|����A����ɂ��ނ�����قǂ̖������ɖ�������Ă��܂����B �[�H���ɒj����㎞�ԂƂȂ���������̑嗁��ɂ͘I�V�����݂���A�����C�̕����L���Ȃ��Ă��āA������̂����C�͏\���ɖ����ł��܂������A�����̐H�����蔲���̂Ȃ����̂ł��������H�ׂ邱�Ƃ��ł��A�[�H�̌�͂����ĕς���āA����s���������邱�Ƃ͂���܂���ł����B������肩�A�`�F�b�N�A�E�g����i�K�ł́A�A���������̗[�H���ǂ�ȃ��j���[�ɂȂ�̂��A���ɋ������킢�����Ƃ������āA����͐���A���łƎv���܂łɂȂ��Ă��܂����B |
| ����Ȉ��ڂ̏̌�A�Q�O�O�X�N�V���ɘA���ŏo�������킯�ł��B�����͍��x�́u�����ڂ́v�Ƃ����Ƃ���ŁA�a���ł��B�u�Ђ߁v��苷���Ȃ��Ă��܂����A�S�̂̍\���͑O��Ǝ����悤�Ȋ����ŁA��̃|�b�g�����������A������������Ă͂���܂���B�ŏ��̕��C�����������ŁA����o���͑O��ƂقƂ�Ǔ����ł������A���̎��͂��łɂP�x�o���ς݂ł�����A�O�Ɋ������悤�ȕs���͂܂������Ȃ��A����Ȃ��́A�ƌ�����S���ł��̂܂ܐH���ɍs���A�H���ł��O��ƑS�������悤�ɖ������܂����B�ڂ̐H�����ꔑ�ړ��l�A�S�����F�Ȃ��y���߂܂����B�����āA���x�͋G�߂�ς��ė��Ă݂悤�Ƃ����S���ɂȂ����̂ł��B �ȏオ�O��܂ł̑�܂��ȗ���ł��B ���݂�̃��j���[�͋G�ߑւ��ŁA�R��ڂ̂��݂�h���́A���j���[�Ƃ��Ă͂P��ړ��l�A�H�̃��j���[�Ȃ̂ł����A�P��ڂ͂X���œ��ɂ���Ƃ������i�F�͂Ȃ������̂ŁA����͌i�F���S�ɏH�̍g�t�̎����ɍs���Ă݂悤���Ƃ������ƂŁA���݂���ӂ̍g�t�̎����ł���炵���A�P�P���̏��{�Ɍ��肵�܂����B |
| ���݂�́A���H���炻��ĕ~�n�ɓ���ƁA�ؗ��̂���O���ʂ��Č����̂Ƃ���܂ōs�������܂łɏ������Ԃ�����܂��B���H�ɂ��̂܂ܖʂ��Ă�����A���H���猺�֑O�̒��ʂ��Ă����ڂ̑O�Ɍ�������Ƃ����^�C�v�̏h�ł͂���܂���B���������A�s�������܂łɂ�����x�O��̃X�y�[�X�̂���h���ڂ��͑�D���ł��B ���֑O�ő��}�Ԃ��~��Ē��ɓ���ƁA���r�[����̓E�b�h�f�b�L�̂���e���X�Ɨ̒낪�ڂ̑O�ɍL����܂��B���̃��r�[�̈֎q�ŁA�h�����̃��b�V�F�Ƃ����������Q�̏Ă��َq�Ɩ��������������A�{���Ȃ炱���ŕ��C��H���̐�������̂ł����A�S�����O�ɗ�������Ƃ������ƂŁA����͏ȗ��A�������������Ɉē����Ă��炢�܂��B����̕����́u���v�Ƃ�����K�̒[�̕����ŁA�O��́u�����ڂ́v�����Q��قNj����Ȃ����W��̘a���B���͌��֑O�̖ؗ������ɖʂ��Ă��܂��B�a���ƌ����Ă��A���_���a���Ƃ��������ŏ��̊Ԃ͌���I�Ȃ��炢�ɂȂ��Ă��܂����A�S�̓I�ɂ͋Â������ł͂Ȃ��A��͂�f���C�Ȃ����ނɓ��邩������܂���B�����A�R����̍L��������A�Q�r�̈֎q�ƃe�[�u�����u����Ă���̂́A�֎q���D���Ȃڂ��Ƃ��Ă͕���̂Ȃ��Ƃ���ł��B�����S�̂̍��Ƃ��ẮA�O��̂����ڂ̂��Q���������Ȃ��������ŁA�قƂ�Ǖς�肪�Ȃ��悤�Ɏv���܂����B ���C�͑O�q�̑嗁���̂ق��ɁA�\��Ȃ��ŎD���Ђ�����Ԃ��ē���ݐ�̔��I�V���A�̗����ƁA�̗����̓����A�Ă�����ł�����܂��B�����嗁��ɓ������Ă��܂������ԑт́A������ɔ��邱�Ƃ��ł��܂����A�������A�Ό��ނ͎g���܂���B�݂��蕗�C�͓���`�Ő�ɖʂ��Ă��܂��B���I�V�Ȃ̂Ŏ��E�������A����Ȃɕω��ɕx�i�F�Ƃ͂����܂��A�삪���E�ɓ��邱�Ƃ�����A�ւ��ȏh�̈͂܂�Ă���I�V���͂����Ɩ�����܂��B�����͂��ׂĂ̗��ꂪ�Q�S���ԉ\�ŘA���̏ꍇ�́A�|�����ł��A�����Ă����Γ���镗�C���ē�����Ƃ������Ƃł����B �m���A���ׂČ����肾�����Ǝv���܂��B�����͂��̋ߕӂ̓����̂��鉷��Ɣ�ׂ�ƁA�m���Ɋ��F�������������܂����A���̑���D�������₩�ŁA�p���Ă��̂������D���ƌ����l�����邩������܂���B���Ƃ��Ƃ��̌X��������̂ł����A�ڂ��̏ꍇ�A��w���ł����c���s�J�ɂȂ�܂����B�����A���L�A���F�ŁA���Ԃ͂Ȃ��A���f�L�����܂���B ���r�[�O�̃o�[�J�E���^�[�ɁA�����n�����̗�₵�����̂��u����Ă��܂��B�Â��āA�����������ł��B |
| �H���͂��ׂĐH�����ŁA�S��O�ɂ����I�[�v���L�b�`���̃J�E���^�[�ɂS���W�����̐Ȃ�����A�����̓��s�[�^�[�D��̂悤�ł��B�J�E���^�[�Ȃ̔w��ɔ����Ƃ����������̏�����������������A����ɒ��H�̃O���[�v�q�p�Ȃ̂��A��̕~���ꂽ���������Ɍ����܂����B �P�P���̘A���͏����̃��C�����X�e�[�L�A����ڂ̃��C�������߂Ă����₫�ɂ��܂����̂ŁA�������J�E���^�[�A����ڂ͌��ł����B���݂�̗����̓��C�����u�X�e�[�L�v�u�����Ă��v�u����Ԃ���ԁv�̂R��̂�������I�Ԃ悤�ɂȂ��Ă��āA�u�����Ă��v��u����Ԃ���ԁv��I�ꍇ�́A����g���W��A�K�����ɂȂ�܂��B �P���ڂ̐��K���j���[������������������̂ł����A����͂��܂背�|�[�g����Ă��Ȃ��A�Q���ڂ̗����𒆐S�ɕ��܂��B���C�����u�����Ă��v�ɂȂ��������ł��Ƃ͕ς��܂��A�u�����Ă��v�̏ꍇ�A�H���͔�����тɂȂ�܂��B�X�e�[�L��I�ԂƁA�H���͋������g���������Ђ��ȂǂɂȂ�͂��ł��B �P���ڂƓ����悤�Ɉ�g�Ɉꖇ�A�傫�Ȃ��i�����u����A�����ɂ́u���݂�̕đ��@��Z�Z��@�H�v�ƍ���̂P���ڂ̂��i�����ƑS�������^�C�g����������Ă��܂��B�������A�����͘A���p�̌����ŁA �E�������̃^���^���@�R���\���[���[�Ƌ��� �E�}�b�V�����[���̉��������� �E�����ڂƐ�{�̂��h�g �E�͂�݂̃o�[�j���J�E�_�� �E�R�Ԃǂ��̃O���j�e�@ �E��Ƃ�̂ɂ���Ƃ��Ԃ� �E�^����̍����\�[�X�T���_�d�� �E�܂���Ƃق���̔��a���@ �E�T�[���C���̂����Ă����݂ꂾ��� �@�đR�̂ЂƂ߂ڂ�@ �E�L���������A�C�X�̃N���[�v��� �Ƃ������C���i�b�v�ł��B �����A���ׂĂ̗��������������܂������s���͂���܂���ł����B������A���ł����Ɉ�ۂɎc�������̂�I��ŏ����Ă����܂��B�u�}�b�V�����[���̉��������Ձv�̓}�b�V�����[���̍���A���������ɖL���ł��������A��i�ł����B�������̓t�����`�o�g�Ƃ������Ƃł������A���̋Z�ʂ�������Ȃ��������ꂽ�X�[�v�������Ǝv���܂��B�u��Ƃ�̂ɂ���Ƃ��Ԃ�v�͂Q��̘A���o�����炢���ƁA�A���̎��ɂ͕K���o��X�y�V�����e���Ǝv���܂��B�P���ł��h������Α�Ƃ�̂ɂ���͕K���H�ׂ���̂ł����A���Ԃ�͘A�����Ȃ��ƐH�ׂ��Ȃ��悤�ŁA�����ޗ��ł������ڂ������܂������Ⴂ�܂��B������ɂ���A�ɂ���͈��|�I�Ȃ��������ŁA�v�킸�������ڂ�Ă��܂��܂��B�u�^����̍����\�[�X�T���_�d���v�ɂ��ẮA�^����Ƃ����̂̓^���̒��S���炵���A���݂�̃��j���[�ł͂悭�g����̂ł����A���̃^���̏_�炩�����ƁB�ڂ��͂��݂�ŏ��߂ă^���͏_�炩���̂��Ƃ������Ƃ�m�����C�����܂��B��������������A����ɎU�炳�ꂽ�s���N�y�b�p�[�Ƃ̒��a�����Ƃ������܂���B�u�T�[���C���̂����Ă����݂ꂾ��Łv�̂��݂ꂾ��Ƃ����̂́A���Ȃ�Â߂̖��X����ł��B�������A���̓������܂�Ȃ����������B�X�e�[�L�łȂ��Ă��\���Ɋy���߂܂��B�����A�����Ă��͍ŏ��A�W�̏���������Ă����̂ł����A�㔼�͎��������ɔC����A���̎��ɒ��q�ɏ���ă^������ꂷ���Ė����Z���A���ǂ��Ȃ��Ă��܂����̂����Ƃ��c�O�ł����B��͂�A�����̏ꍇ�A���������ō��V�`���G�[�V�������ƁA�ǂ̏h�ł��o��������ɂȂ��Ă��܂��X��������܂��B�����A�������͍ŏ��ɏW���I�ɐH�ׂĂ��܂������߁A���̉e���͖Ƃ�A�{���̂����������\���Ɋ��\�ł��܂����B �Ō�͏ꏊ��ς��āA�u�L���������A�C�X�̃N���[�v��݁v�̃f�U�[�g�ƃR�[�q�[�ŁA������t�����`�o�g�̃V�F�t�ł��̂ŏ\���Ɋy���߂܂����B �S�̓I�ɁA����̘A���́A�����Ƃ��ċÂ��������̂P���ځA���̂����������X�g���[�g�Ɋy���ނQ���ڂƂ�������ۂł����B |
| ���H�ł̓J�E���^�[�͎g�킸�A���ׂČ��ɗp�ӂ���܂��B�A���̏ꍇ�̒��H�͗m�H�ɂȂ�炵���̂ł����A����Ȑl�͂P���ڂƓ����悤�ɘa�H�̒��H��H�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B�������A���e�͕ς��܂��B�����̏ꍇ�A���H�ŗm�H��I�����邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��̂ŁA���������Ƃ��a�H�ɂ��Ă��炢�܂����B���H�Ɋւ��Ă͂P���ڂɐH�ׂ������A���p�̌����Ƃ������Ƃł����̂ŁA������A�A���p�̕�����܂��傤�B ���݂�̒��H�́A�����M�̂悤�ȑ傫�Ȏl�p���M���ǂ�Əo����A���̎M�ɂ͂R�~�R�̂X�i���ق�̏������ڂ��Ă���Ƃ����`����{�ł��B�G�߂��ς���Ă��A�A���ɂȂ��Ă��A���̊�{�͕ς��܂���B����̘A���p�����̂X�i�́A�Ƃ��A���V���A�ق���A�����Ă̊O�A�R���Ђ��A�C�ۂ̒ώρA�[���A���Ƌ��y�������ۂ����̂Q�i�Ƃ����g�ݍ��킹�ł����B���̎M�̑��ɁA�n���T���_�A�卪�Ƃ��ڂ��Ɠ��̎ϕ��A����ʎq�A��z�̂S�i���ʂ̏����ŏo����܂����B���X�`�����������A�f�U�[�g�͉ʕ����荇�킹�i�O���[�v�t���[�c�Q��A�I�����W�A�L�[�E�B�A�������j�ŁB�\���ɖ����ł��钩�H�ł����B���H�̌���Ȃ�ς��ăR�[�q�[���T�[�r�X����܂��B |
| �Ƃɂ����A���݂�ŐH�������Ă���ƁA�Ȃ����K���ȋC���ɂȂ�܂��B�ŏ��ɏ������悤�ɂP��ڂ̏h���ł͂���܂ł̕s�����ꋓ�ɕX���������A�Q��ڂ̏h�����͏��[���H���̒��O�ɁA�g�тŖ��Ƃ�肠���ăJ���J�����Ă����̂��A�J�E���^�[�ɒ����A��ڂ̗�����H�ׂ��r�[�ɁA�����Ȃ��炢�ɉ��₩�A�ɂ��₩�ɂȂ�܂����B �܂��A���������P�O���̏h�Ƃ����̂͂�����������̂ł����A���݂�̂����Ƃ���͂��ꂼ��Q���Ɍ��肳��Ă���̂ŁA�ő�łQ�O���ɂ����Ȃ�Ȃ��Ƃ����Ƃ���ł��傤�B�����C�ɓ����Ă��A���r�[�ɂ��Ă��A�c�̂�O���[�v�ł��邳���Ƃ������Ƃ�����܂���B ������������݂�̖��͂̈�ł��傤���B���Ƃ��Ƃ̓L�����A�E�[�}���Ƃ��ē����œ����Ă��������ł����A���c�ꂳ�n�߂����̏h���A�킯�����ĂS�N�O�Ɉ����p���A���j���[�A�����������ł��B��������Ƃ������t�͎��͎�����Ȃ��A�����p���c�X�[�c�p�̔w�̍����D�u�Ƃ��������ł��B�[�H�̍Ō�A�f�U�[�g�̎��ɕK���b�������Ă����͂��ł��B�����̃��s�[�^�[�̒��ɂ͂��̏�������t�@����������������̂�������܂���B ���s�[�^�[�ƌ����A���݂�́A�s���s���قNj��S�n�̗ǂ��Ȃ�h�ł��傤�B��قǂ��������悤�ɏh���q�����Ȃ��̂ŁA�]�ƈ��Ƌq�Ƃ����݂��Ɋ猩�m��ɂȂ�m���������A�܂��ĘA���������ɂ��̊m���͏オ��܂��B���͂��̂P�P���̂R��ڂ̏h���̎��A�đ�w�܂Ō}���ɗ��Ă�������̂ł����A�}���ɗ����j���]�ƈ����A�吨�̐V������~�q�̒����炵������Ƃڂ��������Ă���܂����B���ł��A�Q��ڂ̏h�����̑����S�������Ƃ������Ƃł����B�ڂ��͑��̋q�����Ȃ��ꍇ�͉^�]��Ɏ���U�߂ɂ���̂ŁA�q�̒��ł��o�����₷���̂ł��傤���A�������T�[�r�X�ƁA�債�����̂��Ǝv���܂����B�������Ċ猩�m��ɂȂ�A���݂��ɋْ����邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�A��胊���b�N�X�����؍݂��ł���悤�ɂȂ�܂��B�Q��ڂ̏����̃J�E���^�[�Ȃ͑S�������s�[�^�[���ƃV�F�t�������Ă��܂����B ���ꂱ��Ə����Ă��܂������A�������A���Ƃ����Ă����݂�̍ő�̖��͂͂��̗[�H�ł��B���݂�̗[�H�́u�����v�Ƃ������ƂŁA���ׂĂ̗����ɋ��́A��������ł͐H�ׂ��Ȃ��悤�Ȓ��������ʂ��g���A�����������̒����ɏI���Ȃ����������ƁA�����Ƃ��Ă̊����x�������Ă��܂��B����ł����Ƌ������H�ׂ����鋙�t�h�͐��̐��قǂ��邵�A������H�ׂ�����X�́A�ē��A�X�e�[�L�n�E�X�A�S�Ă��A�t�����`�ȂǂȂǁA���ɂ��܂�����܂����A���̂悤�ɋ��̑��l�ȕ��ʂ�l�X�ȕ��@�Œ������A���Ε��Ɍ������\�����Ă���X���A�Ǖ��ɂ��Ăڂ��͑��ɒm��܂���B�������������j���[�����h�Ƃ��Ă��M�d�ȑ��݂ł����A����ɁA���������������łȂ��A���������A���������[�Y�i�u���ȗ����ŐH�ׂ����Ă����h�Ƃ��āA���݂�͓��{�̏h�̒��ł��H�L�Ƃ������鑶�݂ł��傤�B ���A�R��A�v�T��������ōl���Ă݂�ƁA�i�s�a�̂��̕]���͂�����Ɛh������悤�Ɏv���܂��B �q����3.5�_�A�H�����T�_�A�嗁�ꂪ3.5�_�A�T�[�r�X���S�_�A�����x���T�_�Ƃ����Ƃ��낪�Ó��Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |
| �g�n�l�d | ���X�g | �铒�̏h | ���J���̏h | �����߂̏h | �V���̏h |
| �V���̉��� | �����̉��� | �F�X����߂��� | �����\���̃y�[�W | �X�V���� | �f���� |